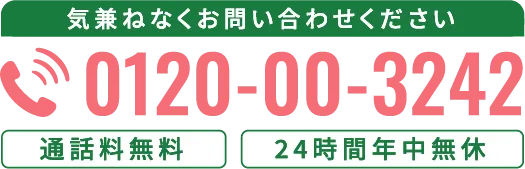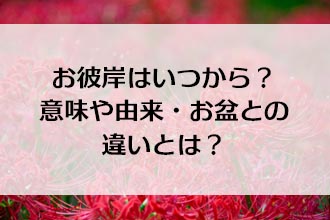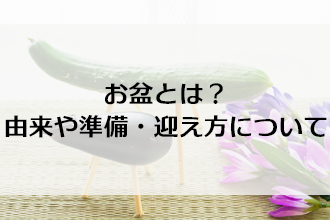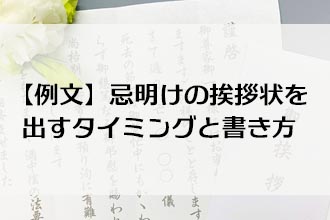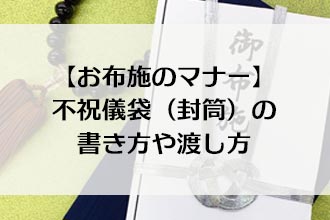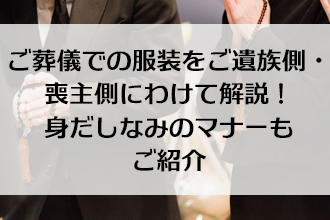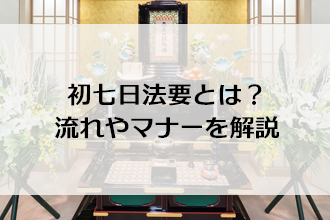「法事」と「法要」の違いとは?法要までの準備や法要の手順

公開日:2021年5月10日
故人様がお亡くなりになって忌明け(四十九日目)などの節目には、法事・法要が執り行なわれます。法事・法要は、ご遺族やご親族などが集い、故人様の想い出を語り合う大切な場となっています。
[@目次@]
「法事」と「法要」の違いとは?

皆さまは、「法事」と「法要」の違いをご存じでしょうか?法事と法要は、区別されずに使われることが多い言葉ですが、厳密に言えば違うものです。
「法要」は追善供養とも呼ばれ、故人様を偲び、ご寺院による読経や焼香を行なう仏教的な儀式のことを言います。一方、「法事」は、法要と法要後の会食までをあわせた一連の行事を指す言葉です。
また、「法事」は仏教行事全般を指して使われることもあり、故人様やご先祖様を偲ぶ、「お盆」や「お彼岸」などの仏教行事を含むことがあります。
追善供養とは?

追善供養(ついぜんくよう)とは、亡くなった方に対して行なう供養のことです。
法要だけでなく、仏壇に手を合わせるなど、日々の行ないも追善供養にあたります。「善」は仏教における善行を表し、生きている人が良い行ないをすることが、亡くなった人の善行につながると考えられているのです。
法要としての追善供養には、まず、忌日ごとに供養する中陰法要があります。
仏教では、逝去してから忌明け(四十九日)の間を「中陰」と言い、七日ごとに審判を受けます。そして、忌明けとなる四十九日目に、極楽浄土への最終審判が下されるのです。
故人様が無事に極楽浄土(来世)に旅立てるよう、手助けするのがご遺族の務めであり、追善供養の本来の目的です。
※浄土真宗では、亡くなるとすぐに阿弥陀如来の力で成仏できるという考えから、本来、追善供養は必要ありません。浄土真宗の法要は、自分自身が仏の教えに接することが目的です。
忌日の数え方は地方によって異なり、関東地方などでは、亡くなった日を1日目として数えます。関西地方では、亡くなる前日から数えることが一般的です。
中陰法要のあとには、亡くなった翌年以降、故人様の祥月命日(亡くなった月日)に年忌法要が執り行なわれます。
忌明け(四十九日)に関しては『忌明けとは?忌明けにすること・準備やその後について』の記事で詳しくご説明しております。
法要の準備・手順
続いては、法要の準備・手順についてです。
ご寺院へ日時と場所の連絡
法要を行なう際には、ご寺院や参列者の都合も考えて、余裕を持って準備したいところです。少なくとも2~3か月前までには日時と場所を決めましょう。故人様の祥月命日に行なうのが望ましいのですが、来ていただく方のご都合も考慮して、祥月命日から前の土・日・祝日に行なうことが一般的です。
法要は土・日・祝日に集中するため、できるだけ早めに連絡をし、ご寺院や会館の予約を済ませておきましょう。
ご親族などへの案内
日時と場所が決定したら、ご親族などに連絡をします。近親者の場合は電話連絡でも構いませんが、葉書や封書で案内状を送付すると良いでしょう。お招きするのは、ご葬儀に来ていただいたご親族が中心となります。
一般的には一周忌までは、ご親族だけでなく、故人様の友人、知人、お世話になった方など、広い範囲でお招きします。
お食事・供養品の手配
出欠が確認できたら、2週間前を目安に、お食事・供養品の手配をします。会食の人数は、何日前までなら変更可能か確認しておくと良いでしょう。
最終確認
1週間前までに、参加人数、お食事・供養品の数などを最終確認します。御布施の額も、ご寺院に早めに確認しておいた方が良いでしょう。
当日に必要な物の準備
前日までに、位牌(浄土真宗の場合は過去帳)、遺影写真、御布施など、当日必要な物を準備しておきます。
法要の服装と持ち物
ご遺族は、三回忌までは喪服を着用される方が多いようです。七回忌法要からは、法要も簡略化され、紺やグレーなどの地味な服装で問題ありません。ご親族は一周忌までは略礼服を着用し、三回忌からは地味な服装にしていくと良いでしょう。
回を重ねるごとに、喪の表現を軽くするという意味で、少し明るめの色を選びます。
地味な服装と言ってもカジュアルな服装は避け、基本的には、女性はワンピースかスーツ、男性はスーツを着用します。
施主の持ち物
位牌(浄土真宗の場合は過去帳)、遺影写真、御布施、数珠など(寺院で法要を行なう場合はお供え物やお花など)
参列者の持ち物
御香典、お供え物、数珠など
法要当日の手順
施主様と血縁の濃い方は、法要開始の30分前には会場に到着するようにしましょう。聖職者がお見えになりましたら、御布施・御車料・御膳料をお渡して、法要読経を依頼します。(会食時に同席される場合は、御膳料は必要ありません。)
法要の流れの一例
読経→参列者による焼香→法話→施主のご挨拶→お食事→散会
お食事の前には、仏様や故人様に盃を捧げる「献杯」を行なうことも少なくありません。ご親族などに献杯のご挨拶をしていただく時は、事前にお願いしておきましょう。参列者の方々への供養品は、法要の散会までにお渡しします。聖職者への供養品も準備しておくと、尚良いでしょう。
忌明け法要、年忌法要は平安祭典へ

今回は、法事・法要について、ご説明しました。故人様とご縁の深かった方々が集う法要は、故人様との想い出を語り合い、故人様とのご縁によって、新たな絆を結ぶ大切な機会ともなります。平安祭典も、皆さまのお役に立てれば何よりです。
平安祭典では神戸・阪神間での忌明け法要、年忌法要などを承っております。また満中陰のお返しもお選びいただけます。
平安祭典の法要については下記のページをご覧ください。
法事・法要について
詳細は平安祭典までお問い合わせください。
平安祭典祭典でお葬式をされていない方のご法要も承ります。
《平安祭典法要受付》
フリーダイヤル 0120-18-4142 (受付 9:00~17:00)
お問い合わせ、ご予約の際は「平安祭典のホームページを見た」とお伝えください。
※年末年始は休業(12/30~1/3)