

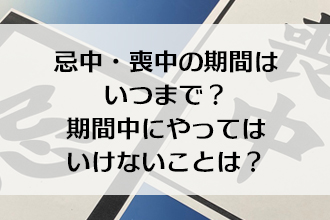
公開日:2023年11月6日
ご家族やご親戚など近親者を亡くした後は、生活の中で「忌中」や「喪中」という言葉を意識する機会が増えます。
しかし、「忌中と喪中はどう違うのかよくわからない」という方は多いかもしれません。
当記事では、忌中と喪中の違い、それぞれの期間中に控えるべきことについて解説します。
[@目次@]
忌中と喪中とは?喪中と忌中の違いは?
忌中(きちゅう)と喪中(もちゅう)はいずれも故人様を偲んで過ごす期間という意味では同じですが、意味合いや期間が異なります。
忌中は、故人様のご逝去から忌明け法要(四十九日法要)までの期間を指します。
喪中は、忌中を含めて亡くなった方を偲ぶ期間であり、一般的には一周忌法要までの約1年間とされています(※1)。
それぞれの期間中にやってはいけないことや、配慮すべき事柄には違いがあるため注意が必要です。
それでは、忌中と喪中の意味について詳しく解説します。
(※1)喪中に関しては、故人様との関係性により期間が異なる場合があります。
明治7年の太政官布告により「服忌令」(ぶっきりょう)が出され、故人様が配偶者や父母の場合は13か月、子どもの場合は3~12か月、祖父母なら3~6か月、兄弟姉妹なら1~6か月という具体的な喪中の期間が定められました。
この布告自体は昭和22年に撤廃されましたが、現在も喪中の期間を考える際の基準とされることがあるのでご注意ください。
忌中は故人様が冥途で旅をする期間
忌中とは、仏式において一般的に命日から忌明け法要(四十九日法要)が終わるまでの期間です。
この間、ご遺族は故人様の死を悼み、慶事など晴れがましいことは避け、身を慎んで過ごします。
忌中が四十九日間である理由は、仏教の教えによります。
仏教では人が亡くなると、その魂は冥途(めいど)と呼ばれる死者の世界へ行き、7日ごとに生前の行ないに対する裁きを受け、最後の7回目の裁きで行き先が決定するとされています。
この裁きを待つ期間、ご遺族は故人様を偲ぶとともに、無事に極楽浄土へ旅立てることを願って追善供養を行なうのです。
四十九日間の忌中が終わること、または終えた日を「忌明け」と呼びます。
その際に行なう法要が忌明け法要(四十九日法要)であり、忌が明ける区切りの法要として特に大切に考えられています。
忌明けについて詳しくは###kiake_shijyukunichi###をお読みください。
なお、忌中と関連して「忌引き」という言葉があります。
忌引きや忌引き休暇とは、ご親族が亡くなり喪に服するために職場や学校を休むことです。
その間に葬儀の準備・後片付け、各種手続きなども行ないます。
忌引きの日数は故人様との続柄によって変わり、一般的には以下が目安です。
※会社や学校により規定は異なります
・配偶者…7~10日間
・父親・母親…5~7日間
・子ども…5~7日間
・祖父・祖母…3~5日間
・兄弟…3~5日間
喪中は故人様を偲ぶ期間
喪中とは、一般的に一周忌法要までの約1年間を指します。
「喪」の意味は、人の死後、その親族が一定の期間、外出や社交的な行動を避けて身を慎むことです。
喪に服す期間が喪中であり、忌中に引き続き故人様を偲び、身を慎んで過ごします。
日常生活を送る中でも、おめでたい席や晴れやかなシーンへの関わり方には配慮が必要です。
忌中と喪中にやってはいけないことは?
忌中・喪中には、具体的にどのような行動を控えるべきなのでしょうか。
忌中は慶事や祭典は避けるべきとされ、喪中も忌中に引き続き慶事や祭典は避けることが基本です。
忌中に比べ、喪中の間は柔軟に考えて良い部分が増えますので、以下の内容を参考にしてください。
忌中にやってはいけないこと
忌中にやってはいけないことは、次の通りです。
■ 結婚式・結納を行なう
結婚式や結納を行なうのは、避けた方が良いとされています。
しかし、すでに日程が決まっているなど事情がある場合は、予定どおりに行なうか延期するかを両家で相談して決めると良いでしょう。
結婚式に招待された場合は先方に忌中であることを伝えて相談しましょう。
先方に了承していただければ、出席しても構わないと考えられています。
■ 神社にお参りする
神社へのお参りは、控えるべきとされています。
神道では忌中は死の穢れがあると考えられているからです。
仏教では神道とは考え方が異なるため、お寺へのお参りやお墓参りはしても問題ありません。
■ 新年を祝う
鏡餅、門松、しめ縄などの正月飾りやお節料理・お屠蘇などは準備せず、普段どおりに過ごします。
「おめでとうございます」という新年の挨拶、神社への初詣は控え、年賀状ではなく事前に喪中はがき(年賀欠礼状)を出します。
お子様やお孫様へのお年玉については、派手なポチ袋ではなく無地の封筒などを用意し、「おこづかい」として渡してあげても良いでしょう。
■ お祝い事をする
お祝い事は控えるべきではあるものの、例えば、成人式は一生に一度の大切なイベントです。
成人式に出席するかどうかは、ご本人とご家族でよく相談して決めると良いでしょう。
上記の他には、忌中は以下のこともできるだけ避けたほうが良いとされています。
・ 引越し、家の新築・改築を行なう
・ 旅行や、お祭り・スポーツ・飲み会などに参加する
喪中にやってはいけないこと
喪中にやってはいけないことは、次の通りです。
■ 結婚式・結納を行なう
喪中の間も、結婚式や結納を行なうことはなるべく避けたほうが良いとされています。
事情に応じて両家で相談して決めると良いでしょう。
結婚式への出席は、喪中でも問題ありません。
■ 神社にお参りする
神社へのお参りは避けるべきとされています。
■ 新年を祝う
新年を祝うための正月飾り、お節料理、初詣、新年の挨拶、年賀状などは控えるべきとされています。
お年玉については忌中と同様、おこづかいとして渡してあげると良いでしょう。
■ お祝い事をする
お祝い事は控えるべきではあるものの、成人式など大切なイベントについてはご本人とご家族でよく相談して決めると良いでしょう。
成人式が忌中にあたり出席を控えた場合、忌明け後に写真撮影だけ行なう方もいるようです。
また、七五三などを内々でお祝いするのは差しつかえないでしょう。
忌中に引き続き、喪中も華やかなイベント(お祭り・スポーツ・飲み会)や旅行はできれば避けたほうが良いとされています。
しかし、仕事の関係や周囲とのお付き合いのうえで必要なこともあるかもしれません。
状況に応じて参加するか(実施するか)を判断されると良いでしょう。
喪中はがきの出し方について
忌中・喪中は新年の挨拶としての年賀状は控え、喪中はがき(年賀欠礼状)を準備します。
喪中はがきは、遅くとも12月上旬には届くように送ります。
12月に入ってから近親者が亡くなった場合は、喪中はがきの準備が間に合わないこともあります。
その際は、届いた年賀状に対し、1月7日を過ぎてから「寒中見舞い」として故人様が亡くなられたことをお知らせしましょう。
喪中はがきを出す場合、近親者のどこまでを喪中とするのかは難しいところですが、一般的な範囲は以下の通りです。
■ ほとんどの人が喪中とする続柄
父母・子ども 義父・義母 兄弟・姉妹
■ 喪中にする人としない人がいる続柄
祖父母 義兄弟・義姉妹
■ ほとんどの人は喪中にしない続柄
祖祖父母 叔父・叔母 伯父・伯母 従兄弟
あくまで参考ですので、ご自身と故人様とのつながりの深さや偲ぶ気持ちの強さに応じて、喪中とするかどうかを決められても問題ありません。
喪中はがきは、年賀状のやりとりをしている方を中心に送りますが、仕事の関係者には例年どおりに年賀状を出すケースが増えています。
ご葬儀に参列してくださった方など、喪中であることをご存じの方にも、改めて喪中はがきを出しましょう。
なお、喪中はがきと関連して「お中元やお歳暮は贈っても良いのだろうか?」という疑問を持たれるかもしれません。
お中元やお歳暮は日頃の感謝の気持ちを表すものなので、忌中・喪中でも贈って差しつかえありません。
ただし、のし・水引きは避け、白短冊のほうが無難とされています。
まとめ
今回は忌中・喪中の意味とその期間中に控えるべきことを解説しました。
忌中・喪中の過ごし方に関しては知っておくべきしきたりやルールがあります。
しかし、大切なのはあくまでも故人様を偲ぶ気持ちです。
どうすれば良いか迷った時は、ご自身の気持ちを大切に、ご家族やご親戚とよく話し合って決められてはいかがでしょうか。
平安祭典では、ご葬儀・ご供養に関する各種ご相談を承っています。神戸・阪神間でお困りごとがございましたら、平安祭典(0120-00-3242)まで気兼ねなくご相談ください。
続きはこちら
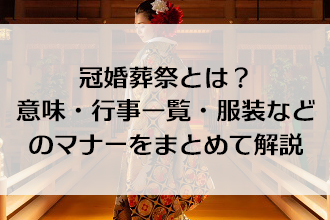
公開日:2023年10月2日
「冠婚葬祭」は、多くの方が人生の中で経験することではないでしょうか。
とはいえ、冠婚葬祭の意味やマナーを詳しく知らず、ご葬儀などへ参列される際に「この服装で良いのかな?」「マナー違反をしていないかな?」など、不安を感じる方もいらっしゃるはずです。
そのような方のために、当記事では冠婚葬祭の意味、どのような行事があるか、服装などのマナーをまとめて解説します。
[@目次@]
冠婚葬祭とは?4文字が持つ意味と行事について
冠婚葬祭とは、古来の四大礼式のことです。
人生の節目に行なわれる通過儀礼の全般を指す言葉で、冠・婚・葬・祭の4文字それぞれに違う意味があり、行事も様々です。
冠婚葬祭にはお金がかかるものですが、将来の冠婚葬祭に備えて掛け金を積み立てを行なう「互助会」というシステムがあります。
正式名称を「冠婚葬祭互助会」と言い、毎月一定額の掛け金を払い込むことにより、契約金額に応じたサービスを受けられるものです。
互助会については###gojyokai_toha###で解説しておりますので、詳細を知りたい方はぜひご覧ください。
それでは、冠・婚・葬・祭それぞれの意味と行事について見ていきましょう。
「冠」の意味と行事
「冠」とは、本来は元服(げんぷく)と呼ばれる成人の儀式のことです。
元服は冠をかぶって行なわれたため、「冠」という字が使われます。
元服は、古来中国における成人儀礼を起源とし、明治以前の日本でも子どもが親の保護下から離れ一人前の大人になることを宣言する儀式として行なわれており、現在の成人式にあたります。
他にも「お宮参り」「お雛祭り」「端午の節句」「七五三」と、子どもの健やかな成長を願う行事があります。
また、年を重ねてからも「還暦」「古希」など、長寿を祝うしきたりが数多く存在し、出産から長寿まで人生のおめでたい行事を指します。
「婚」の意味と行事
「婚」とは、文字通り結婚式のことです。
結婚式は、全くの他人であった2人が、人生を共にすることを誓う契りの儀式で、規模にかかわらず、冠婚葬祭の中で最も慶祝されるべき行事です。
結婚後25年目に行なう「銀婚式」や50年目に行なう「金婚式」など、結婚した後にも夫婦の絆を祝うための記念行事があります。
「葬」の意味と行事
「葬」とはご葬儀の意味で、ご葬儀は「葬送儀礼」の略です。
ご葬儀は、仏教・神道・キリスト教などの宗教儀礼に則って行なわれる「葬儀式」、その後に行なわれる故人様との最期のお別れである「告別式」があります。
ただし、現在では「葬儀式」と「告別式」はひとまとめに考えられることが多く、一般的には「葬儀・告別式」と案内されます。
ご葬儀には、お通夜を行なわない「一日葬」、ご家族や親戚などが中心に参列する「家族葬」、故人様とゆかりのある方々が集まる「一般葬」、参列者の多い「社葬・大型葬」などがあり、その規模は様々です。
とはいえ、どのようなご葬儀であっても、故人様への「たむけの心」を表し、弔う行事であることに変わりはありません。
平安祭典がどのようなご葬儀をお手伝いできるかについては、『ご葬儀の種類・費用』のページでご紹介しています。
ご関心をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧いただけますと幸いです。
###sougi_nagare###でも、ご葬儀について詳しく解説しております。
「祭」の意味と行事
「祭」とは、本来は順調な狩猟や豊作を願い、長寿や健康を祈るための宗教的儀式でした。
時代の移り変わりと共に意味合いが変化しており、現在は「年中行事」と認識されています。
年中行事の例としては、「お正月」「節分」「お雛祭り」「お彼岸(春秋)」「花祭り」「端午の節句」「母の日」「父の日」「七夕」「お盆」「敬老の日」「文化の日」などがあり、祝日とされているものも少なくありません。
昨今は核家族化が進んだことにより、ご家族やご親戚が集まる機会は減っています。
しかし、日本ならではの四季を皆で集まって楽しむ機会として、「祭」の価値を再認識することも必要ではないでしょうか。
冠婚葬祭に適した服装は?
続いては、冠婚葬祭に適した服装について解説します。
結婚式とご葬儀に分けて、男女別の服装をご確認ください。
■ 結婚式(男性)
・新郎や新郎新婦の父…正礼装(せいれいそう)
・主賓や親族など…モーニングやタキシード、ブラックフォーマルスーツ
・一般ゲスト(友人や同僚など)…ブラックスーツ
■ 結婚式(女性)
・新郎新婦の母親や親族の既婚女性(着物の場合) …黒留袖(既婚女性の正礼装)、色留袖(既婚女性の祝儀用の第一礼装)
・未婚女性(着物の場合) …振袖(未婚女性の正礼装)
※大振り袖は避け中振り袖や小振り袖を選ぶ
※洋装であればワンピースやツーピースを選ぶ(膝が隠れるほどの丈で露出を控え目にする)
■ ご葬儀(男性)
・故人様から三親等までのご親族(正喪服)…和装なら黒紋付き羽織袴、洋装ならモーニング
・参列者(準喪服)…ブラックフォーマルスーツ
・参列者(略式喪服)…黒を基調としたスーツ
■ ご葬儀(女性)
・故人様から三親等までのご親族(正喪服)…黒無地着物
・参列者(準喪服)…フラックフォーマルスーツ(ワンピースやアンサンブル)
・参列者(略式喪服)…黒を基調としたワンピースやアンサンブル
ご葬儀での服装に関して、故人様から三親等までのご親族は正喪服を着用することが望ましいとされます。しかし、現在は準喪服や略式喪服の着用が主流です。
ご葬儀における服装について詳しく知りたい方は、###sougi_midashinami###をぜひご覧ください。
冠婚葬祭について知っておきたいマナー
ここからは、社会人として知っておきたい冠婚葬祭のマナーをご紹介します。
冠・婚・葬・祭の4つに分けて、内祝い・結婚祝い・御香典・お年玉に関するマナーをご確認ください。
冠:内祝い
内祝いとは、本来は身内のお祝いという意味で、家庭内での祝いごとの際にご近所や親戚に贈るものでした。
しかし、現在はいただいたお祝いに対するお返しとして、贈ることが増えています。
※当記事では「お返し」としての内祝いについて説明していきます。
■ 内祝いを送る祝いごとの例
・結婚
・出産
・初節句
・新築
・快気
■ 内祝いの贈り方
・結婚祝いは入籍1ヶ月以内に贈る
・出産祝いはお宮参りのすぐ後に贈る
・のし紙をかけ、のしには「内祝い」や「寿」と書く
・お礼状を添える
■ 内祝い(お返しとして)の相場
・いただいたお祝いの半分~1/3程度の金額の品物
婚:結婚祝い
結婚祝いは、入籍したご夫婦へのお祝いです。
結婚式に参列する際のご祝儀が結婚祝いにあたりますが、最近は結婚式や披露宴を行なわない方も増えています。
そのような場合でも、仲の良い友人やお世話になっている知人が入籍をされた際は、結婚祝いをされると良いでしょう。
■ 結婚祝い(ご祝儀)の渡し方
・のし紙をかけ、のしには「寿」や「壽」、「御結婚御祝」と書く
・袱紗(ふくさ)と呼ばれる布に包んで持参する
■ 結婚祝い(ご祝儀)の相場
・新郎新婦の友人や知人、同僚などの場合は3万円ほど
・新郎新婦の兄弟姉妹や叔父、叔母の場合は5万円~10万円ほど
参考サイト:祝儀(結婚祝い)等に関するアンケート調査(平成29年度) | 一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会
葬:御香典
御香典とは、本来は故人様に線香や花を供えることでした。
現在ではご遺族を経済的に助ける慣習として、御香典をお渡しすることが通例です。
「香」という字は線香を意味するため、御香典という言葉は仏式でのみ使用されます。
■ 御香典の渡し方
・白無地の袋に白黒の結び切りの水引の不祝儀袋に入れて持参する
・袋には「御香典」または「御仏前(浄土真宗の場合)」と薄墨で書く
・中袋の裏面に金額、住所、名前を書く(金額は旧字体で書く)
■ 御香典の相場
・故人様が友人や知人、同僚などの場合は5千円~1万円
・故人様がおじやおばの場合は1万円~3万円
・故人様が兄弟姉妹(義理の兄弟姉妹も含む)の場合は3万円~5万円
・故人様が両親(義理の両親も含む)の場合は5万円~10万円
御香典の相場や渡し方などのマナーについては、以下の記事でも解説しています。
###kouden_manner###
###sougi_noshi###
祭:お年玉
お年玉とは、お正月に歳神(としがみ)を迎えるための鏡餅のことだったそうです。
そのお餅を家長が子どもに分け与える習慣が変化し、現在はお正月にお金を渡す習慣を「お年玉」と呼ぶようになりました。
■ お年玉の渡し方
・ポチ袋に入れて渡す
・新札を入れる
・親がいる前で渡す
・4千円台の金額を避ける(「4」が忌み数なので)
■ お年玉の相場
・小学生未満…2千円
・小学生…3千円~5千円
・中学生…5千円
・高校生…5千円もしくは1万円
・大学生、専門学生、社会人…1万円
参考サイト:お年玉に関するアンケート調査 | 足利銀行
足利銀行が行なったアンケート調査によると、お年玉の相場は上記の金額だそうです。現金で渡さない場合は、図書券などの金券や品物を渡しても構いません。
まとめ
当記事では、冠婚葬祭の意味や行事、マナーについて解説しました。
冠婚葬祭は人生の節目に行なわれる通過儀礼ですから、参列される際などはその意味やマナーを理解しておきたいものです。
平安グループでは、「冠婚葬祭のトータルプランナー」として、次のような業務を行なっています。
■ 冠婚
・エスタシオン・デ・神戸:結婚式や成人式の衣裳レンタル
・株式会社 平安(ふれあい推進係):平安会員様へ賀寿(がじゅ)のお祝いを実施
■ 葬祭
・平安祭典:ご葬儀や法事・法要の施行
葬祭についてはもちろん、冠婚についてもお役に立てるところがあるかと存じます。
冠婚葬祭についてのお困りごとなどがございましたら、平安グループ各社にご相談ください。
【葬祭】
平安祭典 TEL 0120-00-3242 受付時間 24時間年中無休
平安祭典 法要受付 TEL 0120-18-4142 受付時間 9:00~17:00
【冠婚】
エスタシオン・デ・神戸 TEL 078-371-5111
受付時間 11:00~19:00 休館日:毎週火曜日
衣裳レンタル シンデレラ TEL 078-371-3701
受付時間 11:00~18:00(※土日祝は10:00~19:00)
【その他】
本社 TEL 078-351-1001 受付時間 9:00~17:30 休業日:土日祝
続きはこちら
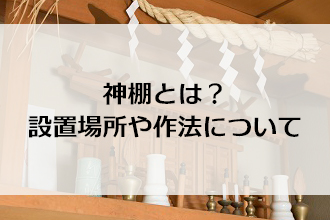
公開日:2022年4月11日
皆さまは「神棚」をご存知でしょうか?
ご自宅に仏壇と神棚、両方を設置されているご家庭も多いことと思います。
一方で、ご自宅を新築なさるなどして、これから設置しようというご家庭もあるかもしれません。
身近にご先祖を感じることができる場所だからこそ、神棚の設置場所や方角、作法など基本的な知識は知っておきたいですよね。
そこで今回は、神棚に関するあれこれをご紹介します。
そもそも神棚とは?
神棚とは、神道(しんとう、しんどう)において神様を祀るための棚で、家や企業の事務所などに設置されているもので、神社同様にとても神聖な場所です。
棚の上に置かれた札宮(ふだみや)の中には、神社でいただいた御神札(おふだ)を納め、毎日参拝し、神様に感謝の気持ちを示します。
また、古来から日本では、ご先祖の霊をご供養することで、ご先祖が神となり子孫を守ってくれるという考えがあります。
そのため神棚で神様を祀ることで、ご先祖を祀る意味にもなるとされています。
神棚はどこに祀るか?祀るのに適した方角は?
ご自宅を新築した際などに、神棚を購入し、家の中のどこに祀るか悩まれる方もいらっしゃるかもしれません。
神棚は清浄かつ明るく静かな部屋の高い所に祀ります。
いつも綺麗にし、日当たりが良く人が集まりやすいリビングや和室などが良いでしょう。
方角は、太陽の光が多くあたるとされる南、もしくは東が神棚の正面と向き合うように祀ります。
人の出入りがあるドアの上や、不浄とされるトイレと背中合わせになっている場所、仏壇と向かい合わせになるような配置はできる限り避けます。
仏壇と同じ部屋に祀ること自体は問題ないのですが、どちらかを拝もうとすると、どちらかにお尻を向けてしまうことになりますので、向かい合わせにならないよう気を付けてください。
高さは、天井近く(私たちの目線より高い場所)に祀ります。
もちろん、家の造りなど様々な事情で、上で記したような高さのない場所に神棚を祀らなければならないこともあるでしょう。
しかし、大切なのはお祀りする気持ちなので、絶対に避けなければならないということではありません。
なお、神棚を新しく設置する際は、大安などの吉日に行なうと良いとされています。
神棚の上に付ける「雲板」「雲文字」とは?
二階建ての一軒家やマンションで、神棚を祀る部屋の上にさらに部屋があり、人が神棚の上を歩く可能性がある場合、神棚の上には「雲」をかたどった木製の飾り「雲板」や、紙に「雲」と書いた飾り「雲文字」を付けます。
「雲」を付けることで、神様に「神棚の上には何も存在しませんよ」「失礼はありませんよ」と伝えることになります。
なお、「雲」の代わりに「天」や「空」の文字を用いるケースもあります。
御神札(おふだ)の納め方
御神札とは、神様の御霊(みたま)が宿ったご分霊であるとされており、神社の名前やご祭神の名前が記されています。
御神札は神社の社務所や札所で頒布されています。
神棚の札宮に納める御神札には、神宮大麻(じんぐうたいま=伊勢神宮の御神札)や氏神札(地元の氏神様の御神札)、崇敬神社(すうけいじんじゃ)の御神札などがあります。
御神札は、新年のタイミングで一年に一度、新しいものに取り替えましょう。
古い御神札は、年末年始に神社内の古札収所、あるいは古札受付などと書かれた場所に返納します。
返納した御神札は神職がお焚き上げをしてくれます。
神具の設置方法と神棚のお供え、お参りの作法
神棚には、札宮以外にも神具(しんぐ)を設置します。
主な神具には、神鏡(しんきょう)、皿、水玉、榊立(さかきたて)、瓶子(へいし、へいじ)があります。
主な神具
・ 神鏡
札宮の扉の前に祀ります。
・ 皿
洗米や塩を乗せるための器です。
洗米は向かって中央、塩は向かって右に置きます。
・ 水玉
水を入れてお供えします。
お供えする時はふたをとって向かって左に置きます。
・ 榊立
榊を左右1本ずつお供えします。
・ 瓶子
御神酒をお供えするための器です。
ふたをとって左右1本ずつお供えします。
神様へのお供えのことを神饌(しんせん)と呼び、毎朝、神棚にお供えをします。
榊は毎月1日、御神酒とともに新しいものに取り替えると良いとされています。
神様の御霊(みたま)が宿ったご分霊であるとされる御神札が納められている神棚は、家の中にある神社です。
神棚のお参りの作法は、神社の参拝の作法と同様に「二拝二拍手一礼」が基本となります。
「神棚封じ」とは?
神道では死を穢(けが)れと見なします。
これは「気枯れている状態」のことで、不浄・汚れていることではありません。
この「穢れ」に触れぬよう、ご自宅に神棚がある場合、ご家族にご不幸があった際には「神棚封じ」を行ないます。
神棚封じとは、白布や半紙を貼り、神棚を隠すことです。
「神棚封じ」の手順
・ 神棚封じはご遺族ではなく、(穢れが及んでいない)第三者が行なう
・ 神棚に挨拶をし、亡くなった方の氏名を伝える
・ 神棚の榊や御神酒、お供え物を下げる
・ 神棚の扉を閉め、白布や半紙を貼り神棚を隠す
・ 神道における忌中の期間は50日なので、50日間神棚封じを行なう
神棚封じの期間はお供えを控えます。
失礼に当たると思う方もいるかもしれませんが、穢れがある状態で神棚に触れることのほうが良くないこととされています。
ご家族にご不幸があった際には、ご葬儀の準備とともに神棚封じを忘れずに行ないましょう。
神棚は神様を祀る大切な場所
いかがだったでしょうか。
今回は神棚に関するあれこれについてご紹介しました。
ご先祖を祀る仏壇同様に、神棚は神様を祀る大切な場所です。
また、冒頭でも述べた通り、古来から日本では、ご先祖の霊をご供養することで、ご先祖が神となり子孫を守ってくれるという考えがあります。
もし、ご家庭に神棚がなければ、一度お祀りすることをご検討されてみても良いかもしれません。
平安祭典では、神戸・阪神間でのご供養に関するご相談を承っております。
気兼ねなくお問い合わせください。(0120-00-3242)
続きはこちら
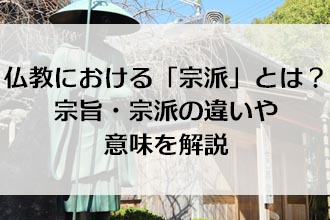
公開日:2022年3月21日
2018年にNHKが実施したアンケート調査によると、日本人が信仰する宗教は「仏教」 が31%、「神道」 が3%、「キリスト教」 が1%、「信仰する宗教なし」 が62%だったそうです。(その他:1%、無回答:2%)
ご葬儀を仏式で行なう方が多い中で、「仏教」の31%は、少ない印象を受けます。
「信仰する宗教なし」 と回答した方の多くは、実際には仏教を信仰しているかもしれませんね。
ところで、日本人の多くが信仰している仏教には、ご存知の通り、多くの宗派(しゅうは)があり、古くからある伝統的な仏教だけでも「十三宗五十六派」が存在します。
そこで今回は、この「十三宗五十六派」、そして日本の仏教の代表的な「十三宗」についてご紹介します。
「宗旨」と「宗派」の違いと仏教における歴史
「宗旨」は宗教の教えや教養そのものを、「宗派」は各宗教から生じた分派を意味しています。
日本の伝統的な仏教には、「十三宗五十六派」が存在します。
「十三宗」とは、法相宗、律宗、華厳宗、真言宗、天台宗、日蓮宗、浄土宗、浄土真宗、融通念仏宗、時宗、臨済宗、曹洞宗、黄檗宗のことです。
「五十六派」とは、これらの十三宗から教義・信仰対象などの違いや歴史的経緯により生じた五十六の分派のことです。
一方で、「十三宗五十六派二十八宗派」という呼び方もあります。
これは1940年4月に「宗教団体法」が施行され、宗教団体は認可制となり、五十六派が合同した二十八宗派が認可を取得したことに由来します。
仏教の代表的な「十三宗」
日本の伝統的な仏教である「十三宗」ですが、それぞれの特徴について見てみます。
奈良仏教系
・ 法相宗(ほっそうしゅう、ほうそうしゅう)
開祖:玄奘三蔵(三蔵法師)
本尊:唯識曼荼羅(ゆいしきまんだら)
長い時間をかけ、段階を経て修行を行なうことで成仏に至ると考える。
また、念仏や題目を唱える、坐禅を行なうなど、ひとつの行だけに専念するのではなく、様々な行を推奨する。
遣唐使の僧により日本に伝えられる。
興福寺、薬師寺が本山。
・ 律宗(りっしゅう)
開祖:鑑真和上
本尊:盧舎那仏(るしゃなぶつ)
「戒律」、すなわち自発的に規律を守ろうとする心のはたらきを指す「戒」と、他律的な規則を指す「律」の研究と実践を主とする。
日本には鑑真(がんじん)が伝えた。
唐招提寺が本山。
・ 華厳宗(けごんしゅう)
開祖:杜順
本尊:毘盧舎那仏(びるしゃなぶつ)
毘盧舎那仏とは、明るい光を放つ仏で、毘盧舎那仏の光明により迷っている人々を浄土である華厳世界に導くとされる。
「華厳経」を経典とし、大乗仏教の中でも哲学的で独特な教えを持つ。
聖武天皇が建立した東大寺(奈良の大仏=盧舎那仏像で有名)は、近代以降は華厳宗を名乗る。
密教系
・ 真言宗(しんごんしゅう)
開祖:空海(弘法大師)
本尊:大日如来
空海が唐の都・長安で学んだ密教を基盤とする。
大日如来をすべての根本と考える。
人の心のあり方や価値観などを10の段階に分け、最終的に大日如来と同レベルに達することを説く。(「十住心思想」)
密教系+法華系
・ 天台宗(てんだいしゅう)
開祖:最澄(伝教大師)
本尊:お釈迦様、薬師如来など
中国で学んだ最澄により日本に伝えられた密教。
朝は法華経の南無妙法蓮華経を唱え、夕方は阿弥陀経の南無阿弥陀仏を唱えるという「朝題目夕念仏」という言葉があるが、「妙法蓮華経(法華経)」を根本仏典とする。
天台宗から多くの日本仏教の宗旨が発展した。
比叡山延暦寺が本山。
法華系
・ 日蓮宗(にちれんしゅう)
開祖:日蓮(立正大師)
本尊:お釈迦様、大曼荼羅、日蓮聖人
鎌倉時代中期に日蓮が興す。
本尊・題目・戒壇を三大秘法とし、題目(「南無妙法蓮華経」)を唱えること(唱題)を重視している。
「南無妙法蓮華経」とは「妙法蓮華経(法華経)に帰依する」という意味。
法華宗とも称する。
浄土系
・ 浄土宗(じょうどしゅう)
開祖:法然(円光大師)
本尊:阿弥陀様
鎌倉仏教のひとつ。
修行の価値を認めず、修行による成仏を否定し、念仏を唱えることを重視する。
念仏を唱えることで極楽往生に至ると考える。
・ 浄土真宗(じょうどしんしゅう)
開祖:親鸞(見真大師)
本尊:阿弥陀様
法然の教えを親鸞が継承し発展させる。
人が求めなくとも阿弥陀様が救って下さる、いずれ仏になることが約束されているから、改めて修行する必要はないという教え。
・ 融通念仏宗(ゆうづうねんぶつしゅう)
開祖:良忍(聖應大師)
本尊:十一尊天得如来(中央に阿弥陀様、周囲に10体の菩薩)
毎日何度も念仏を唱えることが修行の中心となる。
一人一人の祈りが全ての人の為となり、全ての人の祈りは自分のためになるという教えを持つ。
華厳宗の影響を受ける。
・ 時宗(じしゅう)
開祖:一遍(証誠大師)
本尊:阿弥陀様または南無阿弥陀仏の書
阿弥陀様を信じる信じないを問わず、仏の本願力は絶対であるがゆえに、念仏さえ唱えれば往生できると説く。
禅宗
・ 臨済宗(りんざいしゅう)
開祖:栄西(千光法師)
本尊:定めはないがお釈迦様が多い
師から弟子への悟りの伝達(法嗣、はっす)を重んじる。
座禅を組みながら師と弟子が問答を繰り返す「看話禅(かんなぜん)」で有名。
ちなみに、「ソモサン(什麼生)」「セッパ(説破)」で知られるアニメの一休さんは、室町時代に実在した臨済宗の僧侶・一休宗純をモデルとしている。
鎌倉幕府、室町幕府という時の政権との結び付きが強く、室町文化の形成にも多大な影響を与えた。
鎌倉時代には上級武士の間で支持された。
・ 曹洞宗(そうとうしゅう)
開祖:道元(承陽大師)
本尊:お釈迦様
「看話禅」の臨済宗とは異なり、黙して坐禅に徹する「黙照禅」で各自が悟りを開いてゆく。
鎌倉時代には地方の武士や一般市民の間で支持された。
・ 黄檗宗(おうばくしゅう)
開祖:隠元(真空大師)
本尊:お釈迦様
江戸時代初期に来日した明末の僧、隠元が開祖。
教義・修行・儀礼・布教などは日本の臨済宗と変わらないが、儀式の形式や使われる言葉は中国・明時代の様式。
ご葬儀では宗旨・宗派の確認を
今回は、仏教における「十三宗五十六派」、日本の仏教の代表的な「十三宗」についてご紹介しました。
宗旨・宗派が異なると、御香典の表書きの書き方や線香の作法も異なる場合もあります。
そのため、ご葬儀に参列なさる際には、喪家の宗旨・宗派の確認をしておきたいところです。
御香典については###kouden_manner###で詳しく説明しています。
平安祭典では神戸・阪神間での仏事に関するご相談を承っております。
気兼ねなくお問い合わせください。(0120-00-3242)
続きはこちら
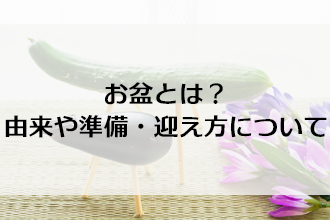
更新日:2026年1月11日 公開日:2021年7月19日
お盆の時期には帰省をして、お墓参りをされる方も多いのではないでしょうか。
日本人にとって大切な年中行事のひとつであるお盆は、故人様やご先祖の霊魂があの世の世界(浄土)からこの世(現世)に戻って来るとされる期間です。
2026年のお盆は、8月13日(木)~8月16日(日)までの4日間です。
お盆の期間中、ご自宅に故人様やご先祖の霊魂をお迎えして、ご供養を行ないます。
今回は、お盆の由来や初盆(新盆)のご法要、お盆の準備・迎え方など、お盆に関する知識をご紹介します。
お墓参りについては###hakamairi_timing###で詳しくご説明しております。
お盆の由来
まずは、お盆の由来についてご紹介しましょう。
お盆は、旧暦7月15日を中心に7月13日~16日の4日間に行なわれる、仏教行事の「盂蘭盆会(うらぼんえ)」に由来するとされています。
「盂蘭盆会」を省略して「お盆」と呼ぶようになったそうです。
なぜ「盂蘭盆会」が旧暦7月15日を中心とした期間に行なわれたのかは、お釈迦様の弟子であった目連(もくれん)の伝説が関係しているのだとか。
目連(もくれん)は、亡くなった自身の母親が餓鬼道に落ちたと知りました。
お釈迦様に相談したところ、「大勢の修行僧が修業を終える7月15日に修行僧にご馳走をふるまえば、功徳により母親も救われるであろう」とおっしゃったのだとか。
目連がお釈迦様の言葉通りのことを実践すると、母親は救われ極楽往生を遂げる…。
これが目連の故事です。
お盆の中でも特別な初盆(新盆)
お盆の中でも、特別なものとされているのが、故人様が亡くなった後の四十九日(忌明け)後に初めて迎えるお盆です。
あの世へと旅立った故人様が初めてご自宅に帰ってくる日であるため、手厚くご供養を行ないます。
四十九日(忌明け)後に初めて迎えるお盆は、地域によって呼び方が異なり、
初盆(はつぼん、ういぼん)、または新盆(にいぼん、しんぼん、あらぼん)と呼ばれます。
また、四十九日(忌明け)の前にお盆が来る場合は、翌年のお盆が初盆(新盆)となります。
初盆(新盆)のご法要
初盆(新盆)は、ご家族だけで行なう場合もあれば、ご親族や故人様と親しかった知人などを招いてご法要を行なう場合もあります。
ご親族などをお招きするのであれば、遅くとも1か月前には案内状を送って詳しい日時などをお知らせしましょう。
初盆(新盆)のご法要は、宗派によって違いがあるものの、通常はご寺院をご自宅などに招いて読経してもらいます。
お盆の時期はどのご寺院も大変忙しいので、遅くとも初盆の1か月前、できれば2か月前には連絡を入れ、あらかじめ日時を決めておきましょう。
初盆(新盆)で聖職者にお渡しする御布施の相場は約1万円~3万円です。
通常のお盆の御布施(約5千円~1万円)よりも多めにお包みします。
場合によって御車料と御膳料を別途お包みします。
また、初盆(新盆)では、絵柄のない白提灯を飾ります。
この提灯は初盆が終わったら送り火で燃やすか、精霊送りにします。ご寺院に納めることもあるようです。
お盆の準備・迎え方
お盆の時期に行なうことには、どのようなことがあるでしょうか。
仏壇の掃除、精霊棚(盆棚)・盆提灯を飾る
仏壇の掃除が終わったら、精霊棚(盆棚)・盆提灯を飾ります。
浄土真宗では、精霊棚(盆棚)・盆提灯を飾る習慣はありません。
故人様が魂となってお盆の時期に帰ってくるという考えがないからです。
精霊棚(盆棚)とは、ご先祖の霊を迎えるための棚のことです。
経机(きょうづくえ)などの台の上に真菰(まこも)で編んだゴザを敷き、位牌、三具足(燭台、花立て、香炉)の他、精霊馬(しょうりょううま=きゅうりの馬やなすの牛)やお供え物を置きます。
精霊棚(盆棚)の脇には盆提灯を置き、お盆の期間中には灯りをつけておきます。
初盆であれば絵柄のない白提灯、初盆以外であれば、絵柄のある提灯を飾ります。
ご先祖のお迎えとお見送り
8月13日の夕方に迎え火を焚いてご先祖の霊魂を迎えます。
その後、お盆の期間中に、ご寺院にお経をあげてもらい、ご供養を行ないます。
8月16日の夕方には送り火を焚いて、ご先祖の霊魂をお送りします。
お墓参り
お墓参りは、地域や宗派によっても違いますが、一般的にお盆初日の8月13日に行なうのが良いとされています。
お盆の風習は地域によって異なることも
いかがだったでしょうか。今回は、お盆の由来やお盆の時期、初盆(新盆)のご法要、お盆の準備・迎え方など、お盆に関する知識をご紹介しました。
お盆の迎え方は地域によって異なります。もし、疑問に思うことがあれば、ご寺院や地域の葬儀社にご相談されてみてはいかがでしょうか。
平安祭典では神戸・阪神間での初盆(新盆)、お盆のご準備などに関するご相談を受け付けております。
気兼ねなくお問い合わせください。
平安祭典祭典でお葬式をされていない方のご法要も承ります。
《平安祭典法要受付》
フリーダイヤル 0120-18-4142 (受付 9:00~17:00)
もしくは下記フォームからお申し込みください。
お問い合わせ、ご予約の際は「平安祭典のホームページを見た」とお伝えください。
※年末年始は休業(12/30~1/3)
続きはこちら
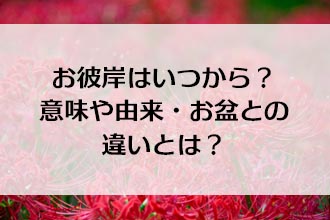
更新日:2026年1月11日 公開日:2021年3月15日
「暑さ寒さも彼岸まで」という慣用句を、皆さまもよくご存知ではないでしょうか。
皆さまは、お彼岸にはお墓参りをするかと思います。でもいったいなぜ、お彼岸にお墓参りをするのでしょうか。今回は、お彼岸の意味や由来、お彼岸のお墓参りなどについて、ご説明します。
[@目次@]
お彼岸の意味と由来、お盆との違いは?
お彼岸とは、仏教とともに古代インドから伝わった考え方です。お彼岸の語源は、菩薩(ぼさつ)が仏になるために行なう修行を指す仏教用語、「波羅蜜(はらみつ)」と同じ意味を持つ「到彼岸(とうひがん)」を由来とする言葉です。
仏教では、私たちのいる煩悩や迷いに満ちた世界を「此岸(しがん)」、ご先祖のいる悟りの世界(極楽)を「彼岸(ひがん)」と呼びます。
「到彼岸」とは、此岸から彼岸に至ることと解釈され、此岸にいる私たちが修行を積むことで、彼岸という悟りの境地に到達できると考えられています。
浄土思想では、極楽浄土は西方にあるとされています。太陽が真東から昇り真西に沈む春分の日と秋分の日は、此岸と彼岸が最も通じやすい日とされ、両日に先祖供養を行なうようになりました。これが、お彼岸にお墓参りをする由来とされています。
ちなみに、お彼岸の初日を「彼岸の入り」、終日を「彼岸の明け」、そして、太陽が真東から昇り、真西に沈む春分の日と秋分の日を「彼岸の中日」と呼びます。
お彼岸とお盆は、お墓参りをするという点はよく似ています。
しかし、此岸の私たちが彼岸のご先祖に近づき、感謝を伝えるお彼岸と、彼岸のご先祖が此岸に帰ってこられるのをお迎えするお盆では、意味が異なります。
お盆に関しては###obon_toha###の記事で詳しくご説明しております。
2026年のお彼岸はいつ?
お彼岸とは、季節の節目となる、日本の年中行事の1つです。春分の日、秋分の日を中日(”なかび”もしくは”ちゅうにち”)に、前後3日、合計7日間が、それぞれ春のお彼岸、秋のお彼岸の期間となります。
ちなみに春分の日は「自然を称え、生物を慈しむ日」、秋分の日は「ご先祖を敬い、亡くなった人々を偲ぶ日」として、国民の祝日に定められています。
2026年の春のお彼岸は、3月17日 彼岸入り、3月20日 中日(春分の日)、3月23日 彼岸明け。
秋のお彼岸は、9月20日 彼岸入り、9月23日 中日(秋分の日)、9月26日 彼岸明けとなります。
彼岸会(ひがんえ)とは?
彼岸会という言葉についてもご説明します。
彼岸会とは、春のお彼岸、秋のお彼岸、それぞれ7日間に行なわれる法会(ほうえ=仏法を説くためやご供養を行なうための僧侶・信徒の集まり)のことです。
ご寺院では、ご先祖をご供養する法要が執り行なわれ、信徒は彼岸会の期間中にご寺院を詣で、お墓参りをするのが習慣となっています。
彼岸会では中日にご先祖に感謝し、残る6日は悟りの境地に達するのに必要な6つの徳目「六波羅蜜(ろくはらみつ=悟りの彼岸に至るための6つの修行徳目)」を1日に1つずつ修めるとされています。
お彼岸のお墓参りと初彼岸
お彼岸にご寺院へお墓参りに出かける場合、いつ行けば良いという決まりはありません。お彼岸の期間中であれば、いつお墓参りをされても構いません。
普段のお墓参り同様に、ご先祖や故人様を偲び、ご供養する気持ちが大切です。
また、故人様が初めてのお彼岸(初彼岸)を迎えられる際には、手厚いご供養を心がけましょう。故人様の初彼岸には、ご自宅にご寺院を招いてお経をあげていただくと良いでしょう。祝日にあたる春分の日、秋分の日を利用して、年忌法要を行なう方もいらっしゃいます。
ご自宅のお仏壇へのお供え
お彼岸中、ご自宅のお仏壇には、お花や果物や甘い菓子、精進料理などをお供えします。小豆(あずき)を原材料とするお団子や、春のお彼岸には”ぼたもち”、秋のお彼岸には”おはぎ”などがお仏壇にお供えされます。
ちなみに”ぼたもち”と”おはぎ”は基本的には同じものです。季節の花(牡丹と萩)にちなんで、それぞれ呼び方が異なっています。
ちなみに、”ぼたもち”は、牡丹の花に似せて丸くて大きく、”おはぎ”は、萩の花のように小ぶりでほっそりと作るのだとか。
諸説ありますが、”ぼたもち”と”おはぎ”の原料である小豆は、古くから邪気を払う食べ物として信じられてきたため、”ぼたもち”と
”おはぎ”は、お彼岸中にご先祖をご供養する食べ物として定着したそうです。
お彼岸は、故人様やご先祖に想いを馳せる貴重な機会
いかがだったでしょうか?今回は、お彼岸の意味や由来、ご自宅のお仏壇へのお供えなどについて、ご説明しました。お彼岸は、故人様やご先祖に想いを馳せる貴重な機会です。ご家族でお仏壇を掃除したり、お墓参りに行かれてはいかがでしょうか。
お墓参りに関しては###hakamairi_timing###の記事で詳しくご説明しております。
神戸・阪神間でご葬儀・ご法要に関してお困りごとがありましたら、
平安祭典(0120-00-3242)まで気兼ねなくお問い合わせください。
続きはこちら