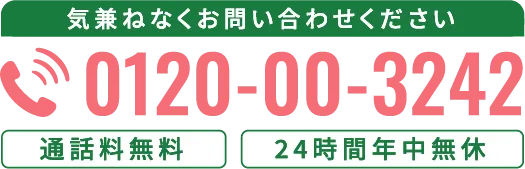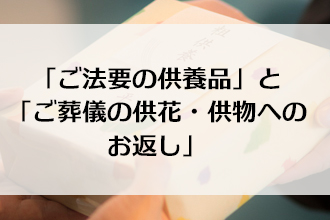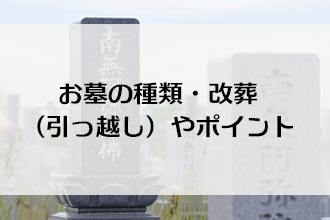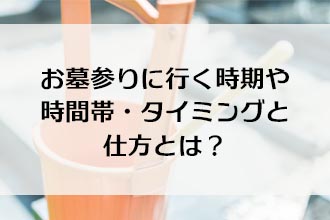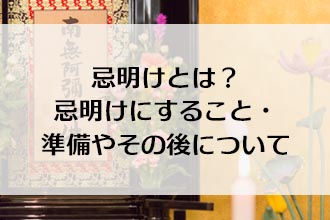開眼供養に必要な準備とは?御布施の表書きや当日の流れを解説

公開日:2022年9月19日
新たにお墓を建てたり、仏壇や位牌を購入した際は、「開眼供養」を行ないます。
とはいえ、そういった経験は何度もあることではないため、開眼供養についてよくご存じない方が多いのではないでしょうか。
そこで当記事では、開眼供養について詳しく解説します。
新しくお墓や仏壇、位牌の購入を検討される際の参考になさってください。
[@目次@]
開眼供養は魂を入れる大切な儀式

開眼供養とは、お墓、仏壇、位牌などを新しく購入した際に、魂を込める儀式のことです。
ご寺院の読経により魂を込めることで、墓石や仏壇(ご本尊)、位牌などが、ただの物からご供養すべき対象となります。
開眼供養の歴史は古く、東大寺が建立されたとき、最後に大仏の目を入れてご法要を行なったことに由来するそうです。
なお、開眼供養の読み方は「かいげんくよう」です。
ほかにも開眼法要(かいげんほうよう)、入仏法要(にゅうぶつほうよう)、入魂式(にゅうこんしき)、御魂入れ(みたまいれ)、お性根入れ(おしょうねいれ)、魂入れ(たましいいれ)、などと呼ばれることもあります。
開眼供養の準備で必要なことは?
開眼供養の対象がお墓か仏壇か、また、ご法要を同時に行なうかなどの条件で、日程や規模が異なります。
特にご法要を同時に行なう場合は、参列者も多くなることが多いので、念入りに準備をしておきましょう。
ここからは、開眼供養の準備について詳しくご説明します。
開眼供養の日程や当日の流れを決める

開眼供養を行なう日取りに決まりはありませんが、忌明けなどのご法要と同時に行なうことも多いです。
また、開眼供養を行なう場合は、会場や流れを決める必要があります。
というのも、お墓の開眼供養はお墓で行ないますが、位牌や仏壇の開眼供養は、ご自宅やご寺院、会館などで行なうこともあるからです。
ご寺院や会館で行なう場合は、使用料が必要になることも覚えておきましょう。
さらに、開眼供養をどのような流れで行なうか事前に決めておくことも大切です
お墓の開眼供養と法要を同時に行なうのであれば、ご自宅やご寺院で法要を行なった後、お墓へ移動する必要があります。
会食を予定しているなら、どのタイミングで会食するかなどもあわせて検討しておくと良いでしょう。
ご寺院の都合もあるため、早めに日程や流れを相談されるようおすすめします。
開眼供養にお呼びする方を決める

開眼供養に誰をお呼びするか決まりはありませんが、ご法要と同時に行なう場合はご家族・ご親族などをお呼びすることが一般的です。
ご法要は別日に行ない、お墓や仏壇の開眼供養のみを行なう場合は、ご家族だけのごく少数で行なうことも多いです。
開眼供養にお呼びする方が決まったら、日時・場所・会食の有無を、1か月前を目安にお知らせします。
出欠の返事は2週間前を目安に設定すると、会食や供養品の準備がスムーズに行なえるでしょう。
会食・供養品(粗供養)の準備をする

開眼供養の終了後、会食を行なう場合は、会場や料理を手配します。
自宅で会食をする場合、仕出し弁当などを手配することが一般的です。
また、参列された方にお渡しする供養品(粗供養)も手配しておきます。
供養品については、『「ご法要の供養品」と「ご葬儀の供花・供物へのお返し」』で詳しくご説明しています。
御布施の準備をする

御布施の相場は、宗旨・宗派、地域によって様々なうえ、ご寺院のお考えによって金額が決まっていることもあります。
おおよその目安として、以下の金額をご紹介しますので、ご参考としてお役立てください。
・ お墓の開眼供養(納骨も含む)
目安:30,000円~50,000円
水引:紅白
表書き:開眼供養御礼
※浄土真宗のみ建碑法要御礼

・ 仏壇の開眼供養
目安:20,000円~30,000円
水引:紅白
表書き:開眼供養御礼
※浄土真宗のみ入佛慶讃御礼
位牌の開眼供養の場合は個別には用意せず、忌明け法要(四十九日法要)の御布施に含んで渡すことが多いです。
ご供養なのに紅白の水引を使用することに驚かれた方もいらっしゃるかもしれませんが、開眼供養は慶事(お祝いごと)です。
法要を同時に行なう際は、不祝儀袋の御布施もあわせて用意が必要です。
御布施については『【お布施の相場】ご葬儀・法要の際の一般的な金額は?』でもご紹介しています。
喪服の準備をする

開眼供養と法要や納骨を同時に行なう場合は、喪服や準喪服を着用します。
開眼供養のみの場合は、男性は地味な色のスーツに黒のネクタイや靴、女性は無地の地味な色のスーツまたはワンピースに黒の小物を揃えると良いでしょう。
供花・供物の準備をする
供物は、普段仏壇に供えているものと同じでかまいません。
供花は日持ちがしないので、直前に購入すると良いでしょう。
なお、仏壇の開眼供養の際には、赤いロウソクが必要なことが多いです。
赤いロウソクは普段あまり見かけませんが、仏具店などで取り扱っています。
開眼供養当日の流れについて

お墓の開眼供養の場合、当日の流れの一例は以下の通りです。
・ 供花・供物の準備
特別な準備は必要なく、通常のお墓参りと同じでかまいません。
開眼供養が始まる前にお供えしておきます。
↓
・ 除幕
竿石に巻かれた布を取ります。
この布は、開眼供養前のお墓を邪気から守るために巻かれているものです。
↓
・ 読経・焼香
ご寺院の読経の間、順番にお焼香をあげます。
↓
・ 法要後の片付け
供物や線香の灰など、全てきれいに片づけます。
お墓参りについて、詳しくは『お墓参りに行く時期や時間帯・タイミングと仕方とは?』もご覧ください。
開眼供養に呼ばれたら何が必要?

開眼供養に呼ばれた場合は、喪服や御香典の準備をします。
一般的に、参列者を呼ぶ場合は開眼供養と同時に法要を行なうことが多いですが、開眼供養のみか、法要を同時に行なうかを確認のうえ、準備をしてください。
まず服装についてはご遺族と同じで、忌明け法要や納骨を同時に行なう場合は、喪服や準喪服を着用しましょう。
開眼供養だけの場合は、男性は地味な色のスーツに黒のネクタイや靴、女性は無地の地味な色のスーツまたはワンピースに黒の小物を揃えると良いでしょう。
服装については『ご葬儀での服装をご遺族側・喪主側にわけて解説!身だしなみのマナーもご紹介』でも解説しています。
御香典については、次のように準備をしましょう。
・ 法要も同時に行なう場合
水引:黒白、黄白、双銀(銀一色)
表書き:御仏前
※関西地方では特に、黄白の水引を使用することが多いです。

・ 開眼供養のみの場合
< お墓の開眼供養 >
水引:紅白
表書き:建碑御祝
< 仏壇の開眼供養 >
水引:紅白
表書き:開眼御祝または開眼供養御祝
開眼供養とご法要を同時に行なう場合、多めに包まれる方もいらっしゃいますが決まりはなく、参列者の考え方次第です。
御香典について詳しく知りたい方は『御香典の知識・相場・マナー』をご覧ください。
まとめ

当記事では開眼供養についてご紹介しました。
開眼供養とは、ご寺院の読経により魂を込める重要な儀式です。
開眼供養を行なうことで、お墓や仏壇を、故人様を偲ぶ場として引き継いでいけるでしょう。
平安祭典(0120-00-3242)では法要のご相談も承っております。気兼ねなくご相談ください。