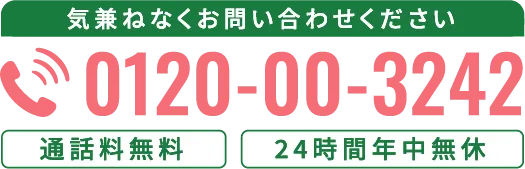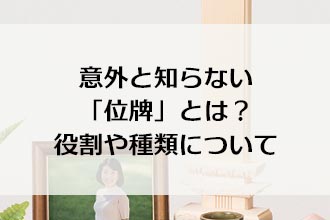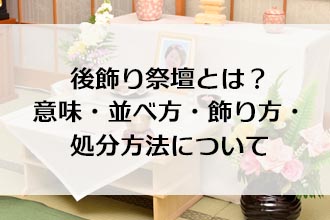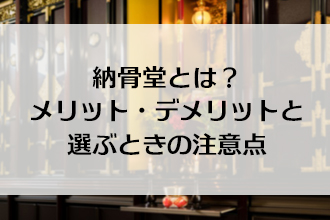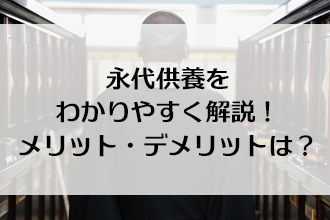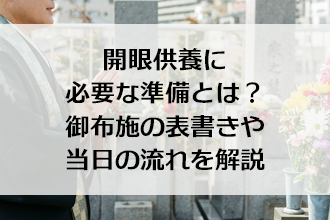【仏壇選びの注意点】ご先祖との対話に適した仏壇を選ぶには?

更新日:2024年9月21日 更新日:2023年4月2日 公開日:2022年9月26日
仏壇は、日本人にとって身近なものといえるでしょう。
しかし、いざご自宅に仏壇が必要となったら「どうやって選べば良い?」「仏具の飾り方は?」といった疑問が出てきますよね。
そこで今回は、仏壇の役割と選び方、必要な仏具と飾り方などについて解説します。
[@目次@]
仏壇の役割・準備する時期とは?
そもそもなぜ仏壇が必要なのでしょう。
あわせて、仏壇の役割や仏壇を準備する時期についてご説明します。
仏壇の役割とは?

仏壇には3つの役割があります。
① 仏様(本尊)を祀り、祈る場所
仏壇とは本来、仏様を祀る台を意味します。
ご寺院にある仏壇(内陣)を模したもので、家の中の「小さなお寺」のような存在です。
家庭における信仰の中心として、日々、仏様に祈りを捧げる場です。
② ご先祖を祀る場所
仏壇はご先祖を祀り、ご供養をする場です。
日々のお参りを通してご先祖とのつながりを感じられ、ご先祖によって受け継がれた命の大切さや感謝を感じることができます。
また、ご家族が亡くなった時は、弔い上げをするまでは故人様のご供養の場でもあります。
③ 悲しみを癒す場所
大切な方が亡くなった時の喪失感と悲しみは、とても大きなものです。
だからこそ、多くの人にとって、仏壇の前で故人様のために祈ったり、故人様と対話をしたりすることで、心の癒しにつながります。
仏壇は、大切な方を偲び、悲しみを癒す「グリーフケア」の場でもあるのです。
いつまでに仏壇を準備する?
ご家族が亡くなり、ご自宅に仏壇がない場合は新たに購入します。
仏壇は忌明け(四十九日)までに準備しましょう。
新しい仏壇を整えたら、一般的には忌明け法要の際にご寺院に開眼供養(本尊や位牌に魂を込める儀式)をしていただきます。
たいていの場合、仏壇は注文から納品までに3週間程度かかることが多いです。
商品によってはそれ以上かかる場合もあるため、早めに検討し始めると安心でしょう。
仏壇選びで大切な4つのポイント
仏壇には、さまざまな種類やデザインがあります。
ここでは仏壇を選ぶにあって大切な4つのポイントをご紹介します。
① 宗派を確認する

仏壇や仏具の種類は宗派によって異なります。
事前に宗派の確認をしておくと良いでしょう。
以下に代表的なものをご紹介します。
・ 八宗用

仏壇の形が八宗(天台宗・真言宗・浄土宗・浄土真宗本願寺派・真宗大谷派・臨済宗・曹洞宗・日蓮宗)共通で、最も多く使用されています。
禅宗様式の須弥壇(しゅみだん)で、宮殿の屋根は千鳥破風・軒は唐破風が一般的です。
・ 西本願寺用

浄土真宗本願寺派(西本願寺)用で、宮殿の屋根は破風・軒は唐破風・柱は金箔です。
・ 東本願寺用

浄土真宗大谷派(東本願寺)用は、宮殿は東本願寺阿弥陀堂を模し、屋根が二重唐破風・柱は黒塗りです。
・ 日蓮正宗用
須弥壇の上に厨子(ずし)を置き、厨子に開閉できる扉つきです。
仏壇に祀る位牌も宗派による決まりごとがありますので、注意が必要です。
位牌については『意外と知らない「位牌」とは?役割や種類について』で詳しく解説しています。
② 仏壇の配置場所や向きを決める

仏壇を選ぶにあたって、まず仏壇を置く場所を決めなければなりません。
以下の点をふまえて検討すると良いでしょう。
・ 向き(方角)
仏教では仏様はどの方角にもいらっしゃるとされるので、仏壇を置く向きに特別な決まりや吉凶はありません。
しかし、一般的には真北を避けて配置する方が多いようです。
また、最適な方角とは諸説あります。どうしても気になるという方は、下記を参考にしてください。
【南面北座説(なんめんほくざせつ)】
お仏壇が北を背にして、南を向くように安置します。
南向きだと直射日光が当たらず、風通しもよく湿気も防げることから、最適とされてきました。
※主な宗派…曹洞宗・臨済宗
【本山中心説(ほんざんちゅうしんせつ)】
仏壇の前で合掌して拝む方向の延長線上に家の宗派の本山がある位置に置きます。
宗派の本山が京都にある場合、関東の居住者と中国・九州の居住者では向きが逆になります。
※主な宗派…真言宗
【西方浄土説(さいほうじょうどせつ)】
古くから極楽浄土は、西方浄土と呼ばれ西にあると信じられてきました。
そのため、東を向くように安置すると、拝むために西方浄土に向かって礼拝できるため最適であるという考え方です。
※主な宗派…浄土真宗・浄土宗・天台宗
・ 避けるべき場所
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、冷暖房の風が直接当たる場所は避けます。
また、同じ部屋の中に神棚がある場合、向いあわせとなる場所や神棚の真下は避けたほうが良いとされています。
・ お参りのしやすさ
動線の悪い場所に仏壇を置くと、日々のお参りがしにくくなってしまうため、ご家族がお参りしやすい場所を選びましょう。
③ 仏壇の種類(デザイン)を決める

配置スぺースの高さ、幅、奥行きを測り、仏壇の種類(上置きタイプ、床置きタイプなど)とサイズを決めます。
代表的な仏壇の種類(デザイン)は次の通りです。
配置スぺースおよび部屋のインテリアなどにあわせて選びましょう。
・ 家具調仏壇 床置きタイプ

機能的でモダンなデザインの仏壇で、洋室にも和室にもマッチします。
広いリビングルームにも置け、存在感があります。
・ 家具調仏壇 上置タイプ

モダンで、かつコンパクトサイズの仏壇です。
インテリアになじみやすく置く場所を選びません。
・ 唐木仏壇 床置きタイプ

黒檀や紫檀など唐木材の美しい木目を生かし、職人がつくり上げる伝統的な仏壇です。
仏間や床の間にも配置でき、格式と存在感が際立ちます。
・ 唐木仏壇 上置きタイプ

伝統的で格式のある唐木仏壇をコンパクトにした仏壇です。
家具の上など小さなスペースにも配置できます。
・ 金仏壇(塗り仏壇) 床置きタイプ
全体に黒の漆塗りを施し、内部には金箔が施された仏壇です。
仏間や床の間にも配置でき、豪華で威厳を感じさせます。
・ 金仏壇(塗り仏壇) 上置きタイプ
伝統的で豪華な金仏壇をコンパクトにしたタイプで、家具の上など小さなスぺースにも配置できます。
・ 神徒壇(しんとだん)
神道においてご先祖や故人様の霊璽(れいじ)を祀るもので、床置きタイプと上置きタイプがあります。
御霊舎(みたまや)、祖霊舎(それいしゃ)、祭壇宮(さいだんみや)とも呼ばれます。
④ 仏壇の予算(値段)を決める

仏壇の価格は宗派、種類、材質、サイズなどにより、数万円から数百万円とかなり幅があります。
また、仏具店によっても価格設定は異なります。
以下の点を考慮しながら、予算を決めると良いでしょう。
・ 原材料や工法による価格の違い
仏壇に使われる木の種類は、黒檀、紫檀、桑、ウォールナットなどです。
高級な木材を使っていれば、それだけ高価になります。
また、表面の工法も無垢、厚板貼り、薄板貼り、木目調プリント、着色仕上げなどさまざまです。
風合いや色合いを実際に見て確認すると安心でしょう。
・ デザインによる価格の違い
デザインが複雑な仏壇、細かい装飾が多い仏壇など、職人の手間がかかっているものほど高価になります。
・ 仏具の価格
仏具も購入する必要がある場合は、仏壇と仏具をあわせて予算を考えましょう。
セット価格を設けている仏壇店が多いので、内容と価格をよく確認してください。
ほとんどの方が、一度購入した仏壇と一生お付き合いします。
ご希望とご予算に応じて慎重に選ぶことをおすすめします。
仏壇の購入場所については、ご利用された葬儀社で仏壇・仏具を扱っている場合、扱いのない場合も、仏壇・仏具専門店をご紹介いただけることが多いです。
現在は仏壇のインターネット通販も可能ですが、葬儀社や専門店では「実物を見て選べる」「専門家に相談できる」「アフターフォローが受けられる」といったメリットがあります。
仏壇には何を置く?必要な仏具と飾り方

仏壇には、一般的に以下の「六具足」と呼ばれる仏具が必要です。
・ 仏飯器
・ 茶湯器
・ 花立
・ ロウソク立て
・ 香炉
・ 線香差
仏壇・仏具店などでは多くの場合、セット販売されています。
ちなみに、五具足というのは上記から線香差を除いたものです。高月(高杯)は仏壇を購入すると付いてくることが多いですが、ない場合はお皿やお盆で代用していただいてもかまいません。
また、「おりん」と「りん棒」は六具足には含まれていませんが、宗派にあったものが必要です。
次に、仏具の基本的な飾り方をご紹介します。
宗派によっては異なる部分もありますので、それぞれの宗派の飾り方(祀り方)に準じてください。
ご不明なことはご寺院や仏壇・仏具店へご確認ください。
・ 最上段の中央に本尊を祀る
・ 本尊の左右に宗祖名・号の描かれた掛け軸をかける
・ 位牌は本尊より一段低い場所に安置する(ご本尊が隠れないように左右のどちらかに置く)
・ 次の段の中央に仏器膳を置き、仏飯器・茶湯器を置く
※家具調仏壇の場合は仏器膳は置かないことがほとんどです。
・ 仏器善の左右に高月(高杯)を置く
・ 最下段には花立、香炉、ロウソク立て(火立)、マッチ消、おりんなどを置く
まとめ

仏壇は仏様を祀り、ご先祖や故人様をご供養する場であるとともに、大切な人を失った悲しみを癒す役割も担います。
新たに仏壇を購入する際は、忌明け法要までにご準備できるよう、早めに検討し始めることをおすすめします。
宗派、設置場所、デザイン、予算などをふまえてよく検討し、納得のいく仏壇選びをしましょう。
平安祭典では、各種ご相談を承っています。
神戸・阪神間でお困りごとがございましたら、平安祭典(0120-00-3242)まで気兼ねなくご相談ください。