

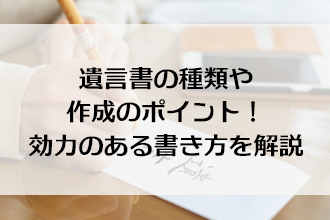
公開日:2021年9月6日
終活の一環として遺言書を残される方は年々増えています。
遺言書と聞くと、書き方が難しいとか、自分には財産がないので必要ないと敬遠される方も多いかもしれません。
しかし、ご遺族が相続のトラブルに巻き込まれないためにも、遺言書は作っておく方が安心です。
今回は遺言書の書き方、種類や作成の際のきまり、実際に起きたトラブルなどをご紹介していきたいと思います。
遺言書とは?
遺言(ゆいごん、いごん、いげん)とは、日常用語としては形式や内容にかかわらず
広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいう。
日常用語としてはゆいごんと読まれることが多い。
このうち民法上の法制度における遺言は、
死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をいい、
法律上の効力を生じせしめるためには、
民法に定める方式に従わなければならないとされている(民法960条)。
法律用語としてはいごんと読まれることが多い。
引用:wikipedia 「遺言」
遺言書は故人様がご遺族に向けた最後の意思表示です。遺言書があれば、ご遺族が相続を巡ってトラブルになるような事態を回避することができます。
ご遺族が遺産相続で争うのは悲しいことですので、ご自身のため、ご遺族のために遺言書を書いておくことをおすすめします。
遺言書2種類の特徴を比較
遺言書は大きく分けて自筆証書遺言・公正証書遺言の2種類があります。
それぞれの特徴やメリット・デメリットについてご紹介していきます。
自筆証書遺言
ご自身が自筆にて便箋などの紙に遺言内容を記載する遺言書です。
ご自身が記載しただけのものであっても、記載方法が正しければ有効です。
「相続トラブルになる可能性は低いけれども、念のために作成しておこう」とお考えの方の多くは自筆証書遺言で作成される傾向があります。
しかし、十分な知識なく作成したために無効になる、あるいは争いに発展するケースもあるので注意が必要です。
※現在では、作成した自筆証書遺言を管轄する法務局に持参すると保管してくれる制度ができています。
公正証書遺言
事前に専門家に相談し、専門家と遺言の原案を作成する遺言書です。
その際に遺言の有効性や、考えられる将来のトラブルについての対策もしっかりと把握して作成します。
→原案が完成すると、担当専門家が公証人と原案について協議する。
→公証人役場に出向き、その場で遺言書を作成する。
専門家や公証人が関与するので、無効やトラブルに発展する可能性が極めて低くなります。トラブルが想定されるケースなどでは、公正証書遺言を作成しておくことが望ましいです。
専門家の報酬は事務所により様々ですが、一般的には10万円~20万円ほどでしょう。
遺言書の書き方・注意点
遺言書は不備があると無効になるため、書き方には注意を払わなければいけません。
一般的な遺言書の書き方と注意点についてご紹介していきます。
遺言書の書き方と注意点
・ 表題をつける
遺言であることがわかるよう、記載することをおすすめします。
・ 誰に何を相続させるかはっきりと記載する
戸籍に書かれた正確な氏名、続柄や生年月日を記載します。(愛称などは無効)
・ 不動産の場合は登記簿通りに記載
正確に特定された記載をします。
・ 預金の場合は、金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号を明記する
預貯金は変動する可能性があるので、金額は明記しなくても問題ありません。
・ 遺言執行者を指定できる
遺言執行者を指定することで、手続きがスムーズに進みます。
・ 付言(ふげん)事項で想いを伝える
相続人に遺したい言葉、相続の意図などを記載します。
・ 日付を記入し、署名・捺印をする
日付が特定できない、署名・捺印のない場合は無効になります。
よくあるトラブルや失敗談
遺言書に関する失敗談やトラブルについて、いくつか事例をご紹介します。
遺言書を見つけて勝手に開封してしまった
遺言書を勝手に開封してしまった場合、5万円以下の罰金を科せられる可能性があります。これは民法1004条で遺言書の検認が定められているためです。
もし見つけたとしても勝手に開封するようなことはせずに専門家にご相談ください。
文字が読めなくて無効になった
文字の癖が強い方が書いた遺言書は解読できない場合があります。
そういった場合、鑑定に出す必要がありますが、それでも解読できない場合は無効になります。
ビデオレターで遺言を残してしまった
映像を残すのが簡単な今の時代ですが、法律上映像での遺言は無効になります。
遺言を残す際は遺言書として紙で作成しましょう。
日付が曖昧で無効に
作成日を令和〇〇年〇月吉日のように曖昧な日付で書いてしまった場合、遺言書は無効になります。
しっかりと特定できる日付を記載するようにしましょう。
まとめ
今回は遺言書についてご紹介しました。終活で遺言書の作成を検討されている方も多いと思います。
ご自身のためにも、ご遺族のためにも正しい遺言書を作成して相続のトラブルなどが起こらないようにしましょう。
相続については###souzoku_tetuduki###で詳しくご説明しております。
神戸・阪神間で終活や遺言書のことでお悩みの方は、下記まで気兼ねなくお問い合わせください。
あさひ行政書士法人(0120-4864-65)
無料相談受付時間 9:00~18:00
行政書士オアシス相続センター (078-251-1414)
無料相談受付時間 9:00~18:00
お問い合わせの際には、「平安祭典のホームページを見た。」とお伝えください。
続きはこちら
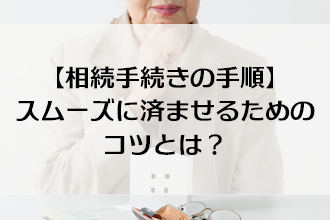
公開日:2021年8月23日
ご家族が亡くなると、非常に多くの手続きが必要となりますが、その中でも特に慎重に行なう必要があるのが相続の手続きです。
何度も経験することではありませんので、どのように相続の手続きを進めれば良いかわからない方も多いかと思います。
今回は相続について、基本的なことや手続きの手順などをご紹介します。
手続きの期限が過ぎてペナルティを受けたり、遺産相続を巡ってトラブルに発展したりすることがないように、一通り知った上で手続きを進めていきましょう。
相続とは?
相続とは、被相続人が生前に所有していた財産を相続人が引き継ぐことを言います。
相続の対象となるのは、不動産、預貯金・株・投資信託などの金融資産、自動車や宝石、絵画などの動産、それに借入金などの負債です。
相続人は、配偶者、子、両親、兄弟姉妹などで、相続順位や相続分も民法で定められています。
ただし、被相続人が生前に遺言書を作成・指名をされていた場合は、その他の方にも引き継ぐことができます。
相続の流れ・手順
その中でも相続に関する手続きは、怠ると手続きが複雑化する、あるいは不利益を被る場合があるので、注意が必要です。
それでは相続の流れをひとつずつ確認していきましょう。
① 遺言書の確認
故人様が遺言書を残していないかを確認します。
鑑定が必要な場合もありますが、公正証書遺言であれば偽造のリスクはほとんどありません。遺言書が有効な場合は、⑤の遺産分割協議は不要です。
遺言書の種類や書き方に関しては###yuigonsyo_kakikata###の記事で詳しくご説明しております。
② 財産リストの作成
相続の対象となる財産を全て洗い出します。
資産が多岐にわたる場合、リスト化に時間を要するため、早めに取り掛かる方が良いでしょう。
③ 相続人の調査・確認
故人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍謄本を収集します。相続人が何名存在しているかの証明として必要になります。
そして証明された法定相続人全員の現在戸籍と住民票(本籍地記載のもの)を収集します。これにより、法定相続人の氏名・続柄・住所が明確になります。
④ 相続放棄(遺産放棄)の検討
財産のうち資産(プラス)と負債(マイナス)の割合によっては、相続放棄も検討する必要があります。
相続放棄とは、資産より負債の方が多い場合に、家庭裁判所に申立てすることにより負債の弁済義務を負わなくて済む制度です。ただし、すべての財産を放棄することになるので、財産を相続することもできません。財産はもらうが、負債は負わないということはできません。
⑤ 相続財産の名義変更
相続人が確定したら、相続財産の名義変更を行ないます。
相続財産の名義変更には、手続きの種類により③の戸籍一式をはじめとする様々な添付書類が必要です。
また相続財産を法定相続人で、どのように分割するのかを話し合い、合意した証明として《遺産分割協議書》が必要となります。
この書類にすべての相続人が署名をし、実印を押印し、印鑑証明書を添付しなければなりません。
不動産の名義変更や預金・株・投資信託の名義変更、解約もこれらの書類が必要です。
1人でも実印の押印を拒否した場合は、遺産分割協議では手続きできないので、家庭裁判所で調停の手続きに移ります。遺産分割協議が難航した場合、時間を要します。従って、手続きはできるだけ早期に着手することをおすすめします。
⑥ 相続税の申告
遺産を相続する場合、相続税が発生します。純資産額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告が必要です。
※詳しくは下記「相続税はいくらから?」でご説明します。
以上が遺産相続に関する流れです。聞きなれない難しい言葉が多いかもしれませんが、ひとつずつ進めていきましょう。
相続税はいくらから?
相続する各人の「課税価格の合計額」が基礎控除額※を上回ると、その額に応じて相続税がかかります。
相続の純資産額が基礎控除額を超える場合、故人の死亡から10ヶ月以内に相続税の申告および納税が必要です。
相続税のボーダーラインとなる基礎控除額の計算方法は以下の通りです。
※3,000万円+600万円×法定相続人の数=相続税の基礎控除額
例えば法定相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円までが申告不要となります。(約9割の方が申告不要に該当します)
相続に関するトラブル
遺産相続はトラブルの原因となることが多く、仲の良い家族だったとしても争いに発展してしまう場合があります。
相続に関するトラブルの例をご紹介しますので、事前に対策をしておきましょう。
● 生前に被相続人の面倒を見た人が、寄与分が欲しいと言ってきた
被相続人の介護を行なっていた相続人がいるような場合に起こりえるトラブルです。
例えば、数名いる相続人のうち1人だけが被相続人の近くに住んでおり、生前に介護などを行なっていたため、寄与分※を主張するといったケースです。
遺産分割協議で合意を得られなかった場合、トラブルになる可能性があります。
※寄与分とは…民法第904条の2
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
● 遺言書の内容によってはトラブルになる可能性も…
被相続人が遺言書を作成していたとしても、その内容によってはトラブルに発展する可能性があります。
例えば、遺言書の内容が
・ 相続人の1人にすべての財産を相続させるとしたもの
・ 第三者にすべての財産を遺贈するとしたもの
があげられます。
これらは遺留分※を無視した極端な例ですが、一般的にも遺留分を超えて記載された遺言書はトラブルになる可能性があります。
※遺留分…遺留分とは、相続人に法律上保証された一定の割合の相続財産をいいます。この場合の相続人とは配偶者又は子(場合によっては直系尊属)に限られます。
● 被相続人に離婚歴がある場合、前妻は相続人になる?
被相続人に離婚歴がある場合、前夫や前妻には相続する権限はありませんが、その子は法定相続人となり、遺産を相続する権利があります。
また子が未成年の場合、離婚した前妻(前夫)が法定代理人として遺産分割協議に参加する場合があります。こういった場合トラブルになりやすいので、注意が必要です。
このようなケースでは、事前に遺言書を作成しておくことが重要です。
トラブルのリスクを的確に考慮した遺言書があれば、遺産分割協議が不要なので、無駄な争いを回避できます。
いくつかのケースをご紹介しましたが、相続でトラブルになることは非常に多く、決して他人事ではありません。慎重に進めていきましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか?今回は相続に関する手続きの流れをご紹介しました。
遺産相続はトラブルに発展しやすいため、非常に慎重に進める必要があります。
少しでも不安がある方は専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
神戸・阪神間で相続のことでお悩みの方は、下記まで気兼ねなくお問い合わせください。
あさひ行政書士法人(0120-4864-65)
無料相談受付時間 9:00~18:00
行政書士オアシス相続センター (078-251-1414)
無料相談受付時間 9:00~18:00
お問い合わせの際には、「平安祭典のホームページを見た。」とお伝えください。
続きはこちら
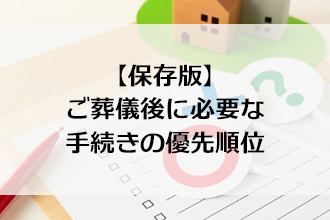
更新日:2025年5月8日 公開日:2021年8月16日
大切な方を亡くされたご遺族の悲しみは計り知れません。しかし、ご葬儀後には様々な手続きを行なわなければなりません。
期限がある手続きなどもあるので、スムーズに進めたいところですが、どう進めれば良いかわからない方も多いかと思います。
今回はチェックリストを確認しながら、ご葬儀後に必要な手続きや優先順位についてご紹介していきたいと思います。
ご葬儀後に必要な手続き一覧チェックリスト
ご葬儀後に必要な手続きは一般的にどういったものがあるのでしょうか?
下記に必要な手続き一覧をご用意しましたので、チェックリストとしてご活用ください。
【ご葬儀後に必要な手続き一覧チェックリスト】
※死亡届の提出および死体埋火葬許可証申請は、死亡を知った日から7日以内の申請が必要ですが、ご葬儀時に届け出は完了しているので省略。(通常、葬儀社が代行)
※手続きの内容は故人様が世帯主、世帯主以外、会社員、年金生活者、就学者など状況に応じて異なります。詳しくは役所や関係各所にご確認ください。
ご葬儀後の手続きで優先順位の高いものは?
チェックリストを見ていただけると、お分かりになるかもしれませんが、ご葬儀後の手続きのすべてを速やかに終わらせる必要はありません。
優先順位の高い、期限の早いものから順に行なっていけば問題ありません。
後々税金や給付金関係のトラブルに発展しないよう、優先順位の高い手続きや期限をしっかりと確認しておくと良いでしょう。
特に優先順位の高い手続きは以下のとおりです。
・ 公的年金受給停止
・ 介護保険資格喪失届
・ 後期高齢者医療資格喪失届
・ 世帯主の変更届
・ 障害者手帳の返却
・ 公共料金(電気・水道・ガス)の名義変更または解約
・ 携帯や電話加入権の名義変更または解約
これらの手続きは期限が14日以内のものが多く、速やかに済ませる必要があります。またこれらは比較的容易な手続きが多く、ご自身で手続きを進めやすい点が特徴です。
該当する項目があれば、優先して手続きを行ないましょう。
専門家のアドバイスが必要な場合も
ご葬儀後の手続きの中でも相続に関する手続きは、慎重に行なわなければなりません。具体的には不動産や預金・株・投資信託・自動車などの資産の名義変更です。
また場合によっては、専門家のアドバイスが必要になることもあります。
例えば
・ 遺言書がある
・ 遺産分割の話し合いがまとまっていない、あるいはまとまりにくい
・ 相続人が複数人いる
・ 相続人が遠方にいる、あるいは海外在中
・ 相続人が未成年
・ 相続人の中に連絡がとれない人がいる
・ 相続税申告の手続きがある
・ デジタル遺産があり、詳細が不明
このような場合、専門家に相談されることをおすすめします。
後々トラブルに発展しないためにも、速やかに専門家に相談して確実に手続きを済ませる方が安心でしょう。
相続については###souzoku_tetuduki###で詳しくご紹介しております。
まとめ
いかがだったでしょうか?
今回はご葬儀後の手続きについてご紹介しました。
ご葬儀後に行なわなければならない手続きは非常に多いので、優先順位を考えて手続きを済ませていきましょう。
また、相続関係の手続きは慎重に行なう必要があり、場合によっては専門家のアドバイスが必要になります。
神戸・阪神間で遺産相続や財産管理、死後事務のことでお悩みの方は、下記まで気兼ねなくお問い合わせください。
あさひ行政書士法人(0120-4864-65)
無料相談受付時間 9:00~18:00
行政書士オアシス相続センター (078-251-1414)
無料相談受付時間 9:00~18:00
お問い合わせの際には、「平安祭典のホームページを見た。」とお伝えください。
続きはこちら
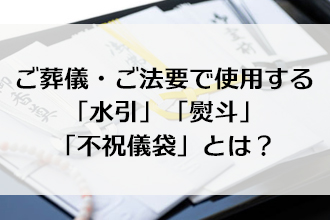
更新日:2021年12月8日 公開日:2021年8月9日
ご葬儀やご法要には、様々なマナーやしきたりがあります。
今回は、ご葬儀やご法要で必要となる「水引(みずひき)」「熨斗(のし)」「不祝儀袋(ぶしゅうぎぶくろ)」についてのお話です。
水引や熨斗にはどのような意味があり、どのような種類があるのか、不祝儀袋を使用する際の書き方などについてご説明します。
「水引」とは?「水引」の意味と種類
「水引」とは、祝儀袋や不祝儀袋といった包み紙を結ぶ紙紐のことです。
水引の起源には諸説がありますが、一説には、飛鳥時代に遣隋使として派遣された小野妹子が帰国した際、同行した隋の使者の貢ぎ物に、紅白の麻紐が結ばれていたことが始まりとされています。
水引の色や本数には意味があります。慶事の水引は赤白、金銀などに奇数の本数、弔事は黒白、双銀、黄白などに偶数の本数です。また、結び方にも意味が込められ、目的によって異なります。
水引の結び方の一例
《結び切り(真結び)》
中央で固く結び、一度結ぶと解くことが難しい「結び切り」は、「二度と繰り返したくない」という願いが込められた結び方です。結婚、お見舞い、葬儀などに用いられます。
《あわじ結び》
「あわじ結び」も、簡単には解けない結び方です。中央に輪を作り、両端を持って引っ張ると、「結び切り」よりも強く結ばれます。輪の部分が「鮑(あわび)」に似ていることから、「あわび結び」とも言われます。慶事、弔事、いずれも使用可能です。
《蝶結び(花結び)》
何度でも解いて結びなおすことができるため、「何度繰り返しても嬉しいこと」に用います。出産、長寿、開店などに用いられます。
「熨斗」とは?ご葬儀・ご法要で使用する「のし紙」とは?
「熨斗(のし)」は本来、祝儀袋の右上に付けられた小さな飾りを指します。「のし紙」とは、贈り物に掛ける「掛け紙」に「熨斗」と「水引」があらかじめ印刷された紙のことです。
昔は、熨斗ではなく、長寿の縁起物である「鮑(あわび)」が添えられていたのだとか。このような経緯、それから、殺生の観点からお供え物に生ものがふさわしくないこともあって、弔事には熨斗のついた、のし紙を用いることはありません。
供養品などの弔事の贈り物には、熨斗がない掛け紙である「弔事用のし紙」を使用します。
「表書き」の種類と書き方
弔事用のし紙の水引の上段には、贈る目的を示す「表書き」を記します。
香典返しの場合、宗旨を問わず使用可能な「志」と書くのが一般的ですが、関西地方では「満中陰志」と記すケースが多いようです(「満中陰」とは、人が亡くなってから四十九日目の忌明けを指す言葉です)。
ご法要で渡す品の表書きは、仏式は「粗供養」、神式は「偲び草」、地方によっては「茶の子」、「○回忌」などと記します。
水引の下段は、一般的には「○○家」「○○」(○○は喪家の姓)と記します。近年では、喪主の氏名をフルネームで入れるケースも見受けられるようになりました。
ご寺院にお礼をお渡しする際の不祝儀袋の書き方
不祝儀袋(ぶしゅうぎぶくろ)とは、香典袋とも呼ばれる、弔事の際に金品を包むための袋です。ご寺院にお礼をお渡しする際には、以下のような表書き・水引を用います。
《仏式のご葬儀の場合》
「御布施」…水引は銀一色または黒白
「御車料」「御膳料」…水引は黒白
《仏式のご葬儀後以降のご法要の場合》
「御布施」…水引は黄白または黒白
《仏式の納骨の場合》
「御布施」「御礼」…水引は黄白または黒白
御布施については###ofuse_manner###や、###ofuse_kingaku###で詳しくご説明しております。
お通夜、葬儀・告別式に参列する際の不祝儀袋の書き方
お通夜、葬儀・告別式に参列する際には、宗旨・宗派により水引と表書きは異なりますのでご注意ください。
《仏式の場合》
「御香典」「御霊前」…水引は黒白
《神式の場合》
「御玉串料」「御神饌料」「御榊料」…水引は黒白
《キリスト教式の場合》
「御花料」 …水引はなし
宗旨・宗派が分からない場合は「御霊前」としますが、仏式であっても、浄土真宗や曹洞宗では「御霊前」は用いず、「御仏前」を使用します。
ちなみに、忌明け以降のご法要の水引は、関西では黄白が一般的です。仏式のご法要の際の表書きは「御仏前」または「御供」とします。
表書きの下の部分には、包んだ方の名前をフルネームで書きましょう。連名の場合は、横並びで、立場の高い人から順に右から書いていきます。立場に差がない場合は五十音順で書きます。
夫婦の場合、夫は姓名、妻は名だけとします。また4名以上の連名の場合は、「○○一同」としましょう。記入の際は薄墨の筆ペン・サインペンを使うのがマナーで、ボールペンはマナー違反となるので避けましょう。
御香典については###kouden_manner###で詳しくご説明しております。
不祝儀袋の中袋の書き方
不祝儀袋の中袋の表には何も書かず、裏に香典の金額と住所、氏名を右から順に書きましょう。または、表の中央に金額を書き、裏の左側に住所、氏名を書くパターンもあります。金額は改ざんを防止するため、壱、弐といった大字で記入します。
お金を入れる時は、裏向きで入れて、肖像画が下になるようにします。新札を使うとあらかじめ準備していたことになるとされるため、あまりくしゃくしゃでない程度のお札を入れるのがマナーです。
新札しか用意できない場合は、長辺を縦に折って折り目を付けてから入れましょう。
水引・熨斗・不祝儀袋に関する知識は大人のマナー
いかがだったでしょうか。今回は、ご葬儀・ご法要で使う水引・熨斗・不祝儀袋についてご説明をしました。
水引・熨斗・不祝儀袋に関する知識は、大人のマナーでもあるので、覚えておいて決して損はありません。
平安祭典では、様々なご相談を受け付けています(0120-00-3242)。
神戸・阪神間で仏事に関するお困りごとがございましたら、気兼ねなくお問い合わせください。
続きはこちら
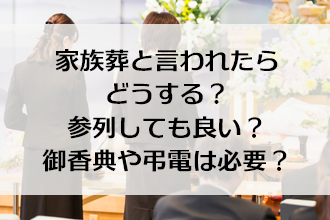
更新日:2023年11月6日 公開日:2021年7月26日
「家族葬」は一般的にはご家族やご親族を中心に、少人数で行なわれるご葬儀のことを言います。
その名前から、ご家族だけで行なうご葬儀と考えられることが多いですが、親しいご友人や故人様がお世話になった会社の方などが参列する場合もあります。
今回は家族葬における参列者の範囲や、御香典や弔電が必要かの判断についてご紹介します。
[@目次@]
家族葬に参列できる範囲は?
家族葬に参列して良いか、どう判断すればいいでしょうか?
基本的には、
・ 訃報に家族葬や参列辞退と言った旨の記載がある
・ 訃報にご葬儀の日時や葬儀場の記載がない
こういった場合は、参列は遠慮するのがマナーです。
故人様との関係が深かった方などは、ご葬儀に参列して故人様を見送りたいという想いもあると思いますが、基本的に家族葬は身内を中心に行なうご葬儀なので、参列についての確認連絡がない場合は、参列しない方が無難です。
家族葬に弔電は必要?
弔電とは、訃報を受けたが、通夜、葬儀・告別式に参列できない場合に、お悔やみの気持ちを伝える電報のことを言います。
家族葬であっても、訃報に弔電辞退の記載がなければ、弔電を送っても問題はないでしょう。
弔電の内容は、家族葬でも一般葬でも特に変わりはありません。
しかし、弔電辞退の案内があった場合は、弔電を送るのは失礼にあたります。故人様への哀悼の意を捧げたい気持ちも分かりますが、弔電辞退のご意向を汲んで弔電を送るのは控えましょう。
弔電については###chouden_toha###や###chouden_bunrei###で詳しくご説明しております。
家族葬の御香典 相場やマナーは?
家族葬でも、香典辞退のご意向が示されている場合を除いて、御香典は持参するのが基本的なマナーです。
また、家族葬における御香典の相場についても一般葬と同様です。
基本的な御香典の相場は以下のとおりです。
もし香典を辞退された場合は、御香典を持参する必要はありません。
訃報や葬儀案内で「香典辞退」の記載があれば、ご意向を汲んで御香典を渡さないのがマナーです。
無理に御香典をお渡しすると、香典返しを準備しなければならないので、ご親族に負担をかけてしまいます。
家族葬の場合、香典辞退されることもあるので、しっかり確認をしたほうが良いでしょう。
御香典の相場やマナーに関しては###kouden_manner####の記事で詳しくご説明しております。
家族葬を後日知った時は?
身内のみで家族葬を行なったあとに訃報を知らされることもあります。
ご葬儀には参列できなくとも、ご遺族に御香典を渡したい場合はどうすれば良いでしょうか?
基本的には御香典は直接手渡すのがマナーですので、ご自宅に弔問してお渡しします。
※弔問とはご遺族のもとを訪ね、お悔やみの言葉を伝えることです。
ここで大切なのは、 御香典を受け取ってもらえるのか、弔問しても大丈夫なのかということをご遺族にしっかり確認をすることです。
葬儀後は様々な手続きが必要で、ご遺族にとっては精神的にも肉体的にも負担の多い時期です。そんな中、時間を取ってもらうわけですので、ご遺族に十分配慮することを忘れてはなりません。
また、遠方に住んでいるなど、どうしてもすぐに弔問できない場合は御香典を郵送します。
御香典を郵送する際には、現金書留封筒に直接お金を入れるのではなく、不祝儀袋ごと封筒に入れ、必ずお悔やみの手紙も添えて送りましょう。
まとめ
今回は家族葬について、参列できる範囲や御香典、弔電などについてご紹介しました。
家族葬は一般葬と違う部分もありますが、故人様をお送りする大切なご葬儀であることには変わりありません。
無理に参列を希望したりはせず、御香典や弔電なども、ご遺族にしっかり確認したうえで送るようにしましょう。
大切なのは、ご遺族への十分な配慮を忘れないことです。
平安祭典ではすべての会館で家族葬を行なうことが可能です。詳細は下記のページをご覧ください。
平安祭典の家族葬
また、平安祭典では、神戸・阪神間での家族葬についてのご相談も承っております。
気兼ねなくお問い合わせください(0120-00-3242)
続きはこちら
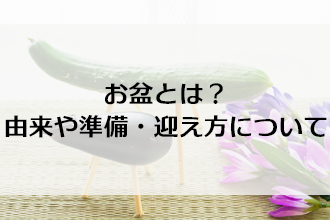
更新日:2025年4月25日 公開日:2021年7月19日
お盆の時期には帰省をして、お墓参りをされる方も多いのではないでしょうか。
日本人にとって大切な年中行事のひとつであるお盆は、故人様やご先祖の霊魂があの世の世界(浄土)からこの世(現世)に戻って来るとされる期間です。
2025年のお盆は、8月13日(水)~8月16日(土)までの4日間です。
お盆の期間中、ご自宅に故人様やご先祖の霊魂をお迎えして、ご供養を行ないます。
今回は、お盆の由来や初盆(新盆)のご法要、お盆の準備・迎え方など、お盆に関する知識をご紹介します。
お墓参りについては###hakamairi_timing###で詳しくご説明しております。
お盆の由来
まずは、お盆の由来についてご紹介しましょう。
お盆は、旧暦7月15日を中心に7月13日~16日の4日間に行なわれる、仏教行事の「盂蘭盆会(うらぼんえ)」に由来するとされています。
「盂蘭盆会」を省略して「お盆」と呼ぶようになったそうです。
なぜ「盂蘭盆会」が旧暦7月15日を中心とした期間に行なわれたのかは、お釈迦様の弟子であった目連(もくれん)の伝説が関係しているのだとか。
目連(もくれん)は、亡くなった自身の母親が餓鬼道に落ちたと知りました。
お釈迦様に相談したところ、「大勢の修行僧が修業を終える7月15日に修行僧にご馳走をふるまえば、功徳により母親も救われるであろう」とおっしゃったのだとか。
目連がお釈迦様の言葉通りのことを実践すると、母親は救われ極楽往生を遂げる…。
これが目連の故事です。
お盆の中でも特別な初盆(新盆)
お盆の中でも、特別なものとされているのが、故人様が亡くなった後の四十九日(忌明け)後に初めて迎えるお盆です。
あの世へと旅立った故人様が初めてご自宅に帰ってくる日であるため、手厚くご供養を行ないます。
四十九日(忌明け)後に初めて迎えるお盆は、地域によって呼び方が異なり、
初盆(はつぼん、ういぼん)、または新盆(にいぼん、しんぼん、あらぼん)と呼ばれます。
また、四十九日(忌明け)の前にお盆が来る場合は、翌年のお盆が初盆(新盆)となります。
初盆(新盆)のご法要
初盆(新盆)は、ご家族だけで行なう場合もあれば、ご親族や故人様と親しかった知人などを招いてご法要を行なう場合もあります。
ご親族などをお招きするのであれば、遅くとも1か月前には案内状を送って詳しい日時などをお知らせしましょう。
初盆(新盆)のご法要は、宗派によって違いがあるものの、通常はご寺院をご自宅などに招いて読経してもらいます。
お盆の時期はどのご寺院も大変忙しいので、遅くとも初盆の1か月前、できれば2か月前には連絡を入れ、あらかじめ日時を決めておきましょう。
初盆(新盆)で聖職者にお渡しする御布施の相場は約1万円~3万円です。
通常のお盆の御布施(約5千円~1万円)よりも多めにお包みします。
場合によって御車料と御膳料を別途お包みします。
また、初盆(新盆)では、絵柄のない白提灯を飾ります。
この提灯は初盆が終わったら送り火で燃やすか、精霊送りにします。ご寺院に納めることもあるようです。
お盆の準備・迎え方
お盆の時期に行なうことには、どのようなことがあるでしょうか。
仏壇の掃除、精霊棚(盆棚)・盆提灯を飾る
仏壇の掃除が終わったら、精霊棚(盆棚)・盆提灯を飾ります。
浄土真宗では、精霊棚(盆棚)・盆提灯を飾る習慣はありません。
故人様が魂となってお盆の時期に帰ってくるという考えがないからです。
精霊棚(盆棚)とは、ご先祖の霊を迎えるための棚のことです。
経机(きょうづくえ)などの台の上に真菰(まこも)で編んだゴザを敷き、位牌、三具足(燭台、花立て、香炉)の他、精霊馬(しょうりょううま=きゅうりの馬やなすの牛)やお供え物を置きます。
精霊棚(盆棚)の脇には盆提灯を置き、お盆の期間中には灯りをつけておきます。
初盆であれば絵柄のない白提灯、初盆以外であれば、絵柄のある提灯を飾ります。
ご先祖のお迎えとお見送り
8月13日の夕方に迎え火を焚いてご先祖の霊魂を迎えます。
その後、お盆の期間中に、ご寺院にお経をあげてもらい、ご供養を行ないます。
8月16日の夕方には送り火を焚いて、ご先祖の霊魂をお送りします。
お墓参り
お墓参りは、地域や宗派によっても違いますが、一般的にお盆初日の8月13日に行なうのが良いとされています。
お盆の風習は地域によって異なることも
いかがだったでしょうか。今回は、お盆の由来やお盆の時期、初盆(新盆)のご法要、お盆の準備・迎え方など、お盆に関する知識をご紹介しました。
お盆の迎え方は地域によって異なります。もし、疑問に思うことがあれば、ご寺院や地域の葬儀社にご相談されてみてはいかがでしょうか。
平安祭典では神戸・阪神間での初盆(新盆)、お盆のご準備などに関するご相談を受け付けております。
気兼ねなくお問い合わせください。
平安祭典祭典でお葬式をされていない方のご法要も承ります。
《平安祭典法要受付》
フリーダイヤル 0120-18-4142 (受付 9:00~17:00)
もしくは下記フォームからお申し込みください。
お問い合わせ、ご予約の際は「平安祭典のホームページを見た」とお伝えください。
※年末年始は休業(12/30~1/3)
続きはこちら
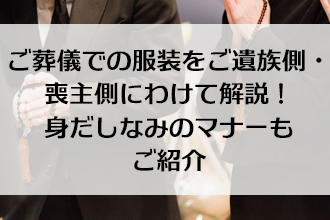
更新日:2023年11月6日 公開日:2021年7月12日
今回は、通夜、葬儀・告別式の際のマナーである身だしなみについてご案内いたします。服装だけではなく、靴やアクセサリー、化粧、髪形などについても、注意すべき点を見ていきましょう。
男性・女性、それぞれの喪服
(正喪服・準喪服・略式喪服)
喪服には、正喪服・準喪服・略式喪服と呼ばれる格式の違いがあります。
故人様から三親等までのご親族は、本来は正喪服を着用するのが望ましいとされていますが、実際には準喪服や略式喪服を着用するのが主流となっています。
《正喪服》
男性は、和装なら黒紋付き羽織袴、洋装ならモーニング、女性は黒無地着物です。
※一番格式の高い正喪服は、喪主・ご遺族側が着用するもので、参列者は着用しません。
《準喪服》
男性は、ブラックフォーマルスーツ、女性は、ブラックフォーマルスーツ(ワンピース、アンサンブル)です。
《略式喪服》
男性は、黒を基調としたスーツ、女性は、黒を基調としたワンピース、アンサンブルなどです。
男性の略式喪服の例
ブラックスーツのダブルかシングルを着用します。
・ シャツ:白無地
・ ネクタイ:黒無地(ネクタイピン不要)
・ 靴下:黒
・ 靴:光沢のない黒(シンプルなもの)
※カフスボタンやポケットチーフなども不要
女性の略式喪服の例
黒無地のアンサンブルやワンピースが多く、肌の露出を避け、夏でも襟元の詰まった長袖が基本です。スカートは、膝が隠れるくらいの長さが目安になります。
・ ストッキング:やや肌が透ける程度の黒
・ 靴:光沢のない黒パンプス
(ピンヒール、かかとやつま先が出るような靴は不可)
・ バッグ:光沢のない黒
(派手な飾り、殺生をイメージさせる爬虫類の革製のものは避けます)
子どもが参列する際の服装
ご葬儀に子どもが参列する際はどういった服装が良いでしょうか?
子どもは大人ほど身だしなみに気を遣う必要はありませんが、マナー違反になるような派手な服装や普段着での参列は避けましょう。
高校生以下の子どもの服装
中学生や高校生の場合は、学校の制服を着用するのが良いでしょう。
小学生以下の子どもの場合は、白のシャツと黒、紺などの落ち着いた色のズボン、スカートなどを着用するのが好ましいです。
大学生の服装
大学生は学校指定の制服がない場合が多いので、リクルートスーツなどを着用して参列すると良いでしょう。
無難なスーツがない場合は、喪服をレンタルするか、ご親族から借りるなどして用意しましょう。
ご葬儀の際の喪主・ご遺族などの服装・マナー
「納棺や湯灌に立ち会う際は、どのような服装が良いのでしょうか」というご質問を受けることがありますが、納棺や湯灌に立ち会う際には平服でも構いません。
お通夜では、喪主・ご遺族側の男性・女性ともに略式喪服を着用することがほとんどです。お通夜の約2時間前には喪服に着替えておきましょう。
ご葬儀では、喪主を務める方は正喪服が望ましいとされています。
正喪服は、葬儀社でレンタルできることもあるのでお尋ねください。
ご葬儀の際の参列者側の服装・マナー
お通夜の場合、参列者は基本的に略式喪服を身に着けます。
急な訃報連絡を受けた場合には、会社帰りなど急いで駆けつけることも多いため
平服でも失礼にはあたりませんが、可能な限り喪服を着用するよう努めましょう。
平服を選ぶ際には、男性は地味な色のスーツに黒のネクタイや靴、女性は無地の地味な色のスーツまたはワンピースに黒の小物を揃えると良いでしょう。
ご葬儀では略式喪服を着用します。
また、夏場や冬場は季節に合わせて、服装の調整をする必要があります。
夏場は暑くてもジャケットを着用するのがマナーです。
冬場に着用するコートは、黒やベージュなどの落ち着いた色のものを用意すると良いでしょう。
靴、アクセサリー、化粧、髪形の注意点
ご葬儀では、華美なアクセサリーや化粧、髪形は避けましょう。これは、喪主・ご遺族側、参列者側、どちらにも言えることです。
靴は金具などの装飾がなく、光沢のない落ち着いたデザインのものを着用するのが好ましいでしょう。
アクセサリーは、結婚指輪、白または黒のパールの一連ネックレス以外を身に着けるのは控えます。
ちなみにパールのネックレスは、二連のものは「不幸が重なる」イメージにつながるため、避けた方が良いとされています。
化粧は控えめにして、ナチュラルな印象に仕上げます。
髪形は、男性も女性も清潔感のあるスタイルにしましょう。
ロングヘアの場合は、黒のヘアゴムやピンで、耳より下で髪をまとめましょう。香りの強い整髪料や香水も控えた方が無難です。
また急なお通夜では、明るい髪色やネイルなどの処置に困ることがあります。
可能であれば、どちらも目立たない色に戻すのが理想です。
ネイルを隠すために黒の手袋をつける女性もいらっしゃいますが、焼香や食事の際には手袋を外さなければならないので、派手なネイルであれば、元に戻した方が良いでしょう。
ご葬儀の際の持ちもの
仏式のご葬儀では、数珠(念珠)を持参します。宗派を問わず使うことができる略式数珠を1つ持っていれば便利です。
ちなみに、数珠には持ち主の念が移ると考えられているため、貸し借りをするのは避けましょう。
※平安祭典では、各種念珠を販売しておりますので、ご入用の際はご用命ください。
また、ご参列の時に御香典を持参する際には、袱紗(ふくさ)に包んで持ち運ぶのがマナーです。
袱紗の色は、寒色系、あるいは濃い紫を選びましょう。慶弔兼用できる濃い紫の袱紗を1枚持っていると役立ちます。
ハンカチは白または黒の無地のものを用意しましょう。
傘を持つ場合も、落ち着いた色でシンプルなデザインにします。
身だしなみは最低限のマナー
いかがだったでしょうか。今回は、通夜、葬儀・告別式の際のマナーである、服装や身だしなみについてご案内いたしました。
ご葬儀において何よりも大切なのは、故人様を弔う気持ちです。とはいえ、最低限のマナーでもある身だしなみにも気を遣いたいところですね。
神戸・阪神間でご葬儀に関するお困りごとがございましたら、気兼ねなく平安祭典(0120-00-3242)へお問い合わせください。
また、平安祭典では事前相談を承っております。
神戸・阪神間で事前相談をご希望の方は下記のフォームからお申し込みください。
事前相談予約フォーム
続きはこちら
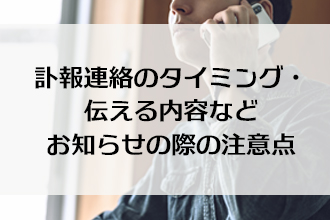
更新日:2021年8月13日 公開日:2021年7月5日
大切な方が亡くなった際に、ご遺族が最初に行なうことは訃報連絡です。故人様と関わりがあった方々に訃報をきちんとお知らせすることで、故人様と悔いのないお別れをしていただくことができます。
今回は、訃報連絡のタイミングや内容、気をつけるべきことをご紹介します。
訃報連絡の返信については###fuhourennraku_hensin###で詳しくご説明しております。
訃報連絡のタイミング
大切な方が亡くなった際に、訃報をお知らせするタイミングは2つあります。
① 亡くなった直後にすぐにお知らせする
② 葬儀日程が決まってからお知らせする
まずは亡くなった直後に、ご家族やご親族など、すぐに連絡を取らなければならない方にご連絡し、その後、葬儀日程やご葬儀の場所が決まってから、その他の方々も含めて改めてご連絡すると良いでしょう。
訃報をお知らせする順序
訃報連絡は、まず、その場にいないご家族やご親族など、故人様と血縁の深い近親者から優先的に行ないます。
とりわけ遠方に住んでいる方は、移動に時間を要するため、早めにご連絡しましょう。
ご親族をどこまで呼ぶかは、お付き合いの度合いによっても異なりますが、「親族の三親等」が一つの目安です。
故人様と親しくされていたご友人・知人、そして故人様が会社勤めであれば、会社の関係者の方々にもご連絡します。後々トラブルにならないためにも、漏れのないようにしましょう。
また、近隣の方々にも忘れずに訃報連絡をしましょう。お住まいの地域によっては、自治(町内)会が冠婚葬祭に深く関わっているケースもあります。その場合には、自治(町内)会長にお知らせします。
訃報連絡の内容
訃報連絡としてお知らせするのは、主に以下の内容です。
・ 故人様の名前
・ 通夜、葬儀・告別式の日時・場所
・ 喪主の名前・続柄など
ご葬儀の日時・場所が決定する前にご連絡する場合は、後ほど改めてご葬儀の日時・場所をご連絡する旨を伝えておきましょう。
また、あらかじめご葬儀の形式(仏式、神式、キリスト教式など)をお伝えしましょう。特に、仏式でない形式でご葬儀が執り行なわれる際には、参列者も準備がしやすくなります。
訃報連絡は、主に電話で行ないますが、近年ではメールを用いた訃報連絡も増えています。メールであれば、遠方からお越しになる方のために葬儀会場の地図を添付することなどもできます。
平安祭典では、WEBページを利用した訃報システムをご紹介しています。メール転送(拡散)により、お通夜、ご葬儀の情報を共有できるシステムです。正確・迅速に情報を送信でき、多くの方に訃報をお知らせできます。
訃報連絡の際に気をつけること
・葬儀社、ご寺院へのご連絡も忘れずに
ご親族などへの訃報連絡の第一報を済ませたら、ご葬儀の準備を進めるため、葬儀社やお付き合いのあるご寺院にもすぐにご連絡を入れましょう。
葬儀社・ご寺院と打ち合わせをして、ご葬儀の日時・場所が決まり次第、改めて正式な訃報連絡を行ないます。
・ご友人や知人関係への訃報のご連絡は、ご遺族がすべて行なう必要はない
故人様のご友人や知人関係へのご連絡、例えば、故人様が生前所属していた趣味や習い事のグループ、会社関係者への訃報連絡は、ご遺族がお一人おひとりに伝える必要はありません。
グループや会社関係の中の「この人に伝えたらみんなに連絡してくれる」という方にお伝えすれば良いでしょう。
・家族葬の場合も訃報連絡は先に行なう方が良い
訃報連絡は、基本的にご葬儀へのご参列をお願いする方々に対して行ないます。
しかし家族葬の場合など、近親者のみでご葬儀を執り行なう場合でも、ご友人や知人、特に会社関係や近隣の方など、故人様がお世話になった方々には、訃報連絡を行なっておいた方が良いでしょう。
訃報連絡を行なわないと、「なぜ知らせてくれなかったのか」とお叱りを受けることもあります。そのため、あらかじめ訃報をお知らせした上でご参列をご遠慮いただく旨、お伝えされることをお勧めします。
”エンディングノート”を活用し、連絡先リストを作成することもできる
携帯電話の普及により、最近では、連絡先を携帯電話内で管理している人がほとんどです。
そのため、ご遺族が故人様の交友関係をすべて把握しきれず、ご葬儀の際に大変な思いをされることもあります。
そのようなご家族のご負担をなくすためにも、
”エンディングノート”を活用して、いざという時、ご自身の訃報を知らせてほしいご友人・知人関係の連絡先リストを、あらかじめ作成されてはいかがでしょうか。
平安祭典ではエンディングノートをご用意しています
いかがだったでしょうか。今回は訃報連絡のタイミングや内容、気をつけるべきことをご説明いたしました。
最後にご紹介したエンディングノートですが、平安祭典でもエンディングノートをご用意しています。
エンディングノートについては###endingnote_kakikata###で詳しくご説明しております。
神戸・阪神間でエンディングノートをご希望の方は、平安祭典までお電話いただくか(078-856-6890)、お問い合わせ・資料請求フォームから「ご希望の資料」に「エンディングノート」をチェックしてご請求ください。
続きはこちら
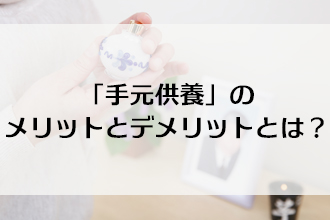
公開日:2021年6月28日
ライフスタイルの多様化に伴い、ご供養の方法も様々になってきました。
従来のように”すべてのご遺骨をお墓に納める”のではなく、一部あるいはすべてのご遺骨を手元に置いておく、「手元供養」と呼ばれるご供養方法を選択される方が増えてきた…という話題は、以前の記事でもお伝えしたとおりです。
※前回の###temotokuyou_toha###もぜひあわせてご覧ください。
今回は、手元供養のメリットとデメリットについてご紹介をします。
そもそも手元供養とは?
手元供養とは、どのようなご供養方法かを再確認しましょう。手元供養とは、従来のようにすべてのご遺骨をお墓や納骨堂に納めるのではなく、” ご遺骨の一部、あるいはすべてを手元に置いておく”ご供養方法です。2000年代以降、このご供養方法を選択される方が増えてきました。
一部のご遺骨を手元に置いておく場合は、火葬場で収骨する際やお墓に納骨をする際に分骨をし、コンパクトなサイズの骨壷やペンダントに入れたり、ダイヤモンドなどに加工します。
すべてのご遺骨を手元に置いておく場合には、骨壷に入ったご遺骨を、そのまま自宅にご安置します(自宅にご遺骨を置くことから、「自宅供養」とも呼ばれます)。
手元供養のメリット・デメリット
手元供養を選択される方が増えてきたとはいえ、そのメリットとデメリットは、どちらも知っておきたいところです。
メリットとしては、次の点が挙げられます。
メリット
・故人様を近くに感じることができる
・お墓に行かなくても毎日お参りができる
・自分らしい飾り方ができる
・宗旨にこだわらずにご供養ができる
・お墓を新しく建てるのに比べ、費用負担が少ない
・お墓のお手入れがいらない
このように、手元供養のメリットは、特に精神的な面での利点が多く挙げられます。故人様のご遺骨が身近に存在することで、ご遺族の喪失感や悲しみも和らぐことでしょう。
また、お墓を持たずに、手元供養だけでご供養をされている方も少なからずいらっしゃいますが、お墓と手元供養を併用されている方が多いのが実状です。
精神的な面での利点が多いとされている手元供養ですが、その一方でデメリットも存在します。
デメリット
・ご親族からご理解を得ることが難しいこともある
・災害によりご自宅などが被災した場合、紛失の恐れがある
手元供養では、ご親族からご理解を得ることが難しいケースが少なくありません。
ご親族の中に「お墓に納めるのが当然」「お墓に納めないと成仏できない」「体がバラバラになってかわいそう」といったような、ネガティブなイメージを持った方がいらっしゃることで、ご理解を得られず、つらい思いをされるご遺族もいらっしゃいます。
ちなみに、お釈迦様のご遺骨も世界各地に分骨されていることもあって、仏教的に分骨は問題がありません。同様にご遺骨を必ず墓地に埋葬しなければならないという決まりはなく、法律的にも分骨は何ら問題がありません。
いずれにせよ、ご自身が亡くなったあとに手元供養をご希望される場合には、ご遺族のご負担を減らすためにも「エンディングノート」を用いて、意思表示をされておいたほうが良いでしょう。
エンディングノートについては###endingnote_kakikata###で詳しくご説明しております。
もう一つのデメリットとして、水害や火災などといった災害により、ご自宅に万が一の事態が起きた際に、紛失の可能性があるという点が指摘されています。お墓と手元供養を併用すれば、このようなリスクに備えることもできるでしょう。
メリットとデメリットをふまえて選択を
今回は、「手元供養」のメリットとデメリットについてご紹介しました。ご検討されている方は、このようなメリットとデメリットが存在することを踏まえたうえで、選択をされてはいかがでしょうか。
平安祭典でも、手元供養をご案内しています。神戸・阪神間で手元供養をご検討されている方は平安祭典(0120-00-3242)まで、ぜひご相談ください。
続きはこちら
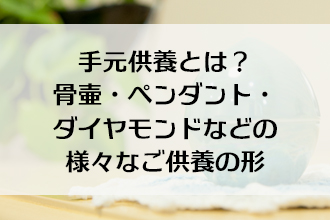
更新日:2021年8月3日 公開日:2021年6月21日
近年、ライフスタイルの多様化が進んでいますが、ライフスタイルの多様化は、ご葬儀の方法やご供養の方法にも広がっています。
例えばご葬儀。最近では家族葬を選択する方が増えています。
一方、ご供養においても、従来のように”すべてのご遺骨をお墓に納める”のではなく、一部あるいはすべてのご遺骨を手元に置いておく、「手元供養」と呼ばれるご供養方法を選択される方が増えてきました。
平安祭典のお客様からも、「お墓に遺骨を全部納めてしまうのはさみしい」というご意見がしばしばあります。そこで今回は、ご供養の多様化の一例として、「手元供養」のご紹介をします。
従来のご供養の方法
まずは、従来のご供養の方法についてご説明しましょう。
ご葬儀のあと、火葬されたご遺骨は骨壷に納められます。仏式なら四十九日の間、ご遺骨はご自宅に安置され、そのあと、お墓や納骨堂に納骨されます。
仏式であれば、命日、年忌法要(一周忌・三回忌・七回忌など)、お彼岸、お盆に、ご遺族はお墓参りをし、故人様を偲びます。また、自宅には仏壇を設置し、位牌をお祀りします。
これが従来のご供養の方法です。従来のご供養では、”すべてのご遺骨をお墓に納める”のが一般的でした。
しかし、大切なご家族を亡くされた喪失感の中で、ご遺骨がすべて目の前からなくなるのは、少しさみしい気持ちになるかもしれません。
そのような課題を解決するのが、手元供養と呼ばれるご供養の方法です。
火葬については###kasou_toha###で詳しくご説明しております。
手元供養とは?
手元供養とは、文字通り” ご遺骨の一部、あるいはすべてを手元に置いておく”ご供養方法です。
一部のご遺骨を手元に置いておく場合は、火葬場で収骨する際や、お墓に納骨をする際に分骨をし、小さな骨壷やペンダントなどに納めたり、ダイヤモンドなどに加工します。すべてのご遺骨を手元に置いておく場合には、骨壷に入ったご遺骨を、そのまま自宅にご安置します。
手元供養の注意点は、分骨したご遺骨をお墓にも納骨する場合には、必ず「分骨証明書」を発行しておく点です。すべてのご遺骨を手元に置く場合は「分骨証明書」は不要ですが、ご遺骨どこかへお納めする場合には必要になるため、まだ決めていない場合には、発行しておいたほうが良いでしょう。
手元供養を選択される方が増え始めたのは2000年代に入ってから。比較的新しいご供養方法です。ちなみに手元供養は、自宅にご遺骨をご安置することから、自宅供養とも呼ばれます。
※ご遺骨をダイヤモンドに加工する場合は、たくさんのご遺骨が必要となります。
手元供養の方法…仏壇は必要?
手元供養の方法には、小さな骨壷を利用する方法、ご遺骨をそのまま、あるいは粉末化してペンダントに入れる方法、ご遺骨をダイヤモンドに加工する方法があります。以下にそれぞれの方法をご紹介します。
小さな骨壷とステージを利用(カビの生えない置き場所へ)
小さな骨壷とは、コンパクトなサイズの骨壷のことです。主に陶器やセラミック、真鍮などでできており、オーソドックスな丸みを帯びた白色の骨壷だけでなく、様々な形や色をした製品が販売されています。
小さな骨壷をステージのうえに置くことで、故人様を偲ぶためのメモリアルな空間になります。
平安祭典では、小さな骨壷と手元供養セットを取り扱っています。故人様がお好きだった色や似合う色の骨壷を選択することが可能です。分骨したご遺骨を納め、仏壇などに飾る手元供養に適しています。
ご自宅に小さな骨壷をご安置する場合、安置場所は直射日光を避け、風通しの良い場所にしましょう。湿気が多い場所では、ご遺骨にカビが生える危険性もあります。
ご遺骨をペンダントに入れ、おしゃれなアクセサリーに
ご遺骨をペンダントトップの中に納めることができる商品もあります。小さな骨壷に比べて、納めることができるご遺骨の量は少ないのですが、ペンダントとして首からかけることができるため、故人様との一体感を感じることができます。
主にステンレス製で軽く、スタイリッシュな商品が多いのも特長です。女性だけでなく、男性にも数多く利用されている手元供養の方法です。アッシュペンダント、メモリアルペンダントとも呼ばれます。
ご遺骨の粉末化は、ご自身で行なっても構いませんし、平安祭典でも有料で承っております。
ご遺骨をダイヤモンドに加工する方法
ダイヤモンドは炭素からできています。実はご遺骨の中には炭素が約2~3%ほどの割合で含まれており、ご遺骨中に含まれる炭素を取り出し、高温と高圧をかけることで人工ダイヤモンドにすることができるのです。
人工ダイヤモンドを作るためには、多くのご遺骨(約400g=骨壷5寸で、8割からすべて)を使用するため、あらかじめご家族・ご親族など、関係する人たちの間で意思の確認をしておいたほうが良いでしょう。
完成したダイヤモンドは、指輪やネックレスなどのアクセサリーに加工することもできます。常に身につけることで、故人様を身近に感じることができるでしょう。
まとめ
いかがだったでしょうか?今回は、ご供養の多様化の一例として、「手元供養」のご紹介をさせていただきました。大切な方を失う喪失感は計り知れないもの。「手元供養」をご活用いただくことで、悲しみも和らぐかもしれません。
弊社では、ご遺族の皆さまが抱く喪失感や悲しみを少しでも和らげる方法を、これからもご紹介できればと考えております。
神戸・阪神間で、ご葬儀やご供養に関するお困りごとがございましたら、平安祭典(0120-00-3242)までご相談ください。
続きはこちら