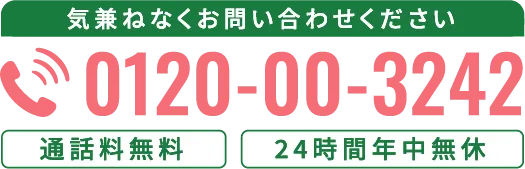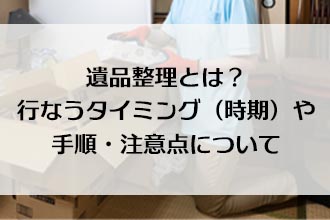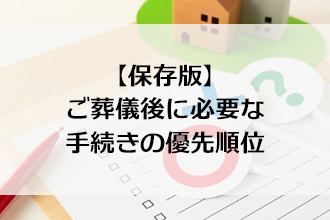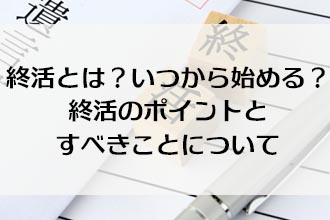【相続手続きの手順】スムーズに済ませるためのコツとは?

公開日:2021年8月23日
ご家族が亡くなると、非常に多くの手続きが必要となりますが、その中でも特に慎重に行なう必要があるのが相続の手続きです。
何度も経験することではありませんので、どのように相続の手続きを進めれば良いかわからない方も多いかと思います。
今回は相続について、基本的なことや手続きの手順などをご紹介します。
手続きの期限が過ぎてペナルティを受けたり、遺産相続を巡ってトラブルに発展したりすることがないように、一通り知った上で手続きを進めていきましょう。
[@目次@]
相続とは?

相続とは、被相続人が生前に所有していた財産を相続人が引き継ぐことを言います。
相続の対象となるのは、不動産、預貯金・株・投資信託などの金融資産、自動車や宝石、絵画などの動産、それに借入金などの負債です。
相続人は、配偶者、子、両親、兄弟姉妹などで、相続順位や相続分も民法で定められています。
ただし、被相続人が生前に遺言書を作成・指名をされていた場合は、その他の方にも引き継ぐことができます。
相続の流れ・手順
その中でも相続に関する手続きは、怠ると手続きが複雑化する、あるいは不利益を被る場合があるので、注意が必要です。
それでは相続の流れをひとつずつ確認していきましょう。
① 遺言書の確認
故人様が遺言書を残していないかを確認します。
鑑定が必要な場合もありますが、公正証書遺言であれば偽造のリスクはほとんどありません。遺言書が有効な場合は、⑤の遺産分割協議は不要です。
遺言書の種類や書き方に関しては『遺言書の種類や作成のポイント!効力のある書き方を解説』の記事で詳しくご説明しております。

② 財産リストの作成
相続の対象となる財産を全て洗い出します。
資産が多岐にわたる場合、リスト化に時間を要するため、早めに取り掛かる方が良いでしょう。
③ 相続人の調査・確認
故人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍謄本を収集します。相続人が何名存在しているかの証明として必要になります。
そして証明された法定相続人全員の現在戸籍と住民票(本籍地記載のもの)を収集します。これにより、法定相続人の氏名・続柄・住所が明確になります。

④ 相続放棄(遺産放棄)の検討
財産のうち資産(プラス)と負債(マイナス)の割合によっては、相続放棄も検討する必要があります。
相続放棄とは、資産より負債の方が多い場合に、家庭裁判所に申立てすることにより負債の弁済義務を負わなくて済む制度です。ただし、すべての財産を放棄することになるので、財産を相続することもできません。財産はもらうが、負債は負わないということはできません。
⑤ 相続財産の名義変更
相続人が確定したら、相続財産の名義変更を行ないます。
相続財産の名義変更には、手続きの種類により③の戸籍一式をはじめとする様々な添付書類が必要です。
また相続財産を法定相続人で、どのように分割するのかを話し合い、合意した証明として《遺産分割協議書》が必要となります。
この書類にすべての相続人が署名をし、実印を押印し、印鑑証明書を添付しなければなりません。
不動産の名義変更や預金・株・投資信託の名義変更、解約もこれらの書類が必要です。
1人でも実印の押印を拒否した場合は、遺産分割協議では手続きできないので、家庭裁判所で調停の手続きに移ります。遺産分割協議が難航した場合、時間を要します。従って、手続きはできるだけ早期に着手することをおすすめします。
⑥ 相続税の申告
遺産を相続する場合、相続税が発生します。純資産額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告が必要です。
※詳しくは下記「相続税はいくらから?」でご説明します。
以上が遺産相続に関する流れです。聞きなれない難しい言葉が多いかもしれませんが、ひとつずつ進めていきましょう。
相続税はいくらから?

相続する各人の「課税価格の合計額」が基礎控除額※を上回ると、その額に応じて相続税がかかります。
相続の純資産額が基礎控除額を超える場合、故人の死亡から10ヶ月以内に相続税の申告および納税が必要です。
相続税のボーダーラインとなる基礎控除額の計算方法は以下の通りです。
※3,000万円+600万円×法定相続人の数=相続税の基礎控除額
例えば法定相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円までが申告不要となります。(約9割の方が申告不要に該当します)
相続に関するトラブル
遺産相続はトラブルの原因となることが多く、仲の良い家族だったとしても争いに発展してしまう場合があります。
相続に関するトラブルの例をご紹介しますので、事前に対策をしておきましょう。
● 生前に被相続人の面倒を見た人が、寄与分が欲しいと言ってきた
被相続人の介護を行なっていた相続人がいるような場合に起こりえるトラブルです。
例えば、数名いる相続人のうち1人だけが被相続人の近くに住んでおり、生前に介護などを行なっていたため、寄与分※を主張するといったケースです。
遺産分割協議で合意を得られなかった場合、トラブルになる可能性があります。
※寄与分とは…民法第904条の2
- 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
● 遺言書の内容によってはトラブルになる可能性も…
被相続人が遺言書を作成していたとしても、その内容によってはトラブルに発展する可能性があります。
例えば、遺言書の内容が
・ 相続人の1人にすべての財産を相続させるとしたもの
・ 第三者にすべての財産を遺贈するとしたもの
があげられます。
これらは遺留分※を無視した極端な例ですが、一般的にも遺留分を超えて記載された遺言書はトラブルになる可能性があります。
※遺留分…遺留分とは、相続人に法律上保証された一定の割合の相続財産をいいます。この場合の相続人とは配偶者又は子(場合によっては直系尊属)に限られます。
● 被相続人に離婚歴がある場合、前妻は相続人になる?
被相続人に離婚歴がある場合、前夫や前妻には相続する権限はありませんが、その子は法定相続人となり、遺産を相続する権利があります。
また子が未成年の場合、離婚した前妻(前夫)が法定代理人として遺産分割協議に参加する場合があります。こういった場合トラブルになりやすいので、注意が必要です。
このようなケースでは、事前に遺言書を作成しておくことが重要です。
トラブルのリスクを的確に考慮した遺言書があれば、遺産分割協議が不要なので、無駄な争いを回避できます。
いくつかのケースをご紹介しましたが、相続でトラブルになることは非常に多く、決して他人事ではありません。慎重に進めていきましょう。
まとめ

いかがだったでしょうか?今回は相続に関する手続きの流れをご紹介しました。
遺産相続はトラブルに発展しやすいため、非常に慎重に進める必要があります。
少しでも不安がある方は専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
神戸・阪神間で相続のことでお悩みの方は、下記まで気兼ねなくお問い合わせください。
あさひ行政書士法人(0120-4864-65)
無料相談受付時間 9:00~18:00
行政書士オアシス相続センター (078-251-1414)
無料相談受付時間 9:00~18:00
お問い合わせの際には、「平安祭典のホームページを見た。」とお伝えください。