

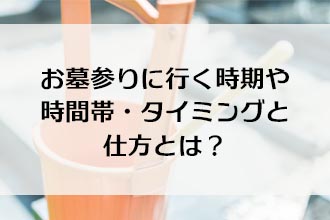
公開日:2021年3月22日
遠方にお墓がある、これまでお墓参りをする機会がなかった、など様々な理由で、お墓参りをしたことがないという若い方が増えています。
ご家族がお亡くなりになって初めて、「お墓参りにはいつ行けば良いのだろう?」「お墓参りは具体的にどのようなことをするのだろう?」と疑問を感じられるようです。
そこで今回は、お墓参りに行くタイミングと仕方について、ご紹介します。
[@目次@]
お墓参りに行くタイミングは?
お墓参りにはいつ行けば良いのでしょうか。
ご自宅の近くにお墓がある場合は、毎日お参りをされる方もいらっしゃいます。休日にご家族やご親戚が集まったタイミングにお墓参りをされるというケースもあります。
「お墓参りにいつ行けば良い」という明確なルールは存在しません。大切なのは故人様やご先祖を想い、ご供養する気持ちです。皆さまのご都合の良いタイミングでお参りをなさってください。
ただ一般的には、故人様の祥月命日や月命日、春と秋のお彼岸、お盆の時期に、ご寺院や霊園などに伺い、お墓参りを行なうものとされています。
また、年末年始にお墓参りに行くことについてご質問をいただきますが、もちろん問題はありません。とはいえ、様々な用事のひとつとしてお墓参りをすることは「ついで参り」と呼ばれ、ご先祖に対して失礼であるとされていますので気をつけましょう。
お彼岸に関しては###higan_toha###、お盆に関しては、###obon_toha###で詳しくご説明しております。
お墓参りの仕方
お墓参りの仕方についても見てみましょう。
お墓参りに行く際の持ち物
お墓参りに行く際には、次のものを用意します。
・ お線香、ろうそく
お線香にはろうそくから火を移すのが正式な方法です。ろうそくに火をつけるためのマッチやライターも用意しましょう。
・ お花やお供え物
お花やお供え物も用意します。お供え物は故人様がお好きだった果物やお菓子・ジュース・お酒などをお供えすると良いでしょう。ちなみにお供え物を置く場合には、半紙や懐紙を用意しておくと便利です。
お供え物はカラスやイノシシなどの野生の動物に荒らされることもあるため、その場でいただくか持ち帰ります。
お墓をご寺院や霊園が管理しているのであれば、お花が枯れた際に片づけてくれるケースもありますが、枯れたまま放置されたままとなっていることも少なくありません。頻繁にお墓参りができない場合には、お供え物と同様に、当日中に持ち帰りましょう。
・ 掃除道具
お墓を掃除するための掃除道具も持っていきましょう。墓石をきれいにするためのスポンジ・タオルや雑巾・歯ブラシ、お墓周りなどの汚れを落とすたわし、雑草を刈るためのスコップ・鎌・剪定ばさみ、玉砂利を洗うためのザル、ごみを持ち帰るためのごみ袋などを持っていきます。
ご寺院や霊園には、墓石に水をかけるための桶やひしゃくを備え付けているところがほとんどですが、貸し出し中のこともあるため、必要に応じてご準備しておいたほうが良いでしょう。
また、掃除をする場合には、動きやすく多少汚れても構わない服や靴を選ぶと良いでしょう。
・ 数珠
数珠はお祈りする際に用います。
お墓参りの手順
ご寺院にお墓がある場合には、先に本堂や御本尊にお参りをしてから、お墓に向かいます。お墓のお掃除を行なってからお線香を焚きましょう。
ご寺院や霊園では、お参りが可能な時間帯が決まっているケースも多いので、あらかじめ参拝可能な時間を確認しておきます。
・ お墓の周りの掃除をする
お墓の周囲に雑草が生えていたら、スコップ・鎌・剪定ばさみなどを利用して刈り取ります。お墓周りの汚れはたわしで落とし、玉砂利を敷いていれば、ザルを用いて水洗いします。
・ 墓石に水をかけて洗い流す
桶とひしゃくを用いて、墓石に水をかけてほこりなどの汚れを流します。
・ 墓石を傷つけないようにスポンジなどで汚れを落とす
墓石は強くゴシゴシとこすらないで、優しく汚れを落としましょう。墓石表面の彫刻部分は、歯ブラシで丁寧に磨くと汚れが落ちやすくなります。
・ 線香台、花立などの付属品を洗う
線香台には灰がたまりやすくなっています。灰を捨て、
水洗いしましょう。また、花立も水を一度抜き、水洗いしてください。
・ 墓石をタオルや雑巾で拭き上げる
一通り掃除が終わったら、乾いたタオルや雑巾で墓石を拭き上げましょう。水鉢には綺麗な水を汲み、花立にお花を飾ります。二つ折りにした半紙や懐紙の上にお供え物を置き、ろうそくに火を灯し、お線香を焚きます。
ろうそくやマッチの燃えかすといった、火の後始末には十分ご注意ください。
お墓参りは、故人様やご先祖を想い、ご供養する良い機会
いかがだったでしょうか?今回は、お墓参りに行くタイミングと仕方について、ご紹介しました。
お彼岸は、故人様やご先祖に想いを馳せる貴重な機会です。ご家族揃ってお墓参りにお出かけになって、皆さまで故人様の想い出話をされてみてはいかがでしょう。
なお、平安祭典では神戸・阪神間でのご葬儀・ご供養のご相談を受け付けております。ご葬儀・ご供養に関するお困りごとがございましたら、0120-00-3242までご連絡ください。
続きはこちら
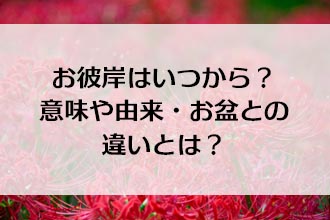
更新日:2025年4月25日 公開日:2021年3月15日
「暑さ寒さも彼岸まで」という慣用句を、皆さまもよくご存知ではないでしょうか。
皆さまは、お彼岸にはお墓参りをするかと思います。でもいったいなぜ、お彼岸にお墓参りをするのでしょうか。今回は、お彼岸の意味や由来、お彼岸のお墓参りなどについて、ご説明します。
[@目次@]
お彼岸の意味と由来、お盆との違いは?
お彼岸とは、仏教とともに古代インドから伝わった考え方です。お彼岸の語源は、菩薩(ぼさつ)が仏になるために行なう修行を指す仏教用語、「波羅蜜(はらみつ)」と同じ意味を持つ「到彼岸(とうひがん)」を由来とする言葉です。
仏教では、私たちのいる煩悩や迷いに満ちた世界を「此岸(しがん)」、ご先祖のいる悟りの世界(極楽)を「彼岸(ひがん)」と呼びます。
「到彼岸」とは、此岸から彼岸に至ることと解釈され、此岸にいる私たちが修行を積むことで、彼岸という悟りの境地に到達できると考えられています。
浄土思想では、極楽浄土は西方にあるとされています。太陽が真東から昇り真西に沈む春分の日と秋分の日は、此岸と彼岸が最も通じやすい日とされ、両日に先祖供養を行なうようになりました。これが、お彼岸にお墓参りをする由来とされています。
ちなみに、お彼岸の初日を「彼岸の入り」、終日を「彼岸の明け」、そして、太陽が真東から昇り、真西に沈む春分の日と秋分の日を「彼岸の中日」と呼びます。
お彼岸とお盆は、お墓参りをするという点はよく似ています。
しかし、此岸の私たちが彼岸のご先祖に近づき、感謝を伝えるお彼岸と、彼岸のご先祖が此岸に帰ってこられるのをお迎えするお盆では、意味が異なります。
お盆に関しては###obon_toha###の記事で詳しくご説明しております。
2025年のお彼岸はいつ?
お彼岸とは、季節の節目となる、日本の年中行事の1つです。春分の日、秋分の日を中日(”なかび”もしくは”ちゅうにち”)に、前後3日、合計7日間が、それぞれ春のお彼岸、秋のお彼岸の期間となります。
ちなみに春分の日は「自然を称え、生物を慈しむ日」、秋分の日は「ご先祖を敬い、亡くなった人々を偲ぶ日」として、国民の祝日に定められています。
2025年の春のお彼岸は、3月17日 彼岸入り、3月20日 中日(春分の日)、3月23日 彼岸明け。
秋のお彼岸は、9月20日 彼岸入り、9月23日 中日(秋分の日)、9月26日 彼岸明けとなります。
彼岸会(ひがんえ)とは?
彼岸会という言葉についてもご説明します。
彼岸会とは、春のお彼岸、秋のお彼岸、それぞれ7日間に行なわれる法会(ほうえ=仏法を説くためやご供養を行なうための僧侶・信徒の集まり)のことです。
ご寺院では、ご先祖をご供養する法要が執り行なわれ、信徒は彼岸会の期間中にご寺院を詣で、お墓参りをするのが習慣となっています。
彼岸会では中日にご先祖に感謝し、残る6日は悟りの境地に達するのに必要な6つの徳目「六波羅蜜(ろくはらみつ=悟りの彼岸に至るための6つの修行徳目)」を1日に1つずつ修めるとされています。
お彼岸のお墓参りと初彼岸
お彼岸にご寺院へお墓参りに出かける場合、いつ行けば良いという決まりはありません。お彼岸の期間中であれば、いつお墓参りをされても構いません。
普段のお墓参り同様に、ご先祖や故人様を偲び、ご供養する気持ちが大切です。
また、故人様が初めてのお彼岸(初彼岸)を迎えられる際には、手厚いご供養を心がけましょう。故人様の初彼岸には、ご自宅にご寺院を招いてお経をあげていただくと良いでしょう。祝日にあたる春分の日、秋分の日を利用して、年忌法要を行なう方もいらっしゃいます。
ご自宅のお仏壇へのお供え
お彼岸中、ご自宅のお仏壇には、お花や果物や甘い菓子、精進料理などをお供えします。小豆(あずき)を原材料とするお団子や、春のお彼岸には”ぼたもち”、秋のお彼岸には”おはぎ”などがお仏壇にお供えされます。
ちなみに”ぼたもち”と”おはぎ”は基本的には同じものです。季節の花(牡丹と萩)にちなんで、それぞれ呼び方が異なっています。
ちなみに、”ぼたもち”は、牡丹の花に似せて丸くて大きく、”おはぎ”は、萩の花のように小ぶりでほっそりと作るのだとか。
諸説ありますが、”ぼたもち”と”おはぎ”の原料である小豆は、古くから邪気を払う食べ物として信じられてきたため、”ぼたもち”と
”おはぎ”は、お彼岸中にご先祖をご供養する食べ物として定着したそうです。
お彼岸は、故人様やご先祖に想いを馳せる貴重な機会
いかがだったでしょうか?今回は、お彼岸の意味や由来、ご自宅のお仏壇へのお供えなどについて、ご説明しました。お彼岸は、故人様やご先祖に想いを馳せる貴重な機会です。ご家族でお仏壇を掃除したり、お墓参りに行かれてはいかがでしょうか。
お墓参りに関しては###hakamairi_timing###の記事で詳しくご説明しております。
神戸・阪神間でご葬儀・ご法要に関してお困りごとがありましたら、
平安祭典(0120-00-3242)まで気兼ねなくお問い合わせください。
続きはこちら
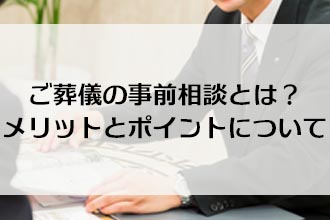
公開日:2021年3月1日
高齢の親御様がいらっしゃる方で、漠然とご葬儀に対する不安を抱く方は少なくありません。内容、お金のこと、お墓のこと…。平安祭典では、そのようなご不安を解消するために、事前相談を行なっています。
ご葬儀に関する様々な不安を解消するためには、ご葬儀について知ることが大切です。今回は、事前相談を行なうメリットとご相談前にイメージしておきたいポイントについて、ご紹介します。
【事前相談のススメ】(平安祭典ホームページ)や###sougisya_erabikata###の記事もぜひあわせてご覧下さい。
事前相談を行なう3つのメリット
まずは、事前相談を行なうメリットをご紹介します。事前相談には、以下のようなメリットがあります。
ご予算の全体像がつかめる
ご葬儀の費用は決して不明瞭なものではありません。「参列者の人数はどのくらいか」「お料理はどうするか」「祭壇にお花をどれくらい飾るか」「香典返しはどうするか」など、ひとつずつ決めていくことで全体の費用が決まります。
事前相談では、仮見積りをもらえるので、ご予算の全体像をつかむことができます。
ご葬儀の一連の流れを知ることで不安が解消される
事前相談を行なうことで、ご予算の全体像はもちろんのこと、仏式であれば、通夜、葬儀・告別式、初七日法要、忌明け法要(四十九日法要)…と、ご葬儀・ご法要の一連の流れを知ることができます。一連の流れがわかれば、漠然とした不安はきっと解消されることでしょう。
その人らしいご葬儀を実現できる
最近では、生前に自らのご葬儀について考え、ご自分の想いを事前にご家族に伝えておかれる方も増えています。事前相談をきっかけに、ご家族皆さまでご葬儀について考えていただければ、心の準備もでき、その人らしいご葬儀の実現につながります。
ご相談前にイメージしていただきたいポイント
続いて、ご相談前にイメージしていただきたいポイントをご説明します。
なお、事前相談をされる葬儀社は、ご自宅の近く、ご希望の場所の近くに会館がある葬儀社の中からいくつか候補を選んでおくと良いでしょう。
ご葬儀を行なう場所
最近では、ネット広告で明朗会計・低価格を売りにしている葬儀社もありますが、自社運営をしていない仲介業者であったり、初期費用にオプション項目を追加すると、結果的に一般的な葬儀社の費用と大差がないケースもあるようです。内容を十分に吟味したうえで、ご検討ください。
宗旨・宗派
仏式であれば、天台宗や真言宗・日蓮宗などを宗旨と言います。宗派とは、宗旨から分かれた分派(○○宗○○派)のことです。ご葬儀を執り行なうにあたり、宗旨・宗派は大切な情報になります。また、事前相談では、菩提寺(先祖が代々眠っているお墓があるお寺のこと)の有無についてもお伺いします。
宗旨・宗派については###shuuha_shuushi###で詳しくご説明しております。
香典返し
ご遺族のご負担になりやすいのが香典返しです。
香典返しをどうするか悩まれるご遺族も少なくありません。
最近では、香典返しが大変といった理由で香典を辞退される
ご遺族も増えていますが、香典をいただくことで喪家のご葬儀費用の負担は軽くなります。
また、香典返しをお通夜、葬儀・告別式の当日にお渡しする「当日返し」とすれば、ご葬儀と一緒に済ませることができ
後々手間がかかることはありません。
その他
葬儀社では、ご葬儀に関して具体的なご相談も承っています。お花が好きな方であれば、お花(祭壇飾り)をたくさん飾ったり、趣味の人であれば趣味の品を祭壇に置いたりなど、その人らしいご葬儀のための演出も可能です。
内容についてのご要望があれば、事前にご相談なさってみてはいかがでしょうか。
これらが、ご相談前にイメージしていただきたいポイントとなります。ご希望をまとめていただいたうえで事前相談をしていただくと、ご葬儀の概要が見えてくることでしょう。
ご不安を和らげるお手伝いを
いかがだったでしょうか。
今回は、ご葬儀の事前相談についてご紹介させていただきました。
冒頭でも述べたとおり、漠然とご葬儀に対する不安を抱く方は少なくありません。
平安祭典のスタッフ一同、ご葬儀について知っていただくことで、皆さまのご不安を和らげるお手伝いをさせていただきたく思っています。
平安祭典(0120-00-3242)では、神戸・阪神間で事前相談を数多く行なっておりますので、気兼ねなくお問い合わせください。
また、神戸・阪神間で事前相談をご希望の方は下記のフォームからお申し込みください。
■事前相談予約フォーム
https://www.heiansaiten.com/inquiry/consultation.php
続きはこちら
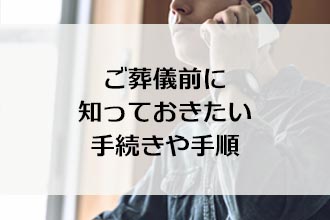
公開日:2021年2月22日
大切なご家族を亡くされたご遺族のお気持ちは計り知れません。悲しみから、何も手につかなくなってしまう方もいらっしゃいます。しかしながら、そのような深い悲しみの中でも、ご葬儀や必要な手続きをはじめ、故人様のためにしなければならないことが数多くあります。
いざという時に備えて、ご葬儀や必要な手続きの手順をあらかじめ理解しておくことは、とても大事なことです。今回は、いざという時に、どのような行動をとらなければならないか、ご葬儀を執り行なううえで知っておきたいことについてご紹介しましょう。
危篤・ご臨終の連絡
いざという時に、どのような行動をとらなければならないかをご紹介します。まずは、ご家族が危篤となったり、ご臨終を迎えた時にすべきことです。
危篤の連絡
危篤とは、亡くなる危険が切迫している状況のことです。医師から危篤と告げられた際には、その場にいないご家族やご親族など、最期に立ち会ってほしい方々に連絡を行ないます。
特に遠方に住むご家族やご親族には、早めにお伝えしたいところです。ちなみに、深夜に医師から危篤を伝えられた場合は、ご親族に電話連絡をしても失礼にはあたりません。
ご臨終の場合
息を引き取られた際には、医師が死亡確認後、医師に死亡診断書(死亡届)を作成してもらいます。ご遺族が死亡届に必要事項を記入し、死後7日以内に役所の戸籍課に提出することで、戸籍や住民登録が抹消され、火葬許可証が交付されます。
死亡診断書は生命保険や社会保険の手続きに必要となります。なお、これらの手続きは、葬儀社が代行することが多いです。
ご臨終の連絡は、ご家族・ご親族に先に行ない、続いて故人様が親しかったご友人・知人に連絡します。故人様が生前お世話になった会社関係の方・近隣の方にも、忘れずにお伝えしましょう。日頃から、いざという時に備えて連絡先リストを作っておくと良いでしょう。
※海外で亡くなった場合は、3ヶ月以内に死亡届を提出することになっています。
ご葬儀の準備(仏式)
続いては、仏式でご葬儀を行なう際の準備についてです。
葬儀社への連絡・ご葬儀の準備
病院でお亡くなりになった場合には、医師が死亡確認をしたあと、入会している葬儀社や生前に事前相談を行なった葬儀社に連絡し、寝台車の手配・ご葬儀の準備を依頼します。寝台車が到着するまでに身支度を整え、医師から死亡診断書(死亡届)を受け取ります。
ご自宅でお亡くなりになった場合、かかりつけの医師が看取る、あるいは24時間以内に診察や治療を行なっていて事件性がない(持病もしくは老衰による自然死)と判断した際には、かかりつけの医師が死亡診断書を作成します。
一方、かかりつけの医師がいない場合には、すぐに119番にかけ状況を説明し、救急車を手配します。その際にはご遺体にはなるべく触れないようにしましょう。
蘇生の可能性がないと判断されると救急隊員が警察に連絡します。そのあと、警察医がご遺体の検案(検査)をし、死体検案書を作成します。
葬儀社に連絡する際には、以下の内容を伝えましょう。
・ 故人様・連絡された方の名前・続柄・連絡先
・ 故人様が現在いらっしゃる場所(病院など)、ご安置先(ご自宅など)
・ 事前相談の有無(加入者証があれば加入者名義や番号)を伝えます
ご寺院への連絡
故人様をご自宅や葬儀会館にご安置したあと、ご寺院へ連絡を行ない、ご葬儀の日程調整(お通夜、葬儀・告別式の日時の調整)をします。ご葬儀の日程は、ご寺院の予定・火葬場の状況をふまえて決まります。
お付き合いのあるご寺院がない場合には、葬儀社がご紹介しますので、ご安心ください。
各方面への連絡
すべての日程が確定した時点で、関係各所へ訃報連絡を行ないます。一般葬ではなく、家族葬を執り行なう場合であっても、ご遺族が家族葬でお送りする意思を明確に伝えるため、お知らせしたほうが良いでしょう。
ご葬儀を行なううえで必要なもの
最後に、死亡時の手続き・ご葬儀で必要となるものをご紹介します。
死亡診断書(死亡届)
先ほどもご説明したとおり、ご家族が病院で亡くなった際には、医師に死亡確認および死亡診断書(死亡届)を作成してもらいます。死亡届は火葬許可証の取得に必要であり、死亡診断書は生命保険の手続きなどに必要となります。死亡診断書は複数コピーをとっておくと役立ちます。
はんこ
死亡届の作成をはじめとした各種役所手続き、葬儀社との各種書類の作成など、何かと必要となるのがはんこです。認め印で構いませんので、常に携帯しておきましょう。シャチハタ印は避けたほうが無難です。
ご葬儀費用
ご葬儀にかかった費用は、ご葬儀が執り行われたあと2~3日ほどでのお支払いとなります。また、お通夜・ご葬儀当日には、ご寺院に御布施をお渡ししなければなりません。生命保険がおりるまでには時間がかかるため、ある程度の現金が必要となり、事前に準備しておく必要があります。
遺影用のお写真
遺影に用いるお写真は、可能なかぎり大きいサイズで、顔が鮮明に映った写真を選ぶと良いでしょう。服装や背景は修正が可能です。疑問点があれば、葬儀社にご相談ください。
平安祭典でも事前相談を承っております。
神戸・阪神間で事前相談をご希望の方は下記のフォームからお申し込みください。
■事前相談予約フォーム
https://www.heiansaiten.com/inquiry/consultation.php
「エンディングノート」がご家族の負担を軽減する
今回は、いざという時のために準備しておきたいことについて、ご紹介させていただきました。
余談ですが、残されたご家族の負担を軽減するひとつの方法に
「エンディングノート」というものがあります。
エンディングノートとは、ご家族に向けて、様々な情報をまとめておくことができるノートのことです。終活ノートとも呼ばれ、ご家族にご自身の情報やご葬儀の希望を伝えることができるものです。
例えば銀行の通帳やカードの情報。身内同士であっても、どこの銀行に通帳やカードを持っているか、すべて把握しきれているわけではありません。エンディングノートに、このような情報を記載しておくと、万が一の際には、ご家族の負担が軽減されるのです。
気になる方は、活用されてはいかがでしょうか。
エンディングノートについては###endingnote_kakikata###の記事で詳しくご紹介しております。
平安祭典でもオリジナルのエンディングノート(無料)をご用意しています。
神戸・阪神間で、エンディングノートに興味をお持ちの方は
平安祭典NCP室(078-856-6890)まで、気兼ねなくお問い合わせください(もしくは、お問い合わせ・資料請求フォームから「エンディングノート希望」と、ご請求ください)。
■お問い合せ・資料請求ページ
https://www.heiansaiten.com/inquiry/inquiry.php
続きはこちら