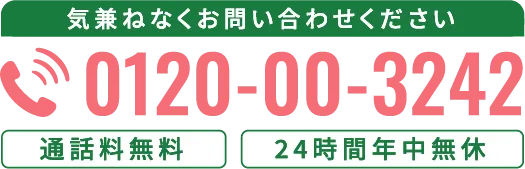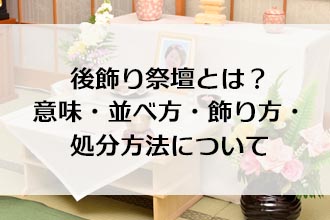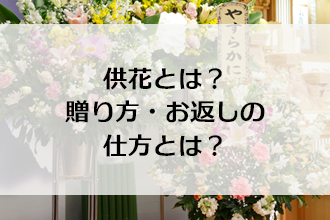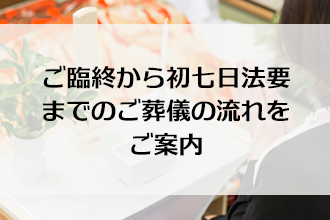枕経・枕飾り・枕花とは?それぞれの意味やマナーについて

公開日:2022年7月18日
ご親族や親しかった方が亡くなると、するべきこと・準備するべきものがあります。
枕経、枕飾り、枕花もその一部ですが、どのようなマナーがあるのかご存じない方も多いのではないでしょうか。
そこで、本記事では枕経(まくらきょう・まくらぎょう)、枕飾り(まくらかざり)、枕花(まくらばな)の意味やマナーについてご説明します。
[@目次@]
枕経とは故人様の枕元で読経すること

枕経とは仏教における儀式で、故人様の枕元で読経することです。
自宅で亡くなる方が多かった時代は、ご臨終が近づくと家にご寺院を呼び、息を引きとる前に枕元で読経をしてもらっていました。
読経によって、故人となる方が安心してあの世へ旅立てるようにという配慮からです。
しかし、大半の方が病院で亡くなる現在は、病院で枕経を行なうことは稀で、ご臨終後、故人様を安置した場所で行なうことが一般的となりました。
枕経のタイミングに特別な決まりはありませんが、会館やご自宅に故人様をご安置した後、できるだけ早く行なうべきとされています。
また、最近では通夜の時に枕経をあげることも少なくありません。
枕経の準備・参列について
続いては、枕経の準備および枕経に参列する際に知っておきたいマナーについてご紹介します。
枕経の依頼方法、参列される際の服装の参考にしてください。
菩提寺・檀那寺に連絡して枕経を依頼する

枕経は、菩提寺・檀那寺にお願いすることが一般的です。
喪主またはご遺族がご寺院に連絡して枕経を依頼し、故人様の安置場所を伝えます。
※菩提寺・檀那寺がない場合は葬儀社にご相談ください。
枕経の所要時間は30分~40分程度です。
枕経の際、ご寺院とお通夜、葬儀・告別式に関する必要事項や戒名などについて相談しておくと、その後の段取りがしやすいでしょう。
近親者のみ参列・地味な服装(平服)でOK
枕経はご臨終からご葬儀までの短い間に執り行なうこともあり、喪主とご家族など近親者のみが参列する場合がほとんどです。
枕経に参列する時の服装は、平服で良いとされています。
平服とはいえ、カジュアル過ぎるもの、派手な色や柄物、肌の露出が多いものなどは控え、落ち着いた色とデザインの地味な服装が望ましいでしょう。
結婚指輪や、パールの一連ネックレス(白または黒)以外のアクセサリー類は、身に付けるのを控えます。
枕飾りとは故人様の枕元に置くお供えもの

故人様は、お通夜、葬儀・告別式までの間はご自宅や会館などに安置されます。
枕飾りとは、この間、故人様の枕元に設置される祭壇です。
机、香炉、燭台、花瓶などを総称して枕飾りといいます。
机の上にお供えするものは、宗旨・宗派、地域によって異なりますが、通常は葬儀社が枕飾りを準備してくれます。
枕飾りは、故人様を安置してすぐ設置されますが、その理由はお通夜の前に弔問に訪れる方に焼香や礼拝を行なってもらうためです。
つまり、枕飾りは簡易的な祭壇の役割を担うものなのです。
また、枕飾りは故人様の魂を導く「道しるべ」でもあります。
人の魂は体から離れた後も現世に留まろうとするといわれるため、故人様の魂をあの世へと導くために、枕経や枕飾りによる供養を行なうのです。
ところで、「枕飾りは後飾り祭壇とは違うのか?」という疑問を持たれる方がいらっしゃるかもしれません。
後飾り祭壇は、火葬後にご自宅でご遺骨を忌明けまで祀るための祭壇であり、枕飾りとは異なります。
後飾りについては、『後飾り祭壇とは?意味・並べ方・飾り方・処分方法について』でも詳しく解説しております。
枕飾りの内容は宗旨によって異なる
枕飾りの内容は宗旨や地域によって異なります。ここでは仏式並びに神式の一例をご紹介します。
先にご説明したように、枕飾りは葬儀社が準備することが多いですが、ご自身でも用意できます。
いずれにしても、わからないことがあれば葬儀社のスタッフやご寺院にご確認いただくと安心でしょう。
仏式の枕飾り
仏式の基本的な枕飾りは、以下のものを揃えます。

・ 白木の台や白布を掛けた台
・ おりん
・ 香炉
・ 線香
・ 燭台
・ 花瓶
・ 樒
・ 水
・ 一膳飯
※地域によっては枕団子を用意することもあります。
※宗派によって枕飾りの内容が異なる場合があります。
神式の枕飾り
神式の基本的な枕飾りは以下のものを揃えます。

・ 八足案(白木の台)
・ 三宝方
・ 洗米
・ 塩
・ 水
・ お神酒
・ 花瓶
・ 榊
枕花とは故人様を悼み枕元に供える花

枕花とは、ご臨終後、故人様が安置されている枕元にお供えするお花のことです。
ご遺族からいち早く訃報を受け取った方が、ご自宅や会館など故人様が安置されている場所へ贈ります。
届いた枕花の飾り方や並べ方に特に決まりはなく、故人様の枕元周辺にお供えすることが一般的です。
枕花は故人様に対する深い哀悼の気持ちを表すものであり、自分の代わりに故人様に寄り添うという意味が込められています。
故人様にお供えした後、お通夜、葬儀・告別式を行なう場所へ移動する際に、一緒にお持ちいただくこともできます。
誰が出す(贈る)?贈り方は?枕花に関するマナー

ご親戚やご友人の訃報を受けた時、「自分は枕花を贈るべきか?」と悩む場合があるかもしれません。
ここでは枕花を贈るかどうかの考え方と、実際の贈り方やマナーについて解説します。
枕花は故人様と親しかった方や近親者が贈る

一般的に枕花を贈るのは、近しいご親戚や特に親交の深かった方が亡くなった時です。
少しでも早く故人様に寄り添いたい、ご遺族の心を慰めたいという気持ちがあれば、枕花をお贈りすると良いでしょう。
枕花を贈るべきかどうか迷った時は、枕花の代わりに、お通夜、葬儀・告別式の式場に供花をお贈りする方法もあります。
枕花はお通夜開始までにご自宅(安置場所)へ贈る

訃報を聞いたらすぐに枕花を手配し、お通夜が始まるまでに故人様が安置されている会館やご自宅などに贈ります。
安置場所に直接お持ちいただいてもかまいません。
枕花を贈る際は、できるだけご遺族のご都合やお通夜のスケジュール、会館のルールなどを確認してタイミングや届け先を決めると、間違いなく受け取ってもらいやすいでしょう。
枕花は籠花で贈ることが一般的

枕花は、白を基調(葉の緑は可)とした籠花(アレンジメント)で贈ることが一般的です。
白以外に青・紫系などの淡い色を加えても失礼にはあたりませんが、バラなどトゲのついた花や香りが強い花は避けましょう。
枕花としては菊、ユリ、カーネーションなどが良く使われており、大きすぎない控えめな籠花が基本です。
枕花の価格は依頼先やアレンジメントの内容によって異なりますが、相場は5,000円~20,000円程度です。
生前の故人様との関係性をふまえて決めると良いでしょう。ちなみに、平安祭典では5,500円(税込)で販売しております。
まとめ

今回は、枕経、枕飾り、枕花について解説しました。
ご遺体の安置場所では故人様の枕元に枕飾りや枕花をお供えし、枕経を行ないます。
故人様への最初の供養として大切なものですので、ご不安な点は葬儀社のスタッフに確認しながら後悔のないよう執り行ないたいものです。
神戸・阪神間で、ご葬儀・ご供養に関するお困りごとがございましたら、平安祭典(0120-00-3242)にご相談ください。