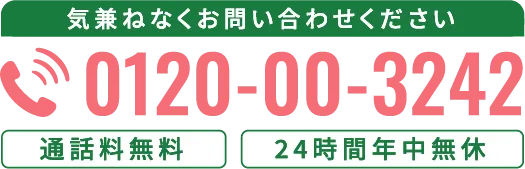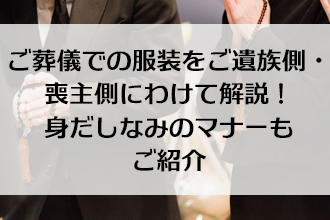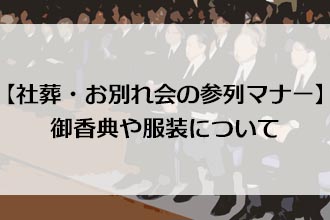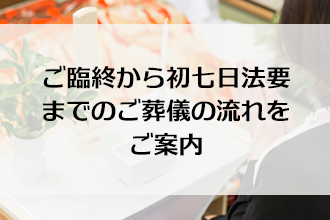社葬・お別れ会とは?流れや参列について

公開日:2021年11月15日
企業の創業者や会長、社長など、企業(団体)の発展に大きく貢献した方が亡くなった際に、「社葬」としてご葬儀を執り行なうことがあります。
社葬は企業の規模に関わらず、いわゆる中小企業であっても執り行なわれますが、「一般的なご葬儀とは具体的にどのような違いがあるのか?」と、疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
今回は「社葬」について、参列の際の注意点なども踏まえてご紹介いたします。
[@目次@]
社葬とは?

一般的に「社葬」とは、企業に多大な功績を残した人物のご葬儀を企業が主体となって行なう、社会的なご葬儀のことを指します。(団体が主体となる場合には「団体葬」)
ご葬儀の運営を親族が主体となって行なう一般的なご葬儀である「個人葬」に対し、企業がその役割を担い、ご葬儀に掛かる費用を企業が負担するのが「社葬」の特徴です。
一般的なご葬儀は「故人の死を悼み、親類やご縁のあった方々でお見送りをする」というプライベートな弔いに重きを置きます。
これに対し、企業を挙げて功労者を追悼し偲ぶことは、故人への何よりの供養であるとともに、対外的には新体制での事業継承を訴え、社内においては故人の遺志を継いで社員一丸となり邁進する決意を新たにする場でもあります。
社葬を執り行なう場合、会場の設営や参列人数など、個人葬よりも規模が大きくなることが多く、準備や打ち合せにも時間が掛かります。
その為、亡くなられてすぐには個人葬(※)を行ない、その後、準備期間をおいて、改めて社葬を執り行なうことが一般的です。
社葬の開催時期に厳密な決まりはありませんが、関係各所への連絡や準備期間も考慮し、忌明け法要(四十九日法要)の前後の時期に合わせて執り行なうことが多いようです。
「個人葬」にも「家族葬」や「一般葬」など形式による通称があるように、「社葬」にも形式によって呼び名が変わる場合があるので、以下で詳しくご説明します。
※ 先行して行なわれる個人葬は「密葬」と呼ばれ、後日「本葬」として執り行なう社葬とは違い、広く案内はせずに近親者と関係者のみで執り行なうことが一般的です。
社葬の形式 合同葬やお別れ会との違い

企業が主体となって執り行なう社葬にも、形式によって「合同葬」や「お別れ会」、「偲ぶ会」など、呼び名が違う場合があります。
これらの意味を、一般的な社葬との違いも含めてご紹介します。
・ 社葬
運営:企業
費用負担:企業
企業(団体)が運営して執り行なう、企業の発展に貢献された方を顕彰(けんしょう)するためのご葬儀です。
故人の信仰されていた宗旨・宗派、もしくは自由葬(無宗葬)で執り行なわれます。
多くの場合、ご遺族、近親者の方のみで個人葬を行なったあとで、本葬として社葬を執り行ないます。
・ 合同葬
運営:ご遺族と企業
費用負担:企業(※)
複数の企業が共同で運営するご葬儀、もしくはご遺族と企業が協同で運営するご葬儀のことを「合同葬」といいます。その場合には、「株式会社●●と株式会社△△の合同葬」、「〇〇家と株式会社●●の合同葬」というような案内をすることが一般的です。合同葬としてご葬儀をされる場合には、社葬・お別れ会のように先行する個人葬と分けて後日改めて行なうのではなく、本葬として執り行なうことも多いようです。
・ お別れ会(偲ぶ会)
運営:企業
費用負担:企業
社葬のスタイルの1つです。基本的には社葬と同じですが、宗教色をなくした式典行事の場合にこの名称を利用することが近年多くなりました。
また、企業だけでなく、故人と縁のある有志が集まって式典を行なう場合にもこの名称が使われます。
葬儀会館やホテル、レストラン、会社施設内の会場などを使用することが一般的です。
式典の進行にも融通が利くため、一定時間セレモニー(弔辞、弔電披露、代表者挨拶、ご焼香や献花などの進行)を行なう場合もあれば、故人の業績などをパネル展示した会場に献花場を設け、到着した方から順に立食形式で軽食を振る舞うという例もあります。
※社葬全般に関わることですが、社内に社葬に関する規定がある場合、
「どこまでの費用を会社側が負担するのか」が明確に定義されていることが多いです。
合同葬の場合は特に、聖職者への御礼など、一部はご遺族側の負担となることもあるので、事前に各企業の社葬規定を確認しておく方が良いでしょう。
社葬の流れ 一般社員は参列できる?

企業が主体となる場合、規模の大きさに関わらず「社葬」という扱いになりますが、個人葬として執り行なわれる一般的なご葬儀と比べると、規模が大きくなることが多いです。
前述したように、主体となるのが誰か、行なう時期、内容は宗教儀礼に則るか否か…など様々な要因により、「社葬」・「合同葬」・「お別れ会」といった名称は変わります。
それぞれに進行の仕方も違うため、一概に決まった「社葬の流れ」というものはありません。
ただし、宗教儀礼に則った形で執り行なう場合は、個人葬と流れは大きく変わりません。
社葬の場合は、故人のご功績の紹介や、代表者からの弔辞などが付け加えられることもありますが、基本的にはそれぞれの宗旨・宗派の一般的な葬儀・告別式と同じと言えるでしょう。
ご葬儀の流れについては『ご臨終から初七日法要までのご葬儀の流れをご案内』で詳しくご説明しています。
・ 社外の社葬の場合
参列に関しては、亡くなってすぐの個人葬(密葬)は近親者と関係者(友人・知人や会社の代表など)で行ない、その後改めてご案内を出す「社葬」や「お別れ会」の場合は、案内が届いてから参列者を社内で決めます。
多くの場合、会社の代表として参列することになるので、故人と同等以上の役職の方、もしくは個人的に繋がりがあった方が参列されます。
「合同葬」の場合も、参列者を選ぶ基準は上記の「社葬」や「お別れ会」と基本的には同じです。
ただし、亡くなられてすぐに本葬として執り行なうことが多いため、日程の連絡が届くのが直前となることもあり、本来なら参列すべき方のスケジュールの調整が難しいということもあるでしょう。
その場合は、参列には代理人を立て、当日までに弔電などを送ることも可能です。
・ 社内の社葬の場合

会社の規模や開催場所、日程などによっても変わりますが、一般社員も含めて社員全員が参列するというケースは少なく、「役員のみ参列」など、範囲を決めて参列することが一般的です。
ただし、社葬の場合、受付や来賓の座席への案内役などは、一般社員が担当することが多いです。
中には、遠方にいる社員がお参りできるように遥拝所を設けたり、朝礼時に黙祷を捧げるなどの対応を取る会社もあります。
また、当社では、合同葬として執り行なったお式のご出棺に際し、霊柩車が火葬場に向かう前に会社の前を通り、社員の方々が外に並んでお見送りをされた…というような例もございます。
なお、開催側、参列側に関わりなく、社葬の場において名刺交換をすることはマナー違反とされるため、注意しましょう。
社葬の参列のマナーについては『【社葬・お別れ会の参列マナー】御香典や服装について』ので詳しくご説明しています。
まとめ

今回は社葬について、形式による名称の違いや、参列の際の注意点などをご紹介いたしました。
社葬は社会的な行事であるため、関係各所に失礼のないよう、気を付けなければいけないことも多いでしょう。
とはいえ、社葬は一般的なご葬儀と違う点もありますが、「故人を偲び、ご遺族に寄り添う」という本質は変わりません。
平安祭典では、社葬を始め、各種団体葬お別れ会など、様々な形式のご葬儀だけでなく、自治会・企業主催の慰霊祭などもお手伝いしております。
社葬のノウハウを持ったスタッフが多数在籍し、事前準備から当日の運営までトータルでサポートさせていただきます。
平安祭典では社葬を行なうことが可能です。詳細は下記のページをご覧ください。
神戸・阪神間で社葬などのご要望がございましたら、平安祭典(0120-00-3242)までお問い合わせください。