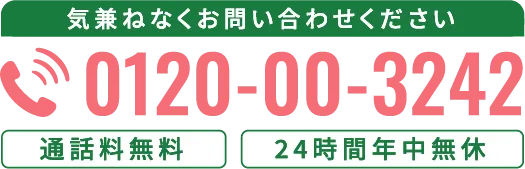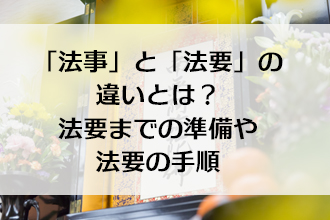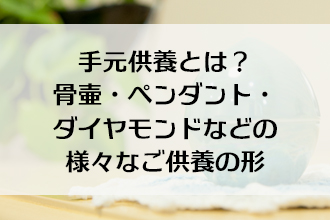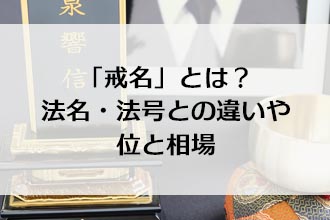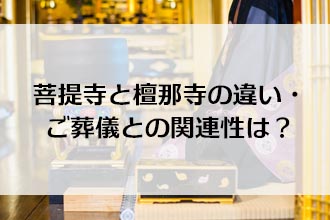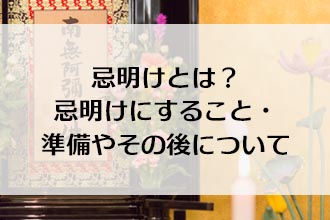意外と知らない「位牌」とは?役割や種類について

更新日:2024年9月22日 公開日:2022年3月7日
位牌(いはい)とは故人様の霊が宿る木の札で、仏壇に祀(まつ)られる大切な仏具です。
しかし「見たことあるけれど、実際にどのような役割を持つものなのかは知らない」という方も多いようです。
そこで今回は意外と知らない位牌についてご説明します。
[@目次@]
礼拝の対象として用いられる位牌

そもそも位牌とはどのようなものなのでしょうか。
位牌とは、仏教においてご供養に用いる仏具で、表面に故人様の戒名(日蓮宗は法号)や俗名(生前の名前)、裏面に没年月日、享年を記した木の札のことです。
主に仏壇に安置され、故人様の依代(よりしろ=霊が宿る対象物)であり、礼拝の対象として用いられます。
ちなみに、位牌は中国の儒教にルーツを持つ風習であるとされ、日本では鎌倉時代から室町時代にかけて禅宗の聖職者が広め、江戸時代には一般庶民に普及したとされています。
なお、数え方は1本、1基などが使われることが多いですが、正しくは「柱(はしら)」で、1柱(ひとはしら)、2柱(ふたはしら)……と数えます。
浄土真宗では位牌の代わりに法名軸や過去帳を用いる

同じ仏教でも、浄土真宗では位牌を祀りません。
これらの宗派では「故人様の魂は亡くなるとすぐに成仏しているため、位牌を祀り礼拝の対象とする必要はない」という考え方があるからです。
浄土真宗では、位牌の代わりに法名軸(法名・没年月日を記した掛軸)や過去帳(法名・俗名・没年月日・享年を記した帳簿)を用います。
ただし、浄土真宗の中でも専修寺系の真宗高田派や地域によっては位牌を祀ることがあります。宗派が浄土真宗の場合には、事前にご寺院にご確認ください。
※浄土真宗では、戒名と呼ばず法名と呼びます。
※浄土真宗は、阿弥陀如来(阿弥陀仏)のみを礼拝の対象としているため、法名軸や過去帳は礼拝の対象ではありません。位牌を祀る真宗高田派においても同様で、礼拝の対象ではありません。
宗派につていは『仏教における「宗派」とは?宗旨・宗派の違いや意味を解説』で詳しくご説明しています。
位牌には大きく分けて3つの種類がある
位牌と聞くと、多くの方は仏壇に祀られているのをイメージするのではないでしょうか。それは「本位牌」と呼ばれるものです。
「本位牌」以外にも「白木位牌」「寺位牌」と、大きく分けて3つの種類が存在します。
この3つの違いについてもご説明します。
・白木位牌
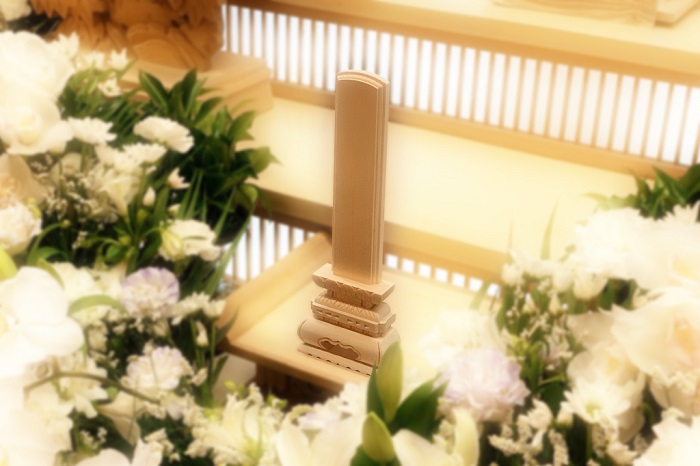
「白木位牌」とは、故人様がお亡くなりになった直後に作られる仮の位牌で、「内位牌」とも呼ばれます。
文字通り白木(しらき=塗料などで加工しないそのままの木材)に、故人様の戒名や俗名、没年月日、享年を記します。
ご葬儀では祭壇に祀られ、ご葬儀後も中陰祭壇(忌明け法要までご遺骨を祀る祭壇)に安置されます。忌明け法要を迎えた後、「本位牌」に替えます。
あくまで四十九日法要までの仮の位牌が「白木位牌」です。
・本位牌
「本位牌」は塗り位牌とも呼ばれ、忌明け法要を迎えた後「白木位牌」に替わり、仏壇に祀られる
位牌のことです。
漆塗りに金箔・沈金・蒔絵などが施された、多くの方がイメージされるであろう位牌です。
四十九日になると故人の魂は成仏し、本位牌に移りますので、それまでに用意しておく必要があります。
ちなみに「本位牌」の作成には、文字彫り・文字書き、漆塗り・検品等に約2週間かかります。
「忌明け法要に間に合わなかった」ということのないよう早めに手配しておきましょう。
・寺位牌
「寺位牌」とは、菩提寺(壇那寺)や本山
(=宗派における特別なご寺院)に安置
するための位牌のことです。
檀家が「本位牌」とは別に「寺位牌」を祀る他、
様々な事情でご自宅に位牌を安置できない方や
永代供養を望まれる方が「寺位牌」を利用します。
平安祭典では各種位牌のご相談を承っています

いかがだったでしょうか。
今回は仏壇に祀られ、礼拝の対象となる位牌についてご説明しました。
皆さまのご参考になれば幸いです。
平安祭典では、ご葬儀・ご供養に関する各種ご相談を承っています。
神戸・阪神間でお困りごとがございましたら、平安祭典(0120-00-3242)まで気兼ねなくご相談ください。