

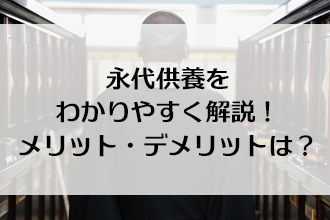
公開日:2022年9月12日
お墓について調べていると「永代供養」という言葉を時折目にします。
永代供養と聞いたことはあっても、漠然としたイメージしかない方が多いのではないでしょうか。
この記事では、永代供養とはどういうものか、費用やメリット・デメリットなどについて解説します。
[@目次@]
永代供養とはどのようなご供養の方法?
永代供養(えいたいくよう)とは、霊園やご寺院がご遺族やご家族に代わって故人様をご供養し、お墓を管理する方法です。
以前は永代供養というと、「身寄りがない」「跡継ぎがいない」「お墓を建てる費用を捻出できない」といった理由で選ばれることが多いものでした。
しかし近年では、宗教観の変化や核家族化が進んだことによって、「子どもにお墓のことで面倒をかけたくない」「お墓よりお金を遺したい」といった理由で永代供養を選ばれる方が増えています。
それではまず、永代供養がどのようなものか詳しく見ていきましょう。
霊園やご寺院にご遺骨を管理・供養してもらう
通常は、ご遺族が年忌法要の際やお盆、お彼岸などにお墓を掃除し、お線香やお花を供えてご供養しますが、永代供養の場合は、一連の管理やご供養をすべて霊園やご寺院にお任せするため、お墓にお参りすることができなくても安心です。
納骨堂と永代供養を混同される方もいらっしゃいますが、管理やご供養の方法に違いがあります。
納骨堂の場合は管理・供養をご遺族が行なうのに対し、永代供養の場合はすべてを霊園やご寺院にお任せできる点が大きな違いです。
納骨堂に関しては、###noukotsudou_toha###で解説しています。
永代使用とはどう違う?
永代供養と似た言葉に「永代使用」がありますが、両者は次のように違う意味を持ちます。
永代供養…永代にわたりご供養してもらうこと
永代使用…永代にわたり墓地を使用すること
永代使用は永代(永い年月)にわたってお墓を使用することで、お墓を建てる場合は永代使用料を支払い、墓地(お墓の土地)を使う権利を取得します。
永代供養の費用について
永代供養を選ぶ場合、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。
お墓の種類などによってさまざまなので、よく確認しておきましょう。
ここからは永代供養の費用について解説します。
永代供養の種類で費用が変わる
永代供養にはさまざまな種類があり、お墓の仕様や大きさ、デザインなどによって費用は変わります。
種類は大きく分けると以下の4つです。※費用はあくまでも目安です。
① 合祀墓(合葬墓)(10万円~30万円)
他の方のご遺骨とあわせてお祀り(合祀)する形式のお墓です。
個別の墓標などはなく、共用の石碑や塔などに手をあわせることになります。
② 樹木葬での永代供養(30万円~70万円)
樹木を墓標とするお墓で、樹木や花壇の下に納骨します。
1名ごとに1本の木を植える場合や、1本の樹木の周りに複数のご遺骨を納める場合などがあります。
③ 納骨堂付きの永代供養(50万円~100万円)
屋内の納骨堂に個々のご遺骨を納める形式の永代供養です。
ロッカー式、自動搬送式(マンション型)、仏壇式、棚式など、さまざまな形態があります。
弔い上げとなる三十三回忌で合祀されることが多いようです。
④ 個人墓のある永代供養(70万円~150万円)
個人墓に永代供養が付いたものです。
故人様1人だけを納めるお墓や、家族みんなを納めることのできるお墓など、さまざまな種類があります。
こちらも三十三回忌を目途とすることが多いようです。
永代供養の場合もお布施が必要
永代供養では、基本的にお墓を管理するご寺院が定期的にご供養を行なうため、ご遺族はご法要を行なわなくても問題ありません。
※ご供養を行なう時期や頻度はご寺院によって異なります。
ですが、故人様の追善供養のためにご遺族がご法要を行なうことももちろん可能です。その場合はお布施が別途必要です。
ただし、永代供養を檀那寺と別のご寺院に依頼している場合、ご遺骨前でご法要したいときは永代供養を依頼しているご寺院へ事前に確認しておきましょう。
永代供養のメリット・デメリット
永代供養のメリットとデメリットは、それぞれいくつかあります。
後悔されないよう、メリットとデメリットを比較のうえ、ご家族でよく検討されてはいかがでしょうか。
メリット
永代供養のメリットは、次の4点です。
① 子ども(後の世代)の金銭的負担が少ない
一般的なお墓では、年間管理費を支払い続ける必要がありますが、永代供養の場合は、基本的に合祀後は年間管理費が不要となります。
また、霊園やご寺院によっては、最初から年間管理費が不要な場合もあります。
② お墓参りでの時間的・体力的な負担が少ない
お墓の管理やご供養をすべて霊園やご寺院に任せられるので、いつでもお墓はきれいな状態に保たれます。
また、永代供養のお墓は比較的交通の便が良い場所にあることが多いです。お墓参りの際に移動の負担が少ないのはメリットでしょう。
③ 子どもにお墓の問題で気苦労をかけない
たとえば1人娘が嫁いだ場合などは、実家のお墓の管理について悩むかもしれません。
お墓を引き継ぐ人がいないと、「実家と義理の実家のお墓の両方を管理しないといけないのかな?」「実家のお墓は墓じまいした方が良いのかな?」など、気苦労をかけてしまいます。
永代供養であれば、お墓の管理を霊園やご寺院に任せられるため、お墓の問題での気苦労を減らすことができます。
④ お墓を建てるよりも費用を抑えられる
お墓を新たに建てると、永代使用料や墓石代などでかなりの額になります。
永代供養で合祀専用のお墓を選んだ場合、費用を抑えられるでしょう。
デメリット
永代供養のデメリットとしては、次の3点が挙げられます。
① 合祀されたご遺骨は元に戻せない
永代供養の合祀では、ご遺骨を骨壷から取り出し、他の方のご遺骨と一緒に埋葬することが一般的です。
後から別のお墓に納骨したり、分骨することはできません。
② ご親族の理解が得られない場合がある
永代供養は、古くから行なわれている供養方法です。
とはいえ先祖へのご供養にこだわりがあったり、古くからの風習を重んじる方には理解しづらい部分もあるでしょう。
ご親族に反対されないためには、事前によく相談されることが大切です。
③ お墓参りでプライベートな時間を持ちにくい
専有スペースや個別の墓石がない永代供養を選んだ場合、合同の供養塔に手を合わせることになります。
そのため、故人様との想い出を振り返ったり、家族の健在を報告したりという、プライベートな時間を持ちにくいかもしれません。
まとめ
当記事では、永代供養について解説いたしました。
ライフスタイルの多様化に伴って、ご葬儀やお墓の形態も多様化しています。
とはいえ、なにより大事なことは、故人様や先祖を大切にするお気持ちです。
お悩みやご不安がございましたら、気兼ねなく平安祭典(0120-00-3242)までご相談ください。
続きはこちら
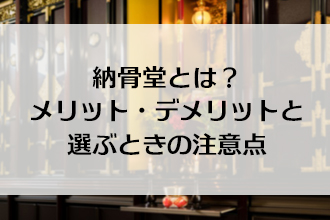
公開日:2022年9月5日
従来、納骨の場所はお墓が一般的でした。
しかし近年、お墓の新しいスタイルである「納骨堂」に興味を持たれる方も増えているようです。
この記事では、納骨堂の定義や種類、納骨堂を選ぶ時の注意点、納骨堂のメリット・デメリットについて解説します。
[@目次@]
納骨堂とはなに?その定義について
納骨堂とは、ご遺骨を収蔵する施設のことです。
一般的に屋内にあり、1つの建物の中にたくさんの収納スペースが設けられています。
法律では、「他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設」(墓埋法第2条第6項)と定められています。
そのため、ご寺院や教会のような宗教施設であっても、許可がなければ他人のご遺骨を長期間預かることはできません。
ただし、ご遺族がご遺骨を自宅で保管する場合は、「他人から委託を受けて」にあてはまらないため、違法ではないと解釈されています。
実は納骨堂は昭和初期からあり、もともとはご遺骨を一時的に預かるためのものでした。
近年では、長期にわたってご遺骨をご供養する場所として、お墓の代わりに利用されています。
納骨堂を利用する際は通常、使用期間を決めて申し込みます。
30年や50年を区切りとしたり、ご法要の節目に合わせるなど、施設が設けているプランの中からご希望に応じて選択することが一般的です。
施設にもよりますが、使用期間が終了した後は、施設内にある供養塔などへ合祀されるケースが多いでしょう。
納骨堂は運営母体によって、大きくは3つに分けられます。
① ご寺院が運営する納骨堂
② 自治体が運営する公営の納骨堂
③ 民間が経営する民営の納骨堂
ご寺院が運営する納骨堂であっても、一般的には宗派を問わずご遺骨を預けられ、檀家になる必要もありません。
また、納骨堂に関連して「永代供養」という言葉もよく聞きますが、納骨堂はお墓の形式のひとつであり、永代供養はお墓の管理形態のひとつです。
永代供養とは、ご遺族に代わり、お墓の管理者にご遺骨の管理やご供養をしてもらう仕組みです。
納骨堂でも、永代供養費を支払って使用期間中の管理やご供養を委託できる「永代供養型」と呼ばれるものもあります。
永代供養については、###eitaikuyou_toha###で詳しく解説しています。
納骨堂のメリット・デメリット
「お墓の継承者がいない」「お墓を建てて管理する費用負担が大きい」といった問題の解決策として注目される納骨堂ですが、一般的なお墓と比べて困ることや問題点はないのでしょうか。
ここからは、納骨堂のメリットとデメリットについてご説明します。
メリット
納骨堂のメリットは、以下の8点です。
① 季節や天候を問わずお参りできる
基本的に屋内なので、空調の利いた環境でいつでも快適にお参りができます。
② シニアに優しい
納骨堂の多くはエレベーターが完備され、バリアフリー化もされているため、お年寄りや車いすの方もお参りしやすいでしょう。
③ 交通アクセスが良い
「駅から近い」「公共交通機関で行きやすい」などアクセスの良い納骨堂が多く、電車や徒歩でお参りに行けます。
④ 費用が抑えられる
一般的なお墓の場合、墓石代や墓地の永代使用料で数百万円のお金がかかります。
納骨堂なら、一般的にその数分の一の費用でご遺骨のご供養ができます。
⑤ 改葬しやすい
改葬(ご遺骨を他の場所に移して埋葬すること)をする場合、一般的なお墓と比べて納骨堂のほうが自由度が高く、手間とコストが少なく済みます。
⑥ 宗旨・宗派を問わない施設が多い
公営や民営の納骨堂では基本的に宗旨・宗派を問わずご遺骨を受け入れてくれます。
ご寺院の運営する納骨堂であっても、一般的に宗旨・宗派は問わず、檀家になる必要もありません。
⑦ 管理の手間が不要
納骨堂は屋内にあり管理者もいるため、掃除や草むしりなどの作業が不要です。
⑧ 無縁墓になる心配がない
一般的なお墓の場合、継承する人がいなくなると無縁墓となってしまいます。
納骨堂では、継承者がいなくなっても最終的には合祀してご供養を続けてくれるので安心です。
デメリット
納骨堂のデメリットとしては、以下の6点が挙げられます。
① 納骨スペースに制限があることが多い
納骨堂では、基本的に骨壷のままご遺骨を納めます。
1つの収蔵スペースに一緒に収蔵できる骨壷の数には制限があることが多いので、ご先祖のご遺骨も一緒にご供養されたいなどの希望がある場合は、注意が必要です。
② お線香を焚けない
屋内の納骨堂の多くは「火気厳禁」で、お線香が焚けません。
代わりに、火を使わないお香や電気式のロウソクを使う方法もあります。
③ 共同スぺースで参拝する場合がある
納骨堂によってはお参りするスペースが共用になっていて、他のご家族と顔をあわす場合や、混雑時は順番待ちをする場合もあります。
「好きな時にスムーズにお参りしたい」「プライバシーを重視したい」という方は参拝スペースについてよくご確認ください。
④ 最終的にご遺骨は合祀される
納骨堂ではほとんどの場合、使用期間を終えると他人のご遺骨と一緒に合祀されます。
将来的には個人のお墓ではなくなり、また、合祀後は改葬ができません。
⑤ 建物の老朽化・倒壊などの可能性
納骨堂は年月とともに老朽化していきますので、大地震などの自然災害による倒壊の可能性もあります。
修繕計画や災害対策がきちんと考えられている施設を選ぶと安心でしょう。
⑥ お供えが制限される場合もある
納骨堂によっては「食べ物やお酒はお供えできない」などの制限が設けられている場合があります。
納骨堂の各種類の特徴
一口に納骨堂といっても実はさまざまな種類があり、費用やプラン、骨壷の納め方、お参りの方法などが異なります。
ここでは代表的なものをご紹介します。
ロッカー式
ロッカー型で、ひとつのスペースに骨壷が1つから数個入る大きさが主流です。
使用スペースの広さによって費用は異なります。
メリット…比較的安価、個別の納骨ができる、想い出の品なども一緒に納められる
デメリット…スペースが小さい、下段にご遺骨を収蔵することへの抵抗感や不快感
自動搬送式(マンション型)
建物の内側に多くの骨壷を収納し、立体駐車場のようなシステムで運用される納骨堂です。
参拝スペースに来たご家族が専用のカードをかざすと、骨壷がコンピューター制御で運ばれてきます。
メリット…アクセスが良い、スタイリッシュ、セキュリティがしっかりしている、設備が充実している
デメリット…費用が比較的高い、故障や停電のリスクがある、お盆などは混雑する可能性がある
仏壇式
仏壇とお墓の両方の機能を備えた納骨堂で、上段が仏壇、下段にご遺骨を収蔵します。
骨壷のスペースは1人用から家族用まで、希望の大きさを選べます。
メリット…仏壇スペースを自由に使える、ご先祖のご遺骨を一緒に納めることもできる
デメリット…費用が比較的高い、宗教色がある
棚式
棚に骨壷を並べるタイプのシンプルな納骨堂です。
メリット…費用が安価
デメリット…個別のお参りができない
その他の種類
先にご紹介した5種類の納骨堂以外に、次のような納骨堂もあります。
・ 位牌式
屋内に位牌を並べます。
ご遺骨を位牌に入れるタイプと、位牌とは別の場所にご遺骨を安置するタイプがあります。
・ 屋内に墓石を建てるタイプ
屋内にお墓を建て、普通のお墓と同じようにお墓参りができます。
季節や天候に関わらずお参りがしやすく、お手入れも簡単です。
納骨堂を選ぶときに注意したいこと
納骨堂を選ぶ時によく確認したい点は主に次の3つです。
① お参りしやすい条件が揃っているか
年配の方でもひとりで安全にお参りできるかを考え、アクセス、周辺環境、施設内の設備(エレベーター・トイレ・休憩所など)をチェックしましょう。
参拝できる曜日と時間、お参りの手順や参拝スペースの環境が希望に合っているかも重要です。
② 費用とシステムが見あっているか
サービス内容や設備と費用が見あっているか、追加でかかる費用は何があるのか、よく確認しましょう。
複数の納骨堂を見比べてみると判断がしやすくなるはずです。
③ ご遺骨の収蔵方法と期間が希望にあっているか
収納スペースに納められるご遺骨の数、使用できる期間、使用期間終了後のご遺骨の扱いなどが希望にあっているか、よく確認したうえで契約しましょう。
まとめ
今回の記事では、納骨堂にはさまざまな種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあることをお伝えしました。
長きにわたり大切なご遺骨のご供養をする場所ですので、ご家族でよく話し合い、慎重に検討されることをおすすめします。
平安祭典では、ご葬儀・ご供養に関する各種ご相談を承っています。
神戸・阪神間でお困りごとがございましたら、平安祭典(0120-00-3242)まで気兼ねなくご相談ください。
続きはこちら
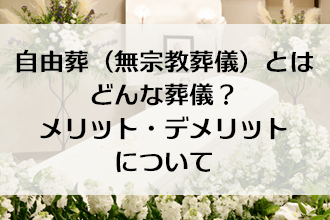
公開日:2022年8月22日
近年、「自由葬」(無宗教葬儀とも呼ばれます)という言葉をよく耳にするようになりました。
ご葬儀の形態が多様化する流れの中、ご自身やご家族のご葬儀として自由葬を検討される方も増えているようです。
そこで本記事では、自由葬の考え方と知っておきたいメリット・デメリットについて解説します。
[@目次@]
自由葬(無宗教葬儀)とはどんなもの?
まず、自由葬とはどのようなご葬儀なのかをご説明します。
自由葬の具体的な内容や流れの一例もご紹介しますので、参考としてお読みください。
特定の儀礼方式や作法のない自由なスタイルの葬儀
一般的に自由葬とは、特定の宗教によらない葬送儀礼を指します。
ご寺院、斎主様、神父様・牧師様といった聖職者による読経や説教を行なわず、自由なスタイルで故人様とのお別れをするご葬儀です。
平安祭典では、宗教的な観点からだけでなく、お客様の多様性を叶える葬儀形態という意味も含め、「自由葬」と呼んでいます。
自由葬は神や仏を否定したり、宗教的な儀礼を排除するものではありません。
たとえば、読経はないが焼香はするなど、ご寺院は呼ばずに仏式のスタイルを基本として執り行なわれることが最も多く見られます。
従来、日本におけるご葬儀のほとんどが仏教をはじめとする何らかの宗教儀礼により執り行なわれてきました。
しかし、ご葬儀に対する価値観の変化もあり、最近では伝統的なご葬儀の慣習にとらわれない新しいご葬儀の形も受け入れられつつあります。
自由葬(無宗教葬儀)の流れ
それでは実際の自由葬の流れをご紹介します。
以下はあくまで一例であり、内容や進行は故人様やご遺族が自由に決められますが、自由葬で最も多いのは、以下のような内容および進行です。
ご寺院を呼ばないので読経はありませんが、仏式のスタイルを基本としています。
・ 開式
・ 合掌
・ 喪主挨拶
・ 喪主焼香
・ 親族焼香
・ 一般焼香
・ お別れ
楽器演奏、スライドショー、お孫様からのお別れの言葉(弔辞)などを盛り込む場合もあります。
また、式場もホテルなど明るい雰囲気の場所を選ぶ方もいらっしゃいます。
自由葬に関して「こんな内容にしたい」「こんなスタイルで送りたい」というご希望がある場合は、ぜひ葬儀社のスタッフにご相談ください。
自由葬(無宗教葬儀)のメリット・デメリット
新しいスタイルのご葬儀として認知されつつある自由葬には、メリットだけでなくデメリットもあります。
自由葬に興味がある方はどちらも把握したうえで、よく検討いただくと良いでしょう。
<メリット>
・ ご葬儀の内容を自由に決められる
形式にとらわれず、故人様やご遺族の希望どおりのご葬儀が行なえます。
ご遺族にとって納得感のあるご葬儀になるでしょう。
・ より深く故人様を偲ぶ葬儀になりやすい
演出や装飾も故人様の個性や好みを反映できるため、故人様をより深く偲ぶご葬儀ができるでしょう。
・ 自分らしい価値観を大切にできる
宗教的儀礼に意義を感じない方にとっては、より自分の価値観にあった有意義なご葬儀を実現できます。
・ ご寺院などへのお礼が不要である
聖職者を呼ばないためお礼は必要ありません。
<デメリット>
・ ご家族やご親族の理解が得にくい
宗教儀礼のない自由葬にご家族やご親族が抵抗感を持ち、異議や不満が出る場合もあります。
周囲の理解と協力を得るためには、日ごろから自由葬に対する考えを伝えて話し合うなど、準備や調整を行なっておくと良いでしょう。
・ 参列者が服装やマナーについて戸惑う
ご葬儀といえば仏式がスタンダードなため、自由葬は初めてや不慣れという方が多いでしょう。
参列される方が戸惑わないよう、ご葬儀の案内の際には御香典・服装・式の内容などをできるだけ詳しく伝え、当日も何かと気配りをすることが大切です。
・ 菩提寺・檀那寺との関係に支障が出ることがある
菩提寺・檀那寺があり、その境内のお墓への納骨を考えている場合は注意が必要です。
必ず事前に菩提寺・檀那寺に意向を伝え、ご相談ください。
・ 思ったより費用がかかる場合がある
「楽器の奏者を呼ぶ」「スライド作成を依頼する」「特別な装飾をする」といった演出をすると、最終的に通常のご葬儀と変わらない費用がかかることもあります。
自由葬なら費用を抑えられるとは限らず、内容によって費用はさまざまです。
自由葬(無宗教葬儀)参列時のマナーについて
ここからは、自由葬に参列する際のマナーについてご説明します。
基本的なマナーは一般葬と同じだと考えて問題ありませんが、ご遺族から案内や指定があれば、それに従いましょう。
一般葬と同じく香典は必要
自由葬の場合も一般葬と同様に御香典を持参することが一般的です。
御香典の金額も一般葬と同じように考えてください。
詳しくは###kouden_manner###でご確認いただけます。
不祝儀袋について、特定の宗教を想像されてしまう絵柄などは避け、無地のものを使用するとよいでしょう。
服装は喪服が望ましい
自由葬に参列する時の服装は、一般葬と同様に喪服が基本です。
男性は黒を基調としたスーツに黒のネクタイ・靴下・ベルト・靴を、女性は黒を基調としたワンピースやアンサンブルなどに、黒のストッキング・靴・バッグをあわせます。
詳しくは###sougi_midashinami###をご覧ください。
自由葬(無宗教葬儀)後の供養について
自由葬を行なった後のご遺骨の供養は、以下の選択肢から故人様やご遺族のご意向に応じて選択できます。
・ 永代供養
寺院や霊園がご遺族に代わってご遺骨の管理をしてくれます。
宗旨・宗派を問わず受け入れてもらえ、「お墓を建てなくても良い」「ご家族が管理をする必要がない」というメリットがあります。
・ 海洋散骨
ご遺骨を粉末化して海に撒きます。
「自然に還る埋葬方法である」「宗教にとらわれない」「維持費などがかからない」などの点から近年、希望者が増えています。
海洋散骨については###sankotu_toha###で詳しく解説しています。
・ 宗旨を問わない墓地
全国には宗旨を問わない墓苑や霊園もたくさんあります。
自由葬後のご遺骨も問題なく納骨できます。
・ 公営墓地
公営墓地への埋葬は宗教や宗派を問わないので、自由葬でも問題なく納骨できます。
費用が抑えられるという点もメリットです。
設備内容などは場所によりさまざまなので、よく比較検討してみると良いでしょう。
※菩提寺・檀那寺への納骨を希望される場合は、必ず事前にご寺院へご相談ください。
まとめ
「故人様らしさ」と「ご遺族の想い」を反映できる自由葬は、心に残るご葬儀になりやすいという良さがあります。
その反面、ご親族の理解が得られなかったり、参列者が戸惑う場合もあるので、事前の調整や配慮が大切です。
特に菩提寺・檀那寺がある場合は、納骨などに際して問題が起きないよう前もってご寺院に相談しましょう。
平安祭典では自由葬を含め、様々なスタイルのご葬儀に対応しております。
平安祭典でのご葬儀の一例は「ご葬儀の種類・費用」にございますので、ご参考になさってください。
神戸・阪神間で、ご葬儀・ご供養に関するお困りごとがございましたら、平安祭典(0120-00-3242)にご相談ください。
続きはこちら
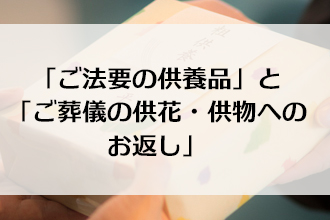
更新日:2024年9月21日 公開日:2022年8月15日
通夜、葬儀・告別式にご参列いただいた方には、喪主やご遺族が感謝の気持ちを込めて、供養品(返礼品)をお渡しします。
同様に、ご法要の際にも、参列していただいた方にお渡しする供養品を用意するのが一般的です。
では、ご法要の供養品には、どのような品物を選ぶと良いのでしょうか。
また、ご葬儀に参列できなかった方から、供花・供物をいただくことがありますが、お返しはどのようにすれば良いのでしょうか。
今回は、「ご法要の供養品」と「ご葬儀の供花・供物へのお返し」についてご紹介します。
ご法要では供養品を用意する
忌明け法要や年忌法要などを執り行なう際には、ご参列いただいた方にお渡しする「供養品」を用意します。
供養品は、あくまでご参列いただいたことへの御礼としてお渡しするもので、厳密には、ご法要のお供えや御香典へのお返しとは別のものなので注意が必要です。
ご法要の当日に参列していただいた方に供養品をお渡しできるように、事前に準備しておきましょう。
ご法要の供養品に適した品物・相場・表書き
ご法要時の供養品に何を選ぶかについて、特に決まりはありません。
通夜、葬儀・告別式の供養品と同じく、お茶やお菓子、コーヒーなどといった食品、タオルのように日常使いできる品物が喜ばれます。
食品を選ぶ際には、軽くてあまりかさばらず、日持ちのする品物を選ぶと良いでしょう。
品物の相場としては、主にご親族・ご親戚にお渡しする品物となるため、2,000~3,000円の品物を選ばれるケースが多いようです。
また、聖職者へ御布施とは別にお礼の意味を込めて3,000~5,000円程度の商品をお渡しする方もいます。
ご法要時の供養品の表書きは、地域や宗旨・宗派によって変わります。
関西地方では一般的に、仏式の場合は「粗供養」、神式やキリスト教式は「偲び草」、地方によっては「茶の子」、「○回忌」などと表記し、水引は黄白の結び切りを用いることが多いようです。
供養品の「熨斗」や「表書き」については###sougi_noshi###でも詳しくご説明しています。
ご葬儀の供花・供物にお返しは必要?
供花・供物とは、通夜、葬儀・告別式の際に祭壇の周りに飾るお花や、缶詰・果物などの盛籠を指します。
また、御香典の代わりとして故人様に弔慰を表すために、供花・供物を贈ることがあります。
近年では香典の受け取りを辞退する「香典辞退」でのご葬儀も増えているので、特にニーズが高まっているかもしれません。
では、喪家の立場で供花・供物を受け取った場合、お返しはどのようにすれば良いのでしょうか?
供花・供物へのお返しには様々な考え方があります。
例えば、「高額な品物でなければお返しは不要」という意見もあれば、「贈っていただいたお気持ちに、御香典と同じようにお返しをしたほうが良い」という意見もあります。
御香典のように現金をそのまま受け取るのではなく、お花や盛籠でお供えされるので、明確な金額がわからない場合もあります。
そうなるとさらに、お返しには迷う方が多いでしょう。
一例ではありますが、供花・供物のお返しの相場をご紹介するので、ぜひご参考になさってください。
ご葬儀の供花・供物のお返しの相場
供花・供物のお返しの相場は、基本的には香典返しと同様です。
地域によって異なりますが、いただいた金額の3分の1から半返しが一般的な相場とされています。
心配な時は、ご親族や地域の年配の方などに相談したり、これまでの慣例を参考にすると良いでしょう。
また、御香典と供花、両方をいただいた場合には、別々にお返しの品物を用意する必要はありませんが、御香典と供花を合算した金額で計算することもあります。
いただいた供花・供物の金額が分からない際には、葬儀社を通じて供花・供物が手配されることが多いので、葬儀社に相談することをおすすめします。
いずれにせよ、供花・供物へのお返しは「お気持ちでいただいたもの」に、こちらも「お気持ちでお返しするもの」なので、あまり金額にとらわれすぎないようご注意ください。
ご葬儀の供花・供物のお返しのタイミングとマナ―
四十九日の忌明け法要後にお返しする習慣がある「香典返し」とは異なり、供花・供物のお返しは、四十九日の前にお渡ししても問題ありません。
表書きは「志」「御供花御礼」などと表記します。
水引は、関西地方では黄白の結び切りが一般的です。
お返しの品物には挨拶状を添えて、供花・供物をいただいたことへの感謝の気持ちを伝えましょう。
「挨拶状」については###kiake_aisatujyou###でも詳しくご紹介しています。
まとめ
今回は、「ご法要の供養品」と「ご葬儀の供花・供物へのお返し」についてご紹介いたしました。
いただいたご厚意に感謝の気持ちを表し、心を込めてお返ししたいものですね。
平安祭典では、ご葬儀が終わった後も、様々なアフターフォローをさせていただきます。供養品についても、それぞれのお客様に寄り添い、ご要望やご予算に合わせた商品選びをお手伝いいたします。
神戸・阪神間でご葬儀・ご供養に関するお困りごとがございましたら、平安祭典(0120-00-3242)まで気兼ねなくご相談ください。
続きはこちら
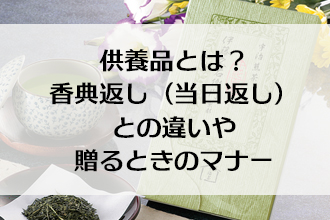
公開日:2022年8月8日
通夜、葬儀・告別式で用意される「供養品」について、皆さまはご存じでしょうか。
意外と知らない方も多いのではないかと思います。
そこで今回は、供養品とは何か、よく混同してしまう香典返しとの違い、供養品として人気の品物、供養品を贈る際のマナー、供養品の表書きの書き方などについてご紹介します。
供養品とは?香典返し(当日返し)との違いとは?
供養品とよく混同してしまうのが、香典返し(当日返し※)ですが、「供養品」と「香典返し」は全く別のものです。
「供養品」は、通夜、葬儀・告別式に参列してくださった方々に「時間を割いて御足を運んでいただいた御礼」としてお渡しする品物です。
対して「香典返し」は、文字通り「いただいた御香典に対するお返し」としてお渡しする品物のことを指します。
香典返しはいただいた御香典の金額に応じた品物をそれぞれお渡しするのに対し、供養品は参列者全員に同じ品物をお渡しすることが一般的です。
供養品の金額の相場としては、1,000円前後の品物が選ばれる傾向にあり、お通夜と葬儀・告別式では、異なる供養品を用意します。
供養品は参列者全員にお渡しするので、足りなくなることがないよう多めに準備しておきます。
ちなみに、地域によっては地域独自の慣習や自治会のルールで、供養品の取り扱いについて規定がある場合があります。
もし不明な点があれば、地域の慣習に詳しい方や自治会の方に事前に確認するようにしましょう。
※香典返しは四十九日法要が済んでから贈るものとされていましたが、近年ではご葬儀当日にお渡しすることが増えており、これを「当日返し」「即日返し」などといいます。
渡すタイミングによって呼び名が変わるだけで、お渡しするお品物の意味は同じです。
供養品として人気の品物は?
供養品として選ばれる品物としては、不祝儀を後に残さないという意味合いから、お茶やコーヒー、菓子類、海苔などの食品、もしくは軽くてかさばらないタオルなどの消耗品が人気です。
商品券などの金券類が選ばれるケースもありますが、金額が分かってしまうためマナー違反だという意見もあり、まだまだ少数派です。
近年では、自分の欲しい商品を自由に選んでいただけるという点から、カタログギフトも供養品として人気です。
供養品を贈る際のマナーとは?
供養品をお渡しする際のマナーについてもご紹介します。
① 供養品にはお礼状を添える
② 御礼状の表書きは「ご挨拶」や「御礼」などとする
③ 御礼状には時候の挨拶を用いない
④ 御礼状には句読点を用いない
⑤ 「不祝儀を後に残さない」といった配慮を行なう際には、食品や消耗品を供養品として選ぶ
⑥ 「四つ足生臭もの」と呼ばれ昔から忌避されている肉や魚の類は供養品として避ける
このような点に注意しましょう。
供養品の御礼状は、2つ折りやカード形式のものが多く、ご葬儀に参列していただいたことに対する謝意、略式であることへのお詫びの言葉などを記載します。
なお、平安祭典では有料で、通夜、葬儀・告別式でお使いいただける御礼状をご用意しております。
文面が複数ございますので、お好きなものをお選びください。
供養品の表書きの書き方
供養品の表書きは、宗旨・宗派によって異なります。
仏式の場合、西日本では、「粗供養」の表書きに白黄の水引をかけるのが一般的です。
東日本では表書きは「志」と書いて、白黒の水引をかけるのが主流です。
また四国・中国地方や九州では「茶の子」という表書きを使用するケースがあります。
なお、供養品に掛ける「熨斗(のし)」は、正式には「掛け紙」と呼びます。
神式やキリスト教の場合は、表書きに「偲び草」が用いられますが、この言葉には「故人を偲ぶ気持ちに代わって品物をお渡しします」という意味が込められています。
「熨斗」や「表書き」については###sougi_noshi###の記事で詳しくご紹介しています。
平安祭典では様々な供養品をご用意しております
いかがだったでしょうか。
今回は供養品とは何か、よく混同してしまう香典返しとの違い、供養品として人気の品物、供養品を贈る際のマナー、供養品の表書きの書き方などについてご紹介しました。
皆さまのご参考になれば幸いです。
なお、平安祭典(0120-00-3242)では、仏事に関するご質問などを受け付けております。
神戸・阪神間にお住まいの方は気兼ねなくご相談ください。
続きはこちら
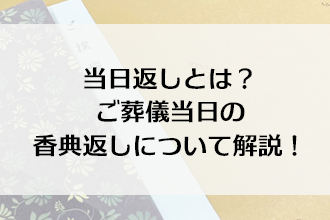
更新日:2025年4月21日 公開日:2022年8月1日
ご葬儀では、参列者から御香典をいただきます。
いただいた御香典に対し、喪家が御礼の品物を贈ることを「香典返し」と呼びます。
従来、香典返しは忌明けが済んでから贈るものとされてきましたが、近年ではご葬儀当日に品物をお渡しする「当日返し」を行なうケースも多くなってきました。
今回は、ご葬儀での香典返し・当日返しについてご紹介します。
供養品と香典返しの違いとは?
「香典返し」に似た言葉に、「供養品」があります。
この2つの言葉を同じものとして使われている方もいますが、厳密には違う意味を持つ言葉なので気を付けましょう。
「供養品」とは、ご参列いただいた御礼として参列者全員にお渡しする品物のことです。
対して「香典返し」とは、文字通りご葬儀において参列者からいただいた「御香典に対するお返しの品物」のことで、供養品と香典返しは全く別のものです。
供養品と香典返しでは、お渡しする品物の価格も異なります。
供養品は、参列の御礼として皆さまに同じ品物をお渡しします。
品物の金額は、地域などにもよりますが、千円前後のものが一般的です。
一方で、香典返しは、いただいた金額の3分の1~半額程度の品物を贈るのが一般的とされています。
「半返し」という言葉を聞いたことがある方も多いでしょうが、半返しとは、いただいた御香典の半分程の金額の品物を、香典返しとして贈ることを意味します。
「御香典」については###kouden_manner###の記事でも詳しくご説明しています。
当日返しとは?
香典返しは、本来、四十九日の忌明けが済んでから贈るものでしたが、近年ではご葬儀当日に品物をお渡しをする「当日返し」という方法が増えてきました。
「当日返し」とは、参列者から御香典をいただいた際に、その場で香典返しの品物をお渡しすることです。
いただいた御香典の金額に合わせて、葬儀会場で参列者に香典返しの品物をお渡しします。
御香典の金額は、故人様との付き合いの深さや関係性などによって異なります。
厳密に金額の設定がされているわけではありませんが、場合によっては、ご親族からは高額の御香典をいただくこともあります。
それぞれの金額に応じた品物をご用意しても良いでしょうし、カタログギフト(※)をお渡しする方も増えています。
当日返しのメリットとしては、ご葬儀の当日に香典返しを直接お渡しできるので、ご葬儀の後にご遺族が香典帳の整理や発送手続きなどをしなくて済み、手間が大幅に軽減されることが挙げられます。
前述の通り、近年では「当日返し」として御香典のお返しをお渡しする方は増えています。
決してマナー違反ではなく、失礼にはなりませんのでご安心ください。
当日返しをご希望される際は、葬儀社にご相談されると良いでしょう。
※カタログギフトには、様々な金額設定のものがあり、平安祭典では3,000円~25,000円のものまで取り扱っています。ご入用の方は、ぜひお問い合わせください。
聖職者への御礼と初七日のお返し
聖職者に対し、御布施とは別に御礼の品をお渡しする場合、金額や品物に特に決まりはありません。
金額は5,000円程度で、お茶などを選ぶことが多いようです。
また近年、ご葬儀当日に初七日法要を行なう方が増えています。
「初七日法要」はご葬儀とは別の儀式であるため、参列者へのお返しを別に準備することが一般的です。
ごくまれに初七日法要時に改めて御香典をいただくことがありますが、もちろんその御香典に対する香典返しも必要となります。
平安祭典では香典返しの品物のご相談を承っています
いかがだったでしょうか。
今回はご葬儀での香典返し(当日返し)についてご紹介しました。
皆さまのご参考になれば幸いです。
平安祭典では、ご葬儀が終わった後も、様々なアフターフォローをさせていただきます。
供養品についても、それぞれのお客様に寄り添い、ご要望やご予算に合わせた商品選びをお手伝いいたします。
神戸・阪神間でお困りごとがございましたら、平安祭典(0120-00-3242)まで気兼ねなくご相談ください。
続きはこちら
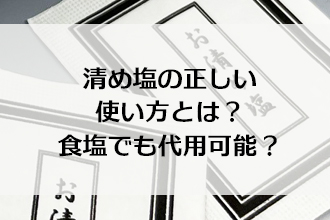
公開日:2022年7月25日
お通夜やご葬儀に参列すると、会葬御礼の挨拶状や供養品と一緒に、小袋に入った塩をいただくことがあります。
この塩は「清め塩(お清め塩)」といわれるものです。
ただ、清め塩について漠然としたイメージはあるものの、意味や使い方を詳しくご存じない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、清め塩とは何なのか、起源や使い方などを解説します。
[@目次@]
清め塩の起源・使う意味とは
清め塩の起源は、神道にあります。
神道では、一般的に死は穢れ(けがれ)であると捉えられてきました。
穢れとは、「気枯れ」とする説もあり、気力の衰えた元気のない状態、汚れていて良くない状態を指します。
また、穢れは他の人に伝染するため、祓い(はらい)清めなければなりません。
死を穢れであると考えると、ご葬儀への参列は、穢れに触れることと同義になります。
そこで、参列者の体を塩で清める必要があるのです。
では、どうして塩を使うのかというと、その理由は神話に由来します。
イザナギノミコトは、黄泉の国(よみのくに)から戻った後、穢れを祓うため海で禊(みそぎ)を行なったという逸話があります。
古来より塩分を含んだ海水には穢れを祓う力があるとされ、後に海水が塩によって代用されるようになりました。
なお、仏教やキリスト教では、死を穢れと捉えません。
そのため、神道では清め塩が必要ですが、仏教やキリスト教では必須ではありません。
ですが、それぞれの地域の習わしや、ご寺院、ご遺族の考え方にもよるので、清め塩の要不要は、宗旨・宗派で一概には語れません。
清めの塩の正しい使い方
清め塩は、必ず使わなくてはならないものではありませんが、使うにあたって基本的なマナーは存在します。
ここからは、清め塩の使い方を解説します。
清め塩は玄関前で体にかける
清め塩は、お通夜やご葬儀からの帰宅時(玄関をまたぐ前)に使います。
体を清めないまま家に入ると、穢れを家に持ち込むことになるため、玄関をまたぐ前に使うのです。
ご葬儀の後、帰宅せずに別の場所へ行くという場合は、会館を出てから使うと良いでしょう。
清め塩を使う手順は、以下の通りです。
① 塩をひとつまみ取る
② 胸に振りかけ、手で払う
③ 背中(肩)に振りかけ、手で払う
④ 足元に振りかけ、手で払う
⑤ 地面(床)に落ちた塩を踏む
ちなみに、胸から足への順番でかける理由は、血の流れる順とされています。
なるべく余らせずに使い切る
いただいた清め塩が余る場合は、普通ごみとして処分してください。
ただし、塩は植物や建造物に悪影響を及ぼすことがあるので、庭や外に撒く処分方法は良くありません。
とはいえ、そのまま捨てることに抵抗があるならば、懐紙などに包んでから処分すると良いでしょう。
また、清め塩には乾燥剤などが入っていることもあるため、調味料としては使えません。
かといって水に流すのも良くありません。というのも、乾燥剤は水と反応すると発熱・発火することがあるためです。
いずれにせよ清め塩は、再利用ができないものです。余らせず、なるべく使い切ることをおすすめします。
もらえなかった場合は食塩で代用可能?
宗派や地域によっては、お通夜やご葬儀で清め塩が配られないこともあります。
そのような場合、ご自宅にある塩、またはお店で買った塩で代用可能です。
清め塩に使用する塩は、海水100%の塩が望ましいとされています。
代用するのであれば、海塩を使いましょう。
清め塩を使い忘れて家に入ってしまったら
清め塩をいただいたのに、使い忘れてご自宅に入ってしまっても、あまり気にする必要はありません。
どうしても気になるようなら、玄関の外に戻り、清め塩をかけると良いでしょう。
まとめ
当記事では清め塩について、意味や起源、使い方などをご紹介しました。
清め塩は、お通夜やご葬儀からの帰宅時、絶対に使わなければいけないというわけではありません。
宗旨・宗派に関わらず個人の考え方によるところが大きいものです。
しかしながら、絶対ではないからこそ、判断に迷うことも多いでしょう。
清め塩だけに関わらず、ご葬儀について何か気になることがございましたら、気兼ねなく平安祭典(0120-00-3242)へお問い合わせください。
続きはこちら
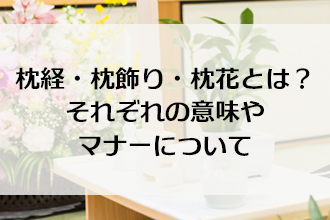
公開日:2022年7月18日
ご親族や親しかった方が亡くなると、するべきこと・準備するべきものがあります。
枕経、枕飾り、枕花もその一部ですが、どのようなマナーがあるのかご存じない方も多いのではないでしょうか。
そこで、本記事では枕経(まくらきょう・まくらぎょう)、枕飾り(まくらかざり)、枕花(まくらばな)の意味やマナーについてご説明します。
枕経とは故人様の枕元で読経すること
枕経とは仏教における儀式で、故人様の枕元で読経することです。
自宅で亡くなる方が多かった時代は、ご臨終が近づくと家にご寺院を呼び、息を引きとる前に枕元で読経をしてもらっていました。
読経によって、故人となる方が安心してあの世へ旅立てるようにという配慮からです。
しかし、大半の方が病院で亡くなる現在は、病院で枕経を行なうことは稀で、ご臨終後、故人様を安置した場所で行なうことが一般的となりました。
枕経のタイミングに特別な決まりはありませんが、会館やご自宅に故人様をご安置した後、できるだけ早く行なうべきとされています。
また、最近では通夜の時に枕経をあげることも少なくありません。
枕経の準備・参列について
続いては、枕経の準備および枕経に参列する際に知っておきたいマナーについてご紹介します。
枕経の依頼方法、参列される際の服装の参考にしてください。
菩提寺・檀那寺に連絡して枕経を依頼する
枕経は、菩提寺・檀那寺にお願いすることが一般的です。
喪主またはご遺族がご寺院に連絡して枕経を依頼し、故人様の安置場所を伝えます。
※菩提寺・檀那寺がない場合は葬儀社にご相談ください。
枕経の所要時間は30分~40分程度です。
枕経の際、ご寺院とお通夜、葬儀・告別式に関する必要事項や戒名などについて相談しておくと、その後の段取りがしやすいでしょう。
近親者のみ参列・地味な服装(平服)でOK
枕経はご臨終からご葬儀までの短い間に執り行なうこともあり、喪主とご家族など近親者のみが参列する場合がほとんどです。
枕経に参列する時の服装は、平服で良いとされています。
平服とはいえ、カジュアル過ぎるもの、派手な色や柄物、肌の露出が多いものなどは控え、落ち着いた色とデザインの地味な服装が望ましいでしょう。
結婚指輪や、パールの一連ネックレス(白または黒)以外のアクセサリー類は、身に付けるのを控えます。
枕飾りとは故人様の枕元に置くお供えもの
故人様は、お通夜、葬儀・告別式までの間はご自宅や会館などに安置されます。
枕飾りとは、この間、故人様の枕元に設置される祭壇です。
机、香炉、燭台、花瓶などを総称して枕飾りといいます。
机の上にお供えするものは、宗旨・宗派、地域によって異なりますが、通常は葬儀社が枕飾りを準備してくれます。
枕飾りは、故人様を安置してすぐ設置されますが、その理由はお通夜の前に弔問に訪れる方に焼香や礼拝を行なってもらうためです。
つまり、枕飾りは簡易的な祭壇の役割を担うものなのです。
また、枕飾りは故人様の魂を導く「道しるべ」でもあります。
人の魂は体から離れた後も現世に留まろうとするといわれるため、故人様の魂をあの世へと導くために、枕経や枕飾りによる供養を行なうのです。
ところで、「枕飾りは後飾り祭壇とは違うのか?」という疑問を持たれる方がいらっしゃるかもしれません。
後飾り祭壇は、火葬後にご自宅でご遺骨を忌明けまで祀るための祭壇であり、枕飾りとは異なります。
後飾りについては、###atokazarisaidan_toha###でも詳しく解説しております。
枕飾りの内容は宗旨によって異なる
枕飾りの内容は宗旨や地域によって異なります。ここでは仏式並びに神式の一例をご紹介します。
先にご説明したように、枕飾りは葬儀社が準備することが多いですが、ご自身でも用意できます。
いずれにしても、わからないことがあれば葬儀社のスタッフやご寺院にご確認いただくと安心でしょう。
仏式の枕飾り
仏式の基本的な枕飾りは、以下のものを揃えます。
・ 白木の台や白布を掛けた台
・ おりん
・ 香炉
・ 線香
・ 燭台
・ 花瓶
・ 樒
・ 水
・ 一膳飯
※地域によっては枕団子を用意することもあります。
※宗派によって枕飾りの内容が異なる場合があります。
神式の枕飾り
神式の基本的な枕飾りは以下のものを揃えます。
・ 八足案(白木の台)
・ 三宝方
・ 洗米
・ 塩
・ 水
・ お神酒
・ 花瓶
・ 榊
枕花とは故人様を悼み枕元に供える花
枕花とは、ご臨終後、故人様が安置されている枕元にお供えするお花のことです。
ご遺族からいち早く訃報を受け取った方が、ご自宅や会館など故人様が安置されている場所へ贈ります。
届いた枕花の飾り方や並べ方に特に決まりはなく、故人様の枕元周辺にお供えすることが一般的です。
枕花は故人様に対する深い哀悼の気持ちを表すものであり、自分の代わりに故人様に寄り添うという意味が込められています。
故人様にお供えした後、お通夜、葬儀・告別式を行なう場所へ移動する際に、一緒にお持ちいただくこともできます。
誰が出す(贈る)?贈り方は?枕花に関するマナー
ご親戚やご友人の訃報を受けた時、「自分は枕花を贈るべきか?」と悩む場合があるかもしれません。
ここでは枕花を贈るかどうかの考え方と、実際の贈り方やマナーについて解説します。
枕花は故人様と親しかった方や近親者が贈る
一般的に枕花を贈るのは、近しいご親戚や特に親交の深かった方が亡くなった時です。
少しでも早く故人様に寄り添いたい、ご遺族の心を慰めたいという気持ちがあれば、枕花をお贈りすると良いでしょう。
枕花を贈るべきかどうか迷った時は、枕花の代わりに、お通夜、葬儀・告別式の式場に供花をお贈りする方法もあります。
枕花はお通夜開始までにご自宅(安置場所)へ贈る
訃報を聞いたらすぐに枕花を手配し、お通夜が始まるまでに故人様が安置されている会館やご自宅などに贈ります。
安置場所に直接お持ちいただいてもかまいません。
枕花を贈る際は、できるだけご遺族のご都合やお通夜のスケジュール、会館のルールなどを確認してタイミングや届け先を決めると、間違いなく受け取ってもらいやすいでしょう。
枕花は籠花で贈ることが一般的
枕花は、白を基調(葉の緑は可)とした籠花(アレンジメント)で贈ることが一般的です。
白以外に青・紫系などの淡い色を加えても失礼にはあたりませんが、バラなどトゲのついた花や香りが強い花は避けましょう。
枕花としては菊、ユリ、カーネーションなどが良く使われており、大きすぎない控えめな籠花が基本です。
枕花の価格は依頼先やアレンジメントの内容によって異なりますが、相場は5,000円~20,000円程度です。
生前の故人様との関係性をふまえて決めると良いでしょう。ちなみに、平安祭典では5,500円(税込)で販売しております。
まとめ
今回は、枕経、枕飾り、枕花について解説しました。
ご遺体の安置場所では故人様の枕元に枕飾りや枕花をお供えし、枕経を行ないます。
故人様への最初の供養として大切なものですので、ご不安な点は葬儀社のスタッフに確認しながら後悔のないよう執り行ないたいものです。
神戸・阪神間で、ご葬儀・ご供養に関するお困りごとがございましたら、平安祭典(0120-00-3242)にご相談ください。
続きはこちら
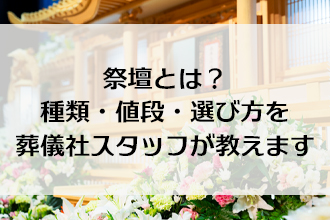
公開日:2022年7月11日
お通夜、葬儀・告別式のさまざまな準備を行なう中で、「祭壇(さいだん)をどう選べば良いのだろう?」と悩まれるご遺族は多いようです。
そこで今回は、祭壇の意味・種類・値段・選び方について解説します。
当記事が祭壇をお選びになる際のお役に立てれば幸いです。
[@目次@]
祭壇とは故人様を供養するための壇のこと
祭壇とは故人様を供養するために設ける壇のことで、葬儀壇(そうぎだん)とも呼びます。
式場の正面に設置し、遺影写真・供物・葬具などを飾ります。
祭壇はお通夜、葬儀・告別式の中心的な場所として、とても大切なものです。
古来は柩の前に小さな机を置いて白布で覆い、位牌や供物を並べていました。
時を経てしだいに机は大きくなり、壇も増えていきました。
また、昔葬儀の時に輿(こし)に柩を納めて担ぎ葬列を組んで埋葬のために墓地へと向かう儀式「野辺送り(のべおくり)」で使用されていた松明(たいまつ)や龍頭(たつがしら)などが形を変えて現在の白木祭壇の輿になったといわれています。
昭和初期に自動車の普及に伴い、霊柩車が日本に導入され、野辺送りがなくなり始めました。この頃に、柩を運ぶための輿を模したものを上部へのせた霊柩車が「宮型霊柩車」です。
霊柩車については###reikyusha_toha###で詳しくご紹介しています。
戦後には「立派な祭壇を用意することこそが手厚い弔いである」という考えが生まれ、祭壇の大型化が進みます。
しかし現在、祭壇は故人様を顕彰(けんしょう)するもの、つまり故人様そのものを表すものと捉えられるようになりました。
故人様の愛用品などを祭壇に飾る例が増えたり、故人様の好みや人柄に合わせた生花祭壇が流行するなど、多様化が進んでいます。
祭壇の違いについて
一口に祭壇といっても、さまざまな種類があり、デザインも多様です。
ここでは代表的なものをご紹介します。
白木祭壇
日本の仏式の葬儀において最も一般的な祭壇で、一部の宗派を除いて広く用いられています。
その名のとおり白木で組まれており、白木の温もりの中に厳粛な美しさが感じられる祭壇です。
白木祭壇に飾るものや配置は宗旨・宗派によって異なりますが、一般的には、遺影写真を飾り、生花・線香・抹香・ロウソク・果物・干菓子・缶詰などを供えます。
近年は故人様の愛用品や好きだった食べ物をお供えする例も増えているようです。
また、大日如来や釈迦牟尼仏などの宗派に基づいたご本尊を祀ります。
祭壇の前には柩を安置し、その手前にご寺院が読経をするための経机を設置します。
神式祭壇
神式の葬儀に用いられる祭壇で、白木のものが一般的です。
三種の神器(さんしゅのじんぎ)である「八咫鏡(やたのかがみ)」、「天叢雲剣(あまのむらくものつるぎ)」、「八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)」を必ず飾ります。
鏡は上段の中央に置き、刀と勾玉は祭壇の両側に、五色旗に吊るします。
また、祭壇の前面にお供えとして神饌物(しんせんもの)(米・塩・海の物・川の物・山の物)や季節のものを並べるのも特徴です。
遺影写真は鏡より一段下、右側に置くのが一般的とされています。
キリスト教式祭壇
キリスト教の葬儀は教会で行なうことも多く、シンプルな飾り付けをすることが一般的です。
柩は祭壇の手前に安置し、その奥に遺影写真を置いて周囲を白い生花で飾ります。
教会によって祭壇の決まりが異なりますので、カトリックの場合は神父様、プロテスタントの場合は牧師様に確認すると安心でしょう。
生花祭壇
生花のみで作る祭壇です。
使用する花の種類や色は、故人様が好きだったものや故人様のイメージなどにあわせて選べます。
デザインも自由度が高く、故人様の趣味や愛用品などをモチーフに祭壇をデザインすることも可能です。
生花祭壇は、美しい花で故人様らしさを豊かに表現できるとあって、近年とても人気があります。
オリジナル祭壇(ブロック祭壇)
平安祭典のオリジナル祭壇はブロック状の壇を重ねています。
直線的なデザインがスタイリッシュで、現代的な雰囲気が感じられる祭壇です。
生花祭壇やオリジナル祭壇は宗旨・宗派を問わず選べ、故人様の好みや人柄に合わせて個性ある祭壇を演出できる点が特長です。
祭壇のお値段はどれくらい?
平安祭典では祭壇のみの料金設定をしておらず、各種プランの中に祭壇が含まれております。
他の葬儀社においても同様の場合が多いようです。
まず葬儀のプランを決め、そのプランに含まれる各種祭壇からご希望のものを選ぶケースが一般的といえるでしょう。
ご参考として、平安祭典の一部のプラン内容と価格をご紹介します。
・ 36万円(ニ)コース…39万6千円(税込)
白木祭壇、神式祭壇、キリスト教式祭壇、生花祭壇、オリジナル祭壇からお選びいただけます。
・ 48万円(ヌ)コース…52万8千円(税込)
白木祭壇、神式祭壇、キリスト教式祭壇、生花祭壇、オリジナル祭壇からお選びいただけます。
プランの詳細は当社ホームページ【平安会員について】をご覧ください。
平安祭典では、白木祭壇やオリジナル祭壇にアレンジ花(有料)を追加することも可能です。
「より華やかな祭壇にしたい」といったご要望にもお応えしています。
家族葬でも祭壇は必要?
近年、ご親族のみの少人数で行なう家族葬の増加に伴い、「家族葬の場合でも祭壇は用意するべきなのか?」という疑問を持つ方がいらっしゃるようです。
平安祭典では、葬儀の規模に関わらず祭壇は必要だと考えております。
というのも、祭壇は故人様を表すものであり、故人様のご供養としての大きな意味をもつからです。
ご寺院を呼ばずに行なう自由葬・無宗葬においても、ほとんどの場合、祭壇が設けられています。
家族葬については###kazokusou_toha###で詳しくご紹介しています。
祭壇選びで大切にしたいポイント
祭壇をお選びになる際、家の宗旨を重視される場合は、宗旨に応じた祭壇をお選びいただくと良いでしょう。
また、宗旨にこだわらず故人様のご希望や人生の物語性を大切にされたい場合は、生花祭壇やオリジナル祭壇をお選びいただくとご要望を叶えやすいでしょう。
祭壇選びで大切なポイントは、故人様らしさを重視すること、ご遺族にとっても後悔のないようしっかりとご検討いただくことです。
平安祭典では、伝統的で上品な白木祭壇、供花が映える白くスタイリッシュなオリジナル祭壇、故人様のイメージを再現できる生花祭壇など、それぞれに特長のある各種祭壇をご用意しております。
どのような祭壇にしたいかというご希望とご予算などを考えあわせ、プランおよび祭壇をお選びいただけます。
まとめ
今回は、お通夜、葬儀・告別式の中心的な場所となる祭壇について解説しました。
大切な祭壇を選ぶにあたり、当記事が少しでもお役に立てれば幸いです。
祭壇に関するご相談、葬儀全般についてのお問い合わせ等ございましたら、平安祭典(0120-00-3242)まで気兼ねなくご連絡ください。
続きはこちら
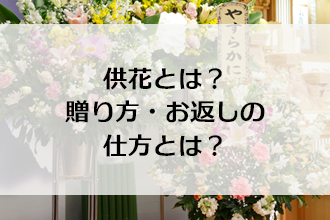
更新日:2023年6月11日 公開日:2022年7月4日
供花は式場をやさしく厳かな空気で包み、ご遺族の気持ちに寄り添ってくれます。
しかし、いざ贈るとなると、どこへ、どのように手配すれば良いのか迷ってしまうことも多いでしょう。
そこで当記事では、「供花」について詳しく解説しています。
贈る意味や手配の方法、供花をいただいた場合のお礼について、参考にしていただけますと幸いです。
[@目次@]
供花とは?供花を贈る意味とは?
供花の読み方は一般的に「きょうか」で、故人様に弔意を表すために贈る花を指します。
親交のあった方から故人様への最後の贈り物であり、ご遺族の悲しみが癒えることを願い贈られるものでもあります。
スタンドに生花を活けた供花、籠に生花を入れた供花などがあり、いずれも贈り主がわかるよう名札が付けられます。
供花の数え方は、1つの供花なら一基(いっき)、2つが対の供花なら一対(いっつい)です。
以前は「供花は一対で贈るもの」という考え方が一般的でしたが、近年は供花の贈り方に関する考え方に変化が見られ、一基で贈る方も多くいらっしゃいます。
ただし、ご親族一同など複数名で贈られる場合は、一対で贈ることが多く、一基より一対の方が飾った際にバランスが取れます。
供花の贈り方については、故人様との関係性や地域の習慣、ご予算などで判断されると良いでしょう。
供花はどんな間柄の人が贈るもの?
供花を贈る間柄に、決まりはありません。
次のように故人様の近親者や、深いお付き合いのあった方が贈る場合が多いです。
・ 親族
・ 友人
・ 故人様と仕事上でつながりのあった方
・ 喪主やご遺族と仕事上でつながりのあった方
・ 遠方や仕事の都合などでご葬儀に参列できない方
・ 御香典を辞退されたため、代わりに弔意を形にしたい方
知っておきたい供花を贈る際の注意点
供花を贈るにあたって、次の点に注意が必要です。
・ 供花の金額や数量などの指定
ご遺族の意向や会館のスペースの問題から、供花の金額、数量などが指定されていることがあります。
指定以外の供花だと受け取りを辞退されることがあるため、十分に注意しましょう。
・ 生花店で注文した供花の扱い
葬儀社ではなく生花店で注文した供花は、会館に持ち込めない葬儀社もあります。
・ 供花の数え方
先にご説明したように、供花は一基や一対という数え方をします。
数え方を間違えて贈ると、贈りたい数より多かったり少なかったりなどのトラブルになることがあるためご注意ください。
供花の手配で不安な点がございましたら、ご葬儀を執り行なう葬儀社へ確認すると良いでしょう。
供花の種類や宗旨・宗派による違い
供花にはいくつか種類があります。
宗旨・宗派による違いもあるため、事前に確認しておきましょう。
【供花の種類】
・ スタンド花(一基10,000円~30,000円ほど)
長い脚のついたスタンドに生花を挿したものです。
スタンドの脚のデザインなどが異なるものもあります。
また、価格や季節によって使用する花材は異なります。
※平安祭典では、12,000円からの取り扱いとなります。
・ 籠花(一ヶ5,000円~30,000円ほど)
籠に生花を活けたものです。
価格や季節によって、使用する花材が異なります。
・ 花輪(一基10,000円~30,000円ほど)
お店の開店祝いなどでよく見かける花輪の弔事版です。
式場の外や入口付近に飾られますが、近年は一部の地域を除いて用いられることが少なくなっています。
※平安祭典では、取り扱いはございません。
【宗旨・宗派による違い】
・ 仏式・神式
菊・百合・カーネーション・胡蝶蘭などの花がよく使われます。
避けた方が良いのは、とげのあるバラや、毒のあるアジサイ、香りの強い花、ツル性の植物などです。
色は白をベースとすることが多く、華美にならないようにします。
また、宗派によっては色花ではなく、樒(しきみ)が使われることもあります。
・ キリスト教式
キリスト教式では、菊はあまり使われず、白い百合やカーネーションを使用することが多いです。
キリスト教式のご葬儀では、一輪ずつ故人様に花を供える「献花」という儀式がありますが、献花は仏式での焼香にあたるもので、供花とはまったくの別物です。
献花について詳しくは###tamagushi_kenka###をご覧ください。
供花を贈るタイミング
供花の手配は、訃報の連絡を受けたら速やかに進めましょう。
お通夜の前日中には注文し、開式の数時間前までには届くよう手配します。
葬儀社が供花の注文受付の締め切り時間を設けていることが多いため、供花の手配についてはご葬儀を執り行なう葬儀社へ確認すると良いでしょう。
なお、お通夜に間に合わない場合は、葬儀・告別式に間に合うよう手配します。
葬儀・告別式に手配できなかった場合は、ご遺族のご自宅へ、後飾り祭壇に供える花としてお贈りしても良いでしょう。
その際は、初七日~忌明け法要(四十九日法要)までを目安として贈ります。
後飾り祭壇、初七日、忌明け法要について詳しくは、ぜひ以下の記事もご覧ください。
###atokazarisaidan_toha###
###shonanoka_houyou###
###kiake_shijyukunichi###
名札(ご芳名)の表記
供花には、贈り主がわかるよう名札が付けられます。
名札は縦書きでフルネームを記載することが一般的です。
連名の場合、人数が多すぎると文字が小さくなるため、4名ほどまでにすると良いでしょう。
その場合は右から、肩書きまたは年齢の高い順に記載します。
友人関係のように上下関係がない場合は、五十音順や順不同でも構いません。
人数が多いならば、「〇〇一同」「〇〇有志一同」などと記します。
夫婦の場合は、苗字1つに名前だけを連名にすると良いでしょう。
【名札(ご芳名)の記載例】
・ 親族
〇〇家一同、〇〇家 兄弟一同、〇〇家 孫一同 など
・ 友人知人
〇〇学校 同窓生一同、〇〇学校 〇〇部OB一同、友人一同 など
・ 会社関係者
〇〇株式会社 代表取締役〇〇〇〇、株式会社〇〇 〇〇部 有志一同 など
※正式な会社名もしくは、会社名と代表者の役職、氏名を書くことが一般的です。
長すぎて入りきらない場合のみ、株式会社を省略し、(株)とします。
供花は葬儀社か生花店へ手配する
供花は生花店でも手配可能ですが、葬儀社での手配をおすすめします。
というのも、供花の内容が細かく指定されている場合があるからです。
ご遺族の意向で供花の種類や数が決められていたり、会館のスペースの都合で数に制限があったり、供花の受け取りそのものを辞退されていることもあります。
葬儀を執り行なう葬儀社は、そういった事情もきちんと把握していますので、適切な案内ができるでしょう。
また、どうすべきか迷ったときにも相談が可能です。
参考までに平安祭典での手配の流れをご紹介いたしますので、ご確認ください。
・ 電話・FAXからの注文
電話で、平安祭典へ問い合わせをする
↓
平安祭典から注文用紙をFAXで受け取る
↓
注文内容を記入し、FAXを返送する
↓
平安祭典から注文内容・名札の確認連絡が入る
↓
注文完了
・ ホームページからの注文
平安祭典ホームページ供花・供物のご注文フォームへアクセスする
↓
必要な項目を入力し、注文する
↓
平安祭典から注文内容・名札の確認メールが届く
↓
注文完了
また平安祭典では、「つなぐシステム」というサービスをご用意しています。
喪主がメールやLINEなどのSNSで、専用のURLをご親族や故人様と親しかった方々に送ると、受け取ったURLをクリックするだけで、お通夜や葬儀・告別式の時間、場所などの確認が可能です。
そのページから、供花・供物などを贈ることもできますので、ぜひご利用ください。
供花のお礼に関するマナーについて
供花のお返しの品を贈る場合は、相場は香典返しと同様で、いただいた金額の3分の1から半返しが一般的です。
御香典と供花の両方をいただいた場合は、合算の金額でお返ししても良いでしょう。
あくまで気持ちをお返しするために贈るものなので、あまり金額にとらわれないようご注意ください。
お返しの内容としては、品物に挨拶状を添えたものが多く、お茶やお菓子などの食品、タオルやハンカチなど普段使いできる品物など選びます。
表書きの文言は「志」「御供花御礼」などです。
水引は、関西地方であれば、黄白の結び切りを使用することが多いでしょう。
まとめ
当記事では、供花の意味や贈り方、供花をいただいた際のお礼のマナーをご紹介しました。
弔意をお花でお伝えしたいと思われたら、まずは葬儀社へご連絡されると良いでしょう。
平安祭典でも、日々ご相談を承っております。
ご不明な点は気兼ねなく(0120-00-3242)までお問い合わせください。
続きはこちら