

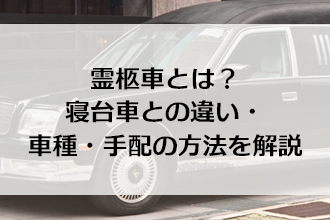
公開日:2022年6月27日
霊柩車は、ご遺体を乗せて運ぶ車ということをご存知の方は多いでしょう。
とはいえ、霊柩車にはどんな種類があるのかなど、よく分からないことも多くありませんか?
当記事では、霊柩車の種類、霊柩車と寝台車の違い、霊柩車の利用料金や手配の方法など、霊柩車について気になる点を分かりやすく解説いたします。
[@目次@]
霊柩車とはどんな車?
霊柩車とは、ご葬儀を執り行なう会館から火葬場まで、故人様をお運びするための車です。
かつて土葬が一般的だった時代は、人の手でご遺体を運んでいました。
ご遺体を柩(座棺)に納めて担いでいましたが、やがて大八車(だいはちぐるま)のような台車で運ぶようになり、大正時代には宗教的装飾が施された霊柩車が登場したようです。
霊柩車と一般車を比べると荷室部分に大きな違いがあり、霊柩車の荷室部分は柩専用の仕様になっています。
レールやローラーで柩がスムーズに出し入れでき、走行中に柩が動かないよう固定できる点が特徴です。
それではここから、霊柩車の種類や運転に必要な免許証の種類について見ていきましょう。
火葬については###kasou_toha###や###kasou_fukusou###の記事で詳しくご紹介しております。
車種は中型~大型・タイプは大きく分けて4種類
霊柩車の車種には、セダンやバンなどの中型〜大型車が多く使われています。
種類を大きく分けると、宮型(輿型)、洋型(リムジン型)、バス型、バン型の4種あり、それぞれ以下のような特徴を持ちます。
・ 宮型(輿型)
宮型とは、日本建築独特の唐破風(からはふ)や豪華な彫り物、金箔などが施された車両です。
かつては柩を神輿のようにかついで運んでいたという、歴史の名残を感じる形状が大きな特徴と言えるでしょう。
・ 洋型(リムジン型)
洋型とは、大型外車や国産高級車をベースに使った霊柩車で、外観はシンプルで高級感があります。
外装にレザーなどを使い、装飾されていることが多いです。
以前は宮型の霊柩車が主流でしたが、近年は洋型が主流になっています。
・ バス型
バス型は、マイクロバスのような霊柩車を思い浮かべていただくと分かりやすいでしょう。
後部に柩を納める空間があるほか、喪主や参列者が一緒に移動できる点が特徴です。
・ バン型
バン型は、バンやワゴンをベースにした霊柩車で、多くは黒や白の車両です。
外観は一般車のままなので、一見しただけでは霊柩車とは分からず目立ちません。
簡素な外観で寝台車として使われることもあります。
ちなみに4種類ある霊柩車のうち、「宮型霊柩車」の数は以下のような理由で年々減少しています。
・ 近隣住民への配慮
遠くからでも目立ち、すぐに霊柩車と分かる見た目は死を連想させることから、敬遠されがちです。
そのため、一目で霊柩車と分かる車両が使用できない自治体(兵庫県加古川市など)もあります。
・ 制作・購入・維持のコスト
ひとつひとつが専門の職人による手作業で作られているため、宮型霊柩車の価格は通常の霊柩車の2〜3倍と言われます。
細かな細工が施されているため、メンテナンスに専門技術が必要で、車両の維持も容易ではありません。
・ 宗旨による違い
仏式・神式には使用できますが、その他の宗旨にはそぐいません。
・ 車両の安全基準厳格化
車両の安全基準が厳格化されたことで、突起が多い宮型は安全基準を満たしにくくなりました。
・ 洋型霊柩車の流行
昭和天皇崩御の際に洋型が使用され、洋型の霊柩車を希望される方が増えました。
緑色の8ナンバーで普通自動車第一種運転免許が必要
霊柩車のナンバープレートは、緑色の8ナンバー(800番台の特種用途自動車ナンバー)です。
ご遺体は法律上では貨物という扱いになるため、霊柩運送は「一般貨物自動車運送事業」にあたり、貨物を運ぶ営業車両には緑色のナンバープレートがつきます。
また、霊柩車はメーカー生産車に特殊部品や装置を付けた架装車両にあたるため、ナンバーは特殊な車両に使用される8ナンバーです。
一般的な霊柩車は普通自動車第一種運転免許で運転可能ですが、10名以上の参列者を乗せるバス型の霊柩車は旅客運送にあたるため、運転には中型自動車第二種運転免許が必要です。
霊柩車と寝台車はどう違う?
霊柩車と寝台車の違いは、「どこからどこへご遺体を運ぶか」という点です。
・ 霊柩車
ご遺体を安置している場所から火葬場へ運ぶ
・ 寝台車
故人様がお亡くなりなった場所(病院など)からご遺体を安置する場所(会館など)へ運ぶ
お迎えに行く場所(病院など)への配慮から、寝台車の外観は一般車両と変わりありません。
構造的にも少し違いがあり、霊柩車の荷室は柩用にローラーレールがついています。
一方の寝台車の荷室は、ストレッチャーの車輪が動きやすいよう平らです。
また、双方の機能を備えている車両もあります。
霊柩車の利用料金・手配の方法について
続いては、霊柩車の利用料金や手配の方法について解説します。
利用料金は車種と走行距離で決まる
霊柩車の利用料金は、車種と走行距離によって決められています。
葬儀社などが霊柩車でご遺体を運ぶには国の許可が必要で、国土交通省に届出を行ない、適正であると認められた料金が適用されます。
霊柩車の車庫から起算して、ご遺体を運ぶ場所までの走行距離に応じた料金が適用されるため、無償でのご遺体搬送は違法です。
とはいえ、霊柩車の利用料金は、ご葬儀のプラン内に含まれていることが多いです。平安祭典でも、多くのプランに霊柩車が含まれています。
ご参考までに、平安祭典の霊柩車の利用料金は以下の通りです。
一般:55,000円(税込)
会員:49,500円(税込)
葬儀社を通じた手配が一般的
霊柩車の手配は、葬儀社を通じて行なわれるのが一般的です。
近年、洋型霊柩車が主流となったため、霊柩車を所有する葬儀社が増えました。
葬儀社が霊柩車を保有していればその霊柩車を使用し、保有していなければ葬儀社から専門業者に手配します。
ご遺族が霊柩車を手配する必要はありませんので、安心して葬儀社へお任せください。
霊柩車の前で親指を隠すのはなぜ?
それでは最後に、霊柩車にまつわる迷信をご紹介します。
霊柩車にまつわる迷信はいくつありますが、「霊柩車を見たら親指を隠す」という迷信をご存知の方は多いのではないでしょうか。
親指を隠す理由としては、以下のような言い伝えがあります。
・ 親の死に目に会えなくなる
・ 親が早死にする
・ 親族に不幸がある
親指と親をかけて、親に良くないことが起こらないよう、親指を隠す行為につながったのかもしれません。
また、次のような理由もあります。
・ 親指の爪の間から霊が入る
古来より人間の親指には魂の出入口があるといった伝承があり、死者の霊魂が入らないよう、親指を隠し自らを守るというものです。
いずれにしても、死を穢れとする日本の文化をあらわす民間伝承といえます。
宮型に代表される霊柩車のイメージも、洋型が主流となることで、少しずつ変わってくるかもしれません。
まとめ
当記事では霊柩車について、車種や手配方法から民間伝承までをご紹介しました。
もし霊柩車に関してご不明な点などがございましたら、平安祭典(0120-00-3242)まで気兼ねなくお問い合わせください。
続きはこちら
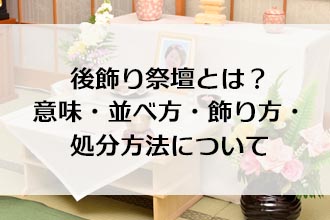
公開日:2022年6月20日
葬儀を執り行なうにあたり、「後飾り(あとかざり)」という言葉を初めて聞く方も多いかもしれません。
今回は、ご自宅でご遺骨を祀るために欠かせない後飾りについて知っておきたいことを解説します。
[@目次@]
後飾り祭壇とはどんなもの?
後飾り祭壇とは、ご遺骨を一時的に祀るための祭壇で、中陰祭壇(ちゅういんさいだん)などとも呼ばれます。
後飾り祭壇は火葬後にご自宅に戻り、ご遺骨を祀る際に準備します。
忌明けまでの間、ご遺族が故人様を供養し、弔問客の方々にお参りしていただくためのものです。
後飾り祭壇を使用する期間は、仏式では四十九日間、神式では五十日間まで、キリスト教式では埋葬の日までとされています。
忌明けについては###kiake_shijyukunichi###の記事で詳しくご説明しております。
後飾り祭壇の購入方法について特に決まりはありませんが、葬儀社に依頼するのが一般的です。
ご参考として、平安祭典で取り扱っている後飾り祭壇をご紹介します。
【平安祭典で取り扱っている後飾り祭壇】
・ 白木中陰祭壇:22,000円(税込)… 仏式用の白木の後飾り祭壇
・ 仮霊舎(かりみたまや):33,000円(税込)… 神式用の白木の後飾り祭壇
・ モダン後飾り:27,500 円(税込)… コンパクトな上置き後飾り祭壇
※宗旨・宗派を問いません
また、ご自身で台や白布などを準備して祭壇を作ることもできます。
後飾り祭壇の並べ方・飾り方のルール
後飾り祭壇の設置場所や飾り方については宗旨・宗派により、またご寺院のお考えやしきたりによっても異なります。
ここでは仏式と神式の一例をご紹介しますが、詳しくはご寺院にご確認いただくことをおすすめします。
ご自宅に仏壇がある場合、後飾り祭壇はできるだけ仏間に設置すると良いでしょう。
位置は仏壇の横が最適ですが、他の場所でもかまいません。
ただし、仏壇と向かい合わせに置くことや、仏壇に背中を向ける形での設置は避けたほうが良いとされています。
床の間の近くに設置する場合は中の窪みの部分ではなく、床の間の「前」に置いてください。
仏間への設置が難しい場合や仏壇がない場合は、スペースが取れる部屋に設置します。
その際は設置する方角にこだわるより、お参りがしやすい場所を選びましょう。
多くの弔問客が予想されるような場合は1階に設置するなど、ご事情に応じて決めて問題ありません。
仏式の場合
仏式の場合は、以下のように祭壇を設置しましょう。
■ 仏式(浄土真宗以外の場合)
一般的に白木の祭壇を用いますが、白木でない場合は白布をかけます。
ほかに以下のような仏具・小物を用意します。
・遺影 ・写真立て ・白木位牌 ・本骨箱 ・胴骨箱 ・お供え ・花瓶 ・生花
・電気灯明 ・ロウソク ・燭台 ・線香 ・香炉 ・巻線香 ・湯呑み ・仏飯
・仏前料理 ・焼香鉢 ・線香立て ・消し壷 ・黒いお盆(切手盆)
・おりん ・りん棒
後飾り祭壇の仏具は、白木のものをご用意いただくことが一般的です。
ただし、おりん・りん棒・焼香鉢などは仏壇で使用しているものを使っていただいてかまいません。
■ 飾り方の例
<上段:胴骨壷、白木位牌、本骨壷、湯呑み、仏飯>
<下段:お供え、遺影>
後飾り祭壇の前に台を設置し、花瓶、巻線香、仏前料理、香炉、燭台、電気灯明を配置します。
黒盆には焼香鉢・線香立て・りん・りん棒・消し壷を置きます。
■ 仏式(浄土真宗の場合)
一般的に白木の祭壇を用いますが、白木でない場合は白布をかけます。
ほかに以下のような仏具・小物を用意します。
・遺影 ・写真立て ・白木位牌 ・本骨箱 ・胴骨箱 ・お供え ・花瓶 ・生花
・電気灯明 ・ロウソク ・燭台 ・線香 ・香炉 ・巻線香 ・仏飯 ・焼香鉢
・線香立て ・消し壷 ・黒いお盆(切手盆) ・おりん ・りん棒
■ 飾り方の例
<上段:胴骨壷、白木位牌、本骨壷、仏飯>
<下段:お供え、遺影>
後飾り祭壇の前に台を設置し、花瓶・香炉・燭台・電気灯明を配置します。
また、黒いお盆(切手盆)には焼香鉢・線香立て・巻線香・おりん・りん棒・消し壷を置きます。
仏式のお供えは、仏飯・お水・お茶・お菓子・果物・生花が基本ですが、故人様が好きだったものをお供えしても良いでしょう。
浄土真宗ではお水はもとより仏飯もお供えしないのが正式とされています。
神式の場合
神式の場合、正式には白木の八足の祭壇(片足に4本ずつ脚をつけた台)を用います。
仏式のような白木の階段式の祭壇を使うことも可能です。白木でない場合は白布をかけます。
ほかに以下のような神具・小物を用意します。
・遺影 ・写真立て ・霊璽 ・本骨箱 ・胴骨箱 ・三方 ・榊
・榊立て ・神鏡 ・篝火 ・電気灯明 ・燭台 ・ロウソク ・生饌 ・菰
神具・小物はすでに使用しているものがあればそれを使ってかまいません。
■ 飾り方の例
<上段…胴骨箱、霊璽、神鏡、本骨箱、榊立て>
<下段…三方、生饌、篝火、電気灯明>
祭壇の下には菰を敷きます。
遺影は祭壇の前に配置します。神式のお供えは、お神酒、水、塩、洗米が一般的です。
後飾り祭壇の処分方法と処分後について
後飾り祭壇はあくまで仮の祭壇のため、忌明け法要を済ませたら必要なくなります。
ご自宅に仏壇がない場合は、忌明け法要までに用意しておきましょう。
ただし、場合によっては、後飾り祭壇をお盆飾りの祭壇として利用することもあります。
処分するか保管しておくか判断に困る場合は、念のためご寺院などにご確認いただくと安心でしょう。
なお、処分の方法は、ご寺院で供養していただく、精霊流しに持っていく、葬儀社に持ち込むなどの選択肢があります。
自治体の回収ルールに従ってゴミとして処分することも可能です。
平安祭典では、弊社でご購入いただいた後飾り祭壇の引き取りサービスを行なっています。ご連絡いただければご自宅に伺って無料でお引き取りいたします。
また、忌明け法要までに本位牌(浄土真宗では過去帳)を準備しておき、忌明け法要の際に故人様の魂を白木位牌から本位牌に移し替えます。
役目を終えた白木位牌は、ご寺院でお焚き上げをしていただくことが一般的です。ただし、ご寺院によっては取り扱いが異なるため、ご確認いただくと良いでしょう。
平安祭典ではゴミとして処分するには忍びないものの供養を代行するサービス(有料)もございます。
位牌については###ihai_toha###の記事で詳しくご説明しております。
まとめ
今回は後飾り祭壇について解説しました。
後飾り祭壇は火葬後から忌明けまでの間、故人様をお祀りする大切な祭壇です。
故人様が安心して旅立ちの準備ができるよう、また、ご遺族や弔問者の方々がお参りしやすいよう、きちんと整えておかれると安心でしょう。
後飾り祭壇のお問い合わせをはじめ、葬儀に関わるご相談などがございましたら、平安祭典(0120-00-3242)までご遠慮なくご連絡ください。
続きはこちら
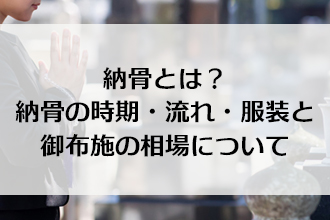
更新日:2024年9月21日 公開日:2022年6月13日
ご葬儀の後に行なわれる納骨について、不安な点をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
今回は、納骨を行なうにあたって知っておきたい情報をまとめてご紹介します。
「納骨の時期は?」「当日の流れは?」「どんな服装で参加する?」「御布施の相場は?」といった疑問を解消していただけますので、ぜひ最後までお読みください。
[@目次@]
納骨とは?納骨をする時期は?
納骨とは、ご遺骨をお墓などに埋葬することです。
埋葬の方法はお墓の種類や地域によって異なります。
墓石の下にある「カロート(納骨棺)」に骨壷をそのまま納める方法が最も一般的です。カロートはコンクリートや石で施工されています。
一方、関西では、ご遺骨を骨壷から納骨袋に入れ替えて埋葬する方法が多く見られます。
カロートの床は地面になっており、納骨袋に入れたご遺骨を土の上に置きます。
納骨袋はさらし(綿)や絹など自然素材のものを用意し、納骨袋やご遺骨が長い年月を経て土に還っていくように埋葬します。
また、近年、特に都市部では「納骨堂」を利用する方も増えています。
納骨堂はお墓の種類のひとつで、建物の中でご遺骨を保管してくれる場所です。
さまざまなスタイルの納骨堂がありますが、室内の棚やロッカーに骨壷を納めるのが最も一般的でしょう。
納骨堂によって、納められる骨壷(または骨箱)のサイズや個数の規定が異なりますので、利用する場合は事前の確認が必要です。
納骨をいつ行なうかについては、時期を定めた法律や決まりはなく、ご遺族のお考えで決められます。
一般的には、忌明け法要(または四十九日法要)、百か日法要、一周忌、三回忌などの節目に合わせて行なう方が大半でしょう。
中でも、忌明け法要のタイミングで納骨を行なうケースが最も多いようです。
その理由は、ご法要という大切な節目に、気持ちの整理をつけて「納骨もしよう」と考える方が多いためでしょう。
また、ご法要に集まったご親族がそのまま納骨に立ち会いやすい、ご法要からの流れでご寺院の都合がつきやすいといった理由もあります。
しかし、「まだご遺骨を手元に置いておきたい」と感じているなら、急ぐ必要はありません。心の準備ができたら納骨をすれば良いのです。
また、お墓を建てるには2~3か月ほどかかります。そのため、忌明け法要のタイミングで納骨を行ないたい場合は、事前の準備が必要です。
忌明け法要に関しては、###kiake_shijyukunichi###の記事をぜひご覧ください。
納骨の流れ
ここからは納骨の一般的な流れについてご説明します。
実際には、ご法要のスケジュール、お墓の種類や場所などにより異なる部分もありますので、あくまで参考としてお読みください。
納骨は、ご遺族、ご親戚の立ち会いのもとで行ないます。
用意するものは、ご遺骨、火葬時に受け取る「埋火葬許可証」、霊園に埋葬する場合は「霊園使用許可書」、はんこ、供花、供物、線香、ローソク、遺影、位牌、宗旨・宗派によっては塔婆、御布施などです。
また、事前にご寺院への日程の連絡や、石材店に戒名彫刻の依頼をしておきます。
<納骨の流れ>
供花や供物は納骨が始まる前にお供えしておきます。
■施主挨拶
ご法要で施主挨拶をした場合は省くこともあります。
↓
■納骨
ご遺骨を納めるスペースにご遺骨を安置します。(地域によってはご遺骨を骨壷から納骨袋に移し替えます。)
↓
■読経・焼香
ご寺院の読経の間、順番にお線香をあげます。
↓
■会食
食事をします。スケジュールによっては納骨の前に会食する場合もあります。
近年、納骨はごく近しい身内のみで行なうことが多く、施主挨拶や会食を行なわないケースも増えています。
納骨式での服装
ご法要後に納骨を行なう場合は、喪服を着用される方が多いです。
それ以外の日に納骨を行なう場合は、平服でもかまいません。
平服を選ぶ際には、男性は地味な色のスーツに黒のネクタイや靴、女性は無地の地味な色のスーツまたはワンピースに黒の小物を揃えると良いでしょう。
服装に関して不安をお持ちの方は、###sougi_midashinami###の記事をぜひご覧ください。
納骨での御布施の相場と渡し方
ご法要と同じように、納骨式もご寺院に御布施をお渡しします。御布施の相場は、2~5万円ほどです。
ご法要と同日に納骨を行なう場合は、ご法要の御布施に加え、納骨の御布施を用意します。
また、「御車料」として5千~1万円、「御膳料」として5千~1万円も必要です。
御布施をお渡しするタイミングに特に決まりはありませんが、一般的には納骨の開始前、ご法要がある場合はご法要の開式前にお渡しすることが多いようです。
臨機応変に、ご寺院とのご挨拶やお礼のタイミングでお渡しすれば問題ありません。
御布施の相場や渡し方のマナーについては、###ofuse_kingaku###や###ofuse_manner###の記事で詳しく解説しています。
まとめ
今回は納骨についてご紹介しました。
納骨は、ご遺族のご意向を大切に、気持ちに区切りのついたタイミングで行なえば良いものです。
納骨の準備や流れについては、お墓の種類(一般的なお墓か納骨堂などか)、お墓の場所(ご寺院内の墓地か外の霊園か)、お墓の造り(ご遺骨を納めるカロートの構造)などによっても異なります。
わからないことがあれば、ご寺院や、石材店に確認しながら進めましょう。
平安祭典では、各種ご相談を承っています。
神戸・阪神間でお困りごとがございましたら、平安祭典(0120-00-3242)まで気兼ねなくご相談ください。
続きはこちら
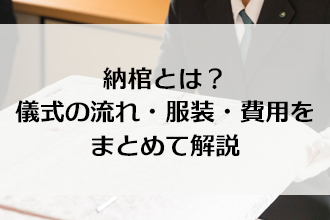
公開日:2022年6月6日
人が亡くなった際、一般的にはお通夜、葬儀・告別式の前に「納棺」を行ないます。
とはいえ納棺に立ち会うご経験は、どなたにとってもそうあることではないでしょう。
そこで今回は、納棺の流れや、服装、費用などについて解説します。
納棺とは?納棺を行なう意味は?
「納棺」とは故人様のご遺体を棺にお納めすることで、平安祭典では「納ノ儀」(おさめのぎ)と呼んでいます。他にも「納棺の儀式」と呼ばれることもあります。
納棺は通常、お通夜開式の数時間前までに、ご遺体が安置されている会館またはご自宅などで行なわれます。
近しいご親族の立ち合いのもと、葬儀社のスタッフや納棺師のサポートを受けながら進めることが一般的です。
納棺後は、お通夜、葬儀・告別式から火葬まで、ご遺族は段取りに気を配ったり、参列者の方々の応対など、何かと慌ただしい状態が続きます。
しみじみと故人様に想いを馳せる時間や心の余裕は、なかなかないでしょう。
だからこそ納棺は、ご遺族と故人様が、ゆっくりと過ごせる最後の貴重な時間となります。
故人様のお顔を間近で見て、お体に触れ、言葉をかける…。あらためて故人様と向き合うことで、ご逝去の悲しみを実感する瞬間でもあるでしょう。
心残りのないお別れができれば、気持ちのうえでひとつの区切りとなるはずです。
納棺には誰が立ち会う?服装は?
一般的に納棺は、近しい親族のみで行ないます。
納棺に立ち会う際の服装は、会館、自宅ともに平服でかまいません。
ただし、ご親戚や参列者がお見えになる可能性があるお通夜開式の約2時間前には、喪服に着替えておくのが良いでしょう。
お通夜、葬儀・告別式の服装については###sougi_midashinami###でも詳しくご紹介しています。
当記事とあわせて、ぜひご覧ください。
納棺の儀式の流れ・所要時間について
ここからは、納棺の流れの一例として、平安祭典で行なっている納ノ儀(納棺)についてご紹介します。
当社スタッフのはじめの言葉の後、合掌、焼香を行ないます
↓
当社スタッフとご遺族(2名ほど)でお布団を持ち上げ、故人様を棺の中にお納めします
↓
当社スタッフがお顔や死装束、お布団を整えます
↓
ご遺族の手でワラジ、笠、杖などの副葬品をお納めします
↓
ご用意いただいた副葬品(故人様ゆかりの品や好きだったものなど)をお納めします
↓
ご遺族の手で掛け布団をかけます
↓
納棺時用の生花(平安祭典では、おくり花と呼んでいます)をご注文いただいた場合は、生花をたむけます
↓
すべての支度が整ったら、全員で合掌します
↓
お柩の蓋を閉じて上から金襴をかけ、さらに修多羅もしくは守り刀を置きます
↓
当社スタッフの結びの言葉で終了です
納棺は、湯灌がある場合は湯灌の後に行なうことが多く、湯灌がない場合はお通夜前のご遺族がご希望されるタイミングで行ないます。
いずれにしても、お通夜の始まる数時間前までに終えておきます。
所要時間は、納棺が30分ほどで、湯灌は1時間ほどです。
納棺に関わる儀式
以下は、納棺に関わる儀式のご参考としてご紹介します。
末期の水(まつごのみず)
ご逝去後、故人様の口元を水潤す、仏教における大切な儀式です。
箸の先に脱脂綿などを巻いて水に浸し、喪主様から順に、故人様の唇を湿らせます。ご自宅や会館に安置後すぐに、ご遺族が行なうのが一般的です。
湯灌(ゆかん)
故人様の身体を清める儀式です。
病院などでもエンゼルケア(死後処置)として清拭が行なわれますが、それとは全く異なります。
湯灌とは、ご遺体を清潔にするのと同時に、亡くなられた方が、来世に導かれるために現世の穢れや煩悩を洗い清めるという意味と、赤ちゃんが生まれた時、産湯につかるように、新たに来世に生まれ変わるためにという願いを込め、新たな旅立ちの準備をする儀式です。
死化粧(しにげしょう)
故人様のお顔がなるべく生前と近い印象になるよう、髪を整えたり、お化粧を施します。
平安祭典では湯灌の際に、この死化粧を行ないます。
また、病院によっては、エンゼルケア(死後処置)の中で死化粧を行なうこともあるようです。
ご遺族の手で行なうことも可能なので、ご希望の方は葬儀社のスタッフへ事前にお伝えいただくと良いでしょう。
死装束(しにしょうぞく)への着替え
仏教では浄土への旅の支度として、故人様に死装束を着せるのが一般的です。
全身白の仏衣などを左前に合わせて着せ、葬具として笠、袈裟、杖、手甲、脚絆、白足袋、草鞋、頭陀袋などを着けます。
湯灌や納棺の際に行なわれることが一般的です。また、死装束ではなく、故人様の思い入れのある服にされる方もいらっしゃいます。
納棺にかかる費用の例
納棺にかかる費用は、依頼する葬儀社や納棺師によって異なります。
また、納棺の範囲(湯灌、死化粧、死装束への着替えを含むか)によっても変わります。
ご参考までに、平安祭典の料金は以下のとおりです。
・ 納棺(納ノ儀)の料金
一般:27,500円(税込)
会員:22,000円(税込)
・ 湯灌の料金
77,000円(税込)
まとめ
今回は、故人様との大切なお別れの儀式である納棺についてご説明しました。
納棺の流れや費用は葬儀社によって異なりますので、事前によく内容をご確認のうえ、心残りのないよう納棺を行ないましょう。
納棺およびお通夜、葬儀・告別式についてのご相談は平安祭典(0120-00-3242)までご連絡ください。
続きはこちら
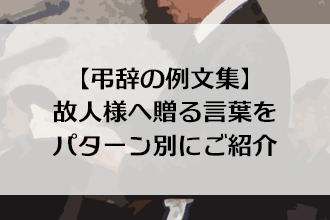
公開日:2022年5月23日
親しかった方が亡くなり、ご遺族から弔辞を依頼されたら…
「どんな内容にしたら良いだろう?」とお悩みになる方も多いでしょう。
本記事では、故人様と弔辞を読む方の関係をふまえ、パターン別の例文をご紹介します。
弔辞の基本的な書き方
通常、弔辞は2~5分ほど、文字数だと1,000文字ほどが目安です。
今回ご紹介する例文はシンプルな形でやや文字数は少なめですので、弔辞の持ち時間にあわせて調整してください。
弔辞に盛り込みたい内容
・故人様との関係性について
・心に残るエピソード(故人様の人柄や功績などがわかるもの)
・ご遺族へのお悔やみの言葉と故人様への最後のお別れの言葉
注意点
・忌み言葉は避ける
・持ち時間を考慮し、長くなりすぎないようにまとめる
・お子様が読む場合は、年齢相応のわかりやすい言葉づかいで読みやすく書く
弔辞の基本的な書き方・読み方の詳細については、###chouji_toha###の記事をご覧ください。
孫からおじいさん・おばあさんへ
(例)小学生の孫からおじいさんへ
おじいちゃんへ
おじいちゃん、もうおじいちゃんに会えないなんてまだ信じられません。
ぼくはおじいちゃんが大すきでした。親せきのみんなから「おじいちゃんに似ている」といわれるのが、とてもうれしかったんだよ。
夏休み、お正月、春休みにおじいちゃんとおばあちゃんに会いに行くのが楽しみでした。
よくおじいちゃんがつってきた魚を、おばあちゃんが料理してくれて食べたね。
ぼくが「おいしいけど、ほねが苦手だ」と言ったら、おじいちゃんが「こうやって最後まできれいに食べなさい」と教えてくれました。
おかげで、ぼくは魚が大すきになったし、魚の食べ方もうまくなったよ。
いつかおじいちゃんといっしょにつりに行きたかったです。
おじいちゃん、今までどうもありがとう。
ぼくは元気に学校へ行って、いろいろなことをがんばります。
友だちもたくさんつくります。
これからもぼくたちのことをずっと見守っていてください。
孫代表 〇〇
上司から部下へ
(例)直属の課長から部下へ
〇〇君、君は最愛のご家族と多くの友人、同僚に見送られ、旅立たれました。
私が今感じている深い悲しみと寂しさは、とうてい言葉で言い表すことはできません。
君は、ともに働く私たちにとって、そして我が社にとって、かけがえのない存在でした。
仕事において有能だっただけでなく、その明るさと思いやりの深さで職場の皆から愛されていました。
君は平成〇年に優秀な成績をもって我が社に入社されました。営業部に配属されると、周囲の期待に違うことなく、すぐに頭角を現し始めました。
優れた思考力、コミュニケーション能力、粘り強さで、着実に成果を出していったのです。
経験を積むにつれ、営業活動のみならず、部内の改革や他部門との連携強化にも積極的に携わるようになりました。
会社の将来を担う人材として大きな期待を寄せられていただけに、君の急逝は惜しんでなお余りあるのであります。
〇〇君、君は幼少の頃からずっとサッカーに打ち込んできたそうですね。
大学在学中はサッカー部の主将を務め、入社後も社内のサッカー部で活躍されました。華麗にプレイするその姿は、今でも私たちの目に焼き付いています。
直属の課長となってから5年以上、君の成長を間近で見守ってきただけに、これほどつらく悲しいことはありません。
それにもまして、長年にわたり君を慈しみ育てられ、君のさらなる活躍を楽しみとされていたご両親のご心痛をご拝察申し上げると、お慰めのことばもありません。
君もまた、天命とはいえ、大切なご両親を残して先立つことはどんなに心のこりだったことでしょう。
〇〇君、どうぞ安らかに。
令和〇〇年〇月〇日
株式会社〇〇〇〇
〇〇部〇〇課
課長 〇〇〇〇
部下から上司へ
(例1)社員代表から社長へ
本日、故〇〇〇〇社長の御霊に対し謹んで哀悼の意を捧げ、社員を代表してお別れのご挨拶を申し上げます。
社長ご永眠のお知らせに接し、社員一同、深い落胆と悲しみを隠しえません。
長年にわたり、社長は強いリーダーシップで社員を統率し、次々と新たな改革に取り組んでこられました。
常に率先して行動し、模範を示してくださるその姿は、私たちにとって憧れであり、多くの薫陶を受けました。
仕事には大変厳しい一方で、優しさと人間味溢れるお人柄で周囲を明るく照らし、広く慕われていました。
社員にも気さくに声をかけ、冗談を飛ばす、あの朗らかな笑顔が今も目に浮かぶようです。
ご功績は枚挙にいとまありませんが、特に、業界に先駆けて新しい技術を導入するというご英断は社運を大きく変えました。
これにより一段と競争力を高め、業界のリーディングカンパニーとしてのポジションを確立できたのは、まさに社長の先見の明があればこそです。
しかし、当社はまだこれからです。社員一同、社長のご遺志を受け継ぎ、社業のさらなる発展に邁進することをお誓い申し上げます。
ご遺族の皆様方には、さぞご心痛のこととお察しいたします。
しかし、社長は見守っていてくださいます。
どうか、お気落ちなさいませんようにお願いいたします。
最後に社長の御霊の安らかなることをお祈りして弔辞といたします。
令和〇〇年〇月〇日
〇〇〇〇株式会社
社員代表 〇〇〇〇
(例2)社員から部長へ
〇〇株式会社〇〇部長のご霊前に、謹んでお別れのご挨拶を申し上げます。
〇〇部長の突然の訃報に、社員一同、筆舌につくしがたい悲しみを感じております
〇〇部長はとてもエネルギッシュな方でした。
常に仕事に全力投球されていただけでなく、社内のゴルフ同好会や宴会でも、皆の中心となって場を盛り上げてくださいました。
その溌剌とした笑顔と体力は、とうてい55歳とは思えず、私たち若い部下を驚かせたものです。
思えば、私は入社からの10年間、ずっと〇〇部長のご指導のもと仕事に取り組んできました。
右も左もわからなかった私に一から仕事を教え、鍛えてくださったのは〇〇部長です。
特に仕事に対するチャレンジ精神と寛容の心を教わりました。
昨年、全く新規のプロジェクトに部をあげて取り組み、無事に成功させられたのも、〇〇部長の統率力と叱咤激励があったからです。
また、〇〇部長は自分に厳しく、人に優しい方でした。
私が悩んでいる様子を見ると、一緒にビールを飲みながらとことん話を聞いてくださいました。
〇〇部長のアドバイスに何度救われたことでしょう。
〇〇部長を上司に持つ私は、他の同僚からも羨ましがられていました。
部長の下で仕事をさせていただいたこと、感謝いたします。
ご家庭のことも会社でよくお話しされていました。
素敵な奥様とかわいいお子さんの自慢話をされる時の嬉しそうな姿を、独身の私はいつも羨ましく思ったものです。
素晴らしい夫、良き父でもあった部長を亡くされたご家族のお気持ちを思うと、慰めの言葉もございません。
部長、どうぞ安らかにお眠りください。
〇〇〇〇株式会社
〇〇〇〇
親しかった友達へ
(例)長年の親友へ
〇〇、突然の訃報に驚きました。
たった数か月前、一緒にテニスをしたというのに、このようなかたちで再会するなんて未だ信じられません。
〇〇との出会いは中学校のテニス部でした。
ダブルスを組んだことがきっかけで、僕たちはいつの間にか親友になっていました。
暑い日も、寒い日も、厳しい顧問のしごきに耐えながら、テニスに明け暮れましたね。
精神的にも体力的にもタフで頑張り屋だった〇〇は、気弱な僕にいつも発破をかけてくれました。
3年生の最後の試合、二人で勝ち取ったトロフィーは今でも僕にとって一番の宝です。
高校以降はそれぞれの道に進みましたが、正月には必ずテニス部の仲間と集まり、新年会をしていました。
社会人になってからは、仕事の相談をしたり、愚痴を言い合ったり、〇〇はずっと僕にとって最も心を許せる友でした。
いつも明るくポジティブに「大丈夫だって!やってみろよ」と言ってくれる〇〇を頼りにしていました。
二人とも結婚してからは家族ぐるみのつき合いとなり、近々キャンプに行こうと話していたのに、残念でなりません。
もう〇〇と一緒に笑い合うことも、テニスもできないなんて、僕は寂しいよ。
でも、〇〇に恥じないよう、この先の人生をしっかりと歩んでいきます。
このような突然のお別れに、ご家族の図りしれない悲しみを察するに慰めのことばもありません。
しかし、〇〇はずっと僕たちの心の中にいます。
〇〇、ありがとう。そして、さようなら。
〇〇〇〇
まとめ
今回はパターン別に弔辞の例文をご紹介しました。
弔辞は故人様に送る最後のメッセージであると同時に、ご遺族に慰めの気持ちを伝えるものです。
何よりも大切なのは、故人様に対する哀悼の想いを伝えることです。
形式や美辞麗句にとらわれず、自分らしい言葉で綴れば良いでしょう。
ご不明なことやご不安がございましたら、気兼ねなく平安祭典(0120-00-3242)までご相談ください。
続きはこちら
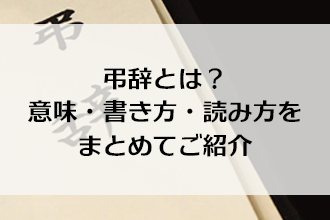
公開日:2022年5月16日
著名人のご葬儀やお別れ会などで弔辞が読まれているシーンをニュースなどで見たことがある方は多いでしょう。
通常の葬儀・告別式では、あまり弔辞を聞いたり読んだりする機会はありませんが、社葬や宗教色のない自由葬などでは、弔辞を依頼される可能性があります。
いざ弔辞を依頼された時の「何をどうしたらよいのだろう…」というお悩みに答えるため、本記事では弔辞の意味や、書き方・読み方についてご紹介します。
弔辞とは?誰が読む?故人様へのお別れの言葉
「弔辞」は「ちょうじ」と読みます。
ちなみに、同音異義語の「弔事(ちょうじ)」は、人が亡くなること、それにまつわるご葬儀など全般を指す言葉です。
ここでは弔辞の意味と、一般的に誰が読むのかを説明します。
弔辞とは故人様へのお別れの言葉
弔辞とは、故人様に贈るお別れの言葉です。
故人様への最後のお手紙のようなもので、葬儀・告別式にて故人様と関係の深かった方が霊前で弔辞を読みます。
ちなみに、弔電とは弔いの気持ちを伝える電報のことです。
弔辞とは異なるものなので、混同しないようご注意ください。
故人様と関係の深かった方が読むもの
通常はご遺族が弔辞を読んで欲しい人へ依頼をします。
弔辞を誰が読むかについて決まりはなく、故人様と特に関係が深かった方に依頼するのが通例です。
プライベートまたは、仕事を通して親しかった方が読むケースが多いでしょう。
たとえば、親友、恩師と生徒の関係だった方、仕事で苦楽を共にした上司や部下、趣味を通して交友のあった方などです。
お孫さんがお手紙として読むこともあります。
弔辞を依頼されたら、特別な事情がない限り引き受けるのが礼儀です。
参列者が自ら「ぜひ弔辞を読ませてほしい」と申し出ることもできますが、時間や進行の都合などで必ずしも読めるとは限りません。
通常の葬儀・告別式で弔辞を読むことは、あまりありませんが、自由葬やお別れ会などであれば1~3名ほど、規模の大きい社葬などの場合は、5名程度になることもあります。
弔辞の書き方と注意点
続いては、弔辞の内容に関する考え方と書式・マナーについて具体的にご紹介します。
弔辞には、「こう書かなければならない」という決まりや定型はありません。
とはいえ、マナーとして気をつけたい点、弔辞の基本とされることを知っておくと安心です。
弔辞の基本とは?構成と盛り込むべき内容
はじめに内容の考え方についてご説明します。
弔辞の基本とされる構成は「出だし」「主題」「結び」です。
・出だし:故人様への呼びかけ、故人様の訃報に接した際の驚きや悲しみの言葉
・主題:故人様とのエピソード、故人様の人柄や功績、故人様に伝えたい約束や決意
・結び:ご遺族へお悔やみの言葉、故人様への最後の言葉
主題には故人様の人柄が伝わるエピソードや感謝の気持ちなど、最も伝えたいことを盛り込みましょう。
過度に感傷的な表現や個人的すぎる話題はなるべく避けたほうが良いとされています。
ご紹介した構成や内容はあくまで参考とお考えください。
故人様との関係を踏まえ、素直な気持ちを自分らしく綴っても良いのです。
弔辞の文字数の目安
弔辞は1人あたり、2~5分間ほどが持ち時間であることが多いです。
人が1分間に話せる文字数はだいたい300文字ほどらしいので、1,000文字ほど(原稿用紙なら2~3枚ほど)を目安に書けば、ちょうど良い長さになるでしょう。
弔辞では「忌み言葉」を使わない
弔辞では「忌み言葉」を使わないのがマナーです。
以下のような忌み言葉を避けて表現を置き換えましょう。
・「重ねる」「くりかえし」の意味を持つ言葉
「まだまだ」「ふたたび」「今一度」「くれぐれも」など
死という不幸が度重なることを避けるという意味からです
・死を直接表現する言葉
「死亡」「死去」など
「逝去」「逝く」「他界する」などに置き換えます
・成仏できないという意味が含まれる言葉
「迷う」「浮かばれない」など
弔辞の文例については、###chouji_reibun###で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
弔辞の書式・たたみ方・包み方
弔辞は、正式には大判の巻紙か奉書紙を用意し、毛筆で薄墨を使って書きます。
毛筆が難しい場合は略式にはなりますが、便箋などにペンで書いても構いません。
弔辞はご遺族が永く手元に保管する場合もあります。
書き損じなどがないよう、一度文面をまとめてから清書をすると良いでしょう。
書き方のルール・注意点
・巻紙の場合は10センチほどの余白を取って書き始める
・奉書の場合は1枚に弔辞が収まるよう、文字量と文字の大きさを調整する
・1行目に「弔辞」と書き、2行目から本文を書く
・最後に日付、肩書、氏名を1行ずつで書く
・書き始めや改行の際も1字下げない
・句読点は打たずに1文字分あける
・包みの表に「弔辞」と書く
たたみ方
・巻紙は文末から10センチ幅で巻き折りにする
・奉書紙は「左から半分に折る」→「三つに屏風折り」→「縦に二つ折り」の手順で折る
包み方
・奉書紙を幅半分に切り、表に「弔辞」と書く
・左が前になるように三つ折りにし、弔辞を書いた紙を包む
弔辞の読み方とマナー
ここからは実際に弔辞を読む時の立ち振る舞いについて確認しましょう。
葬儀・告別式の読経や焼香が一区切りついたタイミングで「弔辞」、その後、弔電紹介という進行が最も一般的です。
※下記の流れはあくまで一例です。
司会者に名前を呼ばれたら、祭壇の前へ進み、ご寺院とご遺族に一礼する
↓
霊前に向き直り、一礼する
↓
弔辞の包みを開いて中身を取り出し、包みをたたんで所定の台や盆に置く
(置く場所がない場合は懐に入れる)
↓
弔辞を左手に持ち、右手を添えて開く
↓
両手で目の高さに捧げ持つようにして弔辞を読む
↓
弔辞を包みに戻し、表書きを霊前へ向けて盆や台に置く
(弔辞をお供えせずそのまま持ち帰ることもある)
↓
霊前に一礼後、ご寺院とご遺族に一礼し、席へ戻る
弔辞は心を込めて、ゆっくりと読みましょう。
故人様だけでなくご遺族に対する慰めの言葉でもありますので、聞き取りやすいよう意識してください。
まとめ
今回は、弔辞の意味、書き方と読み方についてご説明しました。
弔辞は大切な方へのお別れの言葉です。
マナーは守りつつ、自分の言葉で故人様への哀悼や感謝を表現しましょう。
当日の段取りや所作などは事前にしっかり確認しておくと、落ち着いて弔辞を読めるはずです。
弔辞以外にもご葬儀に関する事前相談やお困りごと、ご不安がありましたら、気兼ねなく平安祭典(0120-00-3242)までご相談ください。
続きはこちら
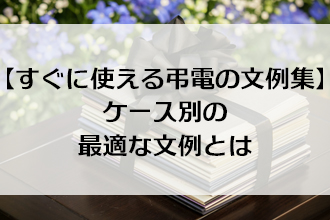
公開日:2022年5月9日
お通夜や葬儀・告別式に参列できない時に送る弔電ですが、メッセージに何を書くべきか迷う方も多いのではないでしょうか。
書き出しの一言から見当もつかないかもしれません。
弔電には「電報」ならではのルールやマナーがあります。
そこで、弔電の文面でお悩みの方のために、当記事では弔電の文例をケース別にご紹介いたします。
ぜひ弔電を送る際の参考になさってください。
弔電の文字数ってどれくらい?
弔電は「手紙」ではなく、参列できない代わりに弔意を伝える「電報」です。
実際の弔電は、たいてい20~80文字ほどのメッセージで送られています。
葬儀・告別式の前のご遺族は、じっくり長文に目を通せる状況にありません。
定型句を交えながら簡潔にまとめるのが、わかりやすく良い弔電と言えるでしょう。
また弔電は葬儀・告別式の最中に司会者によって読み上げられることがあります。
人が話すスピードは、1分間で約300文字が平均とされています。
葬儀・告別式の時間には限りがあるため、弔電は差出人の肩書や名前なども含め、およそ30秒間で読める150文字程度に収めておきたいところです。
とはいえ故人様との関係性によって、メッセージの内容や長さは少し変わると思います。
会社関係のお付き合いや顔見知り程度なら、シンプルに定型句のみでも失礼にはあたりません。
故人様がお友達の場合やご遺族様と親密なお付き合いがあるなら、少し言葉を加えても良いでしょう。
ちなみに電話で申し込む電報は、文字数によって料金が変わるのが通常です。
課金対象の文字には宛名や差出人名も含まれるのでご注意ください。
対してインターネットで申し込む場合は、文字数で料金が変わることはほとんどありません。
文字数制限については各社さまざまですが、少なくとも200文字以上は記載できるようです。
文字数に加え改行位置などを注意すると、読みやすい弔電になるでしょう。
ケース別の弔電例文集
ここからは、ケース別に弔電の文例をご紹介します。
弔電の文面を考える前には、必ず次の2点を確認しましょう。
① 一般的なご葬儀か、社葬など団体のご葬儀か
② 宗旨・宗派(仏教式・神式・キリスト教式など)は何か
また、どのような弔電でも宛先となる喪主の確認が必要です。
弔電内に故人様の敬称を入れる場合、喪主から見た敬称を使用しますので、故人様と喪主の続柄を必ずご確認ください。
弔電の敬称については、###chouden_toha###の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
弔電によく使われる定番の文例
それではまず、弔電によく使われる文例をケース別に見ていきましょう。
ここでご紹介する文例は仏式のご葬儀・告別式へ送る弔電ですが、宗派が浄土真宗の場合は「冥福」という言葉の入った例文は使いません。
◆ 一般的な文例
ご逝去の報に接し衷心よりお悔やみ申し上げます
ご逝去を悼み心からご冥福をお祈りいたします
在りし日のお姿を偲びつつ心からご冥福をお祈り申し上げます
ご逝去の報に接し心から哀悼の意を表します
安らかにご永眠されますようお祈り申し上げます
ご生前のご厚情を深く感謝すると共に故人のご功績を偲び
心からご冥福をお祈り申しあげます
ご訃報に接し胸がふさがる思いです
今はただご冥福をお祈りするばかりです
ご逝去を悼み心からご冥福をお祈り申しあげます
ご家族の皆様が心を合わせ強く歩んで行かれますよう祈っております
●●様のご逝去の報に接し悲しみにたえません
ご遺族様のお嘆きもいかばかりかと拝察いたします
心からご冥福をお祈り申し上げます
悲報に接し痛惜の念でいっぱいです
大切な方とお別れをするご家族皆様のご心痛をお察しいたします
今はただご冥福を祈るばかりです
突然の悲報に接し悲しみにたえません
ご家族皆様方のお嘆きもいかばかりでございましょう
在りし日を偲び心からご冥福をお祈りいたします
●●様がお亡くなりになられた悲しみは
ご家族の皆様にとりまして計りしれないものとお察しいたします
お力落としをお慰めするすべもありませんが心からお悔やみ申し上げます
突然の悲報に接し誠に痛惜の念でいっぱいです
皆様がお気持ちを強く持てますよう心から願うと共に
●●様のご冥福をお祈りいたします
突然の悲報に接し言葉を失っております
遺されたご家族のご心情をお察しし
すぐに駆けつけたい気持ちでいっぱいですが
遙かなる地よりご冥福をお祈りいたします
◆ ご尊父(お父様)が亡くなった場合の文例
ご尊父様のご逝去の報に接し衷心よりお悔やみ申し上げます
ご尊父様のご逝去を悼み謹んでお悔やみ申し上げます
ご尊父様のご功績を偲び心からご冥福をお祈り申し上げます
ご逝去の報に接し謹んで哀悼の意を表します
ご尊父様にはひとかたならぬお世話になりました
ご冥福をお祈りいたします
ご尊父様のご訃報に接し愛惜の念にたえません
弔問かなわぬ非礼をお詫びし謹んでお悔やみ申し上げます
在りし日の姿を偲び心から哀悼の意を表します
ご尊父様からは幾多のご厚情をうけながら
ご恩返しもできず痛惜の念もひとしおです
ご冥福をお祈りいたします
療養中と聞いておりましたが
皆様のご看病の甲斐なく本当に残念なことです
どうかお力落としなさいませんように
ご冥福をお祈りいたします
お父様のご逝去を悼み心よりお悔やみ申し上げます
大事な方にお別れするご家族のお悲しみを察しますと
お慰めの言葉もございません
ただご冥福をお祈りするばかりです
●●様の悲報に接し謹んでお悔やみ申し上げます
ご家族の皆様が心を合わせ
悲しみを乗りこえられますようお祈りいたします
●●様のご逝去を衷心よりお悔やみ申し上げます
遺されましたご家族の皆様のご心痛をお察し申し上げますと共に
心からご冥福をお祈り申し上げます
◆ ご母堂(お母様)が亡くなった場合の文例
ご母堂様のご逝去を悼み衷心よりお悔やみ申し上げます
ご母堂様のご逝去を悼みつつ心からご冥福をお祈りいたします
ご母堂様のご逝去を悼み
謹んでお悔やみ申しあげますと共に
心からご冥福をお祈りいたします
お母様のご逝去に哀悼の意を表します
いつも明るい方でした
面影を胸に刻みつつご冥福をお祈りいたします
ご母堂様のご逝去を謹んでお悔やみ申し上げます
皆様のお悲しみをお察しすると
お慰めの言葉もありません
心よりご冥福をお祈り申し上げます
ご母堂様のご訃報に接し愛惜の念にたえません
弔問かなわぬ非礼をお詫びし
謹んでお悔やみ申し上げます
お母様のご逝去を悼み謹んでお悔やみ申し上げます
お優しかったお顔を思い出しまだ信じられずにおります
今はただご冥福をお祈りいたします
突然の悲報に接しご家族の心痛を思うと胸がふさがる思いです
一日も早くお元気になられますように願いつつお母様のご冥福をお祈り申し上げます
お母様とはよきお付き合いをさせていただきましたから
突然の悲報に涙するばかりです
心からご冥福をお祈り申し上げます
◆ ご子息(息子様)が亡くなった場合の文例
ご子息様のご逝去の報に接し謹んでお悔やみ申し上げます
ご子息様の訃報に接し心よりお悔やみ申し上げます
在りし日のお姿を偲びつつご冥福をお祈りいたします
ご子息様のご逝去を悼み
ご両親様のお嘆きをお察し申し上げますとともに
心よりお悔やみ申し上げます
ご子息様の突然の悲報に接し
ご家族様のご心情いかばかりかとお察しいたします
謹んでお悔やみ申し上げます
ご子息様の突然の悲報に接し驚いております
ご家族の皆様のご心情をお察しし
すぐにもお慰めに飛んでまいりたい気持ちですが
遥かな地よりご冥福をお祈りいたします
ご令息様の突然の悲報に接し
驚きと悲しみに包まれております
あまりに早すぎる旅立ちに
ご家族皆様の深い悲しみをお察し申し上げます
心からご冥福をお祈りいたします
ご子息様がお亡くなりになられたお辛さは
計り知れないものとお察しいたします
一日も早く悲しみの中から立ち直られますように
祈念しております
心からお悔やみ申し上げます
ご令息様の突然の悲報に
ご両親様のお嘆きいかばかりかと拝察申し上げます
在りし日の輝く笑顔を偲び心よりお悔やみ申し上げます
ご令息様の急逝の報に接し悲しみにたえません
前途洋々たる時に突然他界され
ご両親様のお悲しみご無念のお気持ちは
いかばかりかとお察しいたします
謹んでお悔やみ申し上げます
ご子息様のご逝去に深く哀悼の意を表します
精悍なご子息の姿を思い出しますと胸が痛みます
ご家族の皆様のお悲しみはいかばかりかとお察しいたします
謹んでお悔やみ申し上げます
◆ ご令嬢(お嬢様)が亡くなった場合の文例
ご令嬢様のご逝去の報に接し謹んでお悔やみ申し上げます
ご令嬢様の訃報に接し心よりお悔やみ申し上げます
在りし日のお姿を偲びつつご冥福をお祈りいたします
ご令嬢様のご逝去を悼み
ご両親様のお嘆きをお察し申し上げますとともに心よりお悔やみ申し上げます
ご令嬢様の突然の悲報に接し
ご家族様のご心情いかばかりかとお察しいたします
謹んでお悔やみ申し上げます
ご令嬢様の突然の悲報に接し驚いております
ご家族の皆様のご心情をお察しし
すぐにもお慰めに飛んでまいりたい気持ちですが
遥かな地よりご冥福をお祈りいたします
ご令嬢様の突然の悲報に接し驚きと悲しみに包まれております
あまりに早すぎる旅立ちにご家族皆様の深い悲しみをお察しいたします
謹んでお悔やみ申し上げますとともに心からご冥福をお祈りいたします
ご令嬢様がお亡くなりになられたお辛さは
計り知れないものとお察しいたします
一日も早く悲しみの中から立ち直られますように祈念しております
心からお悔やみ申し上げます
ご令嬢様の突然の悲報に
ご両親様のお嘆きいかばかりかと拝察申し上げます
在りし日の美しいお姿を偲び心よりお悔やみ申し上げます
ご令嬢様の急逝の報に接し驚いております
これからのご活躍を楽しみにしておりましたのに
ご両親様のお悲しみご無念のお気持ちは
いかばかりかとお察し申し上げます
謹んでお悔やみ申し上げます
お嬢様のあまりにも若きご他界に
驚きと悲しみに包まれております
ご両親のお気持ちを思うと胸が痛みます
生前のお美しき姿を偲びつつ
心よりお悔やみ申し上げます
可憐なお嬢様の笑顔を忘れる事は出来ません
これからと言う時に先立たれた
ご両親様のお悲しみはいかばかりかとお察しいたします
謹んでお悔やみ申し上げます
◆ 若い方が亡くなった場合の文例
会いたいと思っておりましたのに
こんな突然のお別れになってしまい
驚きと悲しみに包まれております
心よりご冥福をお祈りいたします
突然の悲報に接しただ驚くばかりです
もうあの笑顔にお会いできないのかと思うと悲しくてなりません
在りし日の●●様のお姿を偲び心からご冥福をお祈りいたします
突然の悲報にただ驚くばかりです
●●様の優しい笑顔はいつも私に元気をくれました
在りし日のお姿を偲び心からご冥福をお祈りいたします
ご逝去の報を受け
驚きとともにお元気だったころの
笑い声を思い出しています
まだ語り合いたいことがたくさんあったのにと
痛惜の念でいっぱいです
心からご冥福をお祈りいたします
突然の悲報に接し
運命の過酷さを思わずにはいられません
●●様の在りし日のお姿を偲び
心よりご冥福をお祈りいたします
●●様ご逝去の報を受け胸がふさがる思いです
すぐに駆けつけたい気持ちでいっぱいですが
遙かなる地よりご冥福をお祈りいたします
突然の非報に茫然といたしました
働き盛りのお元気だった●●様の面影が目に浮かびます
将来をとても期待されていた方でしたのに本当に残念でなりません
心からご冥福をお祈りいたします
◆ 会社から弔電を送る場合の文例
●●様の悲報に接し謹んでお悔やみ申し上げます
ご生前の笑顔ばかりが目に浮かびます
どうぞ安らかな旅立ちでありますよう
心からお祈りいたします
ご逝去を悼み
故人のご功績をたたえ
心から哀悼の意を表します
貴社社長様のご逝去の報に接し
衷心より哀悼の意を表します
貴社社長様のご訃報に接し
ご生前のご功績を偲び
衷心より哀悼の意を表します
貴社社長様のご生前のご功績を偲び
心からご冥福をお祈り申し上げます
貴社社長様のご訃報に接し
当社社員一同謹んで哀悼の意を表します
ご遺族の皆様ならびに社員のご一同様に
心からお悔やみ申し上げます
●●社長様のご逝去の報に接し哀惜の念にたえません
優しい笑顔共に過ごした思い出等 在りし日の思い出は尽きません
遠くから手を合わせ安らかにご永眠されますようお祈りしております
社長様の在りし日のお姿を偲び
心からお悔やみ申し上げます
当社社員一同ご冥福をお祈り申し上げます
会長様の在りし日のお姿を偲びつつ
心からお悔やみ申し上げます
ご回復を祈願しておりましたが残念でなりません
謹んでご冥福をお祈りいたします
突然の訃報 驚きと悲しみでいっぱいです
幾多のご厚情を思えばすぐにでも最後のお別れに
駆けつけなければならないのですが参列できず残念です
衷心よりご冥福をお祈り申しあげます
神式やキリスト教式のご葬儀に弔電を送る
葬儀・告別式が神式やキリスト教式で行なわれるなら、仏教用語は避けましょう。
「成仏」「供養」「合掌」「冥福」「往生」「ご愁傷様」などがそれにあたります。
◆ 神式の文例
御霊のご平安をお祈りいたします
御霊の安らかな眠りをお祈り申し上げます
ご訃報に接し胸がふさがる思いです
御霊の安らかな眠りをお祈りいたします
ご逝去の報に接し心から哀悼の意を表します
安らかにご永眠されますようお祈り申し上げます
在りし日のお姿を偲びつつ御霊の安らかな眠りを心よりお祈りいたします
ご生前のご厚誼を深く感謝するとともに
故人のご功績を偲び
御霊の平安をお祈り申し上げます
ご逝去の報を受け痛惜の念でいっぱいです
弔問かなわぬ非礼をお詫びし謹んでお悔み申し上げます
●●様ご逝去の報に接し悲しみにたえません
ご遺族様のお嘆きもいかばかりかと拝察いたします
御霊の平安を心からお祈り申し上げます
ご逝去を悼み心からお悔やみ申し上げます
皆様がお気持ちを強く持てますよう心から願うと共に
●●様の御霊の平安をお祈りいたします
突然の訃報に接し胸がふさがる思いです
ご家族のお嘆きも計りしれないものとお察しします
お力落としをお慰めするすべもありませんが心よりお悔み申し上げます
◆ キリスト教式の文例
神の御許へ召された●●様が
安らかな眠りにつかれますよう
心からお祈り申し上げます
神様の御許へ召された●●様を偲び心から哀悼の意を表します
●●様が主の御許で安らかに憩われますよう心よりお祈り申し上げます
●●様の訃報を知り心より哀悼の意を表します
ご家族の皆様の上に主のお慰めと励ましがありますようお祈りいたします
●●様と出会えたことを神に感謝いたします
安らかな旅立ちでありますよう心よりお祈り申し上げます
●●様の悲報に接し驚いています
これからは神様のおそばで安らかに過ごされますよう
心よりお祈り申し上げます
●●様の訃報を知り哀しみに堪えません
今は全ての重荷を下ろし
主のもとで憩われていらっしゃることでしょう
ご家族の皆様に主の慰めが
豊かに注がれますようにお祈り申し上げます
地上での働きを終え天に召されました●●様に
安らかな憩いがありますよう
ご家族の上に主の慰めが注がれますよう
お祈り申し上げます
隣人を愛し神様を愛し
聖書の教えを忠実に守って歩まれた
●●様の生涯に思いを馳せつつ
主の御許で安らかに過ごされんことを
お祈りいたしております
地上においてなすべき使命を終えて
主のもとへと召された●●様
主キリストの葡萄の木に繋がれ
永遠のいのちを与えられますよう
そして主の愛が豊かに降り注がれますよう
お祈りいたします
主の戒めを忠実に守り世の塩となり
燭台の灯りとなって正しき行いを示し続けた
●●様の歩みに感謝いたしております
ご家族皆様の上に
主イエス様のお慰めと励ましがありますよう
お祈りいたします
まとめ
当記事では、弔電の文例をケース別にご紹介しました。
以下の点に気を付けて、ふさわしいメッセージを送りましょう。
・正しい敬称で
・長くなり過ぎず簡潔に
・宗旨・宗派にあわせて
文面をどうすべきかわからない場合、文例をそのまま引用しても失礼にはあたらないので、適切なものを選んで送ると良いでしょう。
文例に生前のエピソードを添えると、ご遺族とも想い出を共有できます。
弔事には日常にないルールやマナーもあり、誰しも戸惑うことが多いものです。
お困りごとやご不安があれば、気兼ねなく平安祭典(0120-00-3242)までご相談ください。
続きはこちら
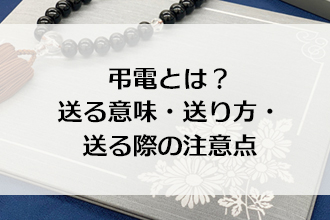
公開日:2022年5月2日
大切な方のお通夜や葬儀・告別式に参列できない時、弔電を送ります。
よく知られる慣例のひとつですが、実際に弔電を手配されたことのある方は、意外に多くないかもしれません。
弔電は頻繁に送るものではないですし、いざ手配するとなると、ルールやマナーが気になることでしょう。
そこで、当記事では弔電について詳しく解説いたします。
弔電とは?弔電を送るのはいつ?
それではまず、弔電の意味や送り方をご説明します。
弔電とはどのようなものか、いつ、どのように送るのかなどをご確認ください。
葬儀・告別式に参列できない時に送る電報
弔電とは、弔いの気持ちを伝える電報です。
大切な方の訃報に際し、お通夜や葬儀・告別式に参列できない場合、葬儀・告別式を執り行なう会館などへ届けます。
遠方であったり仕事の都合がつかなかったり、またコロナ禍以降は、参列に制限があるケースも増えました。
弔電はそういった場合にも、迅速かつ確実にお気持ちを伝えることができます。
弔電の送り方
弔電の手配方法には、電話とインターネットの2つがあります。
ひと昔前は、電報といえば電話をかけて手配するものでした。
近年でも電話での申し込みは可能ですが、より使いやすいインターネットを使われる方が多いでしょう。
「弔電」で検索すれば、たくさんのサービスが出てきます。
さらに、そうしたサービスの他にも、ご葬儀を執り行なう会館に直接弔電を注文できることも多くなりました。
たとえば、平安祭典で採用しているサービスに「つなぐシステム」というものがあります。
使い方は簡単で、ご葬儀の打ち合わせ後すぐに、当社従業員が故人様のご葬儀情報を記した専用の「訃報のご案内ページ」を作成します。
喪主は、そのURLをメールやLINEなどのSNSで親族や故人様と親しかった人に送ると、受け取った側は、URLをクリックするだけで、喪主、通夜や葬儀の時間、場所など、必要な情報の確認が可能です。
さらに「訃報のご案内ページ」から簡単に1通1,000円で弔電を送ることができ、弔電とあわせて、供花・供物などを贈ることもできるサービスです。
また、その際に弔電の例文を見ることができるのも利用者にとってメリットです。
送った弔電は、ご葬儀を執り行なう葬儀社が受け取り、印刷などを行ない、喪主へと手渡されます。
なお、弔辞と混同されてしまうことがありますが、弔辞は故人様へ贈るお別れの言葉です。
一般的に葬儀・告別式などの際、故人様と親交の深かった方がご遺族に依頼されて読み上げるもので、弔電とは異なります。
葬儀・告別式に間に合うように送る
弔電を送るタイミングですが、遅くとも葬儀・告別式開始の数時間前までに届くよう手配しましょう。
さらにいうと、お通夜までに届くのがベストです。
一般的に弔電は、葬儀・告別式の際、司会者によってメッセージと差出人名が紹介されます。
弔電が届いたら喪主やご遺族は事前に内容を確認し、読む順番を決める必要があるため、弔電を送る際は、速やかに手配することをおすすめします。
お届けがご葬儀に間に合わない場合や、訃報を知った時にはすでに葬儀・告別式が終わっていたということもあるかもしれません。
そういった場合は、後日、ご遺族へご連絡した上で、ご自宅へ御香典を持参し手を合わせたり、お悔やみの手紙とともに御香典を現金書留でご自宅へお送りしたりなど、別の方法で弔意を表すと良いでしょう。
宛名と差出人についての注意点
弔電の宛名は喪主の名前とします。
たとえ喪主と面識がなくても、ご遺族と親しい間柄であっても、弔電の宛名には喪主の名前をフルネームで記載しましょう。
喪主の名前がわからない場合は、「〇〇家 ご遺族様」または「故〇〇〇様 ご遺族様」とすると良いでしょう。
※企業や団体が主催するご葬儀であれば、葬儀主催者や責任者、部署名などになります。
一方の差出人名は、故人様と直接のお知り合いの場合は、故人様と差出人との関係がご遺族にわかるように記載しましょう。
仕事関係であれば会社名や団体名を、学生時代の同窓であれば大学名と卒業年度などを併記するとわかりやすいです。
故人様と直接の面識がない場合(同僚のお父様が亡くなられて喪主は同僚のお兄様など)は、連絡のつくご遺族に弔電送付の旨をお伝えしておくと良いでしょう。
また連名で送る場合は、役職や年齢などの上から順に名前を記載します。
人数が多い場合は〇〇一同、とすると良いでしょう。
弔電で使ってはいけない言葉
弔電の文面には、忌み言葉をはじめとした不適切な言葉があります。
日常的に使う語句も多いので、うっかり使うことがないよう弔電の最終確認の際に、必ず見直しましょう。
・忌み言葉
重ね重ね、益々、しばしば、またまた、いよいよ、いろいろ、わざわざ、次々、くれぐれ、皆々様、再び、再三、再三再四、繰り返す、続いて、なおまた、追って…など
・不吉を連想させる言葉
消える、大変、落ちる、とんでもない、数字の四(死)や九(苦)…など
・直接的な表現は避け、婉曲表現に言い換える
死亡→逝去、生存中→生前、急死→突然の事…など
また宗旨・宗派によっても忌み言葉は変わります。
ご葬儀がどの宗旨で行なわれるかわからない場合、宗旨に由来する言葉は使わない方が良いでしょう。
具体的な例を挙げると、仏式全体で避けたい言葉は、「迷う」「浮かばれない」などです。
また浄土真宗では、冥福という言葉は使わないようにします。
神式やキリスト教式であれば、仏式ならではの用語を使わないようにしましょう。
「成仏」「供養」「合掌」「仏」「冥福」「往生」「ご愁傷様」などがそれに当たります。
さらにキリスト教では、「死」は悲しむべき終わりでなく永遠の命の始まりと捉えますので、「お悔み」などの文面は避けたいところです。
弔電の敬称に関する注意点
弔電では、日常生活ではあまり耳にしない敬称が使われることがあります。
「ご尊父様」「ご母堂様」などがその例です。
プライベートのお付き合いやご親戚への弔電の場合は「お父様」や「お母様」でも構わないと思いますが、会社関係や目上の方、少しお付き合いの遠い方へは最上級の敬称を使う方が良いでしょう。
また先ほども触れましたが、原則として弔電の宛名(受取人)は喪主です。
故人様や喪主と面識がなく、その他ご遺族の関係者として弔電を送る場合も宛名は喪主とし、故人様の敬称も喪主から見たものに合わせましょう。
たとえば会社の同僚のお母様が亡くなられた場合、文中に「ご母堂様」と書きたくなるかもしれません。
ですが喪主が同僚のお父様の場合は、文中は喪主から見た敬称の「ご令室」「奥様」という言葉を使用しましょう。
ちなみに、喪主(受取人)と故人様の関係ごとの敬称は以下のようになります。
父 → ご尊父様(ごそんぷさま)、お父様、お父上様
母 → ご母堂様(ごぼどうさま)、お母様、お母上様
夫 → ご主人様、旦那様、ご夫君様(ごふくんさま)
妻 → ご令室様(ごれいしつさま)、ご令閨様(ごれいけいさま)、奥様、奥方様
祖父→ ご祖父様(ごそぼさま)、御祖父様(おじいさま)、祖父君(おじぎみ)
祖母→ ご祖母様(ごそぼさま)、御祖母様(おばあさま)、祖母君(おばぎみ)
兄 → ご令兄様(ごれいけいさま)、兄上様、お兄様
弟 → ご令弟様(ごれいていさま)、弟様
姉 → ご令姉様(ごれいしさま)、姉上様、お姉様
妹 → ご令妹様(ごれいまいさま)、妹様
息子→ ご令息様(ごれいそくさま)、ご子息様(ごしそくさま)
娘 → ご令嬢様(ごれいじょうさま)、ご息女様(ごそくじょさま)、お嬢様
弔電の文例については、###chouden_bunrei###で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
まとめ
弔電は参列できないご自身の代わりとしてお気持ちを表すものです。
ご遺族にとって弔電をいただくのは、慰めのひとつにもなります。
たとえ直接会って励ましの言葉をかけられなくとも、悲しみの中にあるご遺族・ご親族の心に寄り添ってくれるでしょう。
お困りごとやご不安がありましたら、気兼ねなく平安祭典(0120-00-3242)までご相談ください。
少しでもご遺族に弔意を表すお手伝いをさせていただければと思います。
続きはこちら
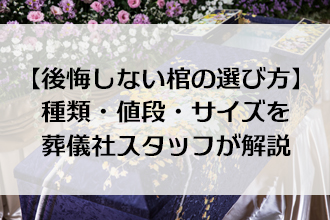
公開日:2022年4月25日
棺とは故人様をお納めするもので、故人様が最後に眠る場所ですのでこだわって選びたい方も多いでしょう。
しかし、素材、形、デザインなど実にさまざまな種類の棺があるため、どれを選ぶか迷ってしまうかもしれません。
そこで、この記事では棺の種類、値段、サイズなどについて解説します。皆さまが納得のいく棺を選ぶ一助となれば幸いです。
棺の意味や歴史について詳しくは、###hitsugi_toha###をご覧ください。
[@目次@]
棺の種類(素材)と値段について
棺には大きく分けて木棺と布棺の2つがあります。そしてもうひとつ、近年注目されてきているのがエコ棺(特殊な合成紙製)です。
ここからは、それぞれの特徴をご紹介していきます。
■木棺:約2万5千円~約10万円
棺として最もベーシックなタイプが木製の「木棺」です。
おそらく「棺」というと、多くの方は木でできた長方形の箱型のものを思い浮かべるのではないでしょうか。
「棺」を代表するシンプルな木棺は、天然木や木目のプリントをベニヤ板に張り付けたものです。
少し高額なものだと天然木で作られた棺もあり、多くの場合、材質には檜・桐・杉などが使われています。
そのほか丸みを帯びた蓋が付けられたものや、ダイナミックな彫刻が施されたものなど、木棺のデザインは多彩です。
また高級感のあるプレミアム棺として、家具のようなデザインの「家具調棺」などもあり、祭壇を重厚感漂う空間にしてくれます。(約30万円~約50万円)
木ならではの温もりや、力強い木彫の実直な雰囲気など、故人様のイメージに合わせてお選びいただくと良いでしょう。
■布棺:約10万円~20万円
布棺とは、合板に綿・絹・麻などの布地を張ったもので、布張棺ともいわれます。
繊細な刺繍や織り柄、華やかなプリント、光沢のあるベルベット調など、布棺は色や柄で大きく印象が変わるのが特徴です。
女性には優美な刺繍、男性ならすっきりと白い織り柄など、性別や故人様のお好み合わせたり、色や柄に季節感を取り入れると、良いかもしれません。
■エコ棺(特殊な合成紙製):約15万円
「エコ棺」とは段ボール製の棺です。
表面は布張りされているので、一見しただけでは段ボールとはわかりません。
メリットはたくさんありますが、特筆すべきはご遺骨がきれいに残りやすい点です。
釘や金具を一切使用していないので、ご遺骨の周りに燃えカスが黒く残ることがありません。
間伐材を使って作られており、燃焼時間が短いため、環境に優しいという面も今の時代に合うのではないでしょうか。従来の棺と比較すると、CO2排出量を40%削減できます。
棺のサイズも大切なポイント
古くから棺のサイズは「尺」で表されてきました。
現在、一般向けに作られた資料などには尺貫法の表記はあまり見られません。
棺のカタログには、たいてい外寸・内寸がcmで記載されています。棺のサイズは一律ではないので、故人様の身長に合ったサイズを選ぶと良いでしょう。
人は亡くなった後つま先が伸び、背伸びした状態になります。従ってベストのサイズは、棺の内寸が故人様の身長+10~15cmです。
また火葬場の炉にもサイズがあり、普通棺と大型棺(巨人棺)などに分けて受け入れられているのが一般的です。
棺の大きさ(外寸)によって、使用する炉の種類が異なりますが、一般的な棺が炉に入らないことはまずありません。
各火葬場では対応可能な棺のサイズが設定されていますが、あまり気にする必要はないでしょう。
まとめ
当記事では棺の種類についてご紹介しました。
棺は故人様が最後の時を過ごす空間であり、ご遺族・参列者の皆さまが故人様を目にする最後の場です。
故人様のお好みやお人柄にあわせたり、祭壇のデザインにあわせると良いかもしれません。また、想い出のシーンをイメージして選ぶのも良いでしょう。
平安祭典では、多くの棺の中からイメージにあうものをご提案しております。
事前相談も受け付けておりますので、気兼ねなく平安祭典(0120-00-3242)までご相談ください。
少しでも故人様のお人柄や弔いの気持ちが感じられる空間となるよう、お手伝いさせていただきます。
続きはこちら
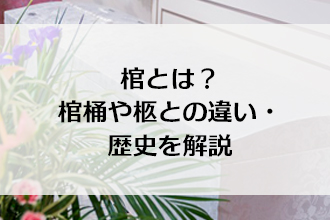
公開日:2022年4月18日
故人様との最後のお別れは、ご遺体が棺に納められた状態で行ないます。
現代の日本で使われる棺は、素材や形など実にさまざまな種類がありますが、どのような棺でも故人様を仰向けでお納めするところが共通点です。
この記事では、棺がどういうものなのか、棺の歴史などをご紹介します。
平安祭典で取り扱う棺もご紹介しますので、ぜひご確認ください。
棺の選び方や種類については、###hitsugi_syurui###で詳しく解説しています。
棺とは?棺・柩・棺桶の違いは?
「ひつぎ」と読む漢字の代表的なものは、「棺」と「柩」の2つです。
辞書を引くと、どちらも「遺体を納めるための箱」と説明されていますが、2つの漢字は次のように少し違った意味を持ちます。
棺:ご遺体が入っていない空の状態の「ひつぎ」
柩:ご遺体が納められた状態の「ひつぎ」
棺はご遺体が入っていない状態なので、ご遺体を納める納棺には「棺」という字が使われます。一方、ご遺体の納められた柩を運ぶ霊柩車には「柩」という字が使われます。
このように同じ「ひつぎ」ですが、ご遺体の有無で使い分けられています。
ちなみに「ひつぎ」を表すものに「棺桶(かんおけ)」という言葉もありますが、これはその昔、桶状の棺が使われていたことに由来しています。(明治期に入るまでは、棺といえば通常は桶型でした。)
今と昔でどう違う?棺の歴史について
古くから日本の棺には、大きく分けて「寝棺(ねかん)」と「座棺(ざかん)」がありました。
「寝棺」は仰向けに寝かし足を延ばした状態で、「座棺」は手足を折り曲げた状態でご遺体が納められます。
寝棺と座棺以前には甕棺(かめかん)もあり、縄文~弥生時代には棺として甕形(かめがた)の土器が使われていました。(棺の歴史としては甕棺→座棺→寝棺と変遷しました)
身分の高い人の墳墓では古代から寝棺が使われていましたが、一般的な棺としては長く座棺が使われていたようです。江戸時代になると、その大半は木製の桶型だったようです。
明治時代に入り、富裕層が寝棺を使用するようになりました。戦後、火葬の一般化と火葬炉の近代化に伴って、寝棺が主流となりました。
現在の日本における、葬送の火葬率は99.9%です。このように寝棺の形状は、火葬の文化とも関係しています。
火葬について詳しくは、###kasou_toha###をご覧ください。
平安祭典の棺をご紹介
ここからは一例として、平安祭典の棺をご紹介いたします。
平安祭典ではさまざまな素材・形の棺をご用意しております。
価格は、木棺であれば2万5千円~10万円ほどが相場です。
オーソドックスな棺は、平らな蓋の四角い「平型棺」や、蓋に台形の膨らみを持たせた「山型棺」などです。
平安祭典が取り扱う棺の中から、代表的なものをいくつかご紹介します。
■きんもくせい
蓋が平らになったスタンダードな平型の木棺。
シンプルで主張しすぎず、落ち着いた印象です。
■シエル
天国へといざなう風をイメージしてデザインされた棺です。
丸みを帯びた蓋がエレガントで、マットな質感の白に気品が感じられます。
■モビリエ
滑らかな肌触りが特徴のタモ材を使用し、ダークブラウンのカラーには高級感と風格があります。
さざ波をイメージした側面のデザインも秀逸です。
■瑠璃華
華道家・假屋崎省吾氏プロデュースの華麗な棺。
実物の花は黄色ですが、金にすることで高貴で華やかなデザインにされています。
高貴な瑠璃色の生地に、金に輝く群雀蘭を施し、華やかでドラマチックなデザインです。
■鳳凰
匠の技で丹念に施された彫刻が迫力の総桐棺です。
釘を使わず組み木で仕上げられ、細部にまでこだわりが感じられます。
■胡蝶蘭
側面・上部・窓にあしらわれた胡蝶蘭は、故人様を柔らかに包み込むようです。
白を基調とした落ち着いた色合いで、年齢や性別を問わずご利用いただけます。
■やさしい棺
釘や金具を一切使用していないので、ご遺骨を傷つけることがなく、きれいな状態で収骨できます。
間伐材の使用や燃焼時間の短縮など、環境への配慮もされた棺です。
棺に入れるものに関する注意点
棺には副葬品として、故人様愛用の品、想い出の品などを一緒に納めます。
必ずしも副葬品を入れる必要はありませんが、想いのこもった品々をたむけることが一般的です。
ただし、副葬品には入れられるものと入れられないものがあるのでご注意ください。
基本的に燃やせるものは入れても良いのですが、金属・ガラス・プラスチックなど、燃えないものや燃やすのに時間がかかるものは入れられません。
副葬品については###fukusohin_toha###の記事で詳しくご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。
まとめ
当記事では、棺についてご紹介いたしました。
棺は、故人様をお納めする大切なものです。心を込めて選ばれると、故人様とのお別れが少しでも豊かなものになるのではないでしょうか。
棺だけでなくご葬儀についてのお悩みやご不安がございましたら、お気兼ねなく平安祭典(0120-00-3242)までお問い合わせください。
心に残るお別れのお手伝いさせていただきます。
続きはこちら