

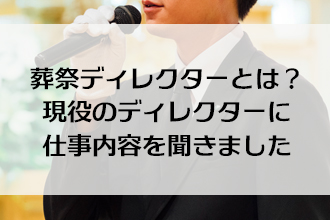
更新日:2023年12月24日 公開日:2023年2月6日
葬祭ディレクターとは葬祭に関する資格で、葬儀社スタッフの能力を測る指標といえます。
とはいえ、葬祭ディレクターについて詳しくご存じない方は多いでしょう。
そこで今回は、現役の葬祭ディレクターにヒアリングを実施。
約1時間にわたって「どのような資格?」「仕事内容や収入は?」など気になる点を質問し、記事を作成しました。
現役葬祭ディレクターならではの意見を記事にまとめておりますので、葬祭ディレクターに関心をお持ちの方はぜひご覧ください。
また、葬祭ディレクター技能試験の内容、技能試験に向けた勉強法などもヒアリングし、###sousaidirector_goukaku###にまとめております。
葬祭ディレクターを目指す方は、ぜひこちらもご覧ください。
なお、平安祭典には2023年12月時点で77名の1級葬祭ディレクターが在籍しており、今回は以下の4名にヒアリングを実施しました。
・神戸平安祭典:稲森 裕之
・阪神平安祭典:宮崎 勝己
・阪神平安祭典:青野 正典
・西神平安祭典:後藤 雅史
[@目次@]
葬祭ディレクターとはどんな資格?
葬祭ディレクターとは葬祭に関する資格で、「ご葬儀を取り仕切る上で、必要な知識や技能を保有している」ことを証明するものです。
葬祭ディレクター技能審査協会が実施する試験(葬祭ディレクター技能審査)に合格すると資格が与えられます。
ただし、受験には葬祭の実務経験が必要になるため、だれでも受験できるわけではありません。
葬祭ディレクターの概要をより詳しく知りたい方は、厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査の公式サイトをご覧ください。
葬祭ディレクターの等級区分
葬祭ディレクターの等級は、1級と2級の2つにわかれています。
それぞれどのような違いがあるのか、順に見ていきましょう。
葬祭ディレクター1級
葬祭ディレクター1級の概要は以下の通りです。
合格すると、個人葬から社葬のような大型葬まで、すべてのご葬儀に対応できる知識と技能を有することが認定されます。
・受験資格:5年以上の葬祭実務経験を有すること、または2級合格後に2年以上の葬祭実務経験を有すること
・審査内容:すべての葬儀における相談、式場設営、式典運営など、葬祭サービスの詳細な知識と技能に関する実技試験と実技筆記
また、1級葬祭ディレクターは次のような金色のカードとバッジケースが与えられます。
ですが、業務中にこのバッジを身につけているかは葬儀社によって異なります。
平安祭典の有資格者はバッジを付けておらず、名刺に厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査 1級葬祭ディレクターであることを記載しています。
葬祭ディレクター2級
葬祭ディレクターの概要は以下の通りです。
合格すると、個人葬についての知識と技能を有することが認定されます。
・受験資格:2年以上の葬祭実務経験を有すること
・審査内容:個人葬における相談、式場設営、式典運営など、葬祭サービスの詳細な知識と技能に関する実技試験と実技筆記
ネームバッジは1級と違い銀色です。
葬祭ディレクターの仕事内容・収入について
続いては、葬祭ディレクターの仕事内容と収入について見ていきましょう。
具体的にどのような業務を行なっているのか、収入の水準はどれくらいなのか、気になる点を質問してみました。
仕事内容は多岐にわたる
葬祭ディレクターの仕事内容は、ご葬儀に関する事前相談から、ご遺体の搬送、お通夜やご葬儀の司会、供花やお食事の準備など、多岐にわたります。
ただし、葬儀会社によって仕事内容には違いがあるため、一例として平安祭典の葬祭ディレクターがどのような仕事をしているのか聞きました。
Q.
葬祭ディレクターの具体的な仕事内容を教えてください。
A.
ご葬儀に関する業務全般を行ないます。
お客様の不安を取り除くために質問に答えることも多いですし、ご葬儀に関する打ち合わせ、司会、施行担当、祭壇の飾りつけや食事の手配など、幅広い業務を行なっています。(稲森)
Q.
仕事をする上で大切にしていることは何ですか?
A.
ご遺族の気持ちに寄り添ってご葬儀を行なうことです。
当然ですが、そのためにはご葬儀に関する知識や技能が必要になります。(青野)
Q.
仕事をしていて嬉しい(やりがいを感じる)のはどんな時ですか?
A.
お客様に感謝をされた時は嬉しいですし、社葬など綿密なシミュレーションが必要な大規模葬儀をやり遂げた時などは、達成感があります。(稲森)
Q.
喪主から「葬祭ディレクターの資格保有者にご葬儀を担当してほしい」というご指定を受けることはありますか?
A.
ほとんどありません。
葬祭ディレクターという資格をご存じない方も多いと思います。
ただ、平安祭典の場合は相談員になるための社内試験制度があり、有資格者の相談員がほとんどの事前相談を行なっています。(後藤)
年齢・資格の種類によって収入には差がある
葬儀会社の給与体系は、各社さまざまです。
年齢・資格の等級によって収入に差が出ることもあれば、資格を取っても収入が変わらないこともあるようです。
そこで、平安祭典の葬祭ディレクターに、収入について1つだけ質問をしてみました。
Q.
葬祭ディレクターの収入水準は高いと思いますか?
A.
葬儀会社によって違いがあると思うので、一概には言えません。
葬祭ディレクターだからといって、収入が上がるとも限りません。
とはいえ、葬祭ディレクターの資格を持っていないと打ち合わせができないシステムの会社だと、資格を持っていると携わる業務が増えるかもしれません。
そうすると、インセンティブなどの面で給与に差が出る可能性はあると思います。
平安祭典の場合は葬祭ディレクターの資格を取り、社内試験にパスして相談員になり、ご葬儀の相談を受ける件数が増えると、収入も上がるのではないでしょうか。(宮崎)
まとめ
当記事では、現役葬祭ディレクターにヒアリングした内容をもとに、葬祭ディレクターの概要、仕事内容、収入などをご紹介しました。
平安祭典には多数の1級葬祭ディレクターが在籍しておりますので、ご葬儀に関するお困りごとなどございましたら、(0120-00-3242)まで気兼ねなくご連絡ください。
繰り返しになりますが、葬祭ディレクターの仕事内容や収入は葬儀社によって差があるため、ここでご紹介した内容はあくまで「平安祭典の場合」とご理解いただけますと幸いです。
続きはこちら
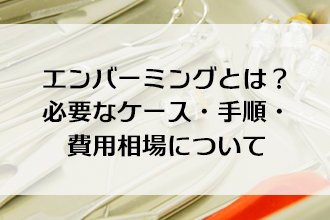
公開日:2023年1月9日
ご葬儀に関連して「エンバーミング」という言葉を聞いたことがあり、どのようなものだろうと関心をお持ちの方は多いかもしれません。
当記事では、エンバーミングの意味、どんな時に必要なのか、さらに手順や費用について解説します。
エンバーミングについて知りたい方、エンバーミングを検討されている方はぜひ最後までお読みください。
[@目次@]
エンバーミングとは?行なう理由は?
エンバーミングとは、ご遺体の長期保存(およそ10~14日)を可能にする技術のことで、日本語では「遺体衛生保全」といいます。
ご遺体を消毒・殺菌して科学的な防腐処置を施し、必要に応じて修復もします。
エンバーミングを行なうのは、エンバーマーと呼ばれる有資格者です。
IFSA(一般社団法人 日本遺体衛生保全協会)の「エンバーマー資格試験」に合格した方だけが、エンバーミングを行なえます。
もともと、土葬が基本の国では主にご遺体からの感染を防ぐために、エンバーミングが行なわれてきました。
ただ、近年はアメリカなどでも火葬が増えつつあるため、エンバーミングは感染症防止だけでなく、公衆衛生に配慮し安全に葬儀を実施するために行なうものとも考えられています。
ちなみに現在の日本において、エンバーミングは一般的に行なわれるものとはいえません。
というのも、日本は火葬文化の国であり、ご遺体を長期保存するケースも稀なため、感染症防止の観点ではほとんど必要性がないからです。
しかし、なんらかの事情でご遺体を長期保存する場合や、火葬までの日数を必要とする場合などは、エンバーミングによってより良いご葬儀を実現できるケースもあります。
ご遺体を衛生的かつ美しく長期保存できる
エンバーミングとは具体的に何をするのかというと、ご遺体を消毒・殺菌したのち、血液を防腐剤などと入れ替えます。
この処置により、ご遺体を衛生的に長期間(およそ10~14日)常温で保存できます。
そのため、亡くなってからご葬儀までが長い場合でもご遺体の腐敗が進むことなく、臭いもほとんど感じない状態を保つことができます。
エンバーミングを行なうとドライアイスや冷蔵庫を使用する必要がないため、ドライアイスを長時間あてることによってできる皮膚の黒ずみも回避できます。
※故人様の状態によってはドライアイスの併用を依頼する場合もあります。
また、必要に応じてご遺体の損傷個所の修復も行ないます。
解剖をされているご遺体や、点滴や薬の副作用で水泡ができている場合、交通事故などで通常なら拝顔が不可能な場合などでも、極力ご生前の状態に近づけるよう処置を行ないます。
ただし、ご遺体の腐敗や外傷が激しく、お顔を見てのお別れが不可能な場合は、特殊な納棺方法で消臭し、棺の蓋を開けてお花や副葬品を納めていただけるように処置を行ないます。
エンバーミングとエンゼルケアはどう違う?
ご遺体の処置に関して「エンゼルケア」という言葉もありますが、エンゼルケアとエンバーミングは目的も処置の範囲も異なります。
エンゼルケア(死後処置)とは、死後に病院などで行なわれる処置です。
「目や口を閉じる」「口腔・鼻腔のケア」「身体の清拭」「体液漏れ防止対策」などにより、主に“表面的に”姿を整えます。
一方、エンバーミングは表面だけでなく体内まで処置を行ない、ご遺体の防腐・殺菌・感染症防止・修復を主な目的としています。
エンバーミングが必要なケースは3つ
エンバーミングが必要なケースは、主に以下の3つです。
① 火葬までに時間が必要なケース
「親族が海外にいる」「事情により葬儀がすぐに行なえない」といった理由から、火葬までの時間が長くなるケースです。
ドライアイスや冷蔵庫を使用してもご遺体の腐敗は徐々に進んでしまうため、エンバーミングを行なって腐敗の進行を抑え、ご遺体を生前に近い姿に維持します。
② ご遺体を海外から空輸で搬送するケース
旅行や出張で海外に行かれた方が亡くなった時や、他国の方が日本で亡くなった時などは、ご遺体を航空機で搬送することがあります。
安全上の観点から航空機内では必要量のドライアイスを使用できないため、エンバーミングが必須となります。
③ 元気だったころの姿で見送りたいケース
解剖や交通事故などにより傷や損傷がある、療養生活で顔が痩せ細ってしまった、点滴や薬の影響で顔がむくんでいるなど、故人様の見た目が生前と大きく変わってしまう例は少なくありません。
エンバーミングによって、「元気だったころの姿にできるだけ近づけたい」「美しいお顔で皆にお別れをしてもらいたい」というご遺族のご要望を叶えられるのです。
エンバーミング処置の手順
ここからは、エンバーミング処置の手順について詳しく解説します。
所要時間はおよそ3時間~4時間で、手順は以下の通りです。
・ ご遺体の洗浄と消毒・殺菌
身体の表面の消毒と洗浄を行ないます。
↓
・ 体内の洗浄と防腐処置
ご遺体の一部を1cm~1.5cmほど切開し(小切開と呼ばれ、状況により切開の大きさは変わります)、そこから血液と防腐剤を入れ替えます。
毛細血管まで防腐剤が浸透したご遺体は皮膚の表面に赤みがさし、より生前の姿に近くなります。
↓
・ 体内の残存物の除去
食道、胃、腸内など消化器官に残っている食物や、呼吸器官の痰などの残存物を吸引し、胸や腹腔の体液も除去します。
↓
・ 縫合、修復、洗浄
防腐剤を注入する際に切開した箇所を縫合します。
その際に、顔や身体で損傷している場所があれば修復し、再度全身の洗浄を行ないます。
↓
・ 洗髪や洗顔
ご遺体の洗髪・洗顔、髭剃りなどして、故人様のお顔やその周囲を整えます。
なお、IFSA(一般社団法人 日本遺体衛生保全協会)では厳格な下記の基準に従い、節度を持ってエンバーミングを行なうと定めています。
そのため、刑法190条(死体損壊罪)や、その他の法律には抵触しません。
・本人またはご家族の署名による同意に基づいて行うこと
・IFSAに認定され、登録されている高度な技術能力を持つ技術者によってのみ行われること
・処置に必要な血管の確保、体腔の防腐のために最小限の切開を行い、処置後には縫合・修復すること
・処置後のご遺体を保存するのは50日を限度とし、火葬または埋葬すること
引用元:エンバーミングとは-エンバーミングの法的解釈 | 一般社団法人 日本遺体衛生保全協会
エンバーミングの費用相場はどれくらい?
エンバーミングの費用は、故人様の状態と処置の内容によって大きく異なります。
具体的な料金は、葬儀社や専門業者にお問い合わせください。
費用のことを考えると、「ドライアイスや冷蔵庫で保存してはダメなのか?」という疑問を持つ方も多いようです。
先述したように、ドライアイスや冷蔵庫は腐敗を遅らせる効果はあるものの、エンバーミングのように腐敗を回避することはできません。
長期保存を目的とされる場合は、エンバーミングを行なうメリットは大きいといえるでしょう。
まとめ
今回はご遺体の防腐処置・修復を行なうエンバーミングについて解説しました。
エンバーミングは、事情によりご遺体を長期保存する場合だけでなく、「元気な頃に近い姿で見送りたい」「心ゆくまでお別れをしたい」といったご遺族のご要望を叶えるためのものでもあります。
エンバーミングは直接専門業者に依頼することもできますが、葬儀社を通して手配をする方が多いようです。
ただし、葬儀社によっては対応していない場合もありますので、事前にご確認いただくと良いでしょう。
事前相談については###sougi_jizensoudan###で詳しくご説明しております。
平安祭典でもエンバーミングのご相談対応やエンバーマーの手配を行なっております。
エンバーミングについて詳しく知りたい方、検討されている方は、ご遠慮なく平安祭典(0120-00-3242)までご連絡ください。
続きはこちら
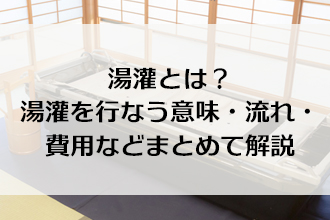
公開日:2022年12月5日
ご葬儀の前には、「湯灌(ゆかん)」という儀式が行なわれることが多いです。
とはいえ、湯灌は実際に何をするのかご存じない方も多いでしょう。
そこで当記事では、湯灌の意味、流れ、費用などを解説します。
ご葬儀をされる際の参考として、お読みいただけますと幸いです。
湯灌とは?死化粧やエンバーミングとの違いは?
それではまず、湯灌とはどのような儀式なのかを解説します。
死化粧やエンバーミングとの違いも見ていきましょう。
湯灌は故人様の身体や精神を清める儀式
湯灌とは、故人様の身体を清める儀式で、納棺に際して行なうものです。
ぬるま湯で身体や頭髪を洗浄してご遺体を清潔にするだけでなく、この世の穢れ(けがれ)、痛み、苦しみを拭き清め、来世への旅支度を整える意味もあります。
生まれたての赤ちゃんがつかる産湯には、身体を清めるとともに、この世での健やかな発育を願うという意味があります。
湯灌にも同じように、現世での穢れを洗い清め、よりよい来世に生まれ変わるようにという願いが込められています。
※病院などでは「エンゼルケア(死後処置の総称)」が行なわれますが、湯灌とは全く違うものなので、混同されないようご注意ください。
昔は習慣としてご遺族が湯灌を行なっていましたが、昨今は葬儀社のスタッフや、専門のスタッフ(湯灌師)が行なうことがほとんどです。
2008年に公開され多くの賞を受賞した映画『おくりびと』の影響から、湯灌師を目指す方も増えています。
湯灌師に聞くと、映画を鑑賞されたご遺族から「あなたたちがおくりびと?」とお声かけいただくことも増えたそうです。
ちなみに、湯灌は必ずしも必要な儀式ではありません。
病院でのエンゼルケアによって表面上はご遺体を綺麗に保つこともできますが、宗教儀式を重視される場合や、ご遺族が故人様の死を受け入れる区切りとするために、湯灌を行なうことが一般的です。
死化粧やエンバーミングとはどう違う?
湯灌と死化粧、エンバーミングは、それぞれ違うものですので、違いを確認しておきましょう。
・ 死化粧
故人様の髪を整え、お化粧を施すことです。
故人様のお顔を生前に近い印象になるよう、美しく整えることで、エンゼルメイクともいいます。
死化粧については、###noukan_toha###の中でも解説しています。
・ エンバーミング
ご遺体を長期保存するための技術で、「遺体衛生保全」とも呼ばれます。
ご遺体の消毒・殺菌・防腐処置や必要に応じて修復することで、およそ10~14日の常温保存を可能にします。
エンバーミングについては、###embalming_toha###で詳しく解説しています。
湯灌の流れについて
湯灌は、次のような流れで行なわれます。会館で行なうにせよ、ご自宅で行なうにせよ、基本的な流れは同じです。
① 浴槽の準備
会館で湯灌を行なう場合は、会館内の湯灌設備がある部屋で浴槽の準備をします。
ご自宅で湯灌を行なう場合は、湯灌師が専用の浴槽を持ってご自宅を訪問し、準備を行ないます。
↓
② 故人様へのマッサージ
硬直をほぐすように、手首・肘・肩など関節を中心にマッサージします。
↓
③ 故人様の移動
儀式の前には、故人様を浴槽まで移動させます。
移動の際は、肌を見せないよう布がかけられます。
↓
④ 口上
湯灌師から、湯灌の儀式についての説明が行なわれます。
↓
⑤ 逆さ水の儀
故人様の身体をお湯で清めます。
ご遺族が逆さ水の儀に立ち会う場合は、交代で足元から胸元へお湯をかけていきます。
お湯の温度は約36~40度前後と、湯灌を行なう業者などによって差があるものの、通常のお風呂よりやや低めに設定されています。
↓
⑥ 顔と髭のお手入れ
洗髪・洗顔・顔剃りといったお手入れが行なわれ、完了した後は顔を拭いて髪を乾燥させます。
↓
⑦ 全身のお清め
シャワーで全身を洗い清めます。
↓
⑧ 死装束への着替えと死化粧
仏教では浄土への旅支度として、故人様に死装束を着せることが一般的です。
全身白の仏衣などを左前にあわせて着せ、笠、袈裟、杖、手甲、脚絆、白足袋、草鞋、頭陀袋などを着けます。
死装束ではなく、故人様の想い入れのある服にされる方もいらっしゃいますが、いずれにせよお着替えは、湯灌や納棺の際に行なわれることが一般的です。
なお、上記した8つの工程のうち、どこまでが湯灌の料金に含まれるかは業者によって異なります。事前に確認しておきましょう。
湯灌の逆さ水とは?
逆さ水とは、故人様を清めるために使うぬるま湯のことです。
通常、ぬるま湯が必要な場合は、熱いお湯に水を加えて温度を調整しますが、湯灌に使うぬるま湯は水に熱湯を足して温度を調整するため、「逆さ水」と呼ばれます。
また、故人様にお湯をかける柄杓(ひしゃく)を左手で持つ「逆さ手」という風習もあります。
物事を普段と逆の手順で行なうことで、「死」を非日常的なものとする考え方に由来するそうです。
湯灌にかかる費用はどれくらい?
湯灌にかかる費用は、業者によって異なります。
従って、「湯灌の費用は〇〇円くらい」と一概には言い切れません。
一例として平安祭典の湯灌料金を挙げると、77,000円(税込)です。
この金額が相場というわけではありませんが、参考までにご確認ください。
平服?喪服?湯灌の際の服装
湯灌に立ち会う際の服装は、基本的に平服でかまいません。
ただし、お通夜までに時間がない場合や、すでに喪服を着ている場合は、喪服のままでかまいません。
平服に着替える必要はありませんので、そのままの服装でお立ち会いください。
また、立ち会う範囲に決まりはありませんが、第二親等までのご親族が立ち会うことが一般的です。
まとめ
当記事では、湯灌について解説しました。
湯灌を行なう意味、流れ、費用など、ご不明な点は解決したでしょうか?
故人様を清める場面に立ち会うことで、ご遺族も故人様の死を受け入れるための区切りになることでしょう。
湯灌を含めてご葬儀に関するお困りごとがございましたら、平安祭典(0120-00-3242)まで気兼ねなくご連絡ください。
続きはこちら
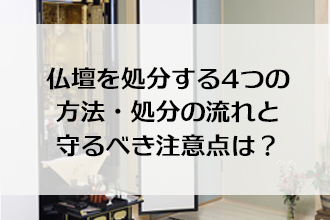
更新日 : 2024年9月14日 公開日:2022年11月7日
仏壇は、ご先祖や故人様を祀り日々のご供養をする場として、とても大切なものです。
とはいえ、「継承する人がいない」「引越し先に設置スペースがない」「買い替える」などの理由から、処分しなければならない場合があるでしょう。
当記事では、仏壇を処分する時に知っておくべき知識や注意点について解説します。
[@目次@]
仏壇処分の方法は4つ!メリット・デメリットを比較
仏壇を処分するには、以下の4つの方法があります。
それぞれにメリットとデメリットがありますので、よくご検討ください。
・ 仏壇・仏具店に依頼する
・ その他の専門業者に依頼する
・ 菩提寺・旦那寺に依頼する
・ 自治体に依頼する
それでは、4つの方法について詳しく見ていきましょう。
仏壇・仏具店に依頼する
仏壇・仏具店でも多くの場合、仏壇の処分に対応しています。
仏壇を扱う専門店ですので、処分の段取りや料金が明確になっていることがほとんどで、「スムーズに手続きができる」「安心感・納得感を持って依頼できる」といった点がメリットといえます。
費用は仏壇のサイズ、引き取り方法、搬送の距離などによりますが、20,000円~80,000円が相場です。
買い替えで新たに仏壇を購入することで、処分費用が安くなるところもあります。
その他の専門業者に依頼する
不用品回収やリサイクルの専門業者に依頼する方法もあります。
処分費用は数万円ほどのケースが多いようです。
業者によっては無料で処分できたり、買い取ってもらえたりすることもあります。
とはいえ業者の多くは閉眼供養に対応していないので、事前にご寺院に依頼し閉眼供養を済ませておきましょう。
専門業者を利用すると手間は少ないものの、他の回収品と一緒に雑に扱われる、時には不法投棄されてしまう、といったリスクもあるため、安心して任せられる業者を選ぶことが大切です。
菩提寺・旦那寺に依頼する
ご寺院によっては、仏壇の引き取りやご供養を行なっています。
閉眼供養から処分まであわせて依頼できれば安心でしょう。
ただ、近年は防災や環境への配慮という理由から仏壇処分(引き取りやお焚き上げ)を実施できない地域も多く、お断りされる場合がほとんどです。
菩提寺・旦那寺がある方は、仏壇の処分に対応していただけるかどうか、一度ご相談いただくことをおすすめします。
ご寺院に依頼する場合、費用は御布施の形でお渡します。
金額の明確な決まりがない場合が多く、相場は10,000円~100,000円ほどです。
ご自身で仏壇を持ち込むか、引き取りに来ていただくかによっても異なる場合がありますので、金額や引き取り方法については事前によくご確認ください。
自治体に依頼する
自治体の不用品回収に粗大ごみとして出すこともできます。
引き取り方法や費用などは各自治体のルールによりますが、手順は一般的には以下の通りです。
閉眼供養が必要な場合は事前に済ませておきましょう。
仏壇のサイズ(高さ・幅・奥行き)を測る
↓
自治体の粗大ごみ処理手数料チケットを購入し、申し込みをする
↓
指定の場所へ持ち込む、または、集積所などで回収してもらう
費用の相場は500円~2,000円程度と比較的安く済みます。
ただし、ご自身で仏壇を運び出す必要があるため、大きな仏壇の場合は大変かもしれません。
また、回収に来てもらう場合、「近所の目が気になる」「家の前やごみ置き場に出すのは気がひける」と感じるかもしれませんので、慎重にご検討ください。
仏壇処分の流れは?処分の前にするべきこと
仏壇を処分するにあたって、忘れてはならないのが閉眼供養(へいがんくよう)です。
一般的に、仏壇を新しく購入するとご寺院に開眼供養(かいげんくよう)という魂を込める儀式をしてもらいます。
開眼供養については###kaigenkuyou_toha###で詳しく説明しています。
開眼供養をされた仏壇を処分する際は必ず閉眼供養を行ない、仏壇から魂を抜いてもらう必要があります。
閉眼供養は菩提寺に直接依頼するのが一般的ですが、処分を頼む仏壇・仏具店や専門業者で閉眼供養の手配をしてくれる場合もありますので、ご確認いただくと良いでしょう。
仏壇を処分する際のおおまかな流れは以下のとおりです。
仏壇の開眼供養がされているかを確認する
↓
菩提寺に連絡する
閉眼供養や仏壇の処分について相談します。
↓
閉眼供養をする(必要な場合)
位牌や仏具も処分する場合はあわせて閉眼供養をしてもらいます。
↓
仏壇を引き取ってもらう
仏壇処分の際に注意する点
仏壇を処分される際には、ご注意いただきたい点が2つあります。
処分前に確認しておきましょう。
貴重品などが入っていないか確認する
仏壇を搬出する前は、引き出しや小物入れなどの収納スペースをすべて確認しましょう。
仏具、古い位牌、遺影などだけでなく、通帳、実印、現金などの貴重品が保管されていることがあります。
気づかずに処分に出してしまわないよう、実家で親が管理していた場合などは特によく確かめてください。
宗派の教理にあった方法で処分する
仏壇の処分に関する考え方やルールは、宗派によって大きく異なります。
仏教のほとんどの宗派では、仏壇も位牌も閉眼供養を行ないますが、中には位牌の閉眼供養は必要ないとするケースもあります。
たとえば浄土真宗の場合、閉眼供養を行なうことは基本的にありません。
というのも、浄土真宗では、人は亡くなった後すぐに仏様になるとする「臨終即往生」(りんじゅうそくおうじょう)という考えがあり、仏壇に故人様の魂が宿るとは考えられていないからです。
ただし、閉眼供養の代わりにご法要を行ないます。
このご法要は遷座法要(せんざほうよう)(または遷仏法要・せんぶつほうよう)と呼ばれ、文字通り、ご本尊の鎮座している場所を遷(うつ)すというものです。
また、創価学会の仏壇は特殊で一般的な仏具店では引き取ってもらえないことが多いため、創価学会専門の仏具店を探す必要があります。
専門業者や自治体に依頼して仏壇を処分した場合でも、仏具やご本尊は創価学会の地区会館などに引き取ってもらうことが多いようです。
処分を検討される場合は、事前に地区会館へご相談されると良いでしょう。
ここでは浄土真宗と創価学会を例に挙げましたが、仏壇の処分は宗派の教理によって異なるという点にご注意ください。
まとめ
今回は、仏壇の処分方法および処分する際の注意点について解説しました。
ご先祖や故人様を祀って日々のご供養を行なってきた仏壇は、閉眼供養を終えても最後まで丁寧に扱いたいものです。
各処分方法のメリット・デメリットをふまえてご家族でよく話し合い、最適な処分方法を選んでいただければ幸いです。
平安祭典では、各種ご相談を承っています。
神戸・阪神間でお困りごとがございましたら、平安祭典(0120-00-3242)まで気兼ねなくご相談ください。
続きはこちら
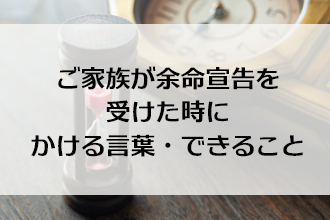
公開日:2022年10月24日
余命宣告を受けると、ご本人はもとよりご家族も大きなショックを受けることと思います。
何も考えられなくなったり、落ち込んだりすることもあるでしょう。
とはいえ余命宣告を受けた以上、残された時間の過ごし方はとても大切です。
そこで、当記事ではご家族が余命宣告を受けた際の心構えや接し方をご紹介します。
限りある時間を有意義に過ごすために、この記事がお役に立つことを願っております。
[@目次@]
ご家族が余命宣告を受けた時の心構え
余命宣告とは、医師が闘病中の方に対して予想される生存期間を告げることです。
たとえば、治療を続けても完治が難しい場合などに、「あなたの余命はあと3か月です」などと宣告します。
ただし、「余命」とされる期間は、その病気の方の50%がなくなる「生存中央値」をもとにした予測値であり、期間内の生存を保証するわけでも、期間後に必ず亡くなるわけでもありません。
そうはいっても、ご家族が余命宣告を受けると相当なショックを受けることは当然です。
宣告された本人に寄り添い、そばで見守り、やりたいことなど、今後についても一緒にサポートすることで、少しずつ受け止められていくのではないでしょうか。
そして自分たちだけで抱え込まずに、友人に話を聞いてもらったり、心理カウンセラーに相談することも考えてみましょう。
かける言葉と注意したい言葉とは
余命宣告を受けたご本人に対し、ご家族としてはどのような言葉をかければ良いか悩まれるでしょう。
「とにかく励まして元気を出してもらおう」とお考えになるかもしれませんが、軽率な励ましはかえってご本人を傷つけることがあります。
「治るかもしれないから」「元気そうに見えるよ」「がんばってね」といった言葉は、避けた方が良いかもしれません。
ご家族も余命宣告を受けた現実を受け入れにくいかもしれませんが、最も不安を抱えているのはご本人だと思います。
ご家族を残して先に逝くことに対し、辛さ・やり切れなさを感じることもあるでしょう。
励ましの言葉ではなく、寄り添うような言葉をかけたり、一緒に涙を流したりすることの方が、ご本人の気を楽にしてあげられるかもしれません。
先ほどもご説明しましたが、自分たちだけで抱え込まずに、適切なケアを受けることも考えてみてください。
余命宣告を受けた後にできること
続いては、余命宣告を受けた後にできることをご紹介します。
落ち着いて1つずつ進めていきましょう。
他の医師にも意見を仰ぐ(セカンドオピニオン)
余命宣告後は、完治を目指したり、延命治療を行なったり、緩和ケアを行なったりと、ご本人とご家族が今後の方針を決めることになります。
その中で、余命宣告をした医師とは別の医師に診察してもらい、「セカンドオピニオン」を仰ぐことも選択肢の1つです。
セカンドオピニオンを仰ぐ場合は、最初に診断を受けた医師から検査の結果やデータをもらい、別の医師に提出します。
仮に末期癌と診断されていても、別の医師が診ると「治る見込みがある」という見解になる可能性もあります。
「余命〇か月」と宣告されて、「はい、わかりました」と納得できる方は少ないでしょう。
ご本人とご家族が納得して残りの時間を過ごすために、セカンドオピニオンを仰ぐことも検討されてはいかがでしょうか。
加入している保険の内容を確認する
余命宣告を受けたご本人が加入されている保険内容も確認してみましょう。
生命保険に加入されている場合は、生前に保険金の一部を支払ってもらえるリビング・ニーズ特約がついていることもあります。
特約によって一部でも保険金を受け取ることができれば、医療費の支払いに充てたり、他の治療費として使えるでしょう。
また、残された時間を有意義に過ごすために使うこともできるはずです。
残りの時間でやってみたいことを一緒に整理する
余命宣告を受けたご本人に、残りの時間でやってみたいこと、会っておきたい人、行ってみたい場所などを聞いて整理しましょう。
全て実現することは難しいかもしれませんが、ご本人の希望をできる限り叶え、残された時間を意義のあるものにしたいところです。
希望を聞きながらリストとして整理しても良いですし、エンディングノートを活用する方法もあります。
エンディングノートとは、ご自身が亡くなるときに備え、情報を整理して書き込んだり、介護や臓器提供の意思、ご葬儀の希望などを書き込むノートのことです。
終活の一環として利用されるものですが、余命宣告を受けた方が残りの時間を有意義に過ごすためにもご活用いただけます。
エンディングノートについては###endingnote_kakikata###でも詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。
相続や遺言書の準備をする
余命宣告を受けたら財産を確認し、相続や遺言書の準備も始めましょう。
誰に何を相続させるかを、遺言書として残しておけば、相続のトラブルを防止できます。
相続に関しては###souzoku_tetuduki###で、遺言書に関しては###yuigonsyo_kakikata###で詳しく解説しております。
なお、エンディングノートに遺言を書かれる方もいらっしゃいますが、エンディングノートには法的拘束力がありませんので、ご注意ください。
ご葬儀の準備をしておく
ご家族が余命宣告を受けて辛い時期であれ、ご葬儀のことを後回しにしていると、バタバタとご葬儀を行なうことになり、後悔されるかもしれません。
ご葬儀の準備は、ご本人のためにもご家族のためにも、早めに始めておきましょう。
###sougi_jizensoudan###で、ご葬儀の事前相談について詳しく解説しております。
いざというときに慌てないよう、よろしければご確認ください。
まとめ
当記事では、ご家族が余命宣告を受けたときの心構えや、かける言葉、できることについてご紹介しました。
余命宣告は大変なショックを受けることですが、残りの時間がわかるということは、「最期を迎える準備ができる」とも捉えられます。
ご本人が亡くなった後に後悔しないよう、ご家族で写真を撮ったり、今までできなかった話をしたり、やってみたかったことを実行したりと、お互いに寄り添う気持ちで残りの時間を過ごされてはいかがでしょうか。
余命宣告は受けたご本人はもとより、ご家族も辛く悲しい思いをされるものです。
だからこそ、体調にも注意しながらご自身の心と向き合い、相続やご葬儀の準備を始めましょう。
くれぐれもご無理はなされませんように。
ご葬儀やご供養のことだけでなく、何かお困りごとがございましたら、平安祭典(0210-00-3242)まで気兼ねなくご連絡ください。
続きはこちら
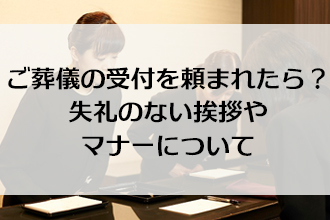
公開日:2022年10月17日
ご葬儀の受付を頼まれたとき、初めてだと「手順を知らない」「マナーがわからない」と慌ててしまいますよね。
そのような不安を解消していただけるよう、当記事では受付を務める際に知っておきたい基本知識やマナーについて解説します。
実際に受付をされるときに慌てないよう、事前にご確認ください。
[@目次@]
ご葬儀の受付の役割とは?
ご葬儀の受付は、ご遺族側の代表として参列者をお迎えする大切な役目です。
手順やマナーをきちんと把握したうえで、参列者に失礼のない対応を心がけましょう。
受付では御香典などの金銭を扱うこともあるため、葬儀社のスタッフではなく、基本的にはご遺族側で数名を選出します。
受付の役割は主に以下の3つです。
① 芳名帳への記帳をお願いする
② 御香典を預かる
③ 供養品(返礼品)をお渡しする
加えて、ご遺族から依頼があれば、御香典の金額を確認し集計する「会計」まで行なうこともあります。
ご葬儀当日の受付の流れ
ここからは、ご葬儀の受付としてすべきことを一般的な流れに沿ってご説明します。
※詳しい手順や役割分担はご葬儀の規模や会館によって異なる場合もありますので、当日、葬儀社のスタッフからの説明をよく確認してください。
ご葬儀開式までに準備をする
受付をされる方は、ご葬儀が始まる1時間前には会館に到着しておきましょう。
会館に到着したら、以下のものが揃っているかを確認します。
ご遺族から特別に依頼などがない限り、持ち物はご葬儀に参列する時と同じでかまいません。
集合時間に遅れないよう、忘れ物がないか確認して家を出ましょう。
・ 数珠
・ ハンカチ
・ 袱紗
・ 御香典
必要なものはたいてい葬儀社で用意しているはずですが、足りないもの、他に必要なものがあれば、葬儀社スタッフに相談してください。
・ 筆記用具
・ 芳名帳:芳名カード
・ 供養品(返礼品)
※会計まで依頼されている場合は香典帳、会社関係のご参列が多いと予想される場合は名刺ホルダーなどを用意することもあります。
通常、受付は数名で行なうため、必要に応じて「記帳をお願いする係」「御香典を受け取る係」「供養品をお渡しする係」などの役割分担を事前に決めておくと良いでしょう。
準備をすべて整えたら参列者を待ちます。
目安として、遅くともご葬儀が始まる30分ほど前には準備を終えておくようにしましょう。
弔問客へ挨拶する
参列者がいらっしゃったら、「ご参列ありがとうございます」や「本日はお忙しい中をお越しいただきまして、誠にありがとうございます」などの挨拶をします。
天候が悪い日は、「お足元の悪い中、ご参列ありがとうございます」といった挨拶もよく使われます。
芳名帳へ記帳していただく・芳名カードを受け取る
挨拶の後、「こちらに記帳をお願いいたします」とお声がけし、芳名帳または芳名カードに氏名と連絡先を記入していただきます。
喪主にとって参列してくださった方の情報はとても大切なので、記入漏れがないようよく確認してください。
氏名だけの方がいれば「お手数ですが、ご住所もご記入いただけますか」とお願いします。
また、故人様やご遺族の会社関係の方が参列された場合、受付で名刺をいただくことがあります。
参列者の社名や役職がわかれば、どのような関係・立場の方が参列してくださったのか把握できるため、とても重要です。
紛失しないよう保管しておき、まとめてご遺族にお渡ししてください。
御香典を預かる
記帳後、参列者から御香典を差し出されたら「お預かりいたします」と言って両手で受け取りましょう。
ゆっくりと一礼し、「ありがとうございます」とお礼を述べます。
ご葬儀によっては、故人様の遺志で御香典を辞退されることがあります。
その場合は、御香典をお持ちになった方に「申し訳ございません。故人様の遺志により、御香典はご辞退申し上げております」と伝え、丁寧にお断わりしてください。
また、参列者がお供えや弔電を持ってこられたら、一旦受付でお預かりし、葬儀社のスタッフに伝えて対応をお願いしましょう。
供養品や当日返しをお渡しする
御香典を受け取ったら、供養品をお渡しします。
「こちらをどうぞ」「お礼の品でございます」などの言葉を添えると良いでしょう。
供養品は参列者1名につき1つずつお渡ししますが、御香典が連名の時は人数分を、会社・団体からなら1つだけお渡しするのが一般的です。
また、供養品とは別に、ご葬儀当日に御香典のお返しをする「当日返し」の場合は、御香典の金額に応じた品もお渡しします。
供養品や当日返しの対応でわからないことがあれば、葬儀社のスタッフに確認してください。
以上が一般的なご葬儀における受付の流れです。
ただし、規模の大きいご葬儀では、「受付係とは別に会計係を設ける」「親族受付・友人受付・会社受付などに分け、複数の受付を設ける」「受付係が参列者を式場へご案内する」など、段取りや役割分担が異なる場合もあります。
いずれにしても、葬儀社のスタッフとご遺族が事前に相談した上で、葬儀社スタッフから受付係にアドバイスをしてもらえますのでご安心ください。
知っておきたいご葬儀の受付マナー
続いては、ご葬儀の受付を務めるにあたり知っておきたい基本的なマナーについて解説します。
品位のある言葉づかいで挨拶する
口調や言葉づかいに関しては、以下の点に気をつけると良いでしょう。
・ 場に相応しい落ち着いたトーンの声を心がける
・ 早口にならずゆっくり話す
・ 丁寧な言葉づかいで対応する
ご遺族の代表であることを忘れずに、品位のある話し方を意識し、参列者に失礼のないよう丁寧な対応をします。
御香典は両手で受け取る
御香典は、必ず両手で受け取ります。
受け取った後は、ゆっくりと一礼をします。
また、会計係がいる場合は、受け取った後にゆっくりと一礼し、参列者が受付を離れてから御香典を渡すようにします。
受付を済ませた方の目の前で、御香典の受け渡しをしないよう気をつけてください。
御香典辞退の場合は丁寧にお断りする
先にご説明したように、ご遺族が御香典を辞退している場合は御香典を持参した方に、故人様の遺志をお伝えして丁寧にお断りします。
ご葬儀の受付の服装は?
受付をする際の服装は参列者と同じと考え、準喪服もしくは略式喪服を着用しましょう。
ご葬儀の服装について、詳しくは###sougi_midashinami###をお読みください。
ご葬儀の受付をする際の注意点
ご葬儀の受付を務めるときは、いくつかの注意点があります。
焼香のタイミング
焼香は開式前に済ませておくか、参列者の焼香が一通り終わったタイミングで行ないます。
受付では御香典などの金銭も預かっていますので、誰もいない状態になるのを避けるため、焼香は交代で行ないましょう。
御香典を喪主へ渡すタイミング
御香典はご葬儀が落ち着いた頃合いを見て、まとめて喪主にお渡しします。
翌日も受付をする予定であっても、必ずその日のうちに喪主にお渡ししましょう。
御香典を預かったたまにしてしまうと、トラブルの心配もありますので、ご注意ください。
ご葬儀の受付を頼む際に知っておきたいこと
それでは、ここからは「ご葬儀の受付を依頼する側」が知っておきたいことを見ていきましょう。
一般的に、受付はどなたへ依頼するものでしょうか?
ご自身が受付を頼むことになった場合、どなたにお願いすれば良いか、お礼はどうすれば良いのかもご説明します。
ご葬儀の受付は誰に依頼すると良い?
受付はご親族に依頼することが一般的です。
ただし、お通夜、葬儀・告別式を通して受付にいなければならないため、直系のご親族は避けることが多いです。
ご葬儀の規模が大きいときは、友人や会社の同僚などに頼むこともあります。
地域によっては慣習として、ご近所の方や自治会の方が受付をすることもあるようです。
受付をしてくれた方へお礼は渡す?
一般的にご親族に対するお礼は不要とされていますが、感謝の気持ちを示したい場合は、お礼の品を渡すなどしても良いでしょう。
友人や同僚に依頼した場合は、現金であれば3,000円~5,000円ほどが相場とされています。
「志」や「御礼」と書いた封筒に入れてお渡しください。
他にも食事やお持ち帰り料理を用意するなど、お礼の方法はさまざまです。
どのようにお礼をするか迷ったら、葬儀社に相談されてはいかがでしょうか。
まとめ
今回は、ご葬儀の受付に関して知っておきたい基本事項をご紹介しました。
受付をされる方はご遺族の代表であるという責任感を持ち、品位とマナーを意識して参列者に対応しましょう。
平安祭典では、ご葬儀・ご供養に関する各種ご相談を承っています。
神戸・阪神間でお困りごとがございましたら、平安祭典(0120-00-3242)まで気兼ねなくご相談ください。
続きはこちら
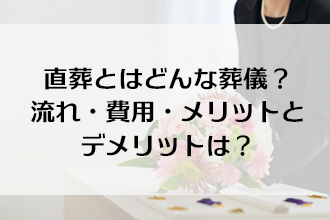
公開日:2022年10月10日
近年、ライフスタイルの多様化に伴い、さまざまな形式のご葬儀が選択できるようになりました。
そのうちのひとつとして、「直葬(ちょくそう)」という非常に簡略化された形式のご葬儀があります。
直葬という言葉を耳にしたことはあっても、参列する機会がほとんどないため、詳しくはよくわからないという方が大多数ではないでしょうか。
この記事では直葬とはどんなご葬儀なのか、メリット・デメリットなどを解説いたします。
[@目次@]
そもそも直葬とはどんな葬儀?
直葬とはお通夜や葬儀・告別式のないご葬儀で、火葬式とも呼ばれます。
一般的なご葬儀の場合、お通夜、葬儀・告別式を行ないますが、直葬の場合はお通夜、葬儀・告別式を行なわず火葬します。
ただし、法律によりご遺体は死亡後24時間以内に火葬できないため、直葬を行なう場合もご遺体の安置が必要です。
直葬を選び後悔しない?直葬のメリットとデメリット
ここからは、直葬のメリットとデメリットをご紹介します。
「直葬にするかどうか迷っている...」という方は、両方をよく理解したうえで検討しましょう。
<メリット>
・ 費用を抑えられる
通常のご葬儀では、式場の利用料等の基本料金をはじめ、御布施、飲食接待費など、さまざまな費用がかかります。
直葬の場合はお通夜、葬儀・告別式を行なわない分、このような費用を抑えることができます。
ご葬儀にかかる費用を抑えたい方にとっては、大きなメリットでしょう。
・ ご遺族の負担を抑えられる
通常のご葬儀では、お通夜、葬儀・告別式を行ないますが、直葬の場合はご遺体の安置後、納棺→出棺→火葬の流れで行ないます。
また、直葬はごく身近な方のみで行なうため、ご寺院や参列者への応対といった心身のご負担も軽減できます。
儀式の細かなマナーや進行などを気にしなくて良い点もメリットでしょう。
<デメリット>
・ ご親族の理解を得にくい場合がある
直葬はご葬儀の形態として多いわけではないため、どのようなものかをご存じでないご親族も多いでしょう。
家のしきたりや古くからの慣習を重んじる方には、理解されにくいかもしれません。
・ 参列を希望される方から不満が出る場合がある
故人様の交友関係は、なかなか把握しきれないものです。
直葬は基本的にご家族やご親族のみで行なうため、ご葬儀に参列できないことに対して、残念な思いをされる方がいらっしゃるかもしれません。
そのような場合、後日改めて自宅へ弔問いただくなど、その都度対応が必要です。
・ 菩提寺・檀那寺へ納骨できない可能性がある
お付き合いをされている菩提寺・檀那寺がある場合は、事前に直葬を行なうことを伝えていないと、ご葬儀を省いたことで納骨を断られることもあります。
菩提寺・檀那寺へ直葬について事前にお伝えして、相談しましょう。
・ ご遺族自身が後悔することもある
故人様とのお別れは一度きりです。
直葬は宗教儀礼を執り行なわないため、後になって、もっと手厚いご葬儀をすればよかったと思われるかもしれません。
実際、予想以上にお別れの時間が足りなかったと感じられる方もいらっしゃるようです。
お亡くなりになったその時は、落ち着いて考えることが難しいこともあります。
故人様のお顔を見て、ゆっくりとお別れできるよう、事前に身近な方々とよく相談されておくと良いでしょう。
直葬の流れ
直葬の流れは以下のようになります。
ご臨終
医師による死亡宣告を経て死亡診断書が作成されます。
病院以外の場所での死因がはっきりしない突然死などの場合は、警察による検視が行なわれることもあり、その場合は死亡診断書ではなく死体検案書が作成されます。
↓
葬儀社(移送先)の手配・ご安置
まず葬儀社に連絡して、故人様を搬送する寝台車の手配をします。
いざという時に慌てないためにも、事前に葬儀社を決めておくと良いでしょう。
法律により死亡後24時間は火葬できないため、安置場所(会館またはご自宅など)へ移動します。
葬儀社との打ち合わせやなども、このタイミングで行なうことが多いです。
↓
納ノ儀(納棺)
納ノ儀(納棺)とは、故人様の身なりを整えて、棺にお納めする儀式です。
↓
出棺~お骨あげ
火葬場の予約時間にあわせて出棺となります。
ご遺族も火葬場へ向かいます。
火葬にかかる時間は、約2時間30分です。
※ご寺院へ依頼されている場合は、ここで読経が行なわれることもあります。
↓
骨あげ
火葬後、遺骨を骨壷に納めます。
喪主から始め、血縁の深い方より順に足元から拾い、最後は喪主が喉仏を納めて終了です。
直葬と聞くと、「病院で亡くなられた後すぐに火葬場へ直行するのかな?」と思われている方がいらっしゃるかもしれません。
ですが、先にご説明したように、直葬といってもご遺体の安置が必要です。
ご遺体が蘇生する可能性もあるため、死亡後24時間が経過するまでは火葬してはならないと法律で定められています。
※感染症による死亡の場合、妊娠7ヶ月に満たない死産の場合は、例外として死亡後24時間以内に火葬されることがあります。
直葬を行なう場合のマナーや注意点
続いては、直葬を行なう場合のマナーをご紹介します。
服装や御香典など、気になるポイントを確認しておきましょう。
直葬の場合も服装は喪服が無難
直葬においても、服装のマナーは通常のご葬儀と同様です。
ただし、ごく身近な近親者だけで行なうことが多いご葬儀であるため、通常のご葬儀ほど厳しくありません。
男性はブラックのフォーマルスーツ、女性もブラックのフォーマルスーツ(ワンピース、アンサンブル)の準喪服を着用します。
準喪服をお持ちでなければ、略式喪服(黒を基調としたスーツ、ワンピースまたはアンサンブル)でも良いでしょう。
ご葬儀の身だしなみについては###sougi_midashinami###で解説しております。
直葬でも御香典を用意しておいた方が良い
直葬はご家族やご親族のみで行なわれることが多いため、御香典のやり取りを省略することがあります。
しかし、一般的なご葬儀と同じく、ご遺族が辞退していなければ御香典を用意しておいた方が良いでしょう。
また御香典をいただいた場合は、後日香典返しをしましょう。
御香典については###kouden_manner###で解説しております。
直葬の費用相場はどれくらい?
直葬の費用は、葬儀社によって異なります。
極端に費用が安い場合は、必要なものが含まれていないこともあるので、事前に確認しておきましょう。
平安祭典では、お通夜、葬儀・告別式を行なわないシンプルプラン(187,000円)をご用意しております。
直葬をご希望の方は『シンプルプランのご紹介ページ』から詳細をご確認ください。
戒名や納骨はどうなる?直葬後の流れについて
直葬にはメリットもあるものの、お骨あげ以降の流れで、判断に迷う点もあります。
直葬を行なう場合、宗教儀礼を執り行なうことはあまり多くないため、戒名がないことがほとんどでしょう。
ご寺院への納骨をお考えの場合、基本的に戒名が必要ですし、ご遺骨をどうするかは考えておきたい点です。
戒名をつけてもらいたい場合は事前に相談を
菩提寺がある場合は、戒名について事前に相談しておきましょう。
直葬を選択してお墓に納骨する際、石碑に先祖の戒名があるにもかかわらず、故人様だけ俗名になると、後々後悔されるご遺族がいらっしゃいます。
結局、改めてご寺院に読経してもらったり、戒名をいただいたりすることもあるようです。
また、ご寺院なしの直葬に反対するご親族とトラブルになるケースもあります。
戒名については###kaimyou_toha###で解説しております。
納骨以外に散骨や手元供養などの方法も
直葬は、ご葬儀という宗教儀礼を省くため、ご寺院に納骨を断られる可能性があります。
そのため、ご寺院への事前相談が必須です。
納骨以外の供養方法として以下の3つがありますが、あくまでもご寺院へ相談して納骨してもらうことが基本だとお考えください。
① 手元供養
② 海洋散骨
③ 樹木葬
上記の供養方法について、平安祭典では海に散骨をする「海里送(かいりそう)」のプランをご用意しています。
海里送では、ご遺族自らが散骨を行なうほか、ご遺骨をお預かりして散骨を代行することも可能です。
また手元供養として、リビングなどに飾っておける小さな骨壷のセットや、いつも故人様を感じられるペンダントタイプもご用意しております。
手元供養については###temotokuyou_toha###で詳しく解説しております。
まとめ
当記事では直葬のメリット・デメリットをはじめ、流れやマナーなどもご紹介しました。
大切な方とのお別れに悔いを残すことのないよう、参考としていただけますと幸いです。
どのようなご葬儀の形とするのか、方法はたくさんありますので、お困りごとがあればぜひ平安祭典(0120-00-3242)までお問い合わせください。
続きはこちら
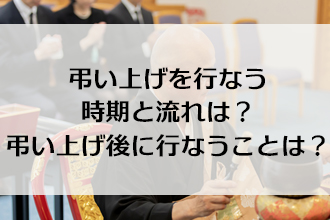
公開日:2022年10月3日
仏事における「弔い上げ(とむらいあげ)」については、「あまり聞きなじみがない」「弔い上げのご法要に参列したことがない」という方も多いのではないでしょうか。
今回は、これから弔い上げを予定されている方のご参考となるよう、弔い上げを行なう時期、流れ、マナーなどについて解説します。
[@目次@]
弔い上げとは?弔い上げの意味について
それではまず、弔い上げは何のためにするのか、どのようなご法要なのかを確認しましょう。
追善供養として最後に執り行なう年忌法要
弔い上げとは、故人様のご供養のために行なう最後の年忌法要です。
追善供養として一周忌、三回忌、七回忌…と重ねてきた年忌法要を、三十三回忌や五十回忌などの節目を最後に終了することを意味し、「問上げ(といあげ)」「問い切り(といきり)」「上げ法要(あげほうよう)」とも呼ばれます。
弔い上げを経て故人様の魂は「個」としてのご供養は終え、「ご先祖」として信奉していくことになります。
弔い上げはひとつの区切りとなる大切な儀式ですが、一般的に弔い上げ御法要の際に、何か特別にやるべきことや決まりのようなものはありません。
とはいえ、ご寺院のお考えや地域の慣習によって、通常のご法要よりも盛大に行なったり、自宅などではなくご寺院で行なったりすることもあるようです。
弔い上げのやり方は、ご寺院や地域により異なるため、事前にご寺院へご相談をされたうえで、どのように弔い上げを行なうかを決めると安心でしょう。
法事法要については###houji_houyou###で詳しくご説明しています。
宗旨によって考え方が違う
弔い上げについては、仏教と神道でそれぞれの考え方があります。
仏教では、一般的に三十三回忌や五十回忌に弔い上げを行なうことが多いです。
仏教においては、亡くなってから長い時間を経るうちに魂は浄化されていき、三十三回忌や五十回忌を迎えるころには、どのような魂も極楽浄土へ行くことを許されると考えられています。
そのため、個としての追善供養を終了する区切りとして弔い上げを行なうのです。
幼い子どもなどの無垢な魂は、早く浄化されると考えられるため、早く弔い上げをする例も多くあります。
神道でも仏教と同じように、三十三年祭や五十年祭に弔い上げを行ない、最後の式年祭として区切りをつけます。
悪いことをする荒御魂(あらみたま)も、そのころには優しく温厚な和御魂(にきみたま)になるといわれているからです。
宗旨宗派については###shuuha_shuushi###で詳しくご説明しています。
近年は弔い上げを早める場合も
弔い上げは、一般的に三十三回忌や五十回忌に行ないますが、近年は七回忌や十三回忌などに早めて行なう方も増えています。
ご法要の施主も参列者も高齢化すると、「ご法要を営むこと自体が難しくなる」「五十回忌などになると故人様の生前を知る方がすでにいない場合がある」といった理由からです。
弔い上げのタイミングは、ご家族のご事情をふまえ、ご寺院にご相談のうえで決められると良いでしょう。
弔い上げの流れについて
弔い上げのやり方や流れについては、先にも述べたとおり特別な決まりごとなどはなく、以下のように通常のご法要と同じ流れで行なうことが多いです。
・ 読経
・ 参列者による焼香
・ 法話
・ 施主のご挨拶
・ お食事
・ 散会
施主挨拶の際には、あらためて参列者にこの法要をもって弔い上げである旨をお伝えすると良いでしょう。
弔い上げでお渡しする御布施の相場は?
ご寺院への御布施は通常の年忌法要と同じと考え、弔い上げ用として特別に御布施をお包みする必要はありません。
ただ、弔い上げということで気持ちとして、多めにお包みする方もいらっしゃいます。
相場としては、相場は30,000円~50,000円といったところでしょうか。
御布施について###ofuse_kingaku###をご確認ください。
※御布施の金額については、宗旨・宗派により、またご寺院の考えやしきたりによっても異なります。詳しくはご寺院にご確認いただくことをおすすめします。
弔い上げを行なう際の服装について
弔い上げのご法要では、喪服・準喪服を着用しましょう。
それまでの年忌法要には平服で参列していても、弔い上げの際は喪服・準喪服の着用が望ましいとされています。
準喪服とは、男性はブラックフォーマルスーツ、女性はブラックフォーマルスーツ(ワンピース、アンサンブル)です。
身だしなみについて詳しくは###sougi_midashinami###でご確認いただけます。
弔い上げの後に行なうこと
先にご説明したように、弔い上げをすると、故人様の魂をご先祖の霊として祀ることになります。
故人様の位牌は、閉眼供養の後、ご寺院でお焚き上げをしていただくことが一般的です。
閉眼供養とは、故人様の位牌から魂を抜くことで、その後、先祖代々の繰出位牌(回転位牌とも)へと移したり、過去帳に記したりすることが多いです。
なお、浄土真宗では、忌明けのタイミングで白木位牌から過去帳に記すので、弔い上げ後もその過去帳を使用します。
位牌の扱いやお焚き上げについては、ご寺院や地域によっても考え方が異なりますので、まずはご寺院に相談されるとよいでしょう。
開眼供養については、###kaigenkuyou_toha###で詳しく解説しております。
まとめ
今回は、最後の年忌法要となる弔い上げについて解説しました。
一般的には三十三回忌や五十回忌に行ないますが、近年は高齢化などの事情から、七回忌や十三回忌などに早めて行なう例も増えています。
ご法要のタイミング、当日の流れ、お焚き上げなどについては、ご寺院とよくご相談されたうえで決めていただくと、悔いのない弔い上げとなるでしょう。
故人様の個の魂としては最後のご供養となるため、心を込めて行ないたいものです。
なお、平安祭典では弔い上げのご法要のお手伝いをしております。
弔い上げや年忌法要についてのお問い合わせ、ご相談などがございましたら、気兼ねなく平安祭典(0120-18-4142)までご連絡ください。
続きはこちら
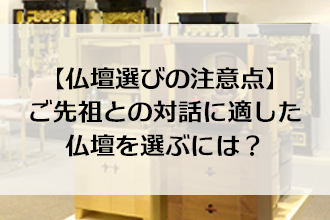
更新日:2024年9月21日 更新日:2023年4月2日 公開日:2022年9月26日
仏壇は、日本人にとって身近なものといえるでしょう。
しかし、いざご自宅に仏壇が必要となったら「どうやって選べば良い?」「仏具の飾り方は?」といった疑問が出てきますよね。
そこで今回は、仏壇の役割と選び方、必要な仏具と飾り方などについて解説します。
[@目次@]
仏壇の役割・準備する時期とは?
そもそもなぜ仏壇が必要なのでしょう。
あわせて、仏壇の役割や仏壇を準備する時期についてご説明します。
仏壇の役割とは?
仏壇には3つの役割があります。
① 仏様(本尊)を祀り、祈る場所
仏壇とは本来、仏様を祀る台を意味します。
ご寺院にある仏壇(内陣)を模したもので、家の中の「小さなお寺」のような存在です。
家庭における信仰の中心として、日々、仏様に祈りを捧げる場です。
② ご先祖を祀る場所
仏壇はご先祖を祀り、ご供養をする場です。
日々のお参りを通してご先祖とのつながりを感じられ、ご先祖によって受け継がれた命の大切さや感謝を感じることができます。
また、ご家族が亡くなった時は、弔い上げをするまでは故人様のご供養の場でもあります。
③ 悲しみを癒す場所
大切な方が亡くなった時の喪失感と悲しみは、とても大きなものです。
だからこそ、多くの人にとって、仏壇の前で故人様のために祈ったり、故人様と対話をしたりすることで、心の癒しにつながります。
仏壇は、大切な方を偲び、悲しみを癒す「グリーフケア」の場でもあるのです。
いつまでに仏壇を準備する?
ご家族が亡くなり、ご自宅に仏壇がない場合は新たに購入します。
仏壇は忌明け(四十九日)までに準備しましょう。
新しい仏壇を整えたら、一般的には忌明け法要の際にご寺院に開眼供養(本尊や位牌に魂を込める儀式)をしていただきます。
たいていの場合、仏壇は注文から納品までに3週間程度かかることが多いです。
商品によってはそれ以上かかる場合もあるため、早めに検討し始めると安心でしょう。
仏壇選びで大切な4つのポイント
仏壇には、さまざまな種類やデザインがあります。
ここでは仏壇を選ぶにあって大切な4つのポイントをご紹介します。
① 宗派を確認する
仏壇や仏具の種類は宗派によって異なります。
事前に宗派の確認をしておくと良いでしょう。
以下に代表的なものをご紹介します。
・ 八宗用
仏壇の形が八宗(天台宗・真言宗・浄土宗・浄土真宗本願寺派・真宗大谷派・臨済宗・曹洞宗・日蓮宗)共通で、最も多く使用されています。
禅宗様式の須弥壇(しゅみだん)で、宮殿の屋根は千鳥破風・軒は唐破風が一般的です。
・ 西本願寺用
浄土真宗本願寺派(西本願寺)用で、宮殿の屋根は破風・軒は唐破風・柱は金箔です。
・ 東本願寺用
浄土真宗大谷派(東本願寺)用は、宮殿は東本願寺阿弥陀堂を模し、屋根が二重唐破風・柱は黒塗りです。
・ 日蓮正宗用
須弥壇の上に厨子(ずし)を置き、厨子に開閉できる扉つきです。
仏壇に祀る位牌も宗派による決まりごとがありますので、注意が必要です。
位牌については###ihai_toha###で詳しく解説しています。
② 仏壇の配置場所や向きを決める
仏壇を選ぶにあたって、まず仏壇を置く場所を決めなければなりません。
以下の点をふまえて検討すると良いでしょう。
・ 向き(方角)
仏教では仏様はどの方角にもいらっしゃるとされるので、仏壇を置く向きに特別な決まりや吉凶はありません。
しかし、一般的には真北を避けて配置する方が多いようです。
また、最適な方角とは諸説あります。どうしても気になるという方は、下記を参考にしてください。
【南面北座説(なんめんほくざせつ)】
お仏壇が北を背にして、南を向くように安置します。
南向きだと直射日光が当たらず、風通しもよく湿気も防げることから、最適とされてきました。
※主な宗派…曹洞宗・臨済宗
【本山中心説(ほんざんちゅうしんせつ)】
仏壇の前で合掌して拝む方向の延長線上に家の宗派の本山がある位置に置きます。
宗派の本山が京都にある場合、関東の居住者と中国・九州の居住者では向きが逆になります。
※主な宗派…真言宗
【西方浄土説(さいほうじょうどせつ)】
古くから極楽浄土は、西方浄土と呼ばれ西にあると信じられてきました。
そのため、東を向くように安置すると、拝むために西方浄土に向かって礼拝できるため最適であるという考え方です。
※主な宗派…浄土真宗・浄土宗・天台宗
・ 避けるべき場所
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、冷暖房の風が直接当たる場所は避けます。
また、同じ部屋の中に神棚がある場合、向いあわせとなる場所や神棚の真下は避けたほうが良いとされています。
・ お参りのしやすさ
動線の悪い場所に仏壇を置くと、日々のお参りがしにくくなってしまうため、ご家族がお参りしやすい場所を選びましょう。
③ 仏壇の種類(デザイン)を決める
配置スぺースの高さ、幅、奥行きを測り、仏壇の種類(上置きタイプ、床置きタイプなど)とサイズを決めます。
代表的な仏壇の種類(デザイン)は次の通りです。
配置スぺースおよび部屋のインテリアなどにあわせて選びましょう。
・ 家具調仏壇 床置きタイプ
機能的でモダンなデザインの仏壇で、洋室にも和室にもマッチします。
広いリビングルームにも置け、存在感があります。
・ 家具調仏壇 上置タイプ
モダンで、かつコンパクトサイズの仏壇です。
インテリアになじみやすく置く場所を選びません。
・ 唐木仏壇 床置きタイプ
黒檀や紫檀など唐木材の美しい木目を生かし、職人がつくり上げる伝統的な仏壇です。
仏間や床の間にも配置でき、格式と存在感が際立ちます。
・ 唐木仏壇 上置きタイプ
伝統的で格式のある唐木仏壇をコンパクトにした仏壇です。
家具の上など小さなスペースにも配置できます。
・ 金仏壇(塗り仏壇) 床置きタイプ
全体に黒の漆塗りを施し、内部には金箔が施された仏壇です。
仏間や床の間にも配置でき、豪華で威厳を感じさせます。
・ 金仏壇(塗り仏壇) 上置きタイプ
伝統的で豪華な金仏壇をコンパクトにしたタイプで、家具の上など小さなスぺースにも配置できます。
・ 神徒壇(しんとだん)
神道においてご先祖や故人様の霊璽(れいじ)を祀るもので、床置きタイプと上置きタイプがあります。
御霊舎(みたまや)、祖霊舎(それいしゃ)、祭壇宮(さいだんみや)とも呼ばれます。
④ 仏壇の予算(値段)を決める
仏壇の価格は宗派、種類、材質、サイズなどにより、数万円から数百万円とかなり幅があります。
また、仏具店によっても価格設定は異なります。
以下の点を考慮しながら、予算を決めると良いでしょう。
・ 原材料や工法による価格の違い
仏壇に使われる木の種類は、黒檀、紫檀、桑、ウォールナットなどです。
高級な木材を使っていれば、それだけ高価になります。
また、表面の工法も無垢、厚板貼り、薄板貼り、木目調プリント、着色仕上げなどさまざまです。
風合いや色合いを実際に見て確認すると安心でしょう。
・ デザインによる価格の違い
デザインが複雑な仏壇、細かい装飾が多い仏壇など、職人の手間がかかっているものほど高価になります。
・ 仏具の価格
仏具も購入する必要がある場合は、仏壇と仏具をあわせて予算を考えましょう。
セット価格を設けている仏壇店が多いので、内容と価格をよく確認してください。
ほとんどの方が、一度購入した仏壇と一生お付き合いします。
ご希望とご予算に応じて慎重に選ぶことをおすすめします。
仏壇の購入場所については、ご利用された葬儀社で仏壇・仏具を扱っている場合、扱いのない場合も、仏壇・仏具専門店をご紹介いただけることが多いです。
現在は仏壇のインターネット通販も可能ですが、葬儀社や専門店では「実物を見て選べる」「専門家に相談できる」「アフターフォローが受けられる」といったメリットがあります。
仏壇には何を置く?必要な仏具と飾り方
仏壇には、一般的に以下の「六具足」と呼ばれる仏具が必要です。
・ 仏飯器
・ 茶湯器
・ 花立
・ ロウソク立て
・ 香炉
・ 線香差
仏壇・仏具店などでは多くの場合、セット販売されています。
ちなみに、五具足というのは上記から線香差を除いたものです。高月(高杯)は仏壇を購入すると付いてくることが多いですが、ない場合はお皿やお盆で代用していただいてもかまいません。
また、「おりん」と「りん棒」は六具足には含まれていませんが、宗派にあったものが必要です。
次に、仏具の基本的な飾り方をご紹介します。
宗派によっては異なる部分もありますので、それぞれの宗派の飾り方(祀り方)に準じてください。
ご不明なことはご寺院や仏壇・仏具店へご確認ください。
・ 最上段の中央に本尊を祀る
・ 本尊の左右に宗祖名・号の描かれた掛け軸をかける
・ 位牌は本尊より一段低い場所に安置する(ご本尊が隠れないように左右のどちらかに置く)
・ 次の段の中央に仏器膳を置き、仏飯器・茶湯器を置く
※家具調仏壇の場合は仏器膳は置かないことがほとんどです。
・ 仏器善の左右に高月(高杯)を置く
・ 最下段には花立、香炉、ロウソク立て(火立)、マッチ消、おりんなどを置く
まとめ
仏壇は仏様を祀り、ご先祖や故人様をご供養する場であるとともに、大切な人を失った悲しみを癒す役割も担います。
新たに仏壇を購入する際は、忌明け法要までにご準備できるよう、早めに検討し始めることをおすすめします。
宗派、設置場所、デザイン、予算などをふまえてよく検討し、納得のいく仏壇選びをしましょう。
平安祭典では、各種ご相談を承っています。
神戸・阪神間でお困りごとがございましたら、平安祭典(0120-00-3242)まで気兼ねなくご相談ください。
続きはこちら
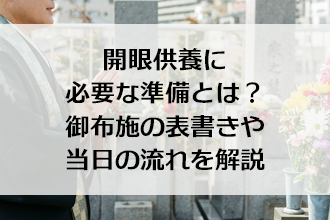
公開日:2022年9月19日
新たにお墓を建てたり、仏壇や位牌を購入した際は、「開眼供養」を行ないます。
とはいえ、そういった経験は何度もあることではないため、開眼供養についてよくご存じない方が多いのではないでしょうか。
そこで当記事では、開眼供養について詳しく解説します。
新しくお墓や仏壇、位牌の購入を検討される際の参考になさってください。
開眼供養は魂を入れる大切な儀式
開眼供養とは、お墓、仏壇、位牌などを新しく購入した際に、魂を込める儀式のことです。
ご寺院の読経により魂を込めることで、墓石や仏壇(ご本尊)、位牌などが、ただの物からご供養すべき対象となります。
開眼供養の歴史は古く、東大寺が建立されたとき、最後に大仏の目を入れてご法要を行なったことに由来するそうです。
なお、開眼供養の読み方は「かいげんくよう」です。
ほかにも開眼法要(かいげんほうよう)、入仏法要(にゅうぶつほうよう)、入魂式(にゅうこんしき)、御魂入れ(みたまいれ)、お性根入れ(おしょうねいれ)、魂入れ(たましいいれ)、などと呼ばれることもあります。
開眼供養の準備で必要なことは?
開眼供養の対象がお墓か仏壇か、また、ご法要を同時に行なうかなどの条件で、日程や規模が異なります。
特にご法要を同時に行なう場合は、参列者も多くなることが多いので、念入りに準備をしておきましょう。
ここからは、開眼供養の準備について詳しくご説明します。
開眼供養の日程や当日の流れを決める
開眼供養を行なう日取りに決まりはありませんが、忌明けなどのご法要と同時に行なうことも多いです。
また、開眼供養を行なう場合は、会場や流れを決める必要があります。
というのも、お墓の開眼供養はお墓で行ないますが、位牌や仏壇の開眼供養は、ご自宅やご寺院、会館などで行なうこともあるからです。
ご寺院や会館で行なう場合は、使用料が必要になることも覚えておきましょう。
さらに、開眼供養をどのような流れで行なうか事前に決めておくことも大切です
お墓の開眼供養と法要を同時に行なうのであれば、ご自宅やご寺院で法要を行なった後、お墓へ移動する必要があります。
会食を予定しているなら、どのタイミングで会食するかなどもあわせて検討しておくと良いでしょう。
ご寺院の都合もあるため、早めに日程や流れを相談されるようおすすめします。
開眼供養にお呼びする方を決める
開眼供養に誰をお呼びするか決まりはありませんが、ご法要と同時に行なう場合はご家族・ご親族などをお呼びすることが一般的です。
ご法要は別日に行ない、お墓や仏壇の開眼供養のみを行なう場合は、ご家族だけのごく少数で行なうことも多いです。
開眼供養にお呼びする方が決まったら、日時・場所・会食の有無を、1か月前を目安にお知らせします。
出欠の返事は2週間前を目安に設定すると、会食や供養品の準備がスムーズに行なえるでしょう。
会食・供養品(粗供養)の準備をする
開眼供養の終了後、会食を行なう場合は、会場や料理を手配します。
自宅で会食をする場合、仕出し弁当などを手配することが一般的です。
また、参列された方にお渡しする供養品(粗供養)も手配しておきます。
供養品については、###okaeshi_kuyouhin###で詳しくご説明しています。
御布施の準備をする
御布施の相場は、宗旨・宗派、地域によって様々なうえ、ご寺院のお考えによって金額が決まっていることもあります。
おおよその目安として、以下の金額をご紹介しますので、ご参考としてお役立てください。
・ お墓の開眼供養(納骨も含む)
目安:30,000円~50,000円
水引:紅白
表書き:開眼供養御礼
※浄土真宗のみ建碑法要御礼
・ 仏壇の開眼供養
目安:20,000円~30,000円
水引:紅白
表書き:開眼供養御礼
※浄土真宗のみ入佛慶讃御礼
位牌の開眼供養の場合は個別には用意せず、忌明け法要(四十九日法要)の御布施に含んで渡すことが多いです。
ご供養なのに紅白の水引を使用することに驚かれた方もいらっしゃるかもしれませんが、開眼供養は慶事(お祝いごと)です。
法要を同時に行なう際は、不祝儀袋の御布施もあわせて用意が必要です。
御布施については###ofuse_kingaku###でもご紹介しています。
喪服の準備をする
開眼供養と法要や納骨を同時に行なう場合は、喪服や準喪服を着用します。
開眼供養のみの場合は、男性は地味な色のスーツに黒のネクタイや靴、女性は無地の地味な色のスーツまたはワンピースに黒の小物を揃えると良いでしょう。
供花・供物の準備をする
供物は、普段仏壇に供えているものと同じでかまいません。
供花は日持ちがしないので、直前に購入すると良いでしょう。
なお、仏壇の開眼供養の際には、赤いロウソクが必要なことが多いです。
赤いロウソクは普段あまり見かけませんが、仏具店などで取り扱っています。
開眼供養当日の流れについて
お墓の開眼供養の場合、当日の流れの一例は以下の通りです。
・ 供花・供物の準備
特別な準備は必要なく、通常のお墓参りと同じでかまいません。
開眼供養が始まる前にお供えしておきます。
↓
・ 除幕
竿石に巻かれた布を取ります。
この布は、開眼供養前のお墓を邪気から守るために巻かれているものです。
↓
・ 読経・焼香
ご寺院の読経の間、順番にお焼香をあげます。
↓
・ 法要後の片付け
供物や線香の灰など、全てきれいに片づけます。
お墓参りについて、詳しくは###hakamairi_timing###もご覧ください。
開眼供養に呼ばれたら何が必要?
開眼供養に呼ばれた場合は、喪服や御香典の準備をします。
一般的に、参列者を呼ぶ場合は開眼供養と同時に法要を行なうことが多いですが、開眼供養のみか、法要を同時に行なうかを確認のうえ、準備をしてください。
まず服装についてはご遺族と同じで、忌明け法要や納骨を同時に行なう場合は、喪服や準喪服を着用しましょう。
開眼供養だけの場合は、男性は地味な色のスーツに黒のネクタイや靴、女性は無地の地味な色のスーツまたはワンピースに黒の小物を揃えると良いでしょう。
服装については###sougi_midashinami###でも解説しています。
御香典については、次のように準備をしましょう。
・ 法要も同時に行なう場合
水引:黒白、黄白、双銀(銀一色)
表書き:御仏前
※関西地方では特に、黄白の水引を使用することが多いです。
・ 開眼供養のみの場合
< お墓の開眼供養 >
水引:紅白
表書き:建碑御祝
< 仏壇の開眼供養 >
水引:紅白
表書き:開眼御祝または開眼供養御祝
開眼供養とご法要を同時に行なう場合、多めに包まれる方もいらっしゃいますが決まりはなく、参列者の考え方次第です。
御香典について詳しく知りたい方は###kouden_manner###をご覧ください。
まとめ
当記事では開眼供養についてご紹介しました。
開眼供養とは、ご寺院の読経により魂を込める重要な儀式です。
開眼供養を行なうことで、お墓や仏壇を、故人様を偲ぶ場として引き継いでいけるでしょう。
平安祭典(0120-00-3242)では法要のご相談も承っております。気兼ねなくご相談ください。
続きはこちら