

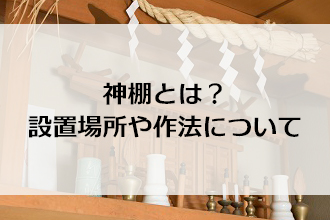
公開日:2022年4月11日
皆さまは「神棚」をご存知でしょうか?
ご自宅に仏壇と神棚、両方を設置されているご家庭も多いことと思います。
一方で、ご自宅を新築なさるなどして、これから設置しようというご家庭もあるかもしれません。
身近にご先祖を感じることができる場所だからこそ、神棚の設置場所や方角、作法など基本的な知識は知っておきたいですよね。
そこで今回は、神棚に関するあれこれをご紹介します。
そもそも神棚とは?
神棚とは、神道(しんとう、しんどう)において神様を祀るための棚で、家や企業の事務所などに設置されているもので、神社同様にとても神聖な場所です。
棚の上に置かれた札宮(ふだみや)の中には、神社でいただいた御神札(おふだ)を納め、毎日参拝し、神様に感謝の気持ちを示します。
また、古来から日本では、ご先祖の霊をご供養することで、ご先祖が神となり子孫を守ってくれるという考えがあります。
そのため神棚で神様を祀ることで、ご先祖を祀る意味にもなるとされています。
神棚はどこに祀るか?祀るのに適した方角は?
ご自宅を新築した際などに、神棚を購入し、家の中のどこに祀るか悩まれる方もいらっしゃるかもしれません。
神棚は清浄かつ明るく静かな部屋の高い所に祀ります。
いつも綺麗にし、日当たりが良く人が集まりやすいリビングや和室などが良いでしょう。
方角は、太陽の光が多くあたるとされる南、もしくは東が神棚の正面と向き合うように祀ります。
人の出入りがあるドアの上や、不浄とされるトイレと背中合わせになっている場所、仏壇と向かい合わせになるような配置はできる限り避けます。
仏壇と同じ部屋に祀ること自体は問題ないのですが、どちらかを拝もうとすると、どちらかにお尻を向けてしまうことになりますので、向かい合わせにならないよう気を付けてください。
高さは、天井近く(私たちの目線より高い場所)に祀ります。
もちろん、家の造りなど様々な事情で、上で記したような高さのない場所に神棚を祀らなければならないこともあるでしょう。
しかし、大切なのはお祀りする気持ちなので、絶対に避けなければならないということではありません。
なお、神棚を新しく設置する際は、大安などの吉日に行なうと良いとされています。
神棚の上に付ける「雲板」「雲文字」とは?
二階建ての一軒家やマンションで、神棚を祀る部屋の上にさらに部屋があり、人が神棚の上を歩く可能性がある場合、神棚の上には「雲」をかたどった木製の飾り「雲板」や、紙に「雲」と書いた飾り「雲文字」を付けます。
「雲」を付けることで、神様に「神棚の上には何も存在しませんよ」「失礼はありませんよ」と伝えることになります。
なお、「雲」の代わりに「天」や「空」の文字を用いるケースもあります。
御神札(おふだ)の納め方
御神札とは、神様の御霊(みたま)が宿ったご分霊であるとされており、神社の名前やご祭神の名前が記されています。
御神札は神社の社務所や札所で頒布されています。
神棚の札宮に納める御神札には、神宮大麻(じんぐうたいま=伊勢神宮の御神札)や氏神札(地元の氏神様の御神札)、崇敬神社(すうけいじんじゃ)の御神札などがあります。
御神札は、新年のタイミングで一年に一度、新しいものに取り替えましょう。
古い御神札は、年末年始に神社内の古札収所、あるいは古札受付などと書かれた場所に返納します。
返納した御神札は神職がお焚き上げをしてくれます。
神具の設置方法と神棚のお供え、お参りの作法
神棚には、札宮以外にも神具(しんぐ)を設置します。
主な神具には、神鏡(しんきょう)、皿、水玉、榊立(さかきたて)、瓶子(へいし、へいじ)があります。
主な神具
・ 神鏡
札宮の扉の前に祀ります。
・ 皿
洗米や塩を乗せるための器です。
洗米は向かって中央、塩は向かって右に置きます。
・ 水玉
水を入れてお供えします。
お供えする時はふたをとって向かって左に置きます。
・ 榊立
榊を左右1本ずつお供えします。
・ 瓶子
御神酒をお供えするための器です。
ふたをとって左右1本ずつお供えします。
神様へのお供えのことを神饌(しんせん)と呼び、毎朝、神棚にお供えをします。
榊は毎月1日、御神酒とともに新しいものに取り替えると良いとされています。
神様の御霊(みたま)が宿ったご分霊であるとされる御神札が納められている神棚は、家の中にある神社です。
神棚のお参りの作法は、神社の参拝の作法と同様に「二拝二拍手一礼」が基本となります。
「神棚封じ」とは?
神道では死を穢(けが)れと見なします。
これは「気枯れている状態」のことで、不浄・汚れていることではありません。
この「穢れ」に触れぬよう、ご自宅に神棚がある場合、ご家族にご不幸があった際には「神棚封じ」を行ないます。
神棚封じとは、白布や半紙を貼り、神棚を隠すことです。
「神棚封じ」の手順
・ 神棚封じはご遺族ではなく、(穢れが及んでいない)第三者が行なう
・ 神棚に挨拶をし、亡くなった方の氏名を伝える
・ 神棚の榊や御神酒、お供え物を下げる
・ 神棚の扉を閉め、白布や半紙を貼り神棚を隠す
・ 神道における忌中の期間は50日なので、50日間神棚封じを行なう
神棚封じの期間はお供えを控えます。
失礼に当たると思う方もいるかもしれませんが、穢れがある状態で神棚に触れることのほうが良くないこととされています。
ご家族にご不幸があった際には、ご葬儀の準備とともに神棚封じを忘れずに行ないましょう。
神棚は神様を祀る大切な場所
いかがだったでしょうか。
今回は神棚に関するあれこれについてご紹介しました。
ご先祖を祀る仏壇同様に、神棚は神様を祀る大切な場所です。
また、冒頭でも述べた通り、古来から日本では、ご先祖の霊をご供養することで、ご先祖が神となり子孫を守ってくれるという考えがあります。
もし、ご家庭に神棚がなければ、一度お祀りすることをご検討されてみても良いかもしれません。
平安祭典では、神戸・阪神間でのご供養に関するご相談を承っております。
気兼ねなくお問い合わせください。(0120-00-3242)
続きはこちら
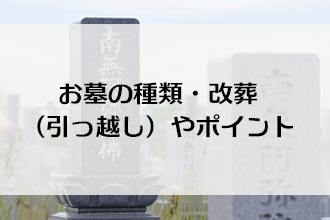
更新日:2024年9月21日 公開日:2022年4月4日
年齢を重ねるにつれ、お墓に関する心配事が出てくる方も多いのではないでしょうか。
例えばお墓を新しく建てること、お墓とは別の供養方法を考えること、既にあるお墓を改葬(引越し)することといった心配事です。
中には、墓じまいを考えている方もいることでしょう。
そこで今回は、お墓についてのあれこれをご紹介します。
お墓を建てる際のポイント
お墓を建てる際には、まず、お墓を建てる場所選びがポイントとなります。
お墓を建てる場所は、公営墓地、民営墓地、寺院墓地が候補となります。
公営墓地とは、都道府県や市区町村といった地方自治体が運営する墓地のことで、民営墓地とは、ご寺院などの宗教法人、あるいは公益法人が運営している墓地のことです。
また、寺院墓地はご寺院が宗教活動として運営している墓地です。
それぞれの墓地にはメリットとデメリットが存在します。
公営墓地
【メリット】
・ 永代使用料・管理費といった費用が安い
・ 宗旨・宗派を問わない
【デメリット】
・ 居住地制限など、申し込みの際の資格制限がある
・ 地域によっては応募倍率が高くなる
民営墓地
【メリット】
・ 公営墓地に比べて申込みの際の資格制限が少ない
・ 宗旨・宗派を問わない
【デメリット】
・ 公営墓地に比べて永代使用料・管理費といった費用が割高である
寺院墓地
【メリット】
・ 聖職者や管理人に、お墓のお手入れを定期的にしていただける
・ ご法要の際に相談に乗っていただける
・ 手厚い供養を期待できる
【デメリット】
・ 原則、そのご寺院び宗旨・宗派の檀家(信徒)でなければ、その寺院墓地を利用できない
いずれにせよ、新しくお墓を建てる際には、後々ご法要を執り行なうことやお参りのことも考え、ご自宅から近い場所に建てることをおすすめします。
お墓とは別の供養方法を選択する人もいる
近年、世代間でお墓に対するイメージ、捉え方に違いが見られるようなってきました。
特に若い世代の中には、お墓を建てずに、納骨堂や自然葬(樹木葬など)、海洋散骨、手元供養などのご供養の方法を選択する方もいます。
お墓を建てずにこれらの供養方法を利用することで、「経済的な負担が減少する」、「跡継(維持・管理の手間)の心配が不要である」といったメリットがあります。
その一方で、「心の拠り所がなくなってしまう」、「親族から良く思われない可能性がある」といったデメリットも生じる点は知っておきたいところです。
散骨については###sankotu_toha###の記事、手元供養については###temotokuyou_toha###の記事でも詳しくご紹介しています。ぜひ、あわせてご覧ください。
お墓の改葬(引越し)とは?
お墓の改葬とは、お墓を別の場所に移転することです。
「郷里のお墓を守っていくのが困難になった」、「郷里のお墓が遠くてなかなかお参りに行けない」、「自宅の近くで供養をしたい」などの理由から、お墓の改葬のニーズが近年高まっています。
なお、お墓の改葬は「墓地埋葬等に関する法律」に定められており、市町村の許可を得なければなりません。
以下にお墓の改葬の手順をご紹介します。
お墓の改葬の手順
・ 新しいお墓を探す(お墓を建てる)
・ 「墓地使用許可証(※)」と「受入証明書」を発行してもらう
※「墓地使用許可証」は墓地によって名称が異なります。
・ 「改葬許可申請書」を市区町村役場から取り寄せる
※自治体によってはダウンロードが可能です。
・ 既存墓地管理者から「埋葬(埋蔵・収蔵・納骨)証明書」を発行してもらう
※証明書は遺骨1名ごとに1通必要です。
・ 既存墓地のある市区町村役場に「改葬許可申請書」を提出し、「改葬許可証」を交付してもらう
※「改葬許可申請書」は自治体ごとに提出書類、名称が異なります。
・ ご寺院に「閉眼供養(魂抜き)」をしていただき、既存墓地から遺骨を取り出す
※既存のお墓の撤去については、石材店などに確認することをおすすめします。
・ 新しい墓地の管理者に「改葬許可証」を提出する
・ ご寺院に「開眼供養(魂入れ)」をしていただいてから遺骨を納骨する
また、「お墓の継承者がいない」、「遠方にあり墓参りが難しい」、「経済的な理由(お墓の維持、管理費がかかる)」などの理由から、お墓を撤去・処分する「墓じまい」を選択する方もいます。
大切なのは、故人様やご先祖を敬う気持ち
いかがだったでしょうか。
今回はお墓についてのあれこれをご紹介しました。
皆さまのご参考になれば幸いです。
お墓に関する心配事が出てくる方も多いと思いますが、大切なのは、故人様やご先祖を敬う気持ちです。
そのような気持ちを大切に、ご供養をされると良いのではないでしょうか。
平安祭典では、ご葬儀・ご供養に関する各種ご相談を承っています。
神戸・阪神間でお困りごとがございましたら、平安祭典(0120-00-3242)まで気兼ねなくご相談ください。
続きはこちら
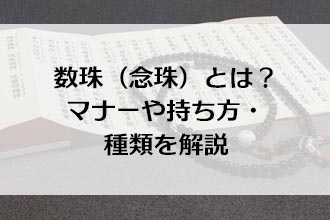
公開日:2022年3月28日
仏式のご葬儀やご法要に参列する際の必需品が「数珠(じゅず)」です。
数珠とは、穴の開いた小さな珠(たま)を中糸で繋げたもので、私たちにとって身近な仏具の1つです。
元々はお経や念仏を唱える際に、珠を動かすことで数を数える道具としても用いられており、これが数珠という名前の由来となっています。
また、仏様を「念」ずる際に用いる「珠」であることから「念珠(ねんじゅ)」とも呼ばれます。
今回は、この数珠(念珠)についてご紹介します。
数珠の歴史
仏具としての数珠の起源については諸説あります。
有力な説は、古代インドにおいてバラモン教の僧が数珠を使っており、この習慣を仏教の開祖であるお釈迦様が取り入れて、仏教でも用いられるようになったのではないかというものです。
昔々、インドのある王様が、国内で疫病が流行したり治安が悪くなっていることをお釈迦様に相談しました。
するとお釈迦様は「ムクロジ(無患子)の木の実を108個繋いで数珠とし、これを肌身離さず持ち念仏を唱えなさい。念仏を唱えるごとに珠を1つずつ珠を動かして数を数え、20万回念仏を唱えれば人々の迷いや苦しみがなくなり、100万回念仏を唱えれば人々の煩悩を断ち切ることができるでしょう」と説かれたそうです。(※)
その後インドから中国に伝わり、日本には、仏教伝来とともに飛鳥時代の頃に中国から伝わりました。
一般に普及したのは、鎌倉時代に浄土教(浄土思想)が流行し、人々が念仏を唱えるようになってからだとされています。
数珠の珠の正式な数は108個ですが、この108という数字は人間の煩悩の数でもあります。現在でも、念仏を唱えるごとに珠を1つずつ動かして数えることで、1つずつ煩悩が消えて清らかな心になると考えられています。
※ この話は『大蔵経(だいぞうきょう)』の中の「佛説木槵子経(ぶっせつもくげんじきょう)」というお経に収録されています。
数珠の種類 「本式数珠」と「略式数珠」の違い
数珠の種類には、宗派ごとに異なる正式な「本式数珠」と、宗派問わず使うことができる「略式数珠」があります。
「本式数珠」は、108個もの珠からなるため、一般的には二重にして使われます。
「略式数珠」は珠の数を減らしたもので、片手にかけて使うことができることから「片手数珠」とも呼ばれます。
仏式のご葬儀やご法要では、数珠を持参することがマナーなので、ご自身用のものを1つは持っておきたいところです。
はじめてご購入されるなら、宗派問わず使え、持ち運びにも便利な「略式数珠」を選ぶのが無難でしょう。
ご自身の宗派にこだわりがある場合は、「本式数珠」を選んでも良いと思います。
なお、宗派の異なるご葬儀に参列される際、ご自身の宗派の数珠を持って出席してもマナー違反ではありません。
ちなみに、数珠には男性用と女性用があり、持ち運びするための数珠袋も男性用・女性用それぞれがありますので、選ぶ際にはご注意ください。
「本式数珠」と「略式数珠」の他にも、「腕輪念珠」と呼ばれるブレスレット型のものがあります。
このブレスレット型は、お守りとしての意味合いが強いため、ご葬儀などでの使用は控えましょう。
略式数珠の持ち方
数珠の持ち方は宗派ごとに異なるとされていますが、略式数珠であれば、基本的には宗派を問わず使え、持ち方も統一されています。
突然のご不幸の際にも慌てないように、略式数珠の持ち方をご紹介します。
基本的な持ち方
数珠を片手で持つ時は、基本的に房を下にして左手に持ちます。
席に座っている時は左手首にかけておき、焼香などで移動する場合には、左手の親指と人差し指の間にかけて持ちます。
焼香をする場合
数珠を持った左手をひじから直角に曲げ、身体の中心からやや左寄り(心臓のあたり)に止めた姿勢で、右手で焼香します。
合掌する場合
一般的には、左手の親指と人差し指にかけた状態で右手を添えて合掌します。
長い数珠の場合は、二連にして左手に持ったまま手を合わせるか、左右の中指に内側の一連だけをかけ合掌します。
焼香の作法については、###shoukou_yarikata###で詳しくご紹介しています。
数珠に関するトラブル こんな時はどうすれば良い?
続いて、数珠に関してよく起きるトラブルと解決方法ご紹介します。
忘れた時は?
数珠の貸し借りをすることはおすすめできません。
これは、数珠には持ち主の念が宿ると言われているためです。
数珠を持つことはマナーではありますが、忘れても問題なく焼香はできます。
平安祭典では、数珠の販売も行なっていますので、ご安心ください。
もし数珠が切れたら?
まれに数珠の珠を繋ぐ紐が劣化して、切れてしまうことがあります。
ご葬儀やご法要の最中などに切れてしまうと、バラバラと珠が散らばってしまい困ってしまいます。
紐が明らかに劣化している場合には、事前に新しく買い替える、あるいは販売店や仏壇店などに修理に出しましょう。
数珠の処分は、そのままゴミとして捨てても構いませんが、ご供養をしてもらいたい場合には、ご寺院や仏具店にご相談ください。
数珠を長持ちさせるためのお手入れ方法
数珠を使い続けていると、紐が劣化するなど様々な不具合が出てきます。
長く使い続けるためにも、適切な使い方、定期的なメンテナンスを心がけましょう。
珠の部分は、汚れたら、柔らかい布で優しく拭きましょう。
また、夏場に数珠を使用すると、汗が付着するので、使用後はそのまましまわずに先に軽く拭き取ります。
数珠の紐は切れやすいため、直射日光の当たるような場所には保管せず、衝撃を与えないことも大切です。
季節ごとに中の紐の摩耗具合をチェックし、不具合があるようであれば仏具店などで紐を交換してもらいましょう。
持ち運ぶ際には専用の数珠袋に入れますが、ご自宅で保管をする場合、数珠袋では房が曲がってしまう可能性もあるので、専用の箱などに入れて保管すると良いでしょう。
素材やデザインにこだわった数珠もある
今回は、数珠(念珠)についてご紹介しました。
最近では、素材やデザインにこだわったものも数多く販売されています。
もしお持ちでなければ、まずは気に入った素材やデザインの数珠を選んではいかがでしょうか。
数珠は主に仏具店で販売されていますが、平安祭典でも、様々な種類の数珠をご用意しています。
お近くの平安祭典にお立ち寄りの際には、ぜひご覧になってください。
続きはこちら
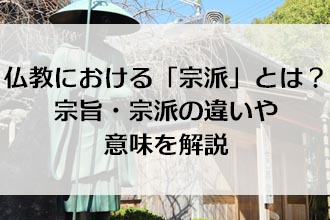
公開日:2022年3月21日
2018年にNHKが実施したアンケート調査によると、日本人が信仰する宗教は「仏教」 が31%、「神道」 が3%、「キリスト教」 が1%、「信仰する宗教なし」 が62%だったそうです。(その他:1%、無回答:2%)
ご葬儀を仏式で行なう方が多い中で、「仏教」の31%は、少ない印象を受けます。
「信仰する宗教なし」 と回答した方の多くは、実際には仏教を信仰しているかもしれませんね。
ところで、日本人の多くが信仰している仏教には、ご存知の通り、多くの宗派(しゅうは)があり、古くからある伝統的な仏教だけでも「十三宗五十六派」が存在します。
そこで今回は、この「十三宗五十六派」、そして日本の仏教の代表的な「十三宗」についてご紹介します。
「宗旨」と「宗派」の違いと仏教における歴史
「宗旨」は宗教の教えや教養そのものを、「宗派」は各宗教から生じた分派を意味しています。
日本の伝統的な仏教には、「十三宗五十六派」が存在します。
「十三宗」とは、法相宗、律宗、華厳宗、真言宗、天台宗、日蓮宗、浄土宗、浄土真宗、融通念仏宗、時宗、臨済宗、曹洞宗、黄檗宗のことです。
「五十六派」とは、これらの十三宗から教義・信仰対象などの違いや歴史的経緯により生じた五十六の分派のことです。
一方で、「十三宗五十六派二十八宗派」という呼び方もあります。
これは1940年4月に「宗教団体法」が施行され、宗教団体は認可制となり、五十六派が合同した二十八宗派が認可を取得したことに由来します。
仏教の代表的な「十三宗」
日本の伝統的な仏教である「十三宗」ですが、それぞれの特徴について見てみます。
奈良仏教系
・ 法相宗(ほっそうしゅう、ほうそうしゅう)
開祖:玄奘三蔵(三蔵法師)
本尊:唯識曼荼羅(ゆいしきまんだら)
長い時間をかけ、段階を経て修行を行なうことで成仏に至ると考える。
また、念仏や題目を唱える、坐禅を行なうなど、ひとつの行だけに専念するのではなく、様々な行を推奨する。
遣唐使の僧により日本に伝えられる。
興福寺、薬師寺が本山。
・ 律宗(りっしゅう)
開祖:鑑真和上
本尊:盧舎那仏(るしゃなぶつ)
「戒律」、すなわち自発的に規律を守ろうとする心のはたらきを指す「戒」と、他律的な規則を指す「律」の研究と実践を主とする。
日本には鑑真(がんじん)が伝えた。
唐招提寺が本山。
・ 華厳宗(けごんしゅう)
開祖:杜順
本尊:毘盧舎那仏(びるしゃなぶつ)
毘盧舎那仏とは、明るい光を放つ仏で、毘盧舎那仏の光明により迷っている人々を浄土である華厳世界に導くとされる。
「華厳経」を経典とし、大乗仏教の中でも哲学的で独特な教えを持つ。
聖武天皇が建立した東大寺(奈良の大仏=盧舎那仏像で有名)は、近代以降は華厳宗を名乗る。
密教系
・ 真言宗(しんごんしゅう)
開祖:空海(弘法大師)
本尊:大日如来
空海が唐の都・長安で学んだ密教を基盤とする。
大日如来をすべての根本と考える。
人の心のあり方や価値観などを10の段階に分け、最終的に大日如来と同レベルに達することを説く。(「十住心思想」)
密教系+法華系
・ 天台宗(てんだいしゅう)
開祖:最澄(伝教大師)
本尊:お釈迦様、薬師如来など
中国で学んだ最澄により日本に伝えられた密教。
朝は法華経の南無妙法蓮華経を唱え、夕方は阿弥陀経の南無阿弥陀仏を唱えるという「朝題目夕念仏」という言葉があるが、「妙法蓮華経(法華経)」を根本仏典とする。
天台宗から多くの日本仏教の宗旨が発展した。
比叡山延暦寺が本山。
法華系
・ 日蓮宗(にちれんしゅう)
開祖:日蓮(立正大師)
本尊:お釈迦様、大曼荼羅、日蓮聖人
鎌倉時代中期に日蓮が興す。
本尊・題目・戒壇を三大秘法とし、題目(「南無妙法蓮華経」)を唱えること(唱題)を重視している。
「南無妙法蓮華経」とは「妙法蓮華経(法華経)に帰依する」という意味。
法華宗とも称する。
浄土系
・ 浄土宗(じょうどしゅう)
開祖:法然(円光大師)
本尊:阿弥陀様
鎌倉仏教のひとつ。
修行の価値を認めず、修行による成仏を否定し、念仏を唱えることを重視する。
念仏を唱えることで極楽往生に至ると考える。
・ 浄土真宗(じょうどしんしゅう)
開祖:親鸞(見真大師)
本尊:阿弥陀様
法然の教えを親鸞が継承し発展させる。
人が求めなくとも阿弥陀様が救って下さる、いずれ仏になることが約束されているから、改めて修行する必要はないという教え。
・ 融通念仏宗(ゆうづうねんぶつしゅう)
開祖:良忍(聖應大師)
本尊:十一尊天得如来(中央に阿弥陀様、周囲に10体の菩薩)
毎日何度も念仏を唱えることが修行の中心となる。
一人一人の祈りが全ての人の為となり、全ての人の祈りは自分のためになるという教えを持つ。
華厳宗の影響を受ける。
・ 時宗(じしゅう)
開祖:一遍(証誠大師)
本尊:阿弥陀様または南無阿弥陀仏の書
阿弥陀様を信じる信じないを問わず、仏の本願力は絶対であるがゆえに、念仏さえ唱えれば往生できると説く。
禅宗
・ 臨済宗(りんざいしゅう)
開祖:栄西(千光法師)
本尊:定めはないがお釈迦様が多い
師から弟子への悟りの伝達(法嗣、はっす)を重んじる。
座禅を組みながら師と弟子が問答を繰り返す「看話禅(かんなぜん)」で有名。
ちなみに、「ソモサン(什麼生)」「セッパ(説破)」で知られるアニメの一休さんは、室町時代に実在した臨済宗の僧侶・一休宗純をモデルとしている。
鎌倉幕府、室町幕府という時の政権との結び付きが強く、室町文化の形成にも多大な影響を与えた。
鎌倉時代には上級武士の間で支持された。
・ 曹洞宗(そうとうしゅう)
開祖:道元(承陽大師)
本尊:お釈迦様
「看話禅」の臨済宗とは異なり、黙して坐禅に徹する「黙照禅」で各自が悟りを開いてゆく。
鎌倉時代には地方の武士や一般市民の間で支持された。
・ 黄檗宗(おうばくしゅう)
開祖:隠元(真空大師)
本尊:お釈迦様
江戸時代初期に来日した明末の僧、隠元が開祖。
教義・修行・儀礼・布教などは日本の臨済宗と変わらないが、儀式の形式や使われる言葉は中国・明時代の様式。
ご葬儀では宗旨・宗派の確認を
今回は、仏教における「十三宗五十六派」、日本の仏教の代表的な「十三宗」についてご紹介しました。
宗旨・宗派が異なると、御香典の表書きの書き方や線香の作法も異なる場合もあります。
そのため、ご葬儀に参列なさる際には、喪家の宗旨・宗派の確認をしておきたいところです。
御香典については###kouden_manner###で詳しく説明しています。
平安祭典では神戸・阪神間での仏事に関するご相談を承っております。
気兼ねなくお問い合わせください。(0120-00-3242)
続きはこちら
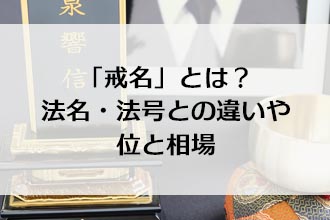
公開日:2022年3月14日
仏式のご葬儀では、故人様に「戒名(かいみょう)」が授けられます。
また、この戒名に似た言葉に「法名(ほうみょう)」や「法号(ほうごう)」というものがあります。
今回は「戒名」とは何か、「法名」や「法号」との違いや位と相場などについてご説明します。
「戒名」と「法名」、「法号」の違いとは?
まずは皆さまも馴染み深い「戒名」からご説明します。
「戒名」とは、故人様が釈迦(しゃか)の弟子、すなわち仏弟子(ぶつでし)になった証として、ご寺院から授けられる名前のことです。
戒名は、ご寺院がご葬儀までに授けるのが一般的です。
仏教の多くの宗派では、この「戒名」という言葉を用いますが、この「戒」という字は「戒律」という言葉からきています。
つまり、「戒律を守り、仏弟子となる証としての名前」が戒名なのです。
一方で、浄土真宗の教えにはこの戒律が無いため、仏弟子として授けられる名前は戒名ではなく「法名」といいます。
また、日蓮宗では「法号」と呼び、これも戒名と同じくご寺院から名前が授けられます。
ちなみに「戒名」や「法名」、「法号」は故人が授かる名前という認識の方が多いかもしれませんが、本来は生前にご寺院から授かる仏教徒としての名前です。
「戒名」と「法名」、「法号」の付け方と構成
「戒名」と「法名」、「法号」の付け方についてもご説明します。
宗派によって若干の差異はあるものの、基本的な構成はほとんど同じで、「院殿号・院号」「道号」「戒名」「位号」の4つとなります。
ひとつずつ見ていきましょう。
・ 院殿号・院号
主にご寺院や社会の発展などに大きく貢献した方には、戒名の最高位「○○院殿」「○○院」などが与えられます。
・ 道号
「道号」とは、悟りを開いた方に与えられる称号のことです。
基本的には2文字で、生前の職業や人柄、性格や趣味などが分かる称号が与えられます(浄土真宗では使用しません)。
・ 戒名
故人が仏門に入った証として与えられる称号です。
一般的には2文字で、生前の本名から1文字付けることが多いです。
浄土真宗では「釋(釋尼)○○」と表記します。
・ 位号
俗名であれば「様」にあたる部分で、故人の性別や年齢によって異なる称号です。
男性は「○○居士」「○○信士」、女性は「○○大姉」「○○信女」、子供であれば「〇〇童子」や「〇〇童女」などが用いられます(浄土真宗では使用しません)。
「戒名」と「法名」、「法号」に使用される文字は漢字のみですが、真言宗では、戒名の前に梵字(※)がつきます。
※ 梵字とは古代インドのサンスクリット語を書き表す文字のことで、真言宗ではこの梵字の「ア」(「阿字」とも)は、ご本尊である大日如来を表します。
戒名の位と相場
戒名・法名・法号を授けていただくことに対する御礼は、御布施に含まれていることが一般的です。
位号のランクを上げたり、院号を付けていただいた場合などに、別途「戒名料」や「院号料」が必要となります。
戒名料や院号料の相場は、宗旨・宗派や、ご寺院の格、または付けていただいた戒名の位によっても変わります。
次の表は、ご寺院に戒名をつつけていただいた場合の相場の一例です。
参考にしてください。
戒名は本位牌や過去帳にも記される
本位牌とは、仏壇に祀(まつ)られる、故人様の魂が宿っているとされる木製の位牌です。
この本位牌に、俗名(生前の名前)、没年月日、享年に加えて、故人様の戒名を記します。
なお、位牌の数が増えた場合には、三十三回忌や五十回忌など節目となるご法要で過去帳にまとめることが多いようです。
また、浄土真宗では位牌の代わりに過去帳を仏壇に祀ります。
家系図の意味合いも強く、普段は仏壇の引き出しに仕舞われているご家庭も多いことでしょう。
位牌については###ihai_toha###で詳しく説明しています。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は「戒名」とは何か、「法名」や「法号」との違いや、位と相場などについてご説明しました。
皆さまの参考になれば幸いです。
また、平安祭典では神戸・阪神間でのご葬儀・仏事などに関するご相談を受け付けております。
お困りごとがございましたら、平安祭典(0120-00-3242)まで気兼ねなくお問い合わせください。
続きはこちら
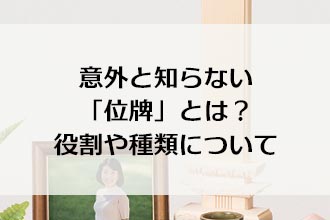
更新日:2024年9月22日 公開日:2022年3月7日
位牌(いはい)とは故人様の霊が宿る木の札で、仏壇に祀(まつ)られる大切な仏具です。
しかし「見たことあるけれど、実際にどのような役割を持つものなのかは知らない」という方も多いようです。
そこで今回は意外と知らない位牌についてご説明します。
礼拝の対象として用いられる位牌
そもそも位牌とはどのようなものなのでしょうか。
位牌とは、仏教においてご供養に用いる仏具で、表面に故人様の戒名(日蓮宗は法号)や俗名(生前の名前)、裏面に没年月日、享年を記した木の札のことです。
主に仏壇に安置され、故人様の依代(よりしろ=霊が宿る対象物)であり、礼拝の対象として用いられます。
ちなみに、位牌は中国の儒教にルーツを持つ風習であるとされ、日本では鎌倉時代から室町時代にかけて禅宗の聖職者が広め、江戸時代には一般庶民に普及したとされています。
なお、数え方は1本、1基などが使われることが多いですが、正しくは「柱(はしら)」で、1柱(ひとはしら)、2柱(ふたはしら)……と数えます。
浄土真宗では位牌の代わりに法名軸や過去帳を用いる
同じ仏教でも、浄土真宗では位牌を祀りません。
これらの宗派では「故人様の魂は亡くなるとすぐに成仏しているため、位牌を祀り礼拝の対象とする必要はない」という考え方があるからです。
浄土真宗では、位牌の代わりに法名軸(法名・没年月日を記した掛軸)や過去帳(法名・俗名・没年月日・享年を記した帳簿)を用います。
ただし、浄土真宗の中でも専修寺系の真宗高田派や地域によっては位牌を祀ることがあります。宗派が浄土真宗の場合には、事前にご寺院にご確認ください。
※浄土真宗では、戒名と呼ばず法名と呼びます。
※浄土真宗は、阿弥陀如来(阿弥陀仏)のみを礼拝の対象としているため、法名軸や過去帳は礼拝の対象ではありません。位牌を祀る真宗高田派においても同様で、礼拝の対象ではありません。
宗派につていは###shuuha_shuushi###で詳しくご説明しています。
位牌には大きく分けて3つの種類がある
位牌と聞くと、多くの方は仏壇に祀られているのをイメージするのではないでしょうか。それは「本位牌」と呼ばれるものです。
「本位牌」以外にも「白木位牌」「寺位牌」と、大きく分けて3つの種類が存在します。
この3つの違いについてもご説明します。
・白木位牌
「白木位牌」とは、故人様がお亡くなりになった直後に作られる仮の位牌で、「内位牌」とも呼ばれます。
文字通り白木(しらき=塗料などで加工しないそのままの木材)に、故人様の戒名や俗名、没年月日、享年を記します。
ご葬儀では祭壇に祀られ、ご葬儀後も中陰祭壇(忌明け法要までご遺骨を祀る祭壇)に安置されます。忌明け法要を迎えた後、「本位牌」に替えます。
あくまで四十九日法要までの仮の位牌が「白木位牌」です。
・本位牌
「本位牌」は塗り位牌とも呼ばれ、忌明け法要を迎えた後「白木位牌」に替わり、仏壇に祀られる
位牌のことです。
漆塗りに金箔・沈金・蒔絵などが施された、多くの方がイメージされるであろう位牌です。
四十九日になると故人の魂は成仏し、本位牌に移りますので、それまでに用意しておく必要があります。
ちなみに「本位牌」の作成には、文字彫り・文字書き、漆塗り・検品等に約2週間かかります。
「忌明け法要に間に合わなかった」ということのないよう早めに手配しておきましょう。
・寺位牌
「寺位牌」とは、菩提寺(壇那寺)や本山
(=宗派における特別なご寺院)に安置
するための位牌のことです。
檀家が「本位牌」とは別に「寺位牌」を祀る他、
様々な事情でご自宅に位牌を安置できない方や
永代供養を望まれる方が「寺位牌」を利用します。
平安祭典では各種位牌のご相談を承っています
いかがだったでしょうか。
今回は仏壇に祀られ、礼拝の対象となる位牌についてご説明しました。
皆さまのご参考になれば幸いです。
平安祭典では、ご葬儀・ご供養に関する各種ご相談を承っています。
神戸・阪神間でお困りごとがございましたら、平安祭典(0120-00-3242)まで気兼ねなくご相談ください。
続きはこちら
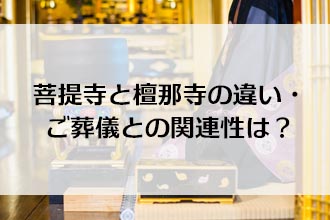
公開日:2022年2月28日
身内に不幸があった際には、私たちはまず家族や親族に連絡し、その後葬儀社や日頃からお付き合いのあるご寺院に連絡を入れます。
この日頃からお付き合いのあるご寺院のことを、「菩提寺(ぼだいじ)」や「檀那寺(だんなでら)」と呼びます。
皆さまに菩提寺や檀那寺がある場合、その存在はとても大切なものとなります。
今回は、菩提寺と檀那寺が、なぜ大切なのかをご紹介します。
菩提寺と檀那寺の違いとは?
まずは菩提寺と檀那寺の言葉の説明をしましょう。
菩提寺と檀那寺は、先祖代々のお墓がある、あるいはご葬儀やご法要を依頼するご寺院という意味として、区別せずに用いられることも多いのですが、厳密には、この2つの言葉の意味は異なります。
まず菩提寺とは、「そのご寺院の宗旨に帰依し、先祖代々のお墓がある、先祖の位牌を納めてあるご寺院」という意味を持つ言葉です。
一方、檀那寺とは、「そのご寺院の檀家となり、日頃から御布施などにより経済的に支えているご寺院」を意味します。
ちなみに「檀那」は古代インドの言葉「ダーナ」に漢字を当てたもので、「御布施」という意味を持ちます。
檀家としてあくまでもそのご寺院の経済活動を支える点が重要であり、必ずしも先祖代々のお墓は必要ありません。
ただ、先祖代々のお墓があり、先祖の位牌を納めていて、かつ檀家として日頃から御布施を行なっているご寺院がある場合には、そのご寺院は菩提寺でもあり檀那寺でもあると言えます。
菩提寺・檀那寺にご葬儀・ご法要を依頼する
ここからはご葬儀における菩提寺・檀那寺との注意点についてご案内します。
ご葬儀やご法要を執り行なう際には、菩提寺や檀那寺に依頼する必要があります。
日時・場所が決まれば、菩提寺・檀那寺のご都合を確認してください。
戒名は故人様の人となりやご趣味・ご職業などを考慮して決めていただけるので、何かご希望があればそのタイミングでご寺院に伝えます。
またその際、お越しになる僧侶の人数を確認しましょう。
なぜなら人数によって御布施の金額が変わってくるからです。
ご法要も菩提寺・檀那寺に連絡し、お経をあげていただきます。
遅くとも1ヶ月前、できれば1ヶ月半~2ヶ月前までにご法要の日時・場所を決めたら、ご寺院のご都合を確認します。
一般的に土・日・祝日やお盆の時期にはご法要を行なうご家庭が多く、どちらのご寺院も多忙になるため、早めに連絡しましょう。
いずれにせよ、菩提寺・檀那寺がある場合には、ご葬儀・ご法要の際は、必ず菩提寺・檀那寺に連絡しましょう。
菩提寺・檀那寺が遠方の場合も、まず連絡を
菩提寺・檀那寺が遠方にある場合でもご葬儀・ご法要を執り行なう際には必ず連絡しましょう。
連絡をした際には、以下の4通りのご回答があるかと思います。
1. 遠くても私が行きます
2. 遠方なので、近隣で付き合いのあるご寺院をご紹介します
3. 葬儀社で紹介してもらってください
4. 戒名はこちらで授けますが、その後は葬儀社でご紹介のあったご寺院に来てもらってください
なお、ご寺院から3・4のようなお返事をいただいた場合には、当社から同じ宗派のご寺院をご紹介いたします。
菩提寺・檀那寺がない、分からない場合にはどうすれば良い?
元々菩提寺や檀那寺がない、あるいはわからない場合もあります。
分からないからといって、そのまま別のご寺院に来ていただいたり、違った宗旨宗派でご葬儀をあげてしまったり…といったことがあってはなりません。
分からない場合は、必ずご親族に確認をしましょう。
ご親族に確認を取るとすぐに菩提寺や檀那寺が判明することも少なくありません。
その他にも、戒名から宗派を推測する方法があります。
実家にある仏壇の掛軸や位牌に書かれている戒名、あるいは墓誌(お墓の横に建てられている石碑)に掘られている戒名を確認することで、宗派や菩提寺・檀那寺を把握する手がかりになります。
それでも不明な場合には、葬儀社に相談しましょう。
宗派については###shuuha_shuushi###で詳しく説明しています。
先祖代々のお墓があっても、納骨ができないことも
いかがだったでしょうか。
今回は、菩提寺・檀那寺についてご説明しました。
菩提寺・檀那寺に関しては、本当はそれらがあるのにも関わらず、別のご寺院でご葬儀を執り行なってしまった、宗派が異なるご寺院に頼んでしまったというトラブルも存在します。
このようなケースでは、先祖代々のお墓があっても、納骨ができないこともありうるので注意しましょう。
平安祭典では神戸・阪神間でのご葬儀・ご法要などに関するご相談を受け付けております。
菩提寺・檀那寺に関するご相談も承っておりますので、お困りごとがございましたら、0120-00-3242まで気兼ねなくお問い合わせください。
続きはこちら
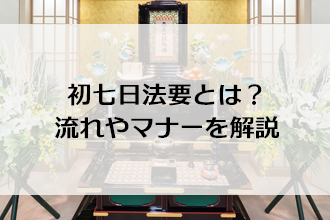
公開日:2022年2月21日
身近な方のご葬儀に際して、初めて葬儀や仏事についてお考えになったり調べたりされるという方がほとんどではないでしょうか。
慶弔の行事は、土地柄や宗派などによって考え方が違ったり、ライフスタイルの変化によって古くからの慣習が変化したりすることも多々あります。
当記事では、現在行なわれている一般的な「初七日法要」について解説いたしますので、参考になさってください。
初七日とは?
宗旨・宗派にもよりますが、仏教には「人は亡くなると魂になり冥途へ行き、生前の行ないについての裁きを受け、次に生まれる世界が決まる」という考えがあります。
冥途での裁きは一七日、二七日、三七日、四七日、五七日、六七日、七七日と、7日おきに7回行なわれ、七七日=四十九日目に最後の審判官である泰山王によって故人様の次の行き先が決められます。
一七日(ひとなのか)のことを通称「初七日(しょなのか)」といい、この日は故人様が亡くなられてから最初の審判を受ける重要な日です。
初七日とは、具体的に、故人様の魂が三途の川のほとりにたどり着く日とされています。
日数の数え方については、地域により違いがありますが、関東では亡くなった日から数えて7日目、関西では亡くなる前日から数えて7日目を「初七日」とすることが多いようです。
裁きによって、三途の川の橋(緩やかな瀬)を渡るのか激流の深みを渡るのか決まるのですが、この裁きは故人様にとって非常に厳しいものになるかもしれません。
仏教では小さな虫を殺すことや飲酒も戒めとされるため、故人様が無事に三途の川を渡れるよう「追善供養」という形でこの世から援護を行なうのです。
「追善供養」とは、生きている我々が故人様のことを想い善行を積むことで、具体的には法要はもちろん日々仏壇に手を合わせたりお墓参りをすることもこれにあたります。
初七日法要の流れ
前述のように、故人様がより良い審判を受けられるように、ご親族が行なう追善供養のひとつが「初七日法要」です。
近年では、この初七日法要を本来の日程より繰り上げるかたちで、ご葬儀の当日に行なうことが主流となっています。
これは昔と違い、親戚縁者が必ずしも近くに住んでいるわけではないことや、仕事の休みがとりにくいなど、現代ならではの事情によるものでしょう。
初七日法要をご葬儀と同日に行なう場合、どのようなスケジュールになるのか、一例をご紹介します。
葬儀・告別式
↓
ご出棺
↓
火葬場で故人様を炉に納める
↓
骨あげ
↓
仕上げ料理
↓
初七日法要(葬儀会館、寺院、自宅など)
↓
解散
ご寺院によって異なりますが法要の時間は約30~60分で、途中にご遺族や参列者にご焼香のご案内があります。
また、火葬場から還ってきたご遺骨をお迎えする「還骨勤行(かんこつごんぎょう)」も初七日法要とあわせて行なうことが多いです。
ご葬儀当日に初七日法要を行なう場合のスケジュールをご紹介しましたが、法要をその日のうちに済ませてしまうのはあくまでも供養する側(ご親族・ご寺院)の都合です。
故人様が審判を受ける正式な「初七日」には、線香や焼香などとともに手を合わせましょう。
なお、初七日法要をご葬儀とは別の日に行なう場合は、早急に場所を決めて参列者にお声がけをする必要があります。
場合によっては、法要後の会食などの準備も必要となるのでご注意ください。
初七日法要のマナーについて
続いては、初七日法要のマナーをご紹介します。
服装やお布施について、心配な点をご確認ください。
初七日法要での服装は?
ご葬儀の後、初七日法要をその日のうちに行なう場合は、特に着替えなどは必要なく、服装はご葬儀のままの喪服で問題はありません。
初七日法要を後日行なう場合も、喪服やそれに準ずる服装で参列しましょう。
ただし、自宅で身内のみが集まりご法要をする場合などは、私服に近い服装で参列する方も多いようです。
ご葬儀、ご法要に関する身だしなみについては###sougi_midashinami###でも詳しくご紹介しているので、あわせてご覧ください。
お布施の相場はどれくらい?
御布施については、まずはご寺院へ確認されることをおすすめします。
あくまで一例ですが、初七日法要のお布施だと相場は3~5万円ほどです。
ご葬儀と別の日に行なう場合、御布施のほか御車料・御膳料も必要となります。
参列者のお供えや御香典は必要?
ご葬儀と同日に初七日法要を行なう場合、参列者からのお供えや御香典の準備は、あると良いですが、絶対ではありません。
お気持ちでされるものでもあり、なくても失礼にはあたりません。
とはいえ、ご葬儀に参列される時点では初七日法要を同日中に行なうかどうか分からない場合もあります。
また、ご葬儀から一貫して御香典を辞退している場合もあるでしょう。
初七日の御香典を迷うようであれば、念のためご準備しておくことをおすすめします。
御香典をご準備される際は###kouden_manner###の記事もぜひご参考になさってください。
どんな間柄の人が初七日法要に参列する?
初七日法要への参列者について、特に決まりはありませんが、ほとんどの場合はご親族・ご親戚のみの参列が一般的です。
ご葬儀と同日に初七日法要をする場合は特に、参列されたご親族が、火葬場への見送り、お骨あげ、その後の初七日法要と、そのまま参加することが多いようです。
日を改めてご法要を行なう場合には、上記のような「参列の見込みがあるご親族・ご親戚」を中心に日時と場所をお伝えしたうえで、出欠の確認をするのが望ましいでしょう。
なお、地域によっては、ご親族に限らず職場関係、ご友人など、広くお声掛けをしてご法要を行なう場合もあるようです。
ご心配なようなら、ご葬儀の経験があるご親族や、葬儀社にご親族内の決まり事や地域の風習などを確認することをおすすめします。
まとめ
当記事では初七日法要についてご紹介しました。
「初七日」は仏教ならではの考え方に基づくもので、非常に奥の深いものです。
ですがご親族・参列者がともに心から故人様を想い、手を合わせることが何よりの供養となるでしょう。
ご葬儀の後に続けて初七日法要を行なうという様式への変化で、負担なくより多くの方にご参列いただけるようになりました。
当記事がご葬儀や法要をどのように行なうかの参考となれば幸いです。
平安祭典ではご要望を細かくお聞きしながら、思い通りのご葬儀を執り行えるよう、お手伝いさせていただきます。
お悩み、ご不安な点などありましたら、気兼ねなく平安祭典(0120-00-3242)までご相談ください。
続きはこちら
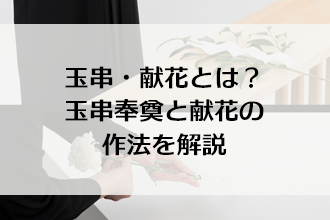
公開日:2022年2月14日
皆さまはご葬儀に参列した際に、玉串奉奠や献花をしたご経験をお持ちでしょうか?
どちらも参列者が行なう故人様とのお別れの儀式で、仏式の「焼香」にあたるものが、神式では「玉串奉奠」、キリスト教式では「献花」です。
とはいえ、「玉串って何だろう?」「玉串奉奠や献花の作法が分からない」という方は多いかもしれません。
そこで当記事では、玉串を捧げる意味や、玉串奉奠と献花の具体的な作法を解説します。
焼香に関しては###shoukou_yarikata###の記事で詳しくご紹介しております。
玉串とは?
玉串とは、榊の枝に紙垂(しで)と呼ばれる紙、または木綿(ゆう/楮こうぞを原料とした布)をつけたものです。
神道の行事や儀式において、斎主や参列者が神前に供えます。
神様のお食事としてお供えする御神饌(ごしんせん/米や酒、塩、魚など)と同じ位置づけです。
玉串の由来は、日本の神話にさかのぼります。
『古事記』の天岩戸のくだりで、お隠れになった天照大神のお出ましを願い、神々は榊に玉や鏡をつけて捧げました。
この話に由来するといわれる玉串は、古来より神様が宿る依代ともされ、神様と人とをつなぐ橋渡しとしての役目も持つといいます。
ちなみに、玉串は榊の枝で作られることがほとんどです。
神棚の両脇にお祀りしてある緑の葉がついた枝をご覧になったことがあるかと思いますが、あれが榊です。
榊は木偏に神と書く通り、神道行事には欠かません。
榊の語源には諸説ありますが、常に緑が生い茂り栄える木=「栄木(さかき)」、また神様の世とこの世の境の木=「境い木(さかいき)」が転じたという説が有力です。
榊は古くから生命力と繁栄の象徴とされてきました。
その榊につける紙垂とは、ギザギザに折られた白い紙のことです。
紙垂には「神聖」「清浄」の意味があり、これをつけることで、榊の枝が神様の依代(神霊がよりつくもの)としての意味を持ちます。
神社の注連縄(しめなわ)や、神職の持つ祓串(はらえぐし)に紙垂がついているのも、そういった理由からです。
※諸説ありますが、紙垂は白い紙を交互に割くことで無限大を表すとされ、神様の力を一片ずつの紙に宿すものといわれています。
玉串奉奠の流れ
神道の儀式のなかで、玉串を神前に供えることを玉串奉奠といいます。
玉串奉奠は玉串を奉奠する儀式のことです。
「奉奠」という漢字の意味を見ていただくと、分かりやすいかもしれません。
「奉」=たてまつる、恭しく(うやうやしく)差し上げる
「奠」=神仏などへの供え物、供物
神事の手引書『神社祭式同行事作法解説』(神社本庁編)によると、「玉串は神に敬意を表し、神威を受けるために祈念をこめて捧げるもの」だそうです。
そのため、玉串奉奠はご葬儀だけでなく、結婚式や地鎮祭、お宮参りなどの祈祷の際にも行なわれます。
慶弔に関わらず行なわれる重要な作法ですので、流れを把握しておかれると役に立つかもしれません。
ご葬儀の場合、一般的には式の終盤に案内されることが多く、斎主が玉串奉奠を行なった後に喪主、続いてご遺族・ご親族、一般の参列者と、故人様と関係性の深い順に行ないます。
玉串奉奠の作法(ご遺族の場合の一例)
① 式場の皆様の方を向き会釈をします。玉串を受け取り、軽く一礼をします。
② 玉串案(台)の手前まで進み、神前に一礼をします。枝先が神前に向くように玉串を右回りに90度回転させます。
③ その後、玉串を垂直に立てて祈念をします。
④ 枝元が神前に向くように右回りで回転させ、玉串案(台)に静かに捧げます。
⑤ 祭壇に向かい二礼二拍手一礼(二拝二拍手一拝)をします。そして、一歩下がり式場の皆様の方を向き、会釈をして席に戻ります。
なお、この時の拍手は音を立てない「しのび手」で行ないます。
一般的にはこのような作法で行なわれますが、宗旨・宗派によって作法が異なる場合もあります。
気になる場合は確認されると良いでしょう。
献花の流れ
「献花」は海外の葬儀ではあまり行なわれない日本独自の慣習で、キリスト教式のご葬儀の場合、カトリック・プロテスタントのどちらでも行なわれます。
献花の作法(ご遺族の場合の一例)
① 式場の皆様の方を向き会釈をします。献花を受け取り、軽く一礼をします。
② 献花台の手前まで進み、献花を胸元まで引き寄せ、心をこめて祈念をします。
③ 献花を持ち替え、茎が霊前に向くようにします。
④ 献花台に静かに捧げます。そして祭壇に向かい黙祷を捧げ、礼拝をします。
⑤ そして、一歩下がり式場の皆様の方を向き、会釈をして席に戻ります。
※上記の作法は一例です
キリスト教では「死」に対する考え方が仏教や神道とは異なり、死は穢れや縁起が悪いことではなく、神の元へ召される祝福すべきこととされています。
死は命の終わりではなく、永遠の命の始まりで、故人様への「献花」はその門出に捧げるものなのです。
まとめ
当記事では、玉串や玉串奉奠、献花についてご紹介しました。
大まかな流れを掴んでおけば落ち着いて対応できると思いますが、心を込めて行なうことが何より大切ではないでしょうか。
平安祭典では、神式やキリスト教式の葬儀のご相談もお受けしています。
お困りごとやお悩みがありましたら、ご遠慮なく平安祭典(0120-00-3242)までご連絡ください。
続きはこちら
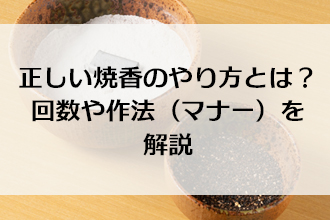
公開日:2022年2月7日
故人様との最後のお別れの場となるご葬儀は、ご遺族やご親族、そして、参列される方々にとって大切な儀式です。
しかし、ご葬儀では、マナーや作法が分からず戸惑われることもあるかと思います。
その中でも焼香(しょうこう)は、宗旨・宗派によって作法が異なるため、難しいイメージを持たれる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、焼香について、意味や作法などをご紹介します。
焼香は仏教的な意味を持つ
焼香とは、ご葬儀やご法要において、お香の1つである「抹香(まっこう)」を使って行なう儀式のことです。
「抹香」とは細かく砕いた粉末状のお香で、これを少量指でつまみ、香炉(こうろ)にくべます。
ご葬儀やご法要でお香を焚くことは、邪気を払って不浄を遠ざけ、また自身の心身を清めるという意味合いがあります。
ちなみに仏教では、お香の香りは仏様や故人様の食べ物と同じであると考えられているため、お香を焚くことは、仏様や故人様に食べ物を捧げるという意味も持ちます。
焼香は、仏教発祥の地で、香木(こうぼく)の産地としても知られるインドから各地へ伝わりました。
日本へは、仏教と同じく6世紀頃に伝来したと考えられています。
インドは高温多湿の地域ということもあり、ご葬儀の際に、ご遺体の腐敗臭を消す目的でお香を焚くようになったそうです。
また、お釈迦様が説法をする際に、集まった人々の体臭が気になったため、元々体臭を消すために用いていたお香を焚いたという説もあります。
焼香は本来仏教においてお香(こう)を焚くこと全般を指します。
このような経緯もあり、焼香は仏教ととても結びつきが強い儀式です。
なお、神式では焼香の代わりとして、玉串を神前に捧げて拝礼する「玉串奉奠(たまぐしほうてん)」、キリスト教式では花を供える「献花」などが行なわれます。
玉串・献花に関しては###tamagushi_kenka###で詳しくご説明しております。
宗旨・宗派ごとに異なる焼香の作法
仏式においては、宗旨・宗派によって焼香の作法が異なります。
ここでは、焼香の流れの一例をご紹介します。
1. 焼香台に近づき、式場の皆様に一礼。その後、祭壇の方を向きます。
2. ご本尊に向かい、もう一度、一礼をします。
3. 右手の親指・中指・人差し指で、お香をこぼさない程度に少量つまみ、静かに香炉にくべます(作法は宗旨・宗派により異なります)。
4. 数珠を両手にかけ、心をこめて合掌をします。その後、一歩下がり式場の皆様の方を向き、一礼して席に戻ります。
ご親族でも、一般の参列者でも、焼香の作法や大まかな流れは特に変わりません。
ただし、参列の人数が多い場合など、席に戻る前の参列者への一礼を割愛したり、焼香の際の順路が決められていることもあります。
その場合は、葬儀社のスタッフの誘導に従ってお進みいただくと良いでしょう。
また、式場の皆さまに向かっての一礼は、ご親族なら一般の参列者に向かって、逆に、一般の参列者ならご親族に向かってするようにご案内されることもあります。
次に、宗旨・宗派ごとの焼香の回数と唱える言葉をご紹介します。
・ 浄土真宗本願寺派(西本願寺)
お香は額に捧げずに1回。
「南無阿弥陀仏」と唱えます。
・ 浄土真宗大谷派(東本願寺)
お香は額に捧げずに2回。
「南無阿弥陀仏」と唱えます。
・ 浄土宗
お香を額に捧げます。
回数は特に決まっていません。
「南無阿弥陀仏」と唱えます。
・ 真言宗
お香を額に捧げて3回。
「南無大師遍照金剛」と唱えます。
・ 日蓮宗
お香を額に捧げて3回。
「南無妙法蓮華経」と唱えます。
・ 日蓮正宗
お香を額に捧げて3回。
「南無妙法蓮華経」と唱えます。
・ 曹洞宗
お香を額に捧げて2回。
ただし、2回目は額に捧げません。
「南無釈迦牟尼仏」と唱えます。
・ 臨済宗
お香を額に捧げます。
回数は特に決まっていません。
「南無釈迦牟尼仏」と唱えます。
・ 天台宗
お香を額に捧げます。
回数は特に決まっていません。
「南無妙法蓮華経(朝)南無阿弥陀仏(夜)」と唱えます。
・ 時宗
お香を額に捧げます。
回数は特に決まっていません。
「南無阿弥陀仏」と唱えます。
・ 創価学会(友人葬)
お香は額に捧げて3回。
「南無妙法蓮華経」と唱えます。
宗旨・宗派によって焼香の回数が異なるのは、焼香に込められた意味が変わってくるからだとされています。
例えば、焼香を1回する場合には、「一に帰る」という仏教の死に対する教えに基づいたもの、2回は主香(しゅこう)と従香(じゅうこう)という考え、3回は仏教で3の数字が大事とされている点に基づくと考えられています。
宗旨・宗派に関しては###shuuha_shuushi###で詳しくご説明しております。
3種類の焼香の方法
焼香の方法には、ご葬儀が行なわれる場所や規模に合わせて、「立礼焼香」、「座礼焼香」、「回し焼香」と呼ばれる3種類の方法があります。
葬儀会館で行なわれる通夜、葬儀・告別式では、立った状態で行なう立礼焼香が選ばれることがほとんどです。
なお、先ほどご紹介した焼香の作法の一例も、立礼焼香での作法となっていまなす。
・ 立礼焼香
ご遺族や会葬者が、順番に立ち、焼香を行ないます。
ご自身の順番が回ってきたら、席を立って遺影・焼香台の前へと進み、焼香が終わったら着席します。
・ 座礼焼香
和室でご葬儀が行なわれる場合は、順番に遺影の前で座った状態で焼香を行なう座礼焼香となります。
遺影・焼香台の前まで移動する際には、中腰で移動するのがマナーです。
・ 回し焼香
ご自宅などの狭い場所で行なう場合、お盆などに乗せて香炉を回し、順番に座ったまま焼香を行ないます。
焼香の順番の決め方と注意点
焼香の順番については、まず初めに喪主が行ない、以降は故人様との血縁の濃い順に行なうのが一般的です。
故人様と同居か別居かなどによっても順番が変わってきますが、明確な決まりはありません。
ご葬儀の際には、ご親族の方はある程度焼香の順に座っておくと良いでしょう。
なお、一般参列者は座った席順に前列から焼香を案内されますが、最前列など、来賓席として座る方が指定されている場合もあるのでご注意ください。
焼香の順番については、ご遺族とご親戚のあいだで、ごくまれにトラブルになることもあります。
トラブルを避けるためにも、事前にご親族間で話し合っておくと良いでしょう。
留め焼香とは?
関西地方を中心とした西日本のご葬儀では「留め焼香(止め焼香)」という習慣があります。
これは、兄弟姉妹など、故人様にとって血縁の濃い人が、あえて最後に焼香を行なう方法です。
留め焼香には、ご親族や参列者に焼香の順番に不備があったとしても、納得してもらうという意味合いや、「不幸を止める」という意味合いが含まれています。
大事なのは真心をこめて焼香すること
いかがだったでしょうか。
今回は、焼香に関する知識についてご紹介しました。
特に焼香の「作法」に関しては宗旨・宗派により決まりはあるものの、実際のご葬儀では、参列者の人数や進行状況により、焼香の回数を1回で済ませることも少なくありません。
また、同じ宗旨・宗派でもご寺院によって異なる場合もあります。
作法に従うことも大切ですが、何より大切なのは真心をこめて焼香し、故人様をご供養することです。
形式に縛られすぎず、故人様との最後の時間をお過ごしください。
神戸・阪神間での仏事に関するご質問がございましたら、平安祭典(0120-00–3242)までお問い合わせください。
続きはこちら