

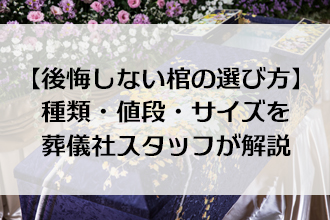
公開日:2022年4月25日
棺とは故人様をお納めするもので、故人様が最後に眠る場所ですのでこだわって選びたい方も多いでしょう。
しかし、素材、形、デザインなど実にさまざまな種類の棺があるため、どれを選ぶか迷ってしまうかもしれません。
そこで、この記事では棺の種類、値段、サイズなどについて解説します。皆さまが納得のいく棺を選ぶ一助となれば幸いです。
棺の意味や歴史について詳しくは、###hitsugi_toha###をご覧ください。
[@目次@]
棺の種類(素材)と値段について
棺には大きく分けて木棺と布棺の2つがあります。そしてもうひとつ、近年注目されてきているのがエコ棺(特殊な合成紙製)です。
ここからは、それぞれの特徴をご紹介していきます。
■木棺:約2万5千円~約10万円
棺として最もベーシックなタイプが木製の「木棺」です。
おそらく「棺」というと、多くの方は木でできた長方形の箱型のものを思い浮かべるのではないでしょうか。
「棺」を代表するシンプルな木棺は、天然木や木目のプリントをベニヤ板に張り付けたものです。
少し高額なものだと天然木で作られた棺もあり、多くの場合、材質には檜・桐・杉などが使われています。
そのほか丸みを帯びた蓋が付けられたものや、ダイナミックな彫刻が施されたものなど、木棺のデザインは多彩です。
また高級感のあるプレミアム棺として、家具のようなデザインの「家具調棺」などもあり、祭壇を重厚感漂う空間にしてくれます。(約30万円~約50万円)
木ならではの温もりや、力強い木彫の実直な雰囲気など、故人様のイメージに合わせてお選びいただくと良いでしょう。
■布棺:約10万円~20万円
布棺とは、合板に綿・絹・麻などの布地を張ったもので、布張棺ともいわれます。
繊細な刺繍や織り柄、華やかなプリント、光沢のあるベルベット調など、布棺は色や柄で大きく印象が変わるのが特徴です。
女性には優美な刺繍、男性ならすっきりと白い織り柄など、性別や故人様のお好み合わせたり、色や柄に季節感を取り入れると、良いかもしれません。
■エコ棺(特殊な合成紙製):約15万円
「エコ棺」とは段ボール製の棺です。
表面は布張りされているので、一見しただけでは段ボールとはわかりません。
メリットはたくさんありますが、特筆すべきはご遺骨がきれいに残りやすい点です。
釘や金具を一切使用していないので、ご遺骨の周りに燃えカスが黒く残ることがありません。
間伐材を使って作られており、燃焼時間が短いため、環境に優しいという面も今の時代に合うのではないでしょうか。従来の棺と比較すると、CO2排出量を40%削減できます。
棺のサイズも大切なポイント
古くから棺のサイズは「尺」で表されてきました。
現在、一般向けに作られた資料などには尺貫法の表記はあまり見られません。
棺のカタログには、たいてい外寸・内寸がcmで記載されています。棺のサイズは一律ではないので、故人様の身長に合ったサイズを選ぶと良いでしょう。
人は亡くなった後つま先が伸び、背伸びした状態になります。従ってベストのサイズは、棺の内寸が故人様の身長+10~15cmです。
また火葬場の炉にもサイズがあり、普通棺と大型棺(巨人棺)などに分けて受け入れられているのが一般的です。
棺の大きさ(外寸)によって、使用する炉の種類が異なりますが、一般的な棺が炉に入らないことはまずありません。
各火葬場では対応可能な棺のサイズが設定されていますが、あまり気にする必要はないでしょう。
まとめ
当記事では棺の種類についてご紹介しました。
棺は故人様が最後の時を過ごす空間であり、ご遺族・参列者の皆さまが故人様を目にする最後の場です。
故人様のお好みやお人柄にあわせたり、祭壇のデザインにあわせると良いかもしれません。また、想い出のシーンをイメージして選ぶのも良いでしょう。
平安祭典では、多くの棺の中からイメージにあうものをご提案しております。
事前相談も受け付けておりますので、気兼ねなく平安祭典(0120-00-3242)までご相談ください。
少しでも故人様のお人柄や弔いの気持ちが感じられる空間となるよう、お手伝いさせていただきます。
続きはこちら
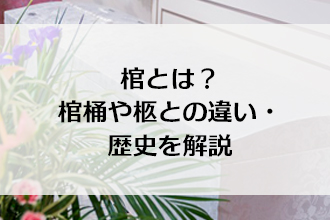
公開日:2022年4月18日
故人様との最後のお別れは、ご遺体が棺に納められた状態で行ないます。
現代の日本で使われる棺は、素材や形など実にさまざまな種類がありますが、どのような棺でも故人様を仰向けでお納めするところが共通点です。
この記事では、棺がどういうものなのか、棺の歴史などをご紹介します。
平安祭典で取り扱う棺もご紹介しますので、ぜひご確認ください。
棺の選び方や種類については、###hitsugi_syurui###で詳しく解説しています。
棺とは?棺・柩・棺桶の違いは?
「ひつぎ」と読む漢字の代表的なものは、「棺」と「柩」の2つです。
辞書を引くと、どちらも「遺体を納めるための箱」と説明されていますが、2つの漢字は次のように少し違った意味を持ちます。
棺:ご遺体が入っていない空の状態の「ひつぎ」
柩:ご遺体が納められた状態の「ひつぎ」
棺はご遺体が入っていない状態なので、ご遺体を納める納棺には「棺」という字が使われます。一方、ご遺体の納められた柩を運ぶ霊柩車には「柩」という字が使われます。
このように同じ「ひつぎ」ですが、ご遺体の有無で使い分けられています。
ちなみに「ひつぎ」を表すものに「棺桶(かんおけ)」という言葉もありますが、これはその昔、桶状の棺が使われていたことに由来しています。(明治期に入るまでは、棺といえば通常は桶型でした。)
今と昔でどう違う?棺の歴史について
古くから日本の棺には、大きく分けて「寝棺(ねかん)」と「座棺(ざかん)」がありました。
「寝棺」は仰向けに寝かし足を延ばした状態で、「座棺」は手足を折り曲げた状態でご遺体が納められます。
寝棺と座棺以前には甕棺(かめかん)もあり、縄文~弥生時代には棺として甕形(かめがた)の土器が使われていました。(棺の歴史としては甕棺→座棺→寝棺と変遷しました)
身分の高い人の墳墓では古代から寝棺が使われていましたが、一般的な棺としては長く座棺が使われていたようです。江戸時代になると、その大半は木製の桶型だったようです。
明治時代に入り、富裕層が寝棺を使用するようになりました。戦後、火葬の一般化と火葬炉の近代化に伴って、寝棺が主流となりました。
現在の日本における、葬送の火葬率は99.9%です。このように寝棺の形状は、火葬の文化とも関係しています。
火葬について詳しくは、###kasou_toha###をご覧ください。
平安祭典の棺をご紹介
ここからは一例として、平安祭典の棺をご紹介いたします。
平安祭典ではさまざまな素材・形の棺をご用意しております。
価格は、木棺であれば2万5千円~10万円ほどが相場です。
オーソドックスな棺は、平らな蓋の四角い「平型棺」や、蓋に台形の膨らみを持たせた「山型棺」などです。
平安祭典が取り扱う棺の中から、代表的なものをいくつかご紹介します。
■きんもくせい
蓋が平らになったスタンダードな平型の木棺。
シンプルで主張しすぎず、落ち着いた印象です。
■シエル
天国へといざなう風をイメージしてデザインされた棺です。
丸みを帯びた蓋がエレガントで、マットな質感の白に気品が感じられます。
■モビリエ
滑らかな肌触りが特徴のタモ材を使用し、ダークブラウンのカラーには高級感と風格があります。
さざ波をイメージした側面のデザインも秀逸です。
■瑠璃華
華道家・假屋崎省吾氏プロデュースの華麗な棺。
実物の花は黄色ですが、金にすることで高貴で華やかなデザインにされています。
高貴な瑠璃色の生地に、金に輝く群雀蘭を施し、華やかでドラマチックなデザインです。
■鳳凰
匠の技で丹念に施された彫刻が迫力の総桐棺です。
釘を使わず組み木で仕上げられ、細部にまでこだわりが感じられます。
■胡蝶蘭
側面・上部・窓にあしらわれた胡蝶蘭は、故人様を柔らかに包み込むようです。
白を基調とした落ち着いた色合いで、年齢や性別を問わずご利用いただけます。
■やさしい棺
釘や金具を一切使用していないので、ご遺骨を傷つけることがなく、きれいな状態で収骨できます。
間伐材の使用や燃焼時間の短縮など、環境への配慮もされた棺です。
棺に入れるものに関する注意点
棺には副葬品として、故人様愛用の品、想い出の品などを一緒に納めます。
必ずしも副葬品を入れる必要はありませんが、想いのこもった品々をたむけることが一般的です。
ただし、副葬品には入れられるものと入れられないものがあるのでご注意ください。
基本的に燃やせるものは入れても良いのですが、金属・ガラス・プラスチックなど、燃えないものや燃やすのに時間がかかるものは入れられません。
副葬品については###fukusohin_toha###の記事で詳しくご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。
まとめ
当記事では、棺についてご紹介いたしました。
棺は、故人様をお納めする大切なものです。心を込めて選ばれると、故人様とのお別れが少しでも豊かなものになるのではないでしょうか。
棺だけでなくご葬儀についてのお悩みやご不安がございましたら、お気兼ねなく平安祭典(0120-00-3242)までお問い合わせください。
心に残るお別れのお手伝いさせていただきます。
続きはこちら
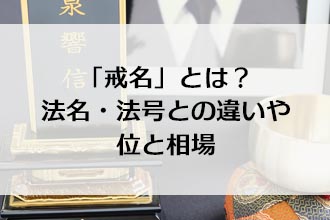
公開日:2022年3月14日
仏式のご葬儀では、故人様に「戒名(かいみょう)」が授けられます。
また、この戒名に似た言葉に「法名(ほうみょう)」や「法号(ほうごう)」というものがあります。
今回は「戒名」とは何か、「法名」や「法号」との違いや位と相場などについてご説明します。
「戒名」と「法名」、「法号」の違いとは?
まずは皆さまも馴染み深い「戒名」からご説明します。
「戒名」とは、故人様が釈迦(しゃか)の弟子、すなわち仏弟子(ぶつでし)になった証として、ご寺院から授けられる名前のことです。
戒名は、ご寺院がご葬儀までに授けるのが一般的です。
仏教の多くの宗派では、この「戒名」という言葉を用いますが、この「戒」という字は「戒律」という言葉からきています。
つまり、「戒律を守り、仏弟子となる証としての名前」が戒名なのです。
一方で、浄土真宗の教えにはこの戒律が無いため、仏弟子として授けられる名前は戒名ではなく「法名」といいます。
また、日蓮宗では「法号」と呼び、これも戒名と同じくご寺院から名前が授けられます。
ちなみに「戒名」や「法名」、「法号」は故人が授かる名前という認識の方が多いかもしれませんが、本来は生前にご寺院から授かる仏教徒としての名前です。
「戒名」と「法名」、「法号」の付け方と構成
「戒名」と「法名」、「法号」の付け方についてもご説明します。
宗派によって若干の差異はあるものの、基本的な構成はほとんど同じで、「院殿号・院号」「道号」「戒名」「位号」の4つとなります。
ひとつずつ見ていきましょう。
・ 院殿号・院号
主にご寺院や社会の発展などに大きく貢献した方には、戒名の最高位「○○院殿」「○○院」などが与えられます。
・ 道号
「道号」とは、悟りを開いた方に与えられる称号のことです。
基本的には2文字で、生前の職業や人柄、性格や趣味などが分かる称号が与えられます(浄土真宗では使用しません)。
・ 戒名
故人が仏門に入った証として与えられる称号です。
一般的には2文字で、生前の本名から1文字付けることが多いです。
浄土真宗では「釋(釋尼)○○」と表記します。
・ 位号
俗名であれば「様」にあたる部分で、故人の性別や年齢によって異なる称号です。
男性は「○○居士」「○○信士」、女性は「○○大姉」「○○信女」、子供であれば「〇〇童子」や「〇〇童女」などが用いられます(浄土真宗では使用しません)。
「戒名」と「法名」、「法号」に使用される文字は漢字のみですが、真言宗では、戒名の前に梵字(※)がつきます。
※ 梵字とは古代インドのサンスクリット語を書き表す文字のことで、真言宗ではこの梵字の「ア」(「阿字」とも)は、ご本尊である大日如来を表します。
戒名の位と相場
戒名・法名・法号を授けていただくことに対する御礼は、御布施に含まれていることが一般的です。
位号のランクを上げたり、院号を付けていただいた場合などに、別途「戒名料」や「院号料」が必要となります。
戒名料や院号料の相場は、宗旨・宗派や、ご寺院の格、または付けていただいた戒名の位によっても変わります。
次の表は、ご寺院に戒名をつつけていただいた場合の相場の一例です。
参考にしてください。
戒名は本位牌や過去帳にも記される
本位牌とは、仏壇に祀(まつ)られる、故人様の魂が宿っているとされる木製の位牌です。
この本位牌に、俗名(生前の名前)、没年月日、享年に加えて、故人様の戒名を記します。
なお、位牌の数が増えた場合には、三十三回忌や五十回忌など節目となるご法要で過去帳にまとめることが多いようです。
また、浄土真宗では位牌の代わりに過去帳を仏壇に祀ります。
家系図の意味合いも強く、普段は仏壇の引き出しに仕舞われているご家庭も多いことでしょう。
位牌については###ihai_toha###で詳しく説明しています。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は「戒名」とは何か、「法名」や「法号」との違いや、位と相場などについてご説明しました。
皆さまの参考になれば幸いです。
また、平安祭典では神戸・阪神間でのご葬儀・仏事などに関するご相談を受け付けております。
お困りごとがございましたら、平安祭典(0120-00-3242)まで気兼ねなくお問い合わせください。
続きはこちら
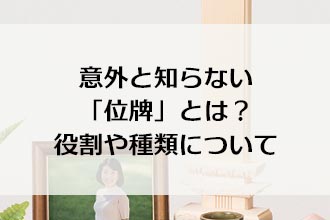
更新日:2024年9月22日 公開日:2022年3月7日
位牌(いはい)とは故人様の霊が宿る木の札で、仏壇に祀(まつ)られる大切な仏具です。
しかし「見たことあるけれど、実際にどのような役割を持つものなのかは知らない」という方も多いようです。
そこで今回は意外と知らない位牌についてご説明します。
礼拝の対象として用いられる位牌
そもそも位牌とはどのようなものなのでしょうか。
位牌とは、仏教においてご供養に用いる仏具で、表面に故人様の戒名(日蓮宗は法号)や俗名(生前の名前)、裏面に没年月日、享年を記した木の札のことです。
主に仏壇に安置され、故人様の依代(よりしろ=霊が宿る対象物)であり、礼拝の対象として用いられます。
ちなみに、位牌は中国の儒教にルーツを持つ風習であるとされ、日本では鎌倉時代から室町時代にかけて禅宗の聖職者が広め、江戸時代には一般庶民に普及したとされています。
なお、数え方は1本、1基などが使われることが多いですが、正しくは「柱(はしら)」で、1柱(ひとはしら)、2柱(ふたはしら)……と数えます。
浄土真宗では位牌の代わりに法名軸や過去帳を用いる
同じ仏教でも、浄土真宗では位牌を祀りません。
これらの宗派では「故人様の魂は亡くなるとすぐに成仏しているため、位牌を祀り礼拝の対象とする必要はない」という考え方があるからです。
浄土真宗では、位牌の代わりに法名軸(法名・没年月日を記した掛軸)や過去帳(法名・俗名・没年月日・享年を記した帳簿)を用います。
ただし、浄土真宗の中でも専修寺系の真宗高田派や地域によっては位牌を祀ることがあります。宗派が浄土真宗の場合には、事前にご寺院にご確認ください。
※浄土真宗では、戒名と呼ばず法名と呼びます。
※浄土真宗は、阿弥陀如来(阿弥陀仏)のみを礼拝の対象としているため、法名軸や過去帳は礼拝の対象ではありません。位牌を祀る真宗高田派においても同様で、礼拝の対象ではありません。
宗派につていは###shuuha_shuushi###で詳しくご説明しています。
位牌には大きく分けて3つの種類がある
位牌と聞くと、多くの方は仏壇に祀られているのをイメージするのではないでしょうか。それは「本位牌」と呼ばれるものです。
「本位牌」以外にも「白木位牌」「寺位牌」と、大きく分けて3つの種類が存在します。
この3つの違いについてもご説明します。
・白木位牌
「白木位牌」とは、故人様がお亡くなりになった直後に作られる仮の位牌で、「内位牌」とも呼ばれます。
文字通り白木(しらき=塗料などで加工しないそのままの木材)に、故人様の戒名や俗名、没年月日、享年を記します。
ご葬儀では祭壇に祀られ、ご葬儀後も中陰祭壇(忌明け法要までご遺骨を祀る祭壇)に安置されます。忌明け法要を迎えた後、「本位牌」に替えます。
あくまで四十九日法要までの仮の位牌が「白木位牌」です。
・本位牌
「本位牌」は塗り位牌とも呼ばれ、忌明け法要を迎えた後「白木位牌」に替わり、仏壇に祀られる
位牌のことです。
漆塗りに金箔・沈金・蒔絵などが施された、多くの方がイメージされるであろう位牌です。
四十九日になると故人の魂は成仏し、本位牌に移りますので、それまでに用意しておく必要があります。
ちなみに「本位牌」の作成には、文字彫り・文字書き、漆塗り・検品等に約2週間かかります。
「忌明け法要に間に合わなかった」ということのないよう早めに手配しておきましょう。
・寺位牌
「寺位牌」とは、菩提寺(壇那寺)や本山
(=宗派における特別なご寺院)に安置
するための位牌のことです。
檀家が「本位牌」とは別に「寺位牌」を祀る他、
様々な事情でご自宅に位牌を安置できない方や
永代供養を望まれる方が「寺位牌」を利用します。
平安祭典では各種位牌のご相談を承っています
いかがだったでしょうか。
今回は仏壇に祀られ、礼拝の対象となる位牌についてご説明しました。
皆さまのご参考になれば幸いです。
平安祭典では、ご葬儀・ご供養に関する各種ご相談を承っています。
神戸・阪神間でお困りごとがございましたら、平安祭典(0120-00-3242)まで気兼ねなくご相談ください。
続きはこちら
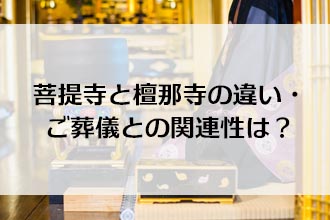
公開日:2022年2月28日
身内に不幸があった際には、私たちはまず家族や親族に連絡し、その後葬儀社や日頃からお付き合いのあるご寺院に連絡を入れます。
この日頃からお付き合いのあるご寺院のことを、「菩提寺(ぼだいじ)」や「檀那寺(だんなでら)」と呼びます。
皆さまに菩提寺や檀那寺がある場合、その存在はとても大切なものとなります。
今回は、菩提寺と檀那寺が、なぜ大切なのかをご紹介します。
菩提寺と檀那寺の違いとは?
まずは菩提寺と檀那寺の言葉の説明をしましょう。
菩提寺と檀那寺は、先祖代々のお墓がある、あるいはご葬儀やご法要を依頼するご寺院という意味として、区別せずに用いられることも多いのですが、厳密には、この2つの言葉の意味は異なります。
まず菩提寺とは、「そのご寺院の宗旨に帰依し、先祖代々のお墓がある、先祖の位牌を納めてあるご寺院」という意味を持つ言葉です。
一方、檀那寺とは、「そのご寺院の檀家となり、日頃から御布施などにより経済的に支えているご寺院」を意味します。
ちなみに「檀那」は古代インドの言葉「ダーナ」に漢字を当てたもので、「御布施」という意味を持ちます。
檀家としてあくまでもそのご寺院の経済活動を支える点が重要であり、必ずしも先祖代々のお墓は必要ありません。
ただ、先祖代々のお墓があり、先祖の位牌を納めていて、かつ檀家として日頃から御布施を行なっているご寺院がある場合には、そのご寺院は菩提寺でもあり檀那寺でもあると言えます。
菩提寺・檀那寺にご葬儀・ご法要を依頼する
ここからはご葬儀における菩提寺・檀那寺との注意点についてご案内します。
ご葬儀やご法要を執り行なう際には、菩提寺や檀那寺に依頼する必要があります。
日時・場所が決まれば、菩提寺・檀那寺のご都合を確認してください。
戒名は故人様の人となりやご趣味・ご職業などを考慮して決めていただけるので、何かご希望があればそのタイミングでご寺院に伝えます。
またその際、お越しになる僧侶の人数を確認しましょう。
なぜなら人数によって御布施の金額が変わってくるからです。
ご法要も菩提寺・檀那寺に連絡し、お経をあげていただきます。
遅くとも1ヶ月前、できれば1ヶ月半~2ヶ月前までにご法要の日時・場所を決めたら、ご寺院のご都合を確認します。
一般的に土・日・祝日やお盆の時期にはご法要を行なうご家庭が多く、どちらのご寺院も多忙になるため、早めに連絡しましょう。
いずれにせよ、菩提寺・檀那寺がある場合には、ご葬儀・ご法要の際は、必ず菩提寺・檀那寺に連絡しましょう。
菩提寺・檀那寺が遠方の場合も、まず連絡を
菩提寺・檀那寺が遠方にある場合でもご葬儀・ご法要を執り行なう際には必ず連絡しましょう。
連絡をした際には、以下の4通りのご回答があるかと思います。
1. 遠くても私が行きます
2. 遠方なので、近隣で付き合いのあるご寺院をご紹介します
3. 葬儀社で紹介してもらってください
4. 戒名はこちらで授けますが、その後は葬儀社でご紹介のあったご寺院に来てもらってください
なお、ご寺院から3・4のようなお返事をいただいた場合には、当社から同じ宗派のご寺院をご紹介いたします。
菩提寺・檀那寺がない、分からない場合にはどうすれば良い?
元々菩提寺や檀那寺がない、あるいはわからない場合もあります。
分からないからといって、そのまま別のご寺院に来ていただいたり、違った宗旨宗派でご葬儀をあげてしまったり…といったことがあってはなりません。
分からない場合は、必ずご親族に確認をしましょう。
ご親族に確認を取るとすぐに菩提寺や檀那寺が判明することも少なくありません。
その他にも、戒名から宗派を推測する方法があります。
実家にある仏壇の掛軸や位牌に書かれている戒名、あるいは墓誌(お墓の横に建てられている石碑)に掘られている戒名を確認することで、宗派や菩提寺・檀那寺を把握する手がかりになります。
それでも不明な場合には、葬儀社に相談しましょう。
宗派については###shuuha_shuushi###で詳しく説明しています。
先祖代々のお墓があっても、納骨ができないことも
いかがだったでしょうか。
今回は、菩提寺・檀那寺についてご説明しました。
菩提寺・檀那寺に関しては、本当はそれらがあるのにも関わらず、別のご寺院でご葬儀を執り行なってしまった、宗派が異なるご寺院に頼んでしまったというトラブルも存在します。
このようなケースでは、先祖代々のお墓があっても、納骨ができないこともありうるので注意しましょう。
平安祭典では神戸・阪神間でのご葬儀・ご法要などに関するご相談を受け付けております。
菩提寺・檀那寺に関するご相談も承っておりますので、お困りごとがございましたら、0120-00-3242まで気兼ねなくお問い合わせください。
続きはこちら
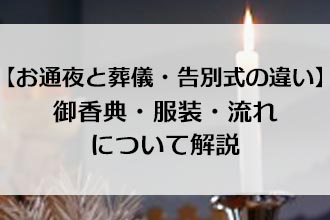
公開日:2021年11月22日
ご遺族やご親族、ご友人などがご遺体を守って一晩過ごすことを「お通夜」といいます。
この「お通夜」と、翌日の「葬儀・告別式」との違いについて、よくわからない方も多いのではないでしょうか?
今回は、お通夜と葬儀・告別式との違いや、お通夜における御香典や服装のマナーなどについてご紹介します。
[@目次@]
お通夜とは?
本来、故人様と最後の夜を過ごすことを「お通夜」といい、一晩中ろうそくの灯りや線香の火を消さずにご遺体を見守り、故人様を偲びます。
「お通夜」という言葉は「夜通し」に由来するといわれています。
ただし、昨今では生活様式の変化に伴い、寝ずの番を省略することも多く、「お通夜」といえば葬儀・告別式の前日にある儀式を指すことがほとんどです。
なお、日程の関係でお通夜の前に数日過ごす場合、この期間を「仮通夜」と呼び、一般的にはご家族のみでゆっくりと、故人様との最後の時間を過ごされることが多いです。
仏式のお通夜の場合、ご寺院に読経をしていただき、参列者による焼香が行なわれるのが一般的です。
ご寺院の退席後に親族代表挨拶がありますが、家族葬の場合は特に、お通夜での挨拶は割愛することが多いようです。
喪主挨拶については###mosyu_aisatsu###でも詳しくご紹介しています。
その後は、参列者にお声掛けをして、「通夜ぶるまい」(漢字では「通夜振る舞い」)の席に案内します。
通夜ぶるまいとは、故人様へのご供養の意味も込めて、ご遺族が故人様と縁のある方々を酒食でもてなすこと、もしくはその場で振る舞われる料理自体を指します。
ただし、通夜ぶるまいの席にお呼びする範囲は地域によっても考え方が様々で、ご親族のみで食事をする場合もあれば、参列されたすべての方にお声掛けする場合もあります。
お通夜と葬儀・告別式の違いは?
お通夜の翌日に行なわれるのが「葬儀・告別式」ですが、先ほどご説明した通夜と具体的にはどのような違いがあるのでしょうか?
ご葬儀とは、正しくは「葬儀式」といい、ご遺族や近親者が故人様を新仏としてあの世へ送るための儀式です。
葬儀式で僧侶から引導を渡された後に、「告別式」が執り行なわれます。
告別式は、生前の故人様と縁のある方々が最後のお別れをする儀式であり、宗教的な意味を持つ儀式は主に前半の葬儀式の部分です。
ただし、今日においては「葬儀式」と「告別式」はひとまとめに考えられ、式の進行も特に区切ることなく行なわれることが多いので、あわせて「葬儀・告別式」と案内することが一般的です。
昔から、友引にご葬儀を行なうと「友を引く=身近な方を一緒に連れて行く」と連想されることから、友引を避けてご葬儀を行なうという風習があります。
「お通夜も友引を避けなければいけないのだろうか?」と疑問に思う方もいるかもしれませんが、その必要はありません。
儀式として重視されるのは、あくまでお通夜の翌日にある「葬儀・告別式」の方なので、友引を避けるとしたら、葬儀・告別式の日程に関してのみです。
そもそも、友引にご葬儀を避けること自体が、いわゆる「迷信」のようなもので、宗教的な意味合いは一切ありません。
とはいえ、あまりに浸透している風習なので、友引にご葬儀を行なう場合は親族間でよく話し合って決める方が良いでしょう。
お通夜で御香典はどうすればいい?
お通夜に参列する際には御香典を持参します。
お通夜、告別式の両方に参列する場合、御香典を持参するのはどちらか一方のみで、お通夜の際に御香典を出していれば、告別式では持参する必要はありません。
両方に持参してしまうと「不幸が重なる」という意味となってしまいますので避けた方が無難です。
また、最近はご遺族の意向で御香典の受け取りを辞退していることも多いので、事前に確認しておいても良いでしょう。
御香典に関するマナーや知識・相場に関しては###kouden_manner###の記事で詳しくご紹介しております。
お通夜の服装 マナー違反にならない服装とは?
葬儀・告別式では喪服の着用がマナーですが、お通夜に参列する際の服装は、必ずしも喪服である必要はありません。
お通夜は「事前に予想・告知がされていない急なこと」なので、「知らせを受けてすぐに、着の身着のまま駆け付けました」というのは決して失礼には当たりません。
喪服(略礼服含む)を準備することが難しい場合は、平服で参列しても問題ありません。
ただし、男性ならダークスーツに白いシャツ、女性ならダークスーツや暗い色のワンピースなどを選ぶのが良いでしょう。
平服で参列する際は、派手な服装や露出の多い服装は避け、落ち着いた服装にしましょう。
ご葬儀の服装や身だしなみに関しては###sougi_midashinami###の記事で詳しくご紹介しております。
お通夜の時間帯は?参列に関して決まりはある?
お通夜は、具体的にどれくらいの時間帯に行なわれているのでしょうか?
決まりはありませんが、一般的に、18時もしくは19時から開始されることが多いです。
「親族ではないが葬儀・告別式に参列してはいけないのか?」とご質問をいただくこともありますが、参列に関して、特に明確な決まりはありません。
日中は仕事や学校があり、参列が難しい方などは、特にお通夜のみ参列されることも多いです。
ご親族・ご親戚の場合は忌引きを利用して両日ともに参列することも可能ですが、それ以外のご友人・会社関係の方などはそれも難しいでしょう。
そのような背景もあり、一般の方は比較的、お通夜だけ参列されることが多いのが現状です。
ただし、本来は決まりがあるわけではないので、予定が合うのであれば葬儀・告別式のみ、もしくは両日とも参列していただいても問題はありません。
ただ、「家族葬で執り行なう」と連絡を受けた場合は、ご自身と故人様(もしくは喪主様)との関係を鑑み、どうしても参列したいのであればご遺族にあらかじめ了承を得るのが望ましいでしょう。
まとめ
今回はお通夜に関して、葬儀・告別式との違いや、御香典・服装のマナーなどについてご紹介しました。
ご葬儀に関することは、非日常的なことが多く、わからないことや困ってしまうことが多いかもしれません。
平安祭典ではご葬儀に関して事前相談も受け付けておりますので、神戸・阪神間でご葬儀に関するお困りごとがございましたら、平安祭典(0120-00-3242)までお問い合わせください。
続きはこちら
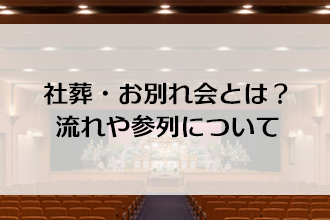
公開日:2021年11月15日
企業の創業者や会長、社長など、企業(団体)の発展に大きく貢献した方が亡くなった際に、「社葬」としてご葬儀を執り行なうことがあります。
社葬は企業の規模に関わらず、いわゆる中小企業であっても執り行なわれますが、「一般的なご葬儀とは具体的にどのような違いがあるのか?」と、疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
今回は「社葬」について、参列の際の注意点なども踏まえてご紹介いたします。
[@目次@]
社葬とは?
一般的に「社葬」とは、企業に多大な功績を残した人物のご葬儀を企業が主体となって行なう、社会的なご葬儀のことを指します。(団体が主体となる場合には「団体葬」)
ご葬儀の運営を親族が主体となって行なう一般的なご葬儀である「個人葬」に対し、企業がその役割を担い、ご葬儀に掛かる費用を企業が負担するのが「社葬」の特徴です。
一般的なご葬儀は「故人の死を悼み、親類やご縁のあった方々でお見送りをする」というプライベートな弔いに重きを置きます。
これに対し、企業を挙げて功労者を追悼し偲ぶことは、故人への何よりの供養であるとともに、対外的には新体制での事業継承を訴え、社内においては故人の遺志を継いで社員一丸となり邁進する決意を新たにする場でもあります。
社葬を執り行なう場合、会場の設営や参列人数など、個人葬よりも規模が大きくなることが多く、準備や打ち合せにも時間が掛かります。
その為、亡くなられてすぐには個人葬(※)を行ない、その後、準備期間をおいて、改めて社葬を執り行なうことが一般的です。
社葬の開催時期に厳密な決まりはありませんが、関係各所への連絡や準備期間も考慮し、忌明け法要(四十九日法要)の前後の時期に合わせて執り行なうことが多いようです。
「個人葬」にも「家族葬」や「一般葬」など形式による通称があるように、「社葬」にも形式によって呼び名が変わる場合があるので、以下で詳しくご説明します。
※ 先行して行なわれる個人葬は「密葬」と呼ばれ、後日「本葬」として執り行なう社葬とは違い、広く案内はせずに近親者と関係者のみで執り行なうことが一般的です。
社葬の形式 合同葬やお別れ会との違い
企業が主体となって執り行なう社葬にも、形式によって「合同葬」や「お別れ会」、「偲ぶ会」など、呼び名が違う場合があります。
これらの意味を、一般的な社葬との違いも含めてご紹介します。
・ 社葬
運営:企業
費用負担:企業
企業(団体)が運営して執り行なう、企業の発展に貢献された方を顕彰(けんしょう)するためのご葬儀です。
故人の信仰されていた宗旨・宗派、もしくは自由葬(無宗葬)で執り行なわれます。
多くの場合、ご遺族、近親者の方のみで個人葬を行なったあとで、本葬として社葬を執り行ないます。
・ 合同葬
運営:ご遺族と企業
費用負担:企業(※)
複数の企業が共同で運営するご葬儀、もしくはご遺族と企業が協同で運営するご葬儀のことを「合同葬」といいます。その場合には、「株式会社●●と株式会社△△の合同葬」、「〇〇家と株式会社●●の合同葬」というような案内をすることが一般的です。合同葬としてご葬儀をされる場合には、社葬・お別れ会のように先行する個人葬と分けて後日改めて行なうのではなく、本葬として執り行なうことも多いようです。
・ お別れ会(偲ぶ会)
運営:企業
費用負担:企業
社葬のスタイルの1つです。基本的には社葬と同じですが、宗教色をなくした式典行事の場合にこの名称を利用することが近年多くなりました。
また、企業だけでなく、故人と縁のある有志が集まって式典を行なう場合にもこの名称が使われます。
葬儀会館やホテル、レストラン、会社施設内の会場などを使用することが一般的です。
式典の進行にも融通が利くため、一定時間セレモニー(弔辞、弔電披露、代表者挨拶、ご焼香や献花などの進行)を行なう場合もあれば、故人の業績などをパネル展示した会場に献花場を設け、到着した方から順に立食形式で軽食を振る舞うという例もあります。
※社葬全般に関わることですが、社内に社葬に関する規定がある場合、
「どこまでの費用を会社側が負担するのか」が明確に定義されていることが多いです。
合同葬の場合は特に、聖職者への御礼など、一部はご遺族側の負担となることもあるので、事前に各企業の社葬規定を確認しておく方が良いでしょう。
社葬の流れ 一般社員は参列できる?
企業が主体となる場合、規模の大きさに関わらず「社葬」という扱いになりますが、個人葬として執り行なわれる一般的なご葬儀と比べると、規模が大きくなることが多いです。
前述したように、主体となるのが誰か、行なう時期、内容は宗教儀礼に則るか否か…など様々な要因により、「社葬」・「合同葬」・「お別れ会」といった名称は変わります。
それぞれに進行の仕方も違うため、一概に決まった「社葬の流れ」というものはありません。
ただし、宗教儀礼に則った形で執り行なう場合は、個人葬と流れは大きく変わりません。
社葬の場合は、故人のご功績の紹介や、代表者からの弔辞などが付け加えられることもありますが、基本的にはそれぞれの宗旨・宗派の一般的な葬儀・告別式と同じと言えるでしょう。
ご葬儀の流れについては###sougi_nagare###で詳しくご説明しています。
・ 社外の社葬の場合
参列に関しては、亡くなってすぐの個人葬(密葬)は近親者と関係者(友人・知人や会社の代表など)で行ない、その後改めてご案内を出す「社葬」や「お別れ会」の場合は、案内が届いてから参列者を社内で決めます。
多くの場合、会社の代表として参列することになるので、故人と同等以上の役職の方、もしくは個人的に繋がりがあった方が参列されます。
「合同葬」の場合も、参列者を選ぶ基準は上記の「社葬」や「お別れ会」と基本的には同じです。
ただし、亡くなられてすぐに本葬として執り行なうことが多いため、日程の連絡が届くのが直前となることもあり、本来なら参列すべき方のスケジュールの調整が難しいということもあるでしょう。
その場合は、参列には代理人を立て、当日までに弔電などを送ることも可能です。
・ 社内の社葬の場合
会社の規模や開催場所、日程などによっても変わりますが、一般社員も含めて社員全員が参列するというケースは少なく、「役員のみ参列」など、範囲を決めて参列することが一般的です。
ただし、社葬の場合、受付や来賓の座席への案内役などは、一般社員が担当することが多いです。
中には、遠方にいる社員がお参りできるように遥拝所を設けたり、朝礼時に黙祷を捧げるなどの対応を取る会社もあります。
また、当社では、合同葬として執り行なったお式のご出棺に際し、霊柩車が火葬場に向かう前に会社の前を通り、社員の方々が外に並んでお見送りをされた…というような例もございます。
なお、開催側、参列側に関わりなく、社葬の場において名刺交換をすることはマナー違反とされるため、注意しましょう。
社葬の参列のマナーについては###syasou_manner###ので詳しくご説明しています。
まとめ
今回は社葬について、形式による名称の違いや、参列の際の注意点などをご紹介いたしました。
社葬は社会的な行事であるため、関係各所に失礼のないよう、気を付けなければいけないことも多いでしょう。
とはいえ、社葬は一般的なご葬儀と違う点もありますが、「故人を偲び、ご遺族に寄り添う」という本質は変わりません。
平安祭典では、社葬を始め、各種団体葬お別れ会など、様々な形式のご葬儀だけでなく、自治会・企業主催の慰霊祭などもお手伝いしております。
社葬のノウハウを持ったスタッフが多数在籍し、事前準備から当日の運営までトータルでサポートさせていただきます。
平安祭典では社葬を行なうことが可能です。詳細は下記のページをご覧ください。
■平安祭典の社葬
神戸・阪神間で社葬などのご要望がございましたら、平安祭典(0120-00-3242)までお問い合わせください。
続きはこちら
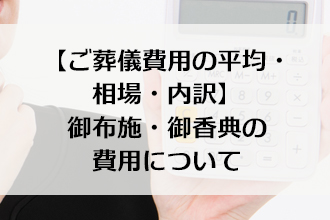
更新日:2025年4月25日 公開日:2021年5月24日
ご葬儀は実際に執り行なってみないと分からないことが多いものです。
特に費用に関しては、ご葬儀を経験されていないと、はっきりとイメージしにくいものです。
事前相談の中でも、ご葬儀費用に関することが、とても多いご相談内容のひとつとなっています。
悔いのないよう故人様をお送りするためにも、前もって、ご葬儀に関する費用について理解を深めることは大切なことです。
そこで今回は、ご葬儀の費用、御布施、御香典の平均的な相場についてご説明します。
[@目次@]
ご葬儀費用の平均的な相場は?
まずは、皆さまの関心が高い、ご葬儀費用の相場についてご説明しましょう。
全国のご葬儀費用の平均的な相場は、およそ100~150万円です。
この金額に、御布施など聖職者へのお礼の費用を加えた金額が、ご葬儀の総費用となります。
※出典…「全互協冠婚葬祭1万人アンケート」
もちろん、この相場はひとつの目安です。
ご葬儀費用は、ご葬儀の内容や規模で変わってきます。
また、地域独自の風習やしきたりも存在するため、ご葬儀費用の相場には地域差が存在することも、頭の片隅に置いておきたいところです。
ご葬儀費用の具体的な内訳についてもご説明しましょう。
ご葬儀費用の具体的な内訳
ご葬儀費用の内訳は、主に
① 固定費(コース費用)
② 変動費
③ オプション
④ 聖職者への御礼(御布施など)
の4つからなります。では、ひとつずつ見ていきます。
① 固定費(コース費用)
まずは固定費(コース費用)。
固定費とは、会館使用料や火葬料など、ご葬儀の規模や参列者の人数に左右されない費用のことです。
ほとんどの葬儀社では、ご葬儀に必要なもの、例えば祭壇や棺、枕飾り、骨壷・骨箱、遺影写真などをセットにしたコースをいくつかご用意しています。
平安祭典のコース内容も、「これさえあれば大丈夫」という基本的なもので構成されています。
平安祭典での一例は「ご葬儀の種類・費用」にございますので、ご参考になさってください。
② 変動費
変動費とは、ご親族や参列者・会葬者の人数などによって変わってくる費用のことです。
例えば、故人様を偲んで飲食を供にする「通夜ぶるまい」、ご親族やお世話になった方々をおもてなしする「仕上げ料理」といったお料理やお飲み物の費用、参列していただいた方などにお渡しする「返礼品」(供養品、香典返し)の費用が人数によって変わってくるため、変動費となります。
お料理・お飲み物や返礼品は、参列される人数が読めない場合には、足りなくなると困るため、気持ち多めの数をご用意しておいたほうが良いでしょう。
ご葬儀で余った返礼品は持ち帰り、ご葬儀のあとにご自宅に弔問があった際にお渡しします。
忌明け法要(四十九日法要)を過ぎたあたりで、余った返礼品は、葬儀社に返品することができます(葬儀社によって異なりますので、ご確認ください)。
③ オプション
ご葬儀の費用には、オプションと呼ばれる追加項目も存在します。
お料理やお花、マイクロバスなどがこれに当たります。
特に固定費(コース費用)以外にお客様が必要と思われるもの、あるいはコースに含まれているけれども異なる種類のものを希望される場合、オプションでの対応となります。
葬儀社の会館でご葬儀を執り行なう際には、会館使用料がオプションになることが多いです。
ちなみに、平安祭典ではすべての会館に仮眠が可能な設備を備えており、遠方からいらっしゃるご親族にゆっくり休んでいただくことが可能です。
④ 聖職者へのお礼(御布施など)
そして最後が聖職者への御礼(御布施など)。
御布施はご寺院に読経していただいたり、戒名をつけていただいた際にお渡しするお礼のことです。
関西地区の御布施の相場は、およそ 25万~30万円です(戒名のランクによっては 100万円以上になることもあります)。
ただし、御布施の額は、宗派、ご寺院とのお付き合いの度合いによっても異なるため、この金額がすべてに当てはまるわけではありません。
詳しくは、ご寺院にご確認ください。
※浄土真宗では「戒名」と呼ばず「法名」と呼び、ランクをつける考え方はありません。
御香典の平均的な相場は?
御香典についてもお話しましょう。
関西地区の御香典の相場は、親・兄弟・姉妹で5万円、祖父母が1万円、職場関係・友人は5千円となっています。
また、叔父・叔母・いとこなど親族の場合には、関係性にもよりますが1万円~10万円の間の金額が相場です。
故人様と直系のご親族であっても、喪主や同居家族以外の方は、持参するのが一般的です。
ご親族や参列者からいただく御香典は、古くからご葬儀を営む喪家への慰労・支援の意味があり、お互いに葬儀費用を扶助する役目を持つとされています。
最近では、香典返しが面倒などの理由で御香典を辞退される方もいらっしゃいます。
ご遺族のお考えにもよりますが、御香典を辞退すれば、ご遺族の費用面でのご負担が増える可能性がある点を考慮に入れておきたいところです。
また、香典返しは、ご葬儀の当日に香典返しを行なう「当日返し」が主流となっているため、後々手間がかかることはありません。
葬儀費用の負担を軽減する補助金・給付金の存在
葬儀費用の負担を軽減するお金として、補助金や給付金の存在があることも知っておきましょう。
例えば、国民健康保険の加入者が亡くなった際には、「葬祭費」の支給があります。
ちなみに神戸市の支給額は5万円です(2025年現在)。
支給を受けるためには、葬儀の領収書などを揃えて申請手続きをしなければいけません。申請期限もあるため注意が必要です(詳しくは、お住いの自治体にお問い合わせください)。
また、公的健康保険・国家公務員共済組合加入者の場合にも、同様に「埋葬費」が支給されます。
この他にも、勤務先の会社から弔慰金が支給されることがあります。
事前相談でご予算をお伝えください
いかがだったでしょうか。
今回は、ご葬儀の費用、御布施や御香典の平均的な相場など、ご葬儀に関する費用についてご説明しました。
平安祭典では、神戸・阪神間での事前のお見積りや費用に関するご相談も受け付けております(0120-00-3242)。気兼ねなくお問い合わせください。
また、神戸・阪神間で事前相談をご希望の方は下記のフォームからお申し込みください。
■事前相談予約フォーム
https://www.heiansaiten.com/inquiry/consultation.php
続きはこちら
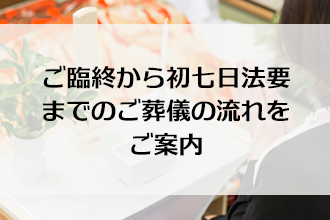
公開日:2021年5月3日
ご葬儀は、故人様を偲び弔うための儀式です。とはいえ、ご遺族は短い時間の中で様々なことを決めていかなければなりません。
今回は仏式を例に、ご葬儀の流れをご説明します。
ご臨終に際しての心構え
病院で臨終を迎えた場合
病院で亡くなられた場合には、医師による死亡宣告を経て、死亡診断書が作成されます。死亡診断書を受け取ったら、まず、記載されている内容(名前や生年月日など)に間違いがないかを確認しましょう。
死亡届、および死体火葬・埋葬許可申請のため、死亡診断書の原本は役所に提出しますが、多くの場合、葬儀社が代行します。
ご自宅で臨終を迎えた場合
かかりつけの医師に連絡し、死亡の原因を調べてもらいます。自然死または病死などの場合、死亡診断書を書いてもらえます。かかりつけの医師がいない場合は、救急車を呼びましょう。
病気以外の急死や外因死、死因不明の場合は警察の検視を受け、死亡診断書ではなく、死体検案書が作成されます。
葬儀社(移送先)の手配
病院で亡くなられた場合、まず葬儀社に連絡して、故人様を搬送する寝台車の手配をしなければなりません。互助会に入っていない、どこの葬儀社にするか見当がつかないといった場合などは、病院で葬儀社を紹介できるか聞いてみましょう。
いざという時に慌てないためにも、事前に葬儀社を決めておき、葬儀・告別式と執り行なう会館やご自宅など、どこに帰るのかを決めておくことが大切です。
ご自宅に帰る場合は、故人様をご安置するスペースを確保します。
また、部屋の温度を低めに設定するなど、室温管理にも気をつけます。
ご安置~ご葬儀の日程などの取り決め
ご安置・末期の水
ご自宅でのご安置の場合、北向きか西向きにご安置します。
ご安置後、末期(まつご)の水を行ないます。末期の水とは、息を引き取られた故人様の口元を水で潤す、仏教における大切な儀式です。
ご寺院へ連絡・枕経
枕元に枕飾りを設置し、お付き合いのあるご寺院に訃報の連絡をして、枕経をあげていただきます。
枕経とは、本来は死にゆく人への案内として、枕元で死をみとりながらあげるお経のことですが、現代ではお亡くなりになって初めてあげてもらうお経のことを指します。
枕経の時には、その場での御布施は不要ですが、後に「枕経料」として包む場合もあります。
お付き合いのあるご寺院がいらっしゃる場合は、あらかじめ連絡先を把握しておきましょう。分からない方は、故人様の兄弟姉妹など、ご親族に宗派を確認することが大切です。
お付き合いのあるご寺院が遠方でいらっしゃることが難しい場合には、お近くの同宗派のご寺院をご紹介いただきます。
ご葬儀の日程などの取り決め
葬儀社とご葬儀の形式や規模、日程などを相談します。ご葬儀の日程は、ご寺院のご都合を考慮して決める必要があるため、枕経のあとに確認をしておきましょう。そのあと、喪主を決定し、飾り付けや費用などご葬儀の内容の打ち合わせを行います。
この時、受付を誰にお願いするのかなども決めておきましょう。
ご葬儀の打ち合わせの際には、参列者を予測して、食事の数(量)を決定します。ご親戚への訃報連絡の際に、お通夜・ご葬儀それぞれの出席人数、お食事を召し上がる方の人数をできる限り確認しておくと良いでしょう。
湯灌の儀・納ノ儀(納棺)
湯灌の儀とは、故人様の体や髪をお湯で洗い清め、新たな旅立ちの準備をする儀式です。
現世の汚れを洗い清めるという意味と、赤ちゃんが産湯につかるように、新たに来世に生まれ変わるためにという願いが込められています。
病院などで行なう「清拭(エンゼルケア)」は、主に皮膚を清潔に保ち、感染を予防するためのもので、意味合いが全く異なります。
納ノ儀(納棺)とは、故人様の身なりを整えて棺にお納めする儀式です。ご遺族と故人様とのかけがえのない時間で、故人様の死を受け止める大切な儀式となっています。この時に、故人様の愛用していた品などを副葬品として納めるので、用意しておきましょう。間に合わなければ、出棺前のお別れの際に納めることもできます。
お通夜・通夜ぶるまい
お通夜は、ご遺族やご親族、ご友人などがご遺体を守って一晩過ごす、ご葬儀前夜に行なわれる儀式のことです。葬儀日程の関係で、お通夜の前日に「仮通夜」を営む場合もあります。
お通夜は、一般的には、《着席~ご寺院入場~読経~ご遺族焼香~参列者焼香~ご遺族代表挨拶》という流れです。
そのあと、参列者の方々を通夜ぶるまいの席に案内します(その場で召し上がらない方には、お持ち帰り料理をご用意することもできます)。通夜ぶるまいとは、故人様へのご供養の意味も込めて、ご遺族が故人様と縁のある方々を、酒食でもてなすことです。
葬儀・告別式
ご葬儀とは、ご遺族や近親者が故人様を新仏としてあの世へ送るための儀式です。ご寺院から引導を渡されたあとに、告別式が執り行なわれます。告別式は、生前の故人様と縁ある方々が最期のお別れをする儀式です。
葬儀・告別式の大まかな流れは、《着席~ご寺院入場~読経~弔電の披露~ご遺族焼香~会葬者焼香~ご寺院退場~ご遺族代表挨拶》となります。聖職者へのお礼(御布施)は、葬儀・告別式の開式前にお渡しすることが多いです。
出棺~お骨あげ
葬儀・告別式のあとに、故人様にお花をたむけてお別れする「お別れの儀」を行い、そのあとに出棺となります。出棺の折に、故人様の使用していた茶碗を割る、クラクションを鳴らすなどの風習もあります。神戸地区では、火葬場でご寺院の読経をいただき、水と樒を使用したお水でのお別れが行なわれます。
火葬にかかる時間は、約2時間30分です。この間に式場に戻り、故人様を偲び、ご親族などをもてなす仕上げ料理を振るまいます。お骨あげは、火葬場の担当者の指示に従って行ないましょう。
火葬に関しては###kasou_toha###の記事で詳しくご説明しております。
初七日法要
ご遺骨になった故人様を式場に連れて帰り、初七日法要を執り行ないます。
本来であれば初七日法要は亡くなってから七日目に行なうものですが、近年では、ご遺族・ご親族が集まっているご葬儀当日に行なうことが一般的です。
初七日法要に関しては###shonanoka_houyou###の記事で詳しくご説明しております。
まとめ
いかがだったでしょうか。今回は、ご葬儀の大まかな流れを、儀式の内容や注意点なども含めてご説明しました。神戸・阪神間で、ご葬儀・ご供養に関するお困りごとがございましたら、平安祭典(0120-00-3242)までご相談ください。
続きはこちら