

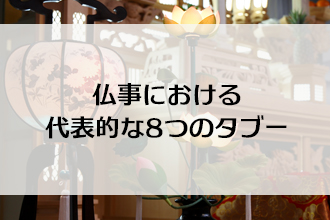
公開日:2021年6月14日
ご葬儀・ご法要などの仏事では、タブーとされていることが意外と多いものです。中には迷信だとされているものもありますが、社会人の知識として一通りは知っておきたいところです。
そこで今回は、「仏事における代表的な8つのタブー」について解説します。
8つのタブー
① 忌み言葉を使ってはならない
忌み言葉とは、不幸を連想させるなど、縁起が悪いため避けるべき言葉のことです。ご葬儀に参列し、ご遺族にお悔やみを述べる際、あるいは喪主としてご挨拶をする際には、マナーとして忌み言葉は使わないようにしましょう。
例えば、「重ね重ね」「返す返す」「くれぐれも」といった重ね言葉や、「追って」「再び」のような言葉は、不幸が重なることを連想させる言葉でありタブーとなります。「消える」「迷う」「苦しむ」などの不吉な表現もできるだけ避けましょう。
また、「死ぬ」「生きる(生きていたとき)」などの直接的な言葉は、「ご逝去」「ご生前」といった言葉に言い換える必要があります。
② ご法要は祥月命日からあとに行なってはならない
祥月(しょうつき)は亡くなった月、命日(めいにち)は亡くなった日という意味を持つ言葉です。祥月命日とは、一周忌以後の故人様が亡くなられた月日を指す言葉です。
一周忌をはじめとするご法要は、祥月命日に執り行なうのが良いとされていますが、実際には、ご寺院の予定に合わせたり、参列されるご親族のご都合がつきやすい週末にずらして行なわれることがほとんどです。
そして、ご法要を祥月命日からずらして行なう場合には、祥月命日よりも前に行なわなければならないとされています。あとにずらすことは、「仏様のことをないがしろにする」ことにつながるという考えがあり、タブーであるとされています。
ただし、どうしても前倒しが難しい状況であるなら、ご寺院やご親族に事情を説明したうえで、日程をずらしましょう。いずれにせよ、一番大切なのは故人様を想う気持ちではないでしょうか。
③ 御香典に新札を用いてはならない
ご祝儀には新札を用いるのがマナーですが、御香典の場合は新札を用いるのはタブーです。なぜなら新札を用いると、御香典を前もって準備していた、つまり不幸を予想していたという意味になってしまうからです。
とはいえ使い古したお札では失礼なので、できるだけきれいなお札を選んだり、新札に折り目を付けましょう。
御香典のマナーについては###kouden_manner###で詳しくご説明しております。
④ 神棚封じをご遺族が行なってはならない
最近では、神棚がないご家庭も増えているようです。神棚封じとは、神棚を半紙で覆って見えないようにすることです。神道では、死を穢(けが)れとして考えているため、ご家庭の中の誰かが亡くなった際には、神様に穢れを近づけないよう神棚を封じます。
ご遺族が神棚封じを行なうケースも多いようですが、神棚封じは、穢れが及んでいるご遺族ではなく、第三者が行なうのが良いとされています。
⑤ 棺に生きている方の写真を入れてはならない
ご家族が、棺に副葬品として写真を入れるケースが多いのですが、棺に生きている方、特にご家族以外の方が写っている写真を入れることはタブーとされています。なぜなら、写っている方が、あの世へ連れて行かれるという言い伝えがあるからです(ただし、ご遺族が納得している場合には問題ありません)。
また、故人様を撮影することは、ご遺族がご自身の判断で行なうことは問題ありません。ちなみに火葬場での写真撮影は、原則禁止となっています。
⑥ 友引にご葬儀を行なってはならない
友引とは六曜の一つです。友引にご葬儀を行なうことはタブーであるという考え方は、全国各地で根強く残っている風習です。
「友引」すなわち「友を引く」という言葉から連想し、友引にご葬儀を行なうと、ご友人があの世へ引き寄せられる、ご不幸が続くなどと考えられています。そのため、友引の日に火葬場が休業する地域も少なくありません。
しかし、元来、友引という日は、勝負ごとの決着がつかない良くも悪くもない日のこと。また、そもそも六曜は仏教とは関係がありません。というわけで、友引にご葬儀を行なってはならないという風習は、迷信に分類されます。
友引にご葬儀を行なうことは問題ありませんが、ご親族の中には気にされる方もいらっしゃることでしょう。そのような際には、故人様の棺の中に「故人様のお供をする」「ご友人の代わり」という意味合いを持つ「お供(友)人形」を入れます。
⑦ 忌明け法要が3か月にまたがってはならない
忌明け法要とは、亡くなってから四十九日後のご法要のこと。亡くなった方は、亡くなってから四十九日(七七日)目に旅を終えるとされています(浄土真宗は、「即身成仏」という考えから、旅をするという概念がありません)。
忌明け法要が3か月にまたがると、「四十九日(しじゅうくにち)」と「三月(みつき)」の語呂合わせで、「始終、苦が身につく」とされています。
気になる場合は、三十五日(五七日)で忌明けとすることもありますが、四十九日(七七日)までの旅路には意味があるので、無理に早める必要はないでしょう。逆に先延ばしにすることは、年忌法要と同様にタブーとされています。
⑧ 逆さごと
逆さごととは、ご葬儀に関する諸々のことを普段とは逆に行なうことです。例えば、死装束を左前に着せる、帯を縦結びにする、北枕、逆さ屏風などが、逆さごとに当てはまります。
あの世とこの世では、物事が逆になっているという考えからくる風習ですが、特に宗教的な意味合いはありません。
知っておいて損はない仏事のタブー
いかがだったでしょうか?今回は、「仏事における代表的な8つのタブー」についてご紹介しました。
仏式のご葬儀・ご法要などを執り行なう際、あるいは参列なさる際には、これらタブーに関する知識を知っておいて損はないでしょう。皆さまの参考になれば幸いです。
平安祭典では、神戸・阪神間での ご葬儀に関するお困りごとや事前見積りに関するご相談を受け付けています(0120-00-3242)。気兼ねなくお問い合わせください。
続きはこちら
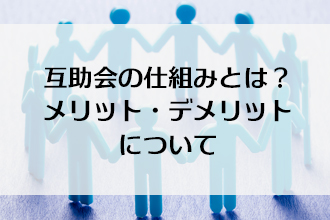
更新日:2023年3月16日 公開日:2021年6月7日
ご葬儀は、人生の最期を飾る大切な儀式です。ご家族のためにも、自分自身のためにも、悔いのないご葬儀にしたいものです。
しかしながら、ご葬儀にはある程度の費用がかかるのも事実です。費用面でのご負担を心配される方も少なからずいらっしゃることでしょう。
そのような費用面でのご負担に対する不安を取り除き、いざという時に役立つのが「互助会」のシステムです。今回は、そのシステムについて、メリットやデメリットを含めてご紹介します。
ご葬儀費用を補填できる互助会システムとは?
互助会は正式名称を「冠婚葬祭互助会」と言い、結婚式やご葬儀など、将来の冠婚葬祭に備えて掛金を積み立てていくシステムです。会員は、毎月掛金を互助会費として積み立てていくことで、将来的に契約金額に応じたサービスを受けられます。
その歴史は長く、昭和23年、「相互扶助の精神」の元に設立されました。終戦後の物資が不足する中、隣近所がお互いに少しずつお金を出し合い1着の花嫁衣裳を購入し、みんなで大切に着回したことが互助会のはじまりです。
ひとりひとりの掛金は少額ですが、会員が集まることで大きな保証を得られる点が、互助会の良いところです。このシステムを利用すれば、いずれ来るご葬儀など、いざという時のご負担が軽くなります。
また、互助会は経済産業大臣の認可事業であり、厳しい審査を通過した企業のみが営業許可を得ることができます。平安祭典(株式会社平安)は一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会 (全互協) に加盟しています。
互助会に入会する意味やメリットとは?
続いては、互助会のメリットを詳しく見ていきましょう。
掛金をご葬儀費用の一部に補填できる
ご葬儀に必要な基本的なものがセットになった複数のコースの中から、生活プランやご要望に合ったコースを選び、掛金を積み立てていきます。
毎月少しずつ掛金を支払うので、いざまとまったお金が必要になった時に安心です。
ご葬儀の際には、ご葬儀費用の一部に補填できます(会館使用料などのオプション、参列者の人数で変動する飲食接待費用などは別途費用が必要となります)。
役務の内容が保証されるので、物価変動の影響を受けない
役務とはサービスのことです。互助会では、金銭の保証ではなく、役務の内容が保証されます。そのため、もし物価が上昇しても、契約したコースについて値上がりは発生しません。
会員専用のコースを利用でき、割引特典がある
会員になった特典として、会員専用のお得なコースを利用することができます。また、契約コースに含まれないオプションなどの追加商品の価格も、会員価格が適用される場合があります。
ご葬儀だけでなく、他の冠婚葬祭などに利用できる場合もある
掛金は、結婚式、成人式やご法要など、ご葬儀以外に利用できることがあります(葬儀社によって内容が異なりますので、事前にご確認ください)。
引越した際には、引越し先の互助会に引き継ぎができる
契約した全互協加盟の葬儀社の営業地域外に引越した際には、引越し先の全互協加盟の互助会に了承を得て引き継ぎをすることができます。全互協に加盟している互助会は、全国に205社(2022年9月現在)あります。
互助会のデメリットとは?解約や金利について
互助会のデメリットも知っておきましょう。
掛金に金利はつかない
銀行など金融機関の預金と異なり、掛金に利息は発生しません。
契約コースの変更はできない
契約時の内容が保証されるため、契約コースの変更ができません(葬儀社によって内容が異なりますので、事前にご確認ください)。
解約する場合には手数料がかかる
互助会を解約する場合には、一定の手数料がかかります。手数料には、会員の募集に関する人件費、会員の管理に関する人件費、会報誌関連費用、保全費用などが含まれます(手数料は上限が決められています)。
互助会と葬儀保険の違い
ご葬儀への備えには、互助会の他に「葬儀保険」というものがあります。
互助会は、毎月掛金を積み立てることで、冠婚葬祭の役務内容の提供を受ける権利を得るシステムです。
一方の葬儀保険は、一般的な生命保険と同様に、いざという時に契約した保険で決まった金額が、ご葬儀費用として現金で支払われるものです。
葬儀保険の掛金は、互助会のように積み立てではなく掛け捨てであるため、万が一解約する際には、互助会と異なり返金がありません。また、契約してから一定期間経った時点で保障が始まります。
皆さまのサポート役として、人生の大切な時に寄り添います
いかがだったでしょうか。今回は、互助会のシステムについて、メリットやデメリットを含めてご紹介しました。冒頭でもお伝えしましたが、費用面でのご負担に対する不安を取り除き、いざという時に役立つのが「互助会」のシステムです。
互助会に加入することは、費用面での安心を得られるだけではありません。事前にご葬儀について考えることで、心の準備ができ、ゆとりある生活を送ることができるのではないでしょうか。
平安祭典では互助会にご加入いただいた方専用のお得なプランがございます。詳しくは「平安会員について」をご覧ください。
事前にご葬儀について相談可能な事前相談については###sougi_jizensoudan###で詳しくご説明しております。
平安祭典では、神戸・阪神間でのご葬儀に関するお困りごとのご相談や事前見積りを受け付けています(0120-00-3242)
気兼ねなくご相談ください。
また、神戸・阪神間で事前相談をご希望の方は下記のフォームからお申し込みください。
事前相談予約フォーム
皆さまのサポート役として、人生の大切な時に寄り添い、お手伝いをさせていただきます。
続きはこちら
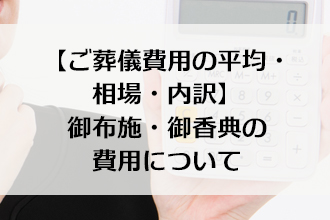
更新日:2025年4月25日 公開日:2021年5月24日
ご葬儀は実際に執り行なってみないと分からないことが多いものです。
特に費用に関しては、ご葬儀を経験されていないと、はっきりとイメージしにくいものです。
事前相談の中でも、ご葬儀費用に関することが、とても多いご相談内容のひとつとなっています。
悔いのないよう故人様をお送りするためにも、前もって、ご葬儀に関する費用について理解を深めることは大切なことです。
そこで今回は、ご葬儀の費用、御布施、御香典の平均的な相場についてご説明します。
[@目次@]
ご葬儀費用の平均的な相場は?
まずは、皆さまの関心が高い、ご葬儀費用の相場についてご説明しましょう。
全国のご葬儀費用の平均的な相場は、およそ100~150万円です。
この金額に、御布施など聖職者へのお礼の費用を加えた金額が、ご葬儀の総費用となります。
※出典…「全互協冠婚葬祭1万人アンケート」
もちろん、この相場はひとつの目安です。
ご葬儀費用は、ご葬儀の内容や規模で変わってきます。
また、地域独自の風習やしきたりも存在するため、ご葬儀費用の相場には地域差が存在することも、頭の片隅に置いておきたいところです。
ご葬儀費用の具体的な内訳についてもご説明しましょう。
ご葬儀費用の具体的な内訳
ご葬儀費用の内訳は、主に
① 固定費(コース費用)
② 変動費
③ オプション
④ 聖職者への御礼(御布施など)
の4つからなります。では、ひとつずつ見ていきます。
① 固定費(コース費用)
まずは固定費(コース費用)。
固定費とは、会館使用料や火葬料など、ご葬儀の規模や参列者の人数に左右されない費用のことです。
ほとんどの葬儀社では、ご葬儀に必要なもの、例えば祭壇や棺、枕飾り、骨壷・骨箱、遺影写真などをセットにしたコースをいくつかご用意しています。
平安祭典のコース内容も、「これさえあれば大丈夫」という基本的なもので構成されています。
平安祭典での一例は「ご葬儀の種類・費用」にございますので、ご参考になさってください。
② 変動費
変動費とは、ご親族や参列者・会葬者の人数などによって変わってくる費用のことです。
例えば、故人様を偲んで飲食を供にする「通夜ぶるまい」、ご親族やお世話になった方々をおもてなしする「仕上げ料理」といったお料理やお飲み物の費用、参列していただいた方などにお渡しする「返礼品」(供養品、香典返し)の費用が人数によって変わってくるため、変動費となります。
お料理・お飲み物や返礼品は、参列される人数が読めない場合には、足りなくなると困るため、気持ち多めの数をご用意しておいたほうが良いでしょう。
ご葬儀で余った返礼品は持ち帰り、ご葬儀のあとにご自宅に弔問があった際にお渡しします。
忌明け法要(四十九日法要)を過ぎたあたりで、余った返礼品は、葬儀社に返品することができます(葬儀社によって異なりますので、ご確認ください)。
③ オプション
ご葬儀の費用には、オプションと呼ばれる追加項目も存在します。
お料理やお花、マイクロバスなどがこれに当たります。
特に固定費(コース費用)以外にお客様が必要と思われるもの、あるいはコースに含まれているけれども異なる種類のものを希望される場合、オプションでの対応となります。
葬儀社の会館でご葬儀を執り行なう際には、会館使用料がオプションになることが多いです。
ちなみに、平安祭典ではすべての会館に仮眠が可能な設備を備えており、遠方からいらっしゃるご親族にゆっくり休んでいただくことが可能です。
④ 聖職者へのお礼(御布施など)
そして最後が聖職者への御礼(御布施など)。
御布施はご寺院に読経していただいたり、戒名をつけていただいた際にお渡しするお礼のことです。
関西地区の御布施の相場は、およそ 25万~30万円です(戒名のランクによっては 100万円以上になることもあります)。
ただし、御布施の額は、宗派、ご寺院とのお付き合いの度合いによっても異なるため、この金額がすべてに当てはまるわけではありません。
詳しくは、ご寺院にご確認ください。
※浄土真宗では「戒名」と呼ばず「法名」と呼び、ランクをつける考え方はありません。
御香典の平均的な相場は?
御香典についてもお話しましょう。
関西地区の御香典の相場は、親・兄弟・姉妹で5万円、祖父母が1万円、職場関係・友人は5千円となっています。
また、叔父・叔母・いとこなど親族の場合には、関係性にもよりますが1万円~10万円の間の金額が相場です。
故人様と直系のご親族であっても、喪主や同居家族以外の方は、持参するのが一般的です。
ご親族や参列者からいただく御香典は、古くからご葬儀を営む喪家への慰労・支援の意味があり、お互いに葬儀費用を扶助する役目を持つとされています。
最近では、香典返しが面倒などの理由で御香典を辞退される方もいらっしゃいます。
ご遺族のお考えにもよりますが、御香典を辞退すれば、ご遺族の費用面でのご負担が増える可能性がある点を考慮に入れておきたいところです。
また、香典返しは、ご葬儀の当日に香典返しを行なう「当日返し」が主流となっているため、後々手間がかかることはありません。
葬儀費用の負担を軽減する補助金・給付金の存在
葬儀費用の負担を軽減するお金として、補助金や給付金の存在があることも知っておきましょう。
例えば、国民健康保険の加入者が亡くなった際には、「葬祭費」の支給があります。
ちなみに神戸市の支給額は5万円です(2025年現在)。
支給を受けるためには、葬儀の領収書などを揃えて申請手続きをしなければいけません。申請期限もあるため注意が必要です(詳しくは、お住いの自治体にお問い合わせください)。
また、公的健康保険・国家公務員共済組合加入者の場合にも、同様に「埋葬費」が支給されます。
この他にも、勤務先の会社から弔慰金が支給されることがあります。
事前相談でご予算をお伝えください
いかがだったでしょうか。
今回は、ご葬儀の費用、御布施や御香典の平均的な相場など、ご葬儀に関する費用についてご説明しました。
平安祭典では、神戸・阪神間での事前のお見積りや費用に関するご相談も受け付けております(0120-00-3242)。気兼ねなくお問い合わせください。
また、神戸・阪神間で事前相談をご希望の方は下記のフォームからお申し込みください。
■事前相談予約フォーム
https://www.heiansaiten.com/inquiry/consultation.php
続きはこちら
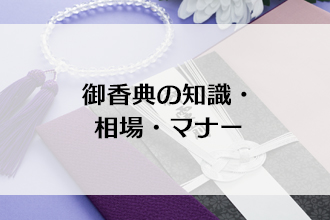
公開日:2021年5月17日
御香典の「香」の字は、かつては故人様に対して、線香や花を供えていたことに由来する…といったことを皆さまご存じでしょうか?
今回は、御香典に関する知識や相場、マナーについてご説明します。
御香典とは?
御香典の「香」の字は、かつては故人様に対して、線香や花を供えていたことに由来します。現代では、故人様に線香や花を供える代わりに、「困った時はお互い様」の精神、「相互扶助」の精神に基づいた、ご遺族を経済的に助ける慣習となっています。
「香」の字が線香を意味することから、「御香典」は仏式にのみ使用します(キリスト教式であれば「御花料」、神式であれば「御玉串料」などとなります)。
御香典の相場
御香典の相場は、故人様との関係性はもちろん、お住まいの地域によっても変わります。以下に一般的な相場をご紹介します。
・近隣、あまりお付き合いのない方…3,000円
・勤務先の上司、同僚、部下、その家族…3,000~10,000円
・友人、知人、その家族 …3,000~10,000円
・親戚…5,000~30,000円
・祖父母…10,000~50,000円
・おじ・おば…10,000~30,000円
・兄弟姉妹…30,000~50,000円
・両親…50,000~100,000円
祖父母、両親、兄弟は義理の関係であっても金額の目安は同じです。また、ご自身が喪主を務める場合や、ご葬儀代金を負担する場合は、御香典は必要ありません。
会社の部署一同など、複数人で御香典を渡す際には、表書きは「○○一同」とし、全員の名前を記した名簿を中袋に入れておきましょう。ご遺族の手間を考え、一同で包む場合は全員が同じ金額になるようにします。
不祝儀袋の種類、水引の色
御香典を包む不祝儀袋(ぶしゅうぎぶくろ)は、故人様の宗旨・宗派に合わせて使い分けましょう。
・仏式 …白無地の袋に白黒の結び切り
「御香典」「御仏前(浄土真宗のみ)」
・神式 …白無地の袋に白黒の結び切り
「御玉串料」「御供物料」「御榊料(おんさかきりょう)」
・キリスト教式 …白無地または十字架やユリの花柄の袋、水引はなし
「御花料」「御ミサ料(カトリック)」
「御霊前」は御香典の表書きとしては万能ですが、浄土真宗と曹洞宗では「御霊前」はふさわしくありません。仏式とだけ判明している場合は、「御香典」または「御香料」を選びましょう。
不祝儀袋や水引に関しては###sougi_noshi###の記事で詳しくご説明しております。
御香典の入れ方や渡し方のマナー
お札の入れ方や渡し方にもマナーがあります。
薄墨を使って書く
不祝儀袋には、基本的には薄墨を使って書きます。
薄墨を使う理由には、涙で墨が薄まったように見えることから、悲しみを表すという説や、墨を十分にする間もなく急いで駆けつけたという説があります。
スタンプを使用してもマナー違反ではありませんが、手書きが無難です。
中袋の裏に金額、住所、名前を書く
ご遺族が整理をする際に必要なので、手間をかけないように、住所などもきちんと書きましょう。また、金額は改ざんを防ぐ目的で、旧字体で表記します。
新札は使わない
あらかじめ準備していたと思われるのを避けるためのマナーです。ただ、あまりくしゃくしゃのお札でも、失礼にあたります。程よい旧札が用意できない場合は、新札に一度折り目を付けます。
お札の向きに注意する
裏面が上になるようにしたうえで、肖像が印刷されている側が底の方になるように入れます。複数枚ある場合は、お札の向きを揃えましょう。
外袋は上側を重ねる
「悲しみで目を伏せている」「不幸や悲しみを流していく」という意味から、上側を重ねます。
持参する時は袱紗(ふくさ)を用いる
袱紗の色は、寒色系あるいは濃い紫が良いでしょう。濃い紫は慶弔で兼用できるので、持っておくと重宝します。
相手から表書きが見えるように渡す
渡す時は相手の目の前で袱紗から取り出し、相手から表書きが見える向きに持ち替えます。切手盆などに乗せるのがマナーですが、なければ袱紗を折りたたんで代用すると良いでしょう。
御香典を渡す時には、「この度はご愁傷さまです」など、短くお悔やみの言葉を添えて渡しましょう。また、お通夜と葬儀・告別式、両方に参列なさるのであれば、お通夜に御香典を持参します。
御香典を郵送する場合
やむを得ない事情でご葬儀に参列できない場合は、御香典を郵送してもマナー違反にはあたりません。郵送する際は、現金書留で不祝儀袋ごと送り、必ずお悔やみの手紙を添えましょう。
時候の挨拶などの前文は省略し、参列できないことへのお詫び、弔意を表す言葉を綴ります。手紙はできれば薄墨で書き、忌み言葉は使わないように注意しましょう。
※忌み言葉とは、「重ね重ね」「ますます」「くれぐれも」「また」「再び」など、不幸が重なる、繰り返すことを連想する言葉などを言います。
御香典に添える手紙の文例
○○様のご訃報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。突然のことで、ただ驚くばかりです。
家族の皆様のご心痛はいかばかりかと拝察いたします。どうかお気持ちを強くお持ちになり、ご自愛くださいませ。
本来であれば、すぐにでも駆け付けたいところでございますが、遠方のため参列できない無礼をどうかお許しください。
心ばかりではございますが、御香典を同封させていただきました。御霊前にお供えくださいますようお願い申し上げます。
香典辞退をされたら
家族葬に参列すると、ご遺族が御香典を辞退されるケースがあります。辞退を伝えられた場合には、ご遺族の気持ちを尊重して、御香典を持参しなくても問題ありません。ただ、どうしても弔意を示したい場合は、供花や盛籠などをお供えする方法があります。
日持ちのする線香やろうそく、菓子類なども良いでしょう。ただし、香典辞退のみでなく、供花や供物も辞退されているケースもあるので注意しましょう。
香典辞退をされて、ご葬儀に参列もできない場合は、代わりに弔電を送る、ご葬儀後に弔問して供物を持参するといったことができます。
まとめ
いかがだったでしょうか。今回は、御香典の知識や相場、マナーについてご説明しました。知っているようで知らないのが御香典の知識や相場、マナーです。皆さまの参考になれば幸いです。
神戸・阪神間で、ご葬儀・ご供養に関するお困りごとがございましたら、平安祭典(0120-00-3242)までご相談ください。
続きはこちら
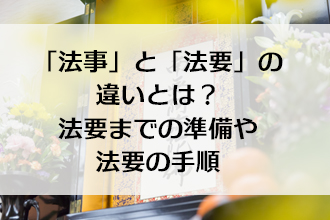
公開日:2021年5月10日
故人様がお亡くなりになって忌明け(四十九日目)などの節目には、法事・法要が執り行なわれます。法事・法要は、ご遺族やご親族などが集い、故人様の想い出を語り合う大切な場となっています。
「法事」と「法要」の違いとは?
皆さまは、「法事」と「法要」の違いをご存じでしょうか?法事と法要は、区別されずに使われることが多い言葉ですが、厳密に言えば違うものです。
「法要」は追善供養とも呼ばれ、故人様を偲び、ご寺院による読経や焼香を行なう仏教的な儀式のことを言います。一方、「法事」は、法要と法要後の会食までをあわせた一連の行事を指す言葉です。
また、「法事」は仏教行事全般を指して使われることもあり、故人様やご先祖様を偲ぶ、「お盆」や「お彼岸」などの仏教行事を含むことがあります。
追善供養とは?
追善供養(ついぜんくよう)とは、亡くなった方に対して行なう供養のことです。
法要だけでなく、仏壇に手を合わせるなど、日々の行ないも追善供養にあたります。「善」は仏教における善行を表し、生きている人が良い行ないをすることが、亡くなった人の善行につながると考えられているのです。
法要としての追善供養には、まず、忌日ごとに供養する中陰法要があります。
仏教では、逝去してから忌明け(四十九日)の間を「中陰」と言い、七日ごとに審判を受けます。そして、忌明けとなる四十九日目に、極楽浄土への最終審判が下されるのです。
故人様が無事に極楽浄土(来世)に旅立てるよう、手助けするのがご遺族の務めであり、追善供養の本来の目的です。
※浄土真宗では、亡くなるとすぐに阿弥陀如来の力で成仏できるという考えから、本来、追善供養は必要ありません。浄土真宗の法要は、自分自身が仏の教えに接することが目的です。
忌日の数え方は地方によって異なり、関東地方などでは、亡くなった日を1日目として数えます。関西地方では、亡くなる前日から数えることが一般的です。
中陰法要のあとには、亡くなった翌年以降、故人様の祥月命日(亡くなった月日)に年忌法要が執り行なわれます。
忌明け(四十九日)に関しては###kiake_shijyukunichi###の記事で詳しくご説明しております。
法要の準備・手順
続いては、法要の準備・手順についてです。
ご寺院へ日時と場所の連絡
法要を行なう際には、ご寺院や参列者の都合も考えて、余裕を持って準備したいところです。少なくとも2~3か月前までには日時と場所を決めましょう。故人様の祥月命日に行なうのが望ましいのですが、来ていただく方のご都合も考慮して、祥月命日から前の土・日・祝日に行なうことが一般的です。
法要は土・日・祝日に集中するため、できるだけ早めに連絡をし、ご寺院や会館の予約を済ませておきましょう。
ご親族などへの案内
日時と場所が決定したら、ご親族などに連絡をします。近親者の場合は電話連絡でも構いませんが、葉書や封書で案内状を送付すると良いでしょう。お招きするのは、ご葬儀に来ていただいたご親族が中心となります。
一般的には一周忌までは、ご親族だけでなく、故人様の友人、知人、お世話になった方など、広い範囲でお招きします。
お食事・供養品の手配
出欠が確認できたら、2週間前を目安に、お食事・供養品の手配をします。会食の人数は、何日前までなら変更可能か確認しておくと良いでしょう。
最終確認
1週間前までに、参加人数、お食事・供養品の数などを最終確認します。御布施の額も、ご寺院に早めに確認しておいた方が良いでしょう。
当日に必要な物の準備
前日までに、位牌(浄土真宗の場合は過去帳)、遺影写真、御布施など、当日必要な物を準備しておきます。
法要の服装と持ち物
ご遺族は、三回忌までは喪服を着用される方が多いようです。七回忌法要からは、法要も簡略化され、紺やグレーなどの地味な服装で問題ありません。ご親族は一周忌までは略礼服を着用し、三回忌からは地味な服装にしていくと良いでしょう。
回を重ねるごとに、喪の表現を軽くするという意味で、少し明るめの色を選びます。
地味な服装と言ってもカジュアルな服装は避け、基本的には、女性はワンピースかスーツ、男性はスーツを着用します。
施主の持ち物
位牌(浄土真宗の場合は過去帳)、遺影写真、御布施、数珠など(寺院で法要を行なう場合はお供え物やお花など)
参列者の持ち物
御香典、お供え物、数珠など
法要当日の手順
施主様と血縁の濃い方は、法要開始の30分前には会場に到着するようにしましょう。聖職者がお見えになりましたら、御布施・御車料・御膳料をお渡して、法要読経を依頼します。(会食時に同席される場合は、御膳料は必要ありません。)
法要の流れの一例
読経→参列者による焼香→法話→施主のご挨拶→お食事→散会
お食事の前には、仏様や故人様に盃を捧げる「献杯」を行なうことも少なくありません。ご親族などに献杯のご挨拶をしていただく時は、事前にお願いしておきましょう。参列者の方々への供養品は、法要の散会までにお渡しします。聖職者への供養品も準備しておくと、尚良いでしょう。
忌明け法要、年忌法要は平安祭典へ
今回は、法事・法要について、ご説明しました。故人様とご縁の深かった方々が集う法要は、故人様との想い出を語り合い、故人様とのご縁によって、新たな絆を結ぶ大切な機会ともなります。平安祭典も、皆さまのお役に立てれば何よりです。
平安祭典では神戸・阪神間での忌明け法要、年忌法要などを承っております。また満中陰のお返しもお選びいただけます。
平安祭典の法要については下記のページをご覧ください。
法事・法要について
詳細は平安祭典までお問い合わせください。
平安祭典祭典でお葬式をされていない方のご法要も承ります。
《平安祭典法要受付》
フリーダイヤル 0120-18-4142 (受付 9:00~17:00)
お問い合わせ、ご予約の際は「平安祭典のホームページを見た」とお伝えください。
※年末年始は休業(12/30~1/3)
続きはこちら
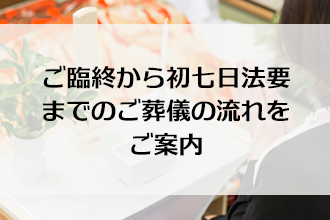
公開日:2021年5月3日
ご葬儀は、故人様を偲び弔うための儀式です。とはいえ、ご遺族は短い時間の中で様々なことを決めていかなければなりません。
今回は仏式を例に、ご葬儀の流れをご説明します。
ご臨終に際しての心構え
病院で臨終を迎えた場合
病院で亡くなられた場合には、医師による死亡宣告を経て、死亡診断書が作成されます。死亡診断書を受け取ったら、まず、記載されている内容(名前や生年月日など)に間違いがないかを確認しましょう。
死亡届、および死体火葬・埋葬許可申請のため、死亡診断書の原本は役所に提出しますが、多くの場合、葬儀社が代行します。
ご自宅で臨終を迎えた場合
かかりつけの医師に連絡し、死亡の原因を調べてもらいます。自然死または病死などの場合、死亡診断書を書いてもらえます。かかりつけの医師がいない場合は、救急車を呼びましょう。
病気以外の急死や外因死、死因不明の場合は警察の検視を受け、死亡診断書ではなく、死体検案書が作成されます。
葬儀社(移送先)の手配
病院で亡くなられた場合、まず葬儀社に連絡して、故人様を搬送する寝台車の手配をしなければなりません。互助会に入っていない、どこの葬儀社にするか見当がつかないといった場合などは、病院で葬儀社を紹介できるか聞いてみましょう。
いざという時に慌てないためにも、事前に葬儀社を決めておき、葬儀・告別式と執り行なう会館やご自宅など、どこに帰るのかを決めておくことが大切です。
ご自宅に帰る場合は、故人様をご安置するスペースを確保します。
また、部屋の温度を低めに設定するなど、室温管理にも気をつけます。
ご安置~ご葬儀の日程などの取り決め
ご安置・末期の水
ご自宅でのご安置の場合、北向きか西向きにご安置します。
ご安置後、末期(まつご)の水を行ないます。末期の水とは、息を引き取られた故人様の口元を水で潤す、仏教における大切な儀式です。
ご寺院へ連絡・枕経
枕元に枕飾りを設置し、お付き合いのあるご寺院に訃報の連絡をして、枕経をあげていただきます。
枕経とは、本来は死にゆく人への案内として、枕元で死をみとりながらあげるお経のことですが、現代ではお亡くなりになって初めてあげてもらうお経のことを指します。
枕経の時には、その場での御布施は不要ですが、後に「枕経料」として包む場合もあります。
お付き合いのあるご寺院がいらっしゃる場合は、あらかじめ連絡先を把握しておきましょう。分からない方は、故人様の兄弟姉妹など、ご親族に宗派を確認することが大切です。
お付き合いのあるご寺院が遠方でいらっしゃることが難しい場合には、お近くの同宗派のご寺院をご紹介いただきます。
ご葬儀の日程などの取り決め
葬儀社とご葬儀の形式や規模、日程などを相談します。ご葬儀の日程は、ご寺院のご都合を考慮して決める必要があるため、枕経のあとに確認をしておきましょう。そのあと、喪主を決定し、飾り付けや費用などご葬儀の内容の打ち合わせを行います。
この時、受付を誰にお願いするのかなども決めておきましょう。
ご葬儀の打ち合わせの際には、参列者を予測して、食事の数(量)を決定します。ご親戚への訃報連絡の際に、お通夜・ご葬儀それぞれの出席人数、お食事を召し上がる方の人数をできる限り確認しておくと良いでしょう。
湯灌の儀・納ノ儀(納棺)
湯灌の儀とは、故人様の体や髪をお湯で洗い清め、新たな旅立ちの準備をする儀式です。
現世の汚れを洗い清めるという意味と、赤ちゃんが産湯につかるように、新たに来世に生まれ変わるためにという願いが込められています。
病院などで行なう「清拭(エンゼルケア)」は、主に皮膚を清潔に保ち、感染を予防するためのもので、意味合いが全く異なります。
納ノ儀(納棺)とは、故人様の身なりを整えて棺にお納めする儀式です。ご遺族と故人様とのかけがえのない時間で、故人様の死を受け止める大切な儀式となっています。この時に、故人様の愛用していた品などを副葬品として納めるので、用意しておきましょう。間に合わなければ、出棺前のお別れの際に納めることもできます。
お通夜・通夜ぶるまい
お通夜は、ご遺族やご親族、ご友人などがご遺体を守って一晩過ごす、ご葬儀前夜に行なわれる儀式のことです。葬儀日程の関係で、お通夜の前日に「仮通夜」を営む場合もあります。
お通夜は、一般的には、《着席~ご寺院入場~読経~ご遺族焼香~参列者焼香~ご遺族代表挨拶》という流れです。
そのあと、参列者の方々を通夜ぶるまいの席に案内します(その場で召し上がらない方には、お持ち帰り料理をご用意することもできます)。通夜ぶるまいとは、故人様へのご供養の意味も込めて、ご遺族が故人様と縁のある方々を、酒食でもてなすことです。
葬儀・告別式
ご葬儀とは、ご遺族や近親者が故人様を新仏としてあの世へ送るための儀式です。ご寺院から引導を渡されたあとに、告別式が執り行なわれます。告別式は、生前の故人様と縁ある方々が最期のお別れをする儀式です。
葬儀・告別式の大まかな流れは、《着席~ご寺院入場~読経~弔電の披露~ご遺族焼香~会葬者焼香~ご寺院退場~ご遺族代表挨拶》となります。聖職者へのお礼(御布施)は、葬儀・告別式の開式前にお渡しすることが多いです。
出棺~お骨あげ
葬儀・告別式のあとに、故人様にお花をたむけてお別れする「お別れの儀」を行い、そのあとに出棺となります。出棺の折に、故人様の使用していた茶碗を割る、クラクションを鳴らすなどの風習もあります。神戸地区では、火葬場でご寺院の読経をいただき、水と樒を使用したお水でのお別れが行なわれます。
火葬にかかる時間は、約2時間30分です。この間に式場に戻り、故人様を偲び、ご親族などをもてなす仕上げ料理を振るまいます。お骨あげは、火葬場の担当者の指示に従って行ないましょう。
火葬に関しては###kasou_toha###の記事で詳しくご説明しております。
初七日法要
ご遺骨になった故人様を式場に連れて帰り、初七日法要を執り行ないます。
本来であれば初七日法要は亡くなってから七日目に行なうものですが、近年では、ご遺族・ご親族が集まっているご葬儀当日に行なうことが一般的です。
初七日法要に関しては###shonanoka_houyou###の記事で詳しくご説明しております。
まとめ
いかがだったでしょうか。今回は、ご葬儀の大まかな流れを、儀式の内容や注意点なども含めてご説明しました。神戸・阪神間で、ご葬儀・ご供養に関するお困りごとがございましたら、平安祭典(0120-00-3242)までご相談ください。
続きはこちら
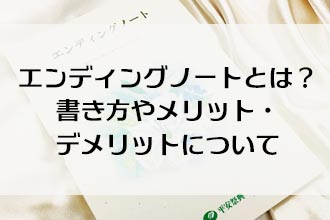
公開日:2021年4月26日
近年、自分自身のご葬儀や相続について生前に準備する「終活」が注目されています。終活は、単に人生の終末に向き合う作業ではありません。終活を通じて自分自身を見つめ直し、人生の後半戦をより豊かにすることができます。
そして、終活の手助けとなるのが「エンディングノート」です。今回は、エンディングノートの必要性や書き方についてご説明します。
いざという時に備え
記入しておくエンディングノート
エンディングノートとは、ご自身のいざという時に備え、ご自身の情報を整理したり、ご家族に介護やご葬儀の希望を伝えるために残すノートのことです。終活の一環として利用されているため、終活ノートとも呼ばれています。
ノートに情報を記入しておくことで、いざという時に、ご家族がスムーズに各種手続きを行なうことができたり、意思を尊重したご葬儀を執り行なってくれることでしょう。
仮にご家族が介護を行わなければならない際にも、ご自身の意思が尊重される可能性が高まります。
その他にも様々な情報を書き出すことで、ご自身の人生を振り返ることができます。これまでの人生を整理することで、残りの人生をより良く過ごすことができるでしょう。
エンディングノートには何を書くのか?
エンディングノートには、どのようなことを書くのでしょう。
基本的に書き方や、書く内容に決まりはありません。ご自身の過去を振り返ったり、ご家族への想いを伝えたり、自由に書き記すことができるのがエンディングノートの良い点です。
エンディングノートは、あらかじめ記入項目が決まっているものがほとんどです。もちろん、無理にすべての項目を埋める必要はありません。書きやすい項目から埋めていっても構いません。また、あとで考えが変わったら書き直しても大丈夫です。
エンディングノートに記述する主な内容
・ ご自身やご家族の情報
生年月日や住所などの基本的な情報、これまでの経歴、ご家族やペットのことなどを記します。家系図を書き込んで、ご自身のルーツをたどることができるタイプもあります。
・ 財産・資産について
預貯金、不動産、生命保険、有価証券、クレジットカードなど、財産・資産についてまとめます。ただし、誰が見るか分からないため、暗証番号などは別にまとめたほうが無難です。
・ ご親族やご友人のリスト
急な入院やご葬儀の際に、関係性や連絡先の分かるリストがあると、ご家族のご負担が減ります。
・ 医療・介護について
いざという時のために、延命治療の希望や介護について記しておくと、ご家族の判断の助けになるでしょう。
・ ご葬儀について
どんなご葬儀にしたいか、といった考えをまとめます。
近年、ご家族の費用面での負担を考慮して、「家族葬」や「ご寺院を呼ばない無宗葬
(自由葬)」を希望される方が増えています。
しかしながら、結果的にご家族のご負担が増えてしまうことが少なくありません。
ご葬儀については、事前にご家族とよく話し合っておくことをおすすめします。
また、せっかく書いても、ご葬儀を執り行なっていただく方に見てもらえないと意味がありません。エンディングノートの存在や保管場所は、ご家族、特にご葬儀を執り行なうであろう方に必ず伝えておきましょう。
エンディングノートのメリット・デメリット
続いては、エンディングノートのメリット・デメリットです。
メリット
・ 基本的に自由な形式で書くことができる
・ ご家族やご友人に想いを伝えることができる
・ 人生を振り返り、現在の自分を改めて見つめ直すことができる
エンディングノートに現在のご自身の考えを自由に書き出すことで、新たな気付きを得ることもあります。また、大切なご家族へ想いを伝えることができます。
デメリット
・ 遺言書のように法的拘束力がない
・ 個人情報などを記した場合、保管場所に
注意しなければならない
・ 相続など内容によってはトラブルにつながることもある
遺言書は、決められた書式に従って書き記すことで、法的効力を持ちます。しかし、エンディングノートはご自身の希望を記すものですが、遺言書とは違い法的な効力を持ちません。
相続についての希望を確実に叶えたい場合には、エンディングノートとは別に遺言書を作成する必要があります。
遺言書に関しては###yuigonsyo_kakikata###の記事で詳しくご説明しております。
平安祭典ではエンディングノートを無料でご用意しています
冒頭でも述べましたが、終活は単に人生の終末に向き合う作業ではなく、自分自身を見つめ直し、残りの人生をより豊かにする作業です。ノートを活用して、ご自身の人生をより豊かなものにしてください。
ちなみに、平安祭典でもオリジナルのエンディングノート(無料)をご用意しています。神戸・阪神間で、エンディングノートに興味をお持ちの方は、平安祭典NCP室(078-856-6890)まで、気兼ねなくお問い合わせください(もしくは、お問い合わせ・資料請求フォームから「エンディングノート希望」と、ご請求ください)。
■お問い合せ・資料請求ページ https://www.heiansaiten.com/inquiry/inquiry.php
続きはこちら
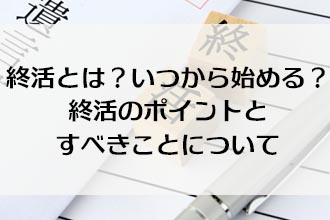
更新日:2021年8月3日 公開日:2021年4月19日
ご自身の人生の最期について考えたり、話すことは、以前はどちらかというとタブー視されてきました。しかし最近では、「終活」という言葉が注目されています。
そこで今回は、終活とはどのようなものか、いつから始めるべきか、終活のポイントとすべきことについてご説明します。
[@目次@]
終活とは?
終活とは、「人生の終わりのための活動」を略した言葉です。ご自身の人生の最期、すなわち死と向き合い、身辺整理をはじめたり、介護や終末期医療、ご葬儀、相続といったことに関して、ご自身の考えをまとめて、周囲に意思表示をしていく作業です。
終活は決してネガティブな作業ではなく、ポジティブな作業です。ご自身が死と向き合い終活を行なうことで、自分自身を見つめ直す機会が生まれ、将来への漠然とした不安が解消し、新たな気持ちになることができます。
終活を行なう際の5つのポイントとすべきこと
終活を行なう際の5つのポイントとすべきことをご説明します。
① 終活はいつから始める?
終活を始めるベストなタイミングは特にありません。しかし、お元気なうちに始めたほうが良いのは確かなことです。いざという時、病気になって体が動かなくなってしまったり、判断力が低下してしまってからでは、終活を行なうのも難しくなってしまいます。やることをリスト化し、できることは早いうちに行なうのが良いでしょう。
② 介護や臓器提供、ご葬儀の内容について決めておきましょう
介護や終末期医療、臓器提供などのご希望をご家族に伝えることも大切です。介護や終末期医療、ご葬儀内容などについて、ご自身の考えをまとめ、ご家族に伝える方法として役立つのがエンディングノートです。
エンディングノートとは終活ノートとも呼ばれ、過去や現在の自分のこと、いざという時のために伝えておきたいことなどを書き留めておくことができるノートのことです。
ある日突然入院してしまう…、介護が必要になる…、亡くなる…ということは誰にでも起こりうることです。
そんないざという時に備えて、どのような介護を受けたいか、費用はどうするか、その他の要望といったことをあらかじめエンディングノートなどに書き記しておくことで、ご家族のご負担が軽減されるでしょう。
また、ご本人の意思で臓器提供を希望される場合は、健康保険証や運転免許証、臓器提供意思表示カードなどに記入しておくことで、ご遺族への意思表示になります。
さらに、ご葬儀となると残されたご家族が訃報連絡をしたり、ご葬儀の内容を決めなければなりません。事前準備として、連絡先リストを作成する、ご葬儀内容の希望をまとめておくといったことができます。
ちなみに、連絡先リストを作成する際には、年賀状を整理し、リスト化するのも効果的です。
平安祭典のエンディングノートには「連絡リスト」の項目があります。ご希望の方は、お問い合わせ・資料請求フォームから「エンディングノート希望」と、ご請求ください)。
■お問い合せ・資料請求ページ
https://www.heiansaiten.com/inquiry/inquiry.php
余裕があるうちに、ご自身の遺影写真の準備もしておきたいものです。
エンディングノートの書き方などについては、###endingnote_kakikata###の記事で詳しくご説明しております。
③ 遺産相続について考えましょう
相続の準備も生前に行なうことが可能です。遺産相続の問題は、資産家など一部の方に限らず、どのようなご家庭でも多かれ少なかれ起こり得ることです。相続に関する揉めごとも少なくありません。
土地家屋・現金・有価証券…、保有している資産によっては、遺言状の作成が必要なケースも出てきます。負の遺産相続が生じてしまう場合も遺言状の作成が必要です。遺言状を書いておくことで、ご自身が亡くなったあと、ご家族・ご親族の間の無用なトラブルを回避することができます。
遺産相続の準備や遺言状の作成は意外と面倒なものです。いわゆる士業と呼ばれる方々に終活の事前相談をする機会があれば、積極的に参加しても良いでしょう。
※平安祭典では、業務提携先の専門家をご紹介しております。
相続に関しては###souzoku_tetuduki###記事で詳しくご説明しております。
④ ご遺骨をどうするか考えましょう
最近では、納骨の方法も多様化しています。先祖代々のお墓に納骨する方法だけでなく、例えば、納骨堂・永代供養墓、散骨、手元供養といった様々な選択肢が存在します。
下記の記事で様々な納骨方法についてご説明しておりますので、ぜひご参考になさってください。
###noukotsudou_toha###
###eitaikuyou_toha###
###sankotu_toha###
###temotokuyou_toha###
ご希望の納骨方法がある場合には、ご家族と話し合って事前に決めておくと良いでしょう。
⑤ 身辺整理について考えましょう
ご自身が亡くなった際、一般的に遺品整理や財産整理はご遺族が行ないます。この遺品整理や財産整理が、想像以上にご遺族の負担となるケースが多いようです。
ですから、なるべくお元気なうちに、ある程度の身辺整理をご自身でしておきたいところです。
ご自身ですぐにできる身辺整理は、身の回りの整理(生前整理)です。まずは家の中を見渡し、必要なものと必要でないものを分けて、不要なものを処分します。もし、ご家族などに形見分けしたいものがあるならば、事前に伝えておきましょう。
ご自身が亡くなったあとに、ご家族が財産関係の手続きを行なうための情報や保管場所を記しておくことも身の回りの整理(生前整理)にあたります。
また、近年ではメールやSNSを利用されている方も多いのではないでしょうか。それらのアカウントをご家族が削除できるようにパスワードを記しておくなど、デジタル遺品の整理も必要です。
その他にも、自分史を書いて過去を見つめ直す、家系図を書いて自分のルーツをたどる、友人・知人関係のリストを整理する、これまで疎遠になっていた友人・知人に連絡を取ったり、会ったりすることも身の回りの整理(生前整理)にあたります。
遺品整理に関しては###ihinseiri_katamiwake###の記事で詳しくご説明しております。
終活は、これからの人生を前向きに歩むための
“道しるべ”
今回は「終活」についてご紹介しました。終活の良いところは、過去を振り返り、未来を考えることができる点です。終活は、これからの人生を前向きに歩むための
“道しるべ”にもなるでしょう。
また、ご葬儀に関しては、葬儀社に事前相談を行なうことで、ご自身の意思が尊重されます。
平安祭典では、神戸・阪神間で事前相談を数多く行なっておりますので、気兼ねなくお問い合わせください。
神戸・阪神間で事前相談をご希望の方は下記のフォームからお申し込みください。
■事前相談予約フォーム
https://www.heiansaiten.com/inquiry/consultation.php
お電話でのご相談をご希望の方は平安祭典(0120-00-3242)まで気兼ねなくお問い合わせください。
続きはこちら
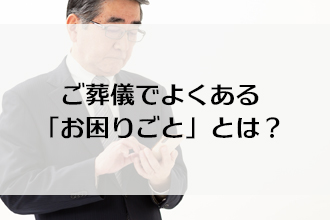
更新日:2024年9月22日 公開日:2021年4月12日
喪主やご遺族としてご葬儀を執り行なう際、いざという時に備えて準備されていたとしても、どうすれば良いか分からないことも少なくありません。
そこで今回は皆さまに、ご葬儀でよくある「お困りごと」をご紹介します。
[@目次@]
こんなお困りごとが…
遠方のご親族への訃報連絡はすべきか
近隣のご親族だけでご葬儀を行なう場合、遠方のご親族にご連絡をすべきか判断に困るものです。ご遺族としては、遠慮してご連絡をしづらいこともあるでしょう。
しかし、そういった場合でも、遠方のご親族には一報を入れておきたいもの(ご連絡をする際には、「ご無理はされないように」と一言添えると良いでしょう)。
事後報告になると、「なぜ呼んでもらえなかったのか」などトラブルになってしまうケースもあるからです。
訃報連絡に関しては###fuhourennraku_timing###の記事で詳しくご説明しております。
遺影写真用のお写真がない
ご葬儀の際に意外と悩むのが遺影写真です。
探しても最近撮影した良いお写真が見つからないことも少なくありません。
遺影写真を選ぶ際には、お顔が大きく写り、ピントが合ったお写真をお願いしています。複数で映っているようなスナップ写真からでも、故人様のお顔部分を取り込んで、遺影写真にすることができます。
もちろん背景画像も修正可能です(服の着せ替えも可能ですが、合成写真となるので多少の違和感があるかもしれません)。小さな画像を引き伸ばすことも可能ですが、あまり小さすぎるとぼやけてしまいます。お顔のサイズが親指の第一関節以上あるお写真をご準備ください。
一年に一度でも、ご家族で写真撮影をしておくと良いかもしれませんね。
遺影写真の選び方に関しては『遺影写真の選び方 撮影方法や背景はどうすれば良い?』の記事で詳しくご説明しております。
お通夜やご葬儀の際の食事の数が読めない
お通夜やご葬儀の参列者の人数は、当日にならなければ分かりません。
お通夜に参列者をもてなす「通夜ぶるまい」、火葬場でのお骨あげの間、ご親族などをもてなす「仕上げ料理」は、いずれも個別にお料理をご用意します。
故人様と親しかったご友人が来られる可能性もあるので、足りないよりも余るくらいを意識して、気持ち多めにご用意しておくと良いでしょう。
菩提寺(檀那寺)が遠方にある
ご葬儀の際、お付き合いのある菩提寺(檀那寺)が遠方であっても、まずはご連絡をしてください。遠方でもお越しになる場合や、近隣のお付き合いのあるご寺院をご紹介していただける場合があります。
お越しになれない場合には、「葬儀社にご寺院を紹介してもらってください」あるいは「戒名はこちらで授けるが、葬儀社に紹介されたご寺院に来てもらってください」などと菩提寺(檀那寺)が判断されるケースがあります。その際には、葬儀社からご寺院をご紹介します。
菩提寺に関しては###bodaiji_dannadera###の記事で詳しくご説明しております。
聖職者へのお礼(御布施)の相場とタイミングが分からない
ご葬儀を執り行なう際のお困りごとのひとつとして、聖職者へのお礼(御布施)に関すること、例えば相場やお渡しするタイミングがあります。
仏式の場合、御布施の額は、ご寺院の格式や住職のお考えによっても異なるため、相場は参考程度にしかなりません。同じ檀家の方に聞くのもひとつの方法ですが、お付き合いの度合いでも異なりますので、直接ご寺院にお尋ねするのが良いでしょう。直接ご相談しても、失礼にはあたりません。
基本的に、御布施をお渡しするタイミングに決まりはありません。ただ、ご葬儀の開式前に、ご挨拶を兼ねて、御布施をお渡しするケースが多いようです。
御布施に関しては###ofuse_kingaku###や###ofuse_manner###の記事で詳しくご説明しております。
遠方から来られるご親族の宿泊先をどうするか
遠方から来られるご親族の宿泊先を心配されるケースもあります。基本的には、お近くのホテルなどを喪家様負担で手配します。平安祭典では、お問い合わせをいただければ、お近くの宿泊施設をご案内しています。
ちなみに、平安祭典の会館には、ご遺族やご親族のための仮眠室をご用意しています。ベッドルーム、バスルーム(ボディソープ、シャンプーなど備え付け)も完備しています。浴衣は備え付けていませんので、お着替えなどは各自でご用意ください。
遺影写真が大きくて飾る場所に困る
遺影写真は、一般的には四十九日法要まで飾ります。ただし、遺影写真に宗教的な意味はなく、無理に飾る必要はありません(ご法要をされる際には、飾ってあげてください)。
平安祭典では、大きな遺影写真をキャビネサイズ程度の小さなサイズに作り直す加工サービスを有料にて承っております。
お写真を処分しても問題はありませんが、大切なお写真ですので、気になる方には遺品供養をご案内しています。平安祭典では、遺品を納める袋をお渡しし、故人様の愛用品などを入れていただき、回収した遺品をご寺院に供養していただくサービスも有料にて承っております。
遺影写真の飾り方に関しては###ieisyashin_kazarikata###の記事で詳しくご説明しております。
お墓はあるが納骨しようかどうか考えている
現在ではご供養の形も多様化して、手元供養、散骨、永代供養など、様々なご供養の方法が存在します。ご家族皆さまでよく相談なさって、納得のいく方法をお選びください。
平安祭典では、故人様のご遺骨を海に還し供養する海洋散骨、ご遺骨の一部を壷やペンダントなどに納め、故人様を身近に感じることのできる手元供養や永代供養のご案内もしております。ご遠慮なくご相談ください。
海洋散骨に関しては###sankotu_toha###、手元供養に関しては###temotokuyou_toha###や###temotokuyou_merit###の記事で詳しくご説明しております。
いざという時の参考に
いかがだったでしょうか。今回は、ご葬儀でよくあるお困りごとをご紹介いたしました。皆さまのいざという時の参考になれば幸いです。
平安祭典では、神戸・阪神間でのご葬儀に関するお困りごとのご相談や、事前見積りを受け付けています(0120-00-3242)。気兼ねなくご相談ください。
事前相談に関しては###sougi_jizensoudan###で詳しくご説明しております。
また、平安祭典でも事前相談を承っております。
神戸・阪神間で事前相談をご希望の方は下記のフォームからお申し込みください。
■事前相談予約フォーム
https://www.heiansaiten.com/inquiry/consultation.php
続きはこちら
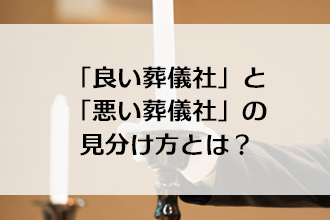
公開日:2021年4月5日
インターネットやSNS上では、ご葬儀を執り行なった方々が、「費用が想定以上に高かった」「葬儀社のスタッフが不親切だった」「電話対応が悪かった」などと書き込んでいるのを見かけます。
お互いのボタンの掛け違いで、そのようなご不満を抱かれた可能性もありますが、世の中にはいわゆる「良い葬儀社」と「悪い葬儀社」というものが、少なからず存在します。
そこで今回は、皆さまに悔いのないご葬儀を執り行なっていただくためにも、良い葬儀社と悪い葬儀社の見分け方をご紹介します。
[@目次@]
良い葬儀社と悪い葬儀社の見分け方とは?
まずは、良い葬儀社の特徴をいくつか挙げてみましょう。
《良い葬儀社の特徴》
① 詳細な見積書の作成ができる
「葬儀費用は分かりづらい点が多く、ブラックボックス化している」という意見があります。しかし良い葬儀社は、明瞭な料金体系となっているため、ご要望に基づき、詳細な見積書を作成することが可能です。まずは事前相談をして、見積書を作成できるのか否かを確認しましょう。
② ご要望に応じた、ご葬儀の提案ができる
良い葬儀社は、ご要望に応じたご葬儀の提案ができます。例えば「費用を抑えたい」というご要望があれば、どの部分を抑えればいいか、どのようなご葬儀になるかを親身になって考えてくれます。
③ 経験豊富なスタッフが在籍し、設備が充実している
葬祭業には、「葬祭ディレクター技能審査」という厚生労働省が認定している制度があります。この制度は、葬祭業に従事する人々の知識・技能の向上を図るための試験で、試験結果に基づき、葬祭ディレクター(1級、2級)の認定が行なわれます。
良い葬儀社には、葬祭ディレクターの資格を保有した経験豊富なスタッフが数多く在籍しています(ちなみに、平安祭典には2023年3月現在、一級葬祭ディレクターが73名在籍しています)。
また、お通夜、葬儀・告別式を執り行なうための設備はもちろん、ご遺族が過ごす控室の設備が充実しているのも、良い葬儀社の条件のひとつと言えるでしょう。
葬祭ディレクターに関しては###sousaidirector_shigoto###や###sousaidirector_goukaku###の記事で詳しくご説明しております。
④ 地元での評判が良い
ご葬儀は地域ごとに風習やしきたりが異なるため、地域に根差した葬儀社を選ぶことが大切になります。どのような業種でもそうですが、地元での評判はとても重要です。
ちなみに、ご葬儀を執り行なうには、大手の葬儀社と中小の葬儀社、どちらが良いとは一概には言えません。大手の葬儀社であっても、中小の葬儀社であっても、良い担当者に巡り合えることが重要なポイントとなります。
大手の葬儀社は、研修マニュアルが行き届いており、スタッフの接遇水準も一定レベル以上あること、経験豊富な葬祭ディレクターが多く、会館などの設備が充実している点が強みです。一方、中小の葬儀社では、ご葬儀前の打ち合わせからアフターフォローまで、すべて同じ担当者が対応するケースが多く、ご遺族に寄り添った親身なサポートを期待できます。
《悪い葬儀社の特徴》
悪い葬儀社の特徴は、良い葬儀社の特徴の逆です。すなわち、見積書を発行できない、ご要望に応じたご葬儀の提案ができない、経験の浅いスタッフしかいない、地元での評判があまりよくない、といった項目が複数当てはまった場合には注意しましょう。
インターネット上での葬儀社選びは慎重に
また、もう一つ注意したい点があります。それはインターネット上での葬儀社選びです。最近では、インターネット上で葬儀社を仲介するサービスが増えてきました。もちろん、仲介サービス自体は悪くはないのですが、このようなサービスで紹介される葬儀社の中には、見積書が出せないなど、決して良いとは言えない葬儀社も含まれています。
また、インターネット上には、「低価格な家族葬」「定額料金の葬儀」などと、低価格を謳って広告を出している葬儀社が存在します。しかし実際は、結局、追加するものが多くなり、逆に高額となってしまい、トラブルになることも少なくありません。
いずれにせよ、インターネット上での葬儀社選びは慎重に行ないたいところです。
良い葬儀社を探すためにも事前相談を
いかがだったでしょうか。今回は、良い葬儀社と悪い葬儀社の見分け方についてご紹介しました。
もし、皆さまが良い葬儀社を選びたいと思うのであれば、候補となる葬儀社に直接赴き、事前相談をすることをお勧めします。事前相談を行ない、詳細な見積書を作成してもらったり、担当者の人柄や各種設備をご自身の目で確認することで、その葬儀社が良い葬儀社なのか(もしくは悪い葬儀社なのか)を判断できるかもしれません。
事前相談に関しては###sougi_jizensoudan###の記事で詳しくご説明しております。
また平安祭典では、神戸・阪神間で事前相談を数多く行なっておりますので、気兼ねなくお問い合わせください。
神戸・阪神間で事前相談をご希望の方は下記のフォームからお申し込みください。
■事前相談予約フォーム
https://www.heiansaiten.com/inquiry/consultation.php
お電話でのご相談をご希望の方は平安祭典(0120-00-3242)までご相談ください。
続きはこちら